新HPCの歩み(第155回)-1998年(d)-
|
アメリカではPITACが中間報告を出し、即戦力の研究ばかりではなく、長期的な視野に立ってリスクを含む研究、とくに基礎研究に投資すべきだと論じた。アメリカはNCARへの日本機の導入をあくまで阻止し、Bill Buzbeeは引退する。ドイツでは、John von Neumann-Institut für Computing (NIC)が発足する。インドは独自にPARAM 10000を開発する。 |
アメリカ政府の動き
1) PITAC
前年、クリントン大統領の大統領令によって設置されたPITAC (President’s Information Technology Advisory Committee)は1998年6月、大統領に書簡を送り、全ての米国民の生活の質と水準を常に行動させるため、情報通信および情報技術(IT)研究への公的投資を著しく増加すべきであると述べた。大統領はこれを受けて、科学技術担当大統領補佐官に、情報通信および情報技術分野で野心的な新研究プログラムを作成するように指示した。
また、PITACは1998年8月に中間報告を提出した。そのなかで、アメリカは長期的根源的な情報技術研究開発への投資を重点的に強化する必要性を勧告している。
2) 下院科学委員会
1998年の下院科学委員会報告書(「未来への扉を開く:新しい国家科学政策」)は科学技術の重要項目として、
(a) 基礎研究の促進
(b) 科学技術成果の新産業技術への活用と社会・環境問題の解決への応用
(c) 科学教育の充実
を挙げている。このうち基礎研究の重視については、その研究費の伸び率が応用研究、開発よりも大きく、予算に反映されている。また米国では、科学技術は経済発展のための牽引力であると位置付けられており、研究開発からその成果の製品化を推進するために、産学官の連携を強化し、技術移転を推進する様々なプログラムが実施されている。科学教育については、2001年1月にブッシュ大統領が発表した「No Child Left Behind」においても、理数科教育の改善が重要な柱の一つとなっている。
科学技術の重点分野についてみると、ライフサイエンス分野では1988年にNIHが中心となってヒトゲノムの解読が本格的に開始され、1990年には「脳研究10か年計画」が提唱された。NIHの予算は2001年度に1996年度の1.7倍と大幅に伸びており、さらに2000年度からの5年間で予算の倍増を目指している。情報通信分野では、1993年に「全米情報通信基盤イニシアティブ( NII)」が提唱され、2000年度予算からは「21世紀のための情報技術イニシアティブ( IT2: Information Technology for the Twenty-First Century)」が開始される。ナノテクノロジーの分野では、1999年9月にNSTCから出されたレポート等を踏まえ、2001年度予算において「国家ナノテクノロジーイニシアチブ( NNI)」が開始されている。
3) ASCI(Pathforward Program)
ASCI Programは、LLNLにおいて2000年に建設予定のASCI White(IBM、10 TFlops)までは目途がついていたが、それ以降は汎用商用製品を用いたスーパーコンピュータでは限界が見えていた。2001年に30 TFlopsの実現や2003年に100 TFlopsの実現には新たな技術開発の必要性が痛感された。1998年2月、Clinton大統領は、ASCIの一環としてPathforward Programを発表し、Digital Equipment社、IBM社、Sun Microsystems 社、Silicon Graphics/Cray社の4社と4年間$50Mの契約を締結した。これにより、現在の商用品の製品開発を加速し、汎用品をスケールアップして30 TFlops以上のマシンを目指す。目標とする技術領域は、(1) 高性能相互接続とスイッチ技術、(2) 分散並列OSや並列プログラミング・ツールなどのソフトウェア、(3) 高性能大規模記憶装置の3領域である。
4) ASCI (Blue Pacific)
さて、1999年始めに3.5 TFlops (peak)を目標としていたASCI Blue Pacificは、予定より3ヶ月早く、1998年10月3日にIBMからLLNLに納入された。価格は$94M。Gore副大統領じきじきに、ホワイトハウスから「世界最高速のコンピュータ」と発表した。このメッセージはアメリカ政府のアーカイブに保存されている(村上弘氏からのご教示)。
|
THE WHITE HOUSE Office of the Vice President
For Immediate Release: Wednesday, October 28, 1998
VICE PRESIDENT GORE ANNOUNCES WORLD’S FASTEST COMPUTER Also Highlights Two New Laws to Create a Faster Internet and Protect U.S. Copyrighted Works in the Digital Age
Washington, DC — Vice President Gore, joined by Energy Secretary Bill Richardson, unveiled today the world’s fastest computer, which will break the “speed barrier for computing” by performing 3.9 trillion calculations per second — 15,000 times faster than the average desktop personal computer. (以下略) |
11月に公表されたTop500には、2セクター(3904プロセッサ)と1セクター(1952プロセッサ)が別々に6位と7位として登録されていたが、Rmaxとしては同一の547 GFlopsとなっていた。11月6日に、SC98出発前の筆者が朴泰祐氏らに送った下記のメールにこう書かれている。朴氏の「間に合わなかった」とは「フルスケールでの測定が」の意味であろう。1セクターしか稼働しなかったようだ(フルシステムは3セクター)。私の「他人の不幸」もそのこと。
|
From: oyanagi@is.s.u-tokyo.ac.jp Date: Fri, 6 Nov 98 12:01:51 JST To: taisuke@taisuke2…..
小柳義夫です。 taisuke> 朴%建部君と一緒@成田です。 よい御旅行を。あちらでお会いしましょう。 taisuke> ASCI Blue はやっぱり間に合わなかったんですね。 Blue も載っています。他人の不幸を喜ぶわけではありませんが、 Rmax # Peak 4 ASCI Blue Mountain 690G 6144 3072G 6 ASCI Blue Pacific 547G 3904 2592G 7 ASCI Blue Pacific 547G 1952 1296G
この6と7の関係が分かりません。6のRmax はおそらく間違いではないかと?? まだ、そこまでしか実験してないのか、それとも政治的にSGIに花を持たせているのか。
ううむ、小柳義夫 |
ところが、現在公開されている1998年11月付のリストでは、ASCI Blue-Pacific CTRとして、6位にIBM設置の1952プロセッサが547 GFlopsで、8位にLLNL設置の1344プロセッサが468.2 GFlopsで載っている。公開後、いつか修正したようである。
その後1999年11月にはフルシステムで2.144 TFlopsを達成し2位を獲得している。このマシンは5856個のPowerPC 604eマイクロプロセッサを含みピークは3.9 TFlopsである。写真はLLNLのページから。
 |
5) ASCI (Blue Mountain)
11月にはASCI Blue MountainがLANLで 完成し、11月のTop500において、690.9 GFlopsで4位獲得した。SGI社はSC98会期中に記者会見を開き、「実はすでに1.61 TFlopsの性能を実測した」と発表した。Horst Simon(NERSC、元SGI社)から聞いた話では、LANLでは幾晩も徹夜したにもかかわらず、締め切りまでにはTFlops以下の値しか出なかったとのことである。1999年11月には1.608 TFlopsでASCI Blue Pacificに次いで3位に付けている。これは、6144個のMIPS R10000プロセッサを含む。
6) ASCI (White)
1998年2月12日に、DOEとIBMは10 TFlopsの性能をもつASCI Whiteを、$85Mの費用を掛け開発する契約を結んだ。
7) NSF PACI
1997年の歴史として述べたように、NSFのPACIプログラムはスーパーコンピュータセンターとしてSDSCとNCSCだけを残し、CTC (Cornell Theory Center)とPSC (Pittsburgh Supercomputer Center)の2センターはメジャーセンターに選ばれなかった。両センターには$11Mの予算が再転換のために付けられた。
CTCは全国レベルのセンターとしての役割を終了し、Cornell大学の学内センターに転換する。運営費用はNew York州から(年$1.2M)、およびIBMを含む企業やNIHから支援をうけ、あとは学内予算でまかなう。現在設置してあるIBM SP2/512は、新型のPOWER2チップ1個からなる160ノードのマシンに入れ替える。前センター長であったMalvin Kalosは責任を取ってか1998年7月LLNLに転任した。NSFの支援でCTCを利用していたユーザのファイル計13 TBは、5000本の磁気テープでSDSCに送られた(HPCwire 1998/4/3)。
PSCはDOEのASCIプロジェクトから$4.5Mの予算を得て、全国レベルのセンターにとどまることとなった。PSCに置かれていた3 TBのデータは、SDSCやNCSAに転送された。3月、NSFから$2.7Mの資金を得てネットワークの研究センター(National Center for Network Engineering)を設立し、次世代インターネットに関する技術開発や実装支援を受け持つこととなった。(HPCwire 1998/4/17)
NPACI(およびSDSC)の所長であるSid Karinは、5月、The NPACI International Affiliates Programを開始し、外国と連携する計画を発表した。11月には、アカデミック環境として初めてのTFlops級のIBP SPを導入する契約を公表した(HPCwire 1998/11/6)。2000年6月のTop500には、SP POWER3 222 MHzシステムが、コア数1152、Rmax=613.00 GFlops、Rpeak=1023.00 GFlopsとして16位にランクしている。その後、増強して11月には8位となる。
8) Next Generation Internet Research ACT of 1998(NGIR法)
1998年10月28日に、”Next Generation Internet Research Act of 1998, P.L. 105-305”が成立した。これはHigh Performance Computing Act of 1991を改正し、Next Generation Internet programのために、1999年度に$67Mを、2000年度に$75Mを計上する権限を与えるものである。目的として、以下の2点を挙げている。
(a) HPC, 人間中心のシステム、高信頼性システム、教育訓練、人材養成などに関係した研究プログラムを推進し、
(b) 連邦政府のネットワーク相互をつなぐ経済的で高速なネットワーク・インフラストラクチャを構築する
9) 社会科学でのスーパーコンピュータ利用
社会科学者はかねがね、政府が理工系にばかり(コンピュータの)予算を注ぎ込んでいて、自分たちの予算はあまりに少ないと文句を言ってきた。ところが、アメリカ政府は社会科学者に対し、スーパーコンピュータの無償利用を提供している。実はそれにもかかわらず、ほとんど利用されていないことが明らかになった。ある社会科学者はスーパーコンピュータは利用が難しいといい、他の者はデスクトップで十分だと言っている。(Chronicle of Higher Educatin, V. 45, No. 3, P.A25-27, Sept 11, 1998)
10) 禁輸措置
アメリカ商務省は、3月、50カ国へのスーパーコンピュータの輸出や再輸出の規制を発表した。その中にはインド、中国、イスラエル、パキスタン、ロシアなどが含まれる。しかし、5月に、IBM社のRS6000 SP2(ノード数不明)が、インドのBangaloreにある兵器研究所に対し輸出許可が出たことが報じられている。
日米貿易摩擦
1) 日本電気は連邦裁判所に提訴
日本電気は1998年6月、Cray Research社が日本電気に対して起こした反ダンピング訴訟に対し不公平な取り扱いを受けたことは、米国憲法修正第5条「大陪審の保障、二重の処罰の禁止、適正手続、財産権の保障」に反すると、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC、日本の高等裁判所に相当する巡回区控訴裁判所の一つだが、特許権、商標権、政府契約などに特化)に訴えた。日本電気は、反ダンピング手続きが始まる前から商務省が、UCARの契約を阻止することを目的として、日本電気がダンピングで有罪であると発表したことは、日本電気が公正で客観的な聴聞を受ける権利を否定されていると問題視した。商務省は偏見をもっているので、この問題を公正に処理する能力がなく、ダンピングがあるかどうかの判定は第三者によってなされるべきだと主張した。
9月、裁判所はこの訴えを退けた(HPCwire 1998/9/4)。日本電気は11月、連邦最高裁に上告し、CAFCの決定は外国に対して二重基準を作っていると論じた(HPCwire 1998/11/6)。
2) 国際通商裁判所の判決
日本電気は、1997年11月、ITC(International Trade Commission)の決定を不服として米連邦国際通商裁判所(The U.S. Court of International Trade)に訴えていたが、HPCwire 1998/12/18号は、共同通信の配信を引用して、国際通商裁判所が、日本電気と富士通がダンピングによってアメリカの産業に害を与えているという1997年9月の連邦政府ITCの判定を差し戻したと報じた。国際通商裁判所はITCに対し、申し立てられている事件について再調査し、90日以内に新しい判断を示すよう命令した。Donald Pogue判事は、Crayが日本の二社から実質的な損害を受けているという申し立てを却下し、ITCは間違った法的基準を適用していると述べた。1997年の判定には、矛盾が内包され、納得できない事実認定がなされていると判断した。
3) ITCの再裁定
これに対し、翌1999年3月、米国ITCは日本のスーパーコンピュータ販売はアメリカの製造会社に損害をもたらすと再び判断する(HPCwire 1999/3/5)。これについては1999年のところで述べる。
4) 日米スーパーコンピュータ協議
これと並行して日米スーパーコンピュータ協議が行われており、9月に終了した。この協議で、アメリカ側は「CPUの演算処理性能(ピーク性能)を要求要件とするのは、米国供給者を排除している。」と主張し、ベンチマークテストによる実効性能を要件とするよう要求があった。京都大学大型計算機センターの入札で、演算処理性能の条件でアメリカ企業が排除されたとの認識のようであった。落札したのは富士通のVPP800/63(Rmax=482.00、Rpeak=504.00 GFlops、1999年11月のTop500で15位)であった。
もう一つの論点は、現在5 GFlopsとなっている、スーパーコンピュータの性能基準であった。日本側は100 GFlopsを主張したが、アメリカ側は25 GFlopsを主張し、引き上げること自体は合意したが、数値については持ち帰って議論することになった。その後、1999年5月1日には50 GFlops以上となり、2000年5月1日には100 GFlops以上となる。何回か書いたが、経緯をまとめると。
|
政府調達におけるスーパーコンピュータの範囲 |
直前のTop500 Rmaxの対応順位 |
|
|
1987年8月1日 |
100 MFlops以上 |
|
|
1990年5月1日 |
300 MFlops以上 |
|
|
1995年4月1日 |
5 GFlops以上 |
121位 |
|
1999年5月1日 |
50 GFlops以上 |
113位 |
|
2000年5月1日 |
100 GFlops以上 |
102位 |
|
2005年5月1日 |
1.5 TFlops以上 |
197位 |
|
2014年4月16日 |
50 TFlops以上 |
500位以下 |
|
2019年12月23日 |
2.0 PFlops以上 |
158位 |
|
2020年12月23日 |
2.4 PFlops以上 |
163位 |
|
2021年12月23日 |
2.88 PFlops以上 |
177位 |
(導入手続きの性能基準は、Rmaxとは書かれていないが、もしギリギリの数値のRmaxのコンピュータがあったら、直前のTop500のどこに位置するかを記した。)
5) Bill Buzbee引退
11年前からNCARのSCD (Scientific Computing Division)に務めていたBill Buzbeeは、日本電気のSX-4の導入に熱心であったが、これまでの動きに失望し、1998年9月までに部長を辞職すると述べた。Buzbee Enterprisesというコンサルタント会社を設立した。2年間は上級研究員としてNCARに残る予定である。Bill Buzbeeは、LANLに25年間勤務したのち、1987年にBoulderのNCARに着任した。
SCDの職員に宛てられたメモの中で、「1998年はSCDの新しい部長を迎える好機であろう。SX-4は手の届かないところに行ってしまい、世界は超並列システムに移りつつある。」と述べた。Buzbeeは「2年前から1998年には引退しようと考えていた」とも述べた。NCARは、1998年5月末には128プロセッサのSGI Origin 2000(1998年6月のTop500で93位tie)を導入し、その後Cray J90を購入した。
6) 遠隔計算サービス
日本電気は、4月15日、海外ユーザ向けにSX-4のリモートコンピューティング・サービスを開始した。SX-4/32を府中事業所内に設置し、CPU使用1時間当たり$100で提供する。100時間以上の場合はさらに割引く。(HPCwire 1998/4/17) どの程度利用されたかは分からないが、1999年、NCARが地球温暖化のシミュレーションに使ったようである。
ヨーロッパの政府の動き
1) NIC(ドイツ)
John von Neumann-Institut für Computing (NIC)は1998年12月7日に開所した。1987年に設立されたHigh Performance Computer Centre (HLRZ)を継承するセンターである。このセンターは、Jülich にある3つのHelmholtz財団の研究センター、Deutsches Elektronensynchrotron DESY(ドイツ電子シンクロトン研究所)、 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung(ヘルムホルツ重イオン研究センター)が共同して設立した。HPでは1997年に設立とあるが、HPCwireによると1998年7月3日にDESYと研究センターが共同研究契約を結んだ。(HPCwire 1999/1/15)
アジアの政府関係の動き
1) インド(PARAM 10000)
インド政府電子情報省の研究機関であるC-DAC(Center for Development of Advanced Computing)は、Sun Enterprise 250サーバ(400 MHzのUltraSPARC II)をノードとして160台結合した PARAM 10000を開発した。ピークは6.4 GFlops。アメリカ商務省は、3月にインドなどに対するスーパーコンピュータの禁輸を発表したばかりであった。翌年3月、インド政府はすべての情報技術研究所にPARAM 10000を設置すると発表する。
2) シンガポールiHPC
シンガポール政府は1998年4月iHPC ((Institute for High Performance Computing)を設立した(Home pageでは8月となっている)。これは、シンガポール内唯一のスーパーコンピュータセンターであり、大学も、研究所も、政府機関も、軍もこの資源を用いていた。もちろん、独自の研究も行う。
この年、SGI Origin 2000 HPC systemを導入した。ピークは9.52 GFlopsである。
筆者は、1999年6月にiHPCの外部諮問委員を頼まれ、2002年8月まで務めた。現在では、スーパーコンピュータ資源提供センターとしての機能はA*STARに移り、iHPCは研究機関となっている。
世界の学界の動き
1) VIA
IEEE Micro 18, #2, pp. 66-76 (Mar/Apr 1998)に、D. Dunning (Intel)らはVIA (The Virtual Interface Architecture)を提唱した。これはユーザレベルのゼロコピー転送であり、Infiniband, iWARP and RoCE標準の基礎となった。仕様書が公開されている。one-sided communicationの一つである。
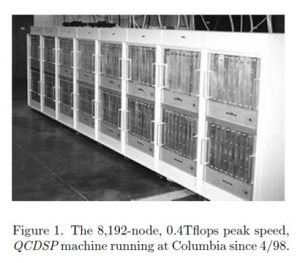 |
|
2) QCDSP
1998年4月、QCD専用計算機QCDSPが、Columbia大学(0.4 TFlops)とBNL (0.6 TFlops)に設置された。写真は、”Status of the QCDSP project” (arXiv:hep-lat/9810004v1)から。1999年10月、理研BNL研究センターはColumbia大学と共同で、QCDSPの後継機として10 TFlops級のスーパーコンピュータ開発に着手する。
3) NCSA(NTクラスタ)
Andrew Chien(UIUC)は、PACIの一環として256プロセッサのWindows NT搭載のクラスタを開発し、複雑な宇宙物理学の流体力学問題を解くことに成功した。このシステムは32台のCompaqワークステーションと、96台のHewlett PackardワークステーションをMyrinetで接続したものである。通信ソフトはChienが自分で開発した。このクラスタは、UIUCキャンパスで、1998年4月27日~30日に開催されたAlliance‘98(参加者900人)で披露された。NCSAは来年このクラスタを512プロセッサに増強する計画である。
4) LANL(Avalon)
LANLの理論天文学グループは68台のAlpha EV56搭載のPCを通信販売で買い、Avalonという名のクラスタを自作した。相互接続には3Comのネットワークスイッチを用いた。費用はわずか15万ドル。コア数68、Rmax=19.33 GFlops、Rpeak=72.48 GFlopsで1998年6月のTop500の314位を占めた。部品がそろってから3日で動いたと豪語していた。Top500史上はじめてのLinuxクラスタであった。後で述べるように、この年のGordon Bell賞の価格性能比部門で2位を獲得する。
自作のクラスタとしては、1997年に述べたように、UC Berkeleyのグループが開発したBERKELEY NOWが1997年6月のTop500に、コア数100、Rmax=10.14 GFlops、Rpeak=33.40 GFlopsで、344位にランクしている。これはSPARC 333 MHzのワークステーションを結合したもので、OSはSolarisであった。
5) Paderborn大学(Linuxクラスタ)
HPCwire 1998/12/18によると、1998年12月はじめ、ドイツのPaderborn大学は、汎用品(COTS)のLinuxクラスタで、LINPACK性能でどこまで性能を出せるか検討した。各社から570台のPCが提供されたが、その中でSamsungから提供された50個のAlphaからなるクラスタが、Linpackで27.993 GFlopsを達成した。しかし、直前の1998年12月のTop500で最高位のT90は、コア数32、Rmax=29.36、Rpeak=57.60 (GFlops) の219位でわずかに及ばない。そこで、これをHanoverの雑誌社Heiseに送り、そこでCPUを600 MHzから666 MHzに取り替え、ホストの1台を含めて17×3にFast Ethernetで接続した。スイッチはHewlett-Packard社製。Linpack性能で30.09 GFlopsを計測し、見事T90を抜いた(Rpeak=68 GFlops)。Top500では210位に相当する。最適化はまだ十分ではない。一番大変だったのは消費電力(10-12 KW)で、フューズが飛ばないよう工夫し、冷却(空冷)も大変だった。総費用は100万マルク(約7500万円)であった。
1999年6月のリストでも361位に相当するが、リストには出ていない。測定後解体したのであろう。T3EでなくT90と比較したところが味噌と言える。
6) GMD (PowerMANNA)
ドイツのGMDのFIRST (Forschungszentrum für Innovative Rechnersysteme und –technologie, English: Research centre for innovative computer systems and technologies)は1990年ごろからi860を用いた超並列コンピュータMANNA (Massively Parallel Architecture for Numerical and Non-numerical Applications)の研究開発を始めていたが、1998年、GMDのThe Institute for Computer Architecture and Software Technologyは、世界初の64ビットPowerPCチップであるMotorola製のMPC620プロセッサを用いた並列コンピュータPowerMANNAを開発した。2000年1月8日~12日にフランスのToulouseで開催されたHPCA-6(IEEE Symposium on High-Performance Computer Architecture)で発表されている。
7) 実問題でのTeraflops達成
PSCのYang Wangらのグループは、1480プロセッサのT3Eを用いて、LSMS(the locally self-consistent multiple scattering)法により磁性のシミュレーションを実行し、11月9日1.02 TFlopsの実効性能を達成した。(HPCwire 1998/12/4)
 |
|
8) AEARU CS(台北)
東アジア研究型大学協会 AEARU (The Association of East Asian Research Universities)は1996年1月に創立された地域大学連合であり、東京大学は最初からのメンバであった。日本からは他に京都大学、大阪大学、東北大学、筑波大学、東京工業大学が加盟している(当時)。全体で17校。1996年10月に、東京大学の蓮實重彦副学長から理学部長を通して連絡があり、1998年4月16日~17日にコンピュータ科学関連の集まり(AEARU CS Meeting)があるので出席せよとのことであった。会場は台湾新竹市の國立清華大學 (National Tsing Hua University)であった。
参加者は、中国、香港、台湾、日本から計12名であった。日本からは筆者の他都倉信樹(大阪大学)が参加した。代表を送らなかったのは、KAIST(韓国)、POSTECH(韓国)、Seoul国立大学(韓国)、筑波大学、東京工業大学であった。大部分の参加者は中国語圏で、ときどき中国語での議論になってしまうので文句を言った。学部レベルの交流は現実的ではなく、大学院レベルおよび若いスタッフの交流について努力しようという結論になった。
企業と大学の関係についても議論になり、筆者は1997年4月から日本で適用された国立大学と民間企業との兼業の新しいルールについて報告した。各国事情はさまざまで、香港のようにアメリカと同様なやり方のところもあるし、ある国のように公式には企業から給料はもらえないが、実際は under the table だ、というところもあった。またある国では、教授が(実質上)作った会社の大半は潰れてしまったとか。
余談であるが、実は前月(3月15日~18日)にも台湾の台北に出かけた。研究室の台湾からの留学生(修士)H君の結婚式に出席するためである。家内と出かけ、こちらの旅費の心配はしなくてもいいから、台湾式の結婚式次第を全部見せてくれと頼んだ。新郎が友人達と車(偶数台、しかも4や8は不可)を連ねて新婦を迎えに新婦宅にでかける「猟妃行列」まで全部参加した。猟妃行列が新婦を乗せてまさに新婦宅を出ようとするとき、新婦の母親が泣きながら陶器の皿を地面にたたき付けた。何事かと思ったら、「覆水盆に返らず」みたいなものだ、と誰かが解説してくれた。新婦が扇を捨てるという儀式もあるそうだ。
新郎宅では男だけで出迎え(儒教文化か?)、新郎新婦はまず家の孔子廟に詣で祖先に報告する。その後はみな出てきてその場で宴会。午後にはホテルで披露宴があった。台湾(中国も同じか?)では乾杯は本当に杯を空にしなくてはならないというぐらいは知っていたが、会場に行ってまずびっくり。ひな壇があって新郎新婦が座るのかと思っていたら、ひな壇のところは演台になっていて、来賓や親族があいさつする間、新郎新婦は立ったまま。私もあいさつした(留学生が通訳)が、気が気でないので手短にすませた。しかし、新郎の父が酔っ払って長話を始めた。中国語はわからないが、「一足す一は二ではなく、三にも四にもなる」とか言っていたらしい。娘(新郎の姉)が早くやめろとサインを送っていた。挨拶がすべて終わると、ひな壇が作られ、新郎新婦が座った。それからは純粋の台湾式宴会であった。新郎の受ける盃には、老酒ではなくウーロン茶が注がれていた。翌日は、日本語のできる運転手のタクシーを頼んで、家内と一日中台北周辺を回った。
次回は国際会議。日本の研究者を中心に省電力CPUに関する国際会議COOL Chips Iが開催され、その後継続的に開催される。3回目のHPC Asia 98は、シンガポールで開催されたが、アジア通貨危機が影を落としていた。6月のTop500ではT3Eが多数登場し上位を独占する。
 |
 |
 |


1件のコメントがあります
Blue Pacific についてのAl Gore のアナウンスについて、
簡単に検索できたものは以下の3つです。最後のUPIの記述が最も長くて詳しいです。
—————–
https://www.ibm.com/ibm/history/history/year_1998.html
Blue Pacific – the world’s fastest computer U.S. Vice President Al Gore announces Blue Pacific – the world’s fastest computer – which is jointly developed by the U.S. Energy Department’s Lawrence Livermore National Laboratory and IBM, can perform 3.9 trillion calculations per second (15,000 times faster than the average desktop computer) and has over 2.6 trillion bytes of memory (80,000 times more than the average PC). It would take a person using a calculator 63,000 years to perform as many calculations as this computer can perform in a single second.
—————-
https://www.computerhope.com/history/1998.htm
U.S. Vice President Al Gore announced Blue Pacific, the world’s fastest computer jointly developed by the U.S. Energy Department’s Lawrence Livermore National Laboratory and IBM. Blue Pacific can perform 3.9 trillion calculations per second (15,000 times faster than the average desktop computer) and had over 2.6 trillion bytes of memory (80,000 times more than the average PC). It would take a person using a calculator 63,000 years to perform as many calculations as this computer can perform in a single second.
—————-
https://www.upi.com/amp/Archives/1998/10/28/US-announces-new-fastest-computer/8900909550800/
U.S. announces new fastest computer
By PAUL BASKEN | Oct. 28, 1998
WASHINGTON, Oct. 28 — Vice President Al Gore hosted a group of the nation’s high-tech industry executives at the White House to announce the creation of a new supercomputer capable of record processing speeds. Gore said today the new ‘Blue Pacific’ machine can handle an unprecedented 3.9 trillion calculations per second, although most of that power will be reserved for classified military applications rather than for such civilian purposes as medical research, environmental protection and weather forecasting. The computer, developed by IBM and the Energy Department’s Lawrence Livermore National Laboratory, is powered by a series of 5,800 ‘PowerPC’ computer processors connected in a package with more than 4 miles of wiring. Gore said the new $96 million computer, packed with 2.5 trillion bytes of memory, ‘will lead to advances in, and greater understanding of, medicine, manufacturing, aviation safety and global climate change.’ However, Energy Secretary Bill Richardson, who joined Gore during the announcement, noted the computer’s full power of 3.9 trillion calculations per second will be reserved only for the department’s work with the Pentagon in nuclear weapons simulations. A portion of the computer with less than a quarter of the speed and memory will be used for other unclassified calculations such as scientific research involving health care, the environment, weather and aviation safety. Richardson suggested the scientific users were satisfied with the arrangement, saying, ‘Our objectives are fulfilled.’ But Nick D’Onofrio, senior vice president for technical manufacturing at IBM, said ‘more needs to be done’ in helping non-military users.
The new computer is the second in a series being developed by the Energy Department with the goal of reaching 100 trillion calculations per second by the year 2004. The department’s previous record-holder, called ‘Option Red,’ hit the 1 trillion calculations per second mark in 1996. Gore also took time during the briefing to highlight two pieces of legislation signed into law by President Clinton. One bill provides funding for a ‘next generation’ Internet that will run 1,000 times faster than the current system, and the second implements U.S. aspects of an international treaty on extending copyright protections to digital matter. —
Copyright 1998 by United Press International. All rights reserved. —
——————————————–