新HPCの歩み(第200回)-2003年(c)-
|
これまでのJSPP(1989年~2002年)に代わって新しいシンポジウム SACSISが始まった。広域ファイルシステムGfarmがオープンソフトウェアとして4月26日公開された。京都大学はFUJITSU PRIMEPOWER HPC2500から成るスカラSMP型のスーパーコンピュータをベクトルの更新で設置した。 |
日本の大学センター等
1) 北海道大学(情報基盤センター設立、SGI Onyx 300)
北海道大学は2003年4月、大型計算機センターおよび情報メディア教育研究総合センターを廃止・転換し、情報基盤センターを設立した。11月には情報基盤センター設置記念式典および記念講演会が挙行された。
これに先立つ3月4日、日本SGIは北海道大学大型計算機センターに、グリッドコンピューティング専用機として「SGI Onyx 300」を納入し、本番稼働が始まったと発表した。ITmediaによると、文部科学省が実施している「eサイエンス」計画に基づいて、全国7つの全国共同利用情報基盤センター(旧大型計算機センター)で始まった、グリッドコンピューティング研究基盤の一部となる。北大計算機センターでは、特に先端科学技術計算における大規模可視化処理の遠隔実行に必要なグリッドコンピューティング適したサービスを提供するという。
2) 東北大学(SX-7)
東北大学情報シナジーセンターは、前年12月からSX-7の試験運用を行っていたが、2003年1月、SX-7の正式運用を開始した。SX-7以降はTop500に登録していない。HPC Challenge benchmarkには登録している(ITmedia 2004/12/21)。
3) 東京大学(iMac)
東京大学は9月24日、情報基盤センターの教育用パソコンとしてApple社のiMacを選定したと発表された。2004年3月から駒場第一と本郷と柏の3カ所に計1400台を設置する。ディスクレスの1 GHzのG4が1150台で、ピークは4 TFlopsになる。サーバもアップル社製。1000台を超える受注は日本では初めてとのことである。前回「科学技術振興調整費「新興分野人材養成」」の項で述べた、パソコン720台を司令塔なしで連携させる実験はこのパソコンを用いたと思われるが、Big MacのようなTop500へのチャレンジはしなかった。
9月ごろアップルコンピュータ社の法人営業部からビデオ取材をしたいという依頼があり、22日に撮影部隊がやって来た。筆者は現在Macのユーザではないが、iMacに搭載されているPowerPCが、実は世界トップクラスのスーパーコンピュータであるASCI Blue Pacificのエンジンなのだということをしゃべってくれとのことであった。
4) 京都大学(PRIMEPOWER HPC2500)
京都大学の学術情報メディアセンターは10月16日、富士通のスーパーコンピュータシステムを納入すると発表した。同システムは、ベクトルコンピュータVPP800の後継で、計算ノードとして対称型マルチプロセッサ(SMP)構成で、CPUはSPARC V9アーキテクチャに準拠したSPARC64 GP(1.56 GHz)を 128 基搭載したFUJITSU PRIMEPOWER HPC2500(2002年発表)を11台と、I/Oノードとして64 CPUを搭載した同装置1台を高速接続する。スカラSMP型のスーパーコンピュータが国立大学に納入されるのは初めて。Linpack測定ではI/Oノードを含めすべてを計算ノードとして用い、コア数1472、Rmax=4.552 TFlops、Rpeak=9.185 TFlopsで、初登場の2004年6月のTop500では24位にランクしている。
毎日新聞11月23日に「宇宙発電:京大がスパコン購入、実用化に向け加速」という記事があったので、宇宙太陽光発電でスパコンに電力を供給するのかと思ったら、スーパーコンピュータを購入して宇宙送電の精密なシミュレーションを行うということであった。京都大学宙空電波科学研究センター(2004年4月からは生存圏研究所)はPRIMEPOWERを2004年1月から導入予定である。
5) 大阪大学
大阪大学サイバーメディアセンターは、2002年からバイオグリッド基盤システムを運用しているが、2003年1月、サイバーメディアセンター吹田地区にデータグリッド基盤システムが整備された。このシステムは、データグリッド蓄積・解析・表示システム(CAVEシステム)小型ドーム表示システム、多人数視点共有立体表示システム、超高圧電子顕微鏡用高精細画像撮影装置、及びこれらの装置とスーパーコンピュータを接続する高速ネットワーク装置で構成されている。
6) 筑波大学
2003年4月、つくばWANに接続し、運用を開始した。
7) 福島大学
2003年4月、福島大学総合情報処理センターが設置される。
8) 奈良女子大学
2003年4月、奈良女子大学情報処理センターを総合情報処理センターに改組。
9) 鹿児島大学
2003年4月、学術情報基盤センターを設置した。
10) 岡崎国立共同研究機構(NEC SX-7+NEC TX7)
計算科学研究センターでは、2003年、汎用計算機枠のIBM SP2とNEC SX-5を、日本電気製NEC SX-7(32 CPU)とNEC TX7(64 CPU)とに更新した。TX7は、Itanium 2を搭載したサーバである。
11) 核融合科学研究所
核融合科学研究所(岐阜県土岐市)は、SX-7/160M5を導入した。2003年11月のTop500では、コア数160、Rmax=1378.00 GFlops、Rpeak=1412.80 GFlopsで81位にランクしている。
日本の学界の動き
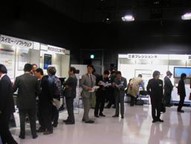 |
|
1) PCクラスタコンソーシアム
2003年2月20日~21日、日本科学未来館において、第二回PCクラスタシンポジウムを開催した。プログラムは以下の通り。写真は企業展示(コンソーシアムのページから)。
2月20日ワークショップ(会員のみ)
|
10:30 |
オープニング (年次報告) |
石川 裕 (PC クラスタコンソーシアム会長) |
|
11:00 |
招待講演 Myrinet Overview&Technology Roadmap |
Chuck Seitz (Myricom 社) |
|
13:30 |
合同部会/パネル討論 部会活動報告&コンソーシアムの今後の活動について |
|
|
17:30 |
懇親会 |
|
2月21日シンポジウム(一般)
|
10:30 |
オープニング・PCクラスタコンソーシアム活動紹介 |
石川 裕 (PC クラスタコンソーシアム会長) |
|
11:00 |
基調講演 Gridコンピューティングの最新動向とNaReGiプロジェクト |
三浦 謙一 (九州大学情報基盤センター客員教授) |
|
13:45 |
SCoreクラスタ導入事例・応用事例・今後の取り組み 13:45~14:05 株式会社ソフトウェアクレイドル SCoreを用いたSTREAM及びSCRYU/Tetraのパラレル化 技術部 黒石浩之 14:05~14:25 三菱プレシジョン株式会社 PCクラスタ技術を用いた並列映像発生 開発統括部 画像情報グループ 劉学振 14:25~14:45 住商エレクトロニクス株式会社 クラスター適用事例「鋳造解析ソフトAGMASOFT」 奥村 俊明 14:45~15:05 日本ヒューレット・パッカード株式会社 HP PCクラスタへの取り組み HP IAクラスタ製品 中野 守 15:05~15:25 富士通株式会社 PC クラスタへの取り組み 工内 隆 15:25~15:45 日本電気株式会社 拡がる適用領域~PCクラスタの現状と今後 中西 浩一 |
|
|
16:00 |
招待講演 汎用プラットフォームを使用した High Performance Computing |
廣田洋一 (Intel 社) |
2003年12月11日~12日には、日本科学未来館において、「第三回PCクラスタシンポジウム業務に浸透するPCクラスタ」を開催した。プログラムは以下の通り。
12月11日テクニカルセッション
|
10:30 |
オープニング |
石川 裕 (東京大学) |
|
10:50 |
SCore入門 |
原田 浩 (日本ヒューレット・パッカード株式会社)
|
|
13:00 |
(セッション1a, 1b の同時並行になります) |
|
|
|
セッション1a SCRYU/Tetraを用いた大規模解析 |
黒石 浩之(株式会社ソフトウェアクレイドル) |
|
|
セッション1b SunGridEngine |
山下 晃弘 (NECシステムテクノロジー株式会社) |
|
13:50 |
(セッション2a, 2b の同時並行になります) |
|
|
|
セッション2a 大規模解析・精度改善のための、RADIOSS機能開発・並列性能向上に関して |
依知川 哲治(メカログジャパン株式会社) |
|
|
セッション2b PCクラスタの運用管理とバッチシステム |
住元 真司 (富士通研究所) |
|
15:10 |
(セッション3a, 3b の同時並行になります) |
|
|
|
セッション3a クラスタプラットフォームとPAM-CRASH 2G
|
新関 浩(日本イーエスアイ株式会社) |
|
|
セッション3b 新しい SCore のアプリケーション |
堀 敦史(スイミー・ソフトウェア株式会社) |
|
16:00 |
PCクラスタプラットフォームの動向 |
|
|
|
HPCテクノロジーへの挑戦 |
池井 満(インテル株式会社) |
|
|
HPC 向けプロセッサAMD Opteron™の紹介 |
Dave Jessel(日本AMD株式会社) |
|
17:30 |
懇親会 |
|
12月11日一般セッション
|
10:30 |
オープニング |
石川 裕(東京大学) |
|
11:00 |
基調講演 そのとき歴史は動いた? 理研の選択:ベクトル並列機からPCクラスタへの転換 |
姫野龍太郎(理化学研究所) |
|
13:30 |
SCoreクラスタ導入事例・応用事例・今後の取り組み |
|
|
13:30 |
HPCサーバに対する取り組み |
竹内義晴(日本電気株式会社) |
|
13:50 |
富士通のPCクラスタへの取り組み |
久門耕一(富士通株式会社) |
|
14:10 |
SCoreのOpteronへのポーティング |
堀 敦史 (スイミー・ソフトウェア株式会社) |
|
14:30 |
画像合成装置を用いたPCクラスタにおけるシミュレーションと可視化の同時処理に関する研究 |
片野 康生 (三菱プレシジョン株式会社) |
|
14:50 |
HPのPCクラスタへの取り組み
|
中野守(日本ヒューレット・パッカード株式会社) |
|
16:00 |
パネル討論:「PCクラスタのセンタ運用」 司会: 石川 裕 (東京大学) パネリスト: 松岡 聡(東京工業大学) 朴 泰祐(筑波大学) 黒川 原佳(理化学研究所) 工藤 知宏(産業技術総合研究所) |
|
2) Gfarm
産業技術総合研究所の建部修見らが開発した広域ファイルシステムGfarm version 1.0 b1がオープンソフトウェアとして4月26日公開された。PCクラスタのローカルディスクを利用して広域ファイルシステムを構築し,グリッドにおける大規模データ処理環境を提供する。Gfarmシステムは,耐故障性向上,負荷分散のためにファイル複製をサポートし、さらに,長距離高速ファイル転送をサポートしている。2002年の SC2002 国際会議において米国から日本へ,それぞれ 4ノードを利用して,理論最大性能 893 Mbps のところ 741 Mbps のファイル転送性能(当時世界最高)を達成した。
2003年11月25日、Gfarm version 1.0を正式に公開した。
3) アドバンスト並列化コンパイラ技術プロジェクト
笠原博徳早稲田大学教授は、2000年9月8日から行っていたアドバンスト並列化コンパイラ(APC)技術プロジェクトを2003年3月に終了した。これは官民共同研究ミレニアムプロジェクトIT21の一部として、新エネルギー・産業技術総合機構(NEDO)からの委託により、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)がアドバンスト並列化コンパイラ技術研究体を組織して進めてきたものである。2月28日讀賣新聞朝刊には「コンピューター並列で処理速度10倍に」「最新鋭のコンピューターより10倍以上速く演算処理ができるソフトを開発したとあり」、まるで400 TFlopsも出るような書きぶりであった。よく読むと、「この並列化コンパイラを使って、16台のCPUで、1台より10.7倍性能向上を実現した」というだけのことであった。
3月20日に早稲田大学理工学部で終了シンポジウムが開催された。プログラムは以下の通り。
|
10:00-10:10 |
開会の挨拶 |
JIPDEC 児玉幸治会長 |
|
10:10-10:15 |
来賓のご挨拶 |
METI |
|
10:15-10:20 |
来賓のご挨拶 |
NEDO |
|
10:20-11:00 |
研究成果概要報告 |
早稲田大学 笠原博徳教授 |
|
11:00-11:50 |
基調講演 |
国際アドバイザリーボード委員長 Prof. David Padua |
|
13:00-13:45 |
技術報告1: アドバンスト並列化コンパイラ技術の開発 |
|
|
13:4514:15 |
招待講演1 |
Prof. Francois Irigoin |
|
14:30-15:15 |
技術報告2: アドバンスト並列化コンパイラ技術の開発 |
|
|
15:15-15:45 |
招待講演2 |
Prof. Monica Lam |
|
16:00-16:30 |
技術報告3: 並列化コンパイラの性能評価技術の開発 |
|
|
16:30-17:00 |
招待講演3 |
Prof. Rudolf Eigenmann |
|
17:10-18:40 |
本プロジェクトの成果活用戦略 |
笠原博徳、富士通、日立 |
|
18:40-18:45 |
閉会の挨拶 |
|
|
12:00-20:00 |
ポスター&デモ(55号館N棟1階大会議室) |
|
7月14日の事後評価でも評価委員長を拝命した。評価委員は以下の通り。
|
委員長 小柳義夫 |
東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 |
|
佐藤三久 |
筑波大学 電子・情報工学系 教授 |
|
関野正明 |
日本ベンチャーキャピタル株式会社 ゼネラルマネージャー |
|
竹内裕明 |
先端起業科学研究所 所長 |
|
姫野龍太郎 |
理化学研究所 |
|
渡瀬芳行 |
高エネルギー加速器研究機構 計算科学センター長 |
8月28日付でweb上に公開された評価書に、委員の個別のコメントが名前付きで掲載されており、異例であった。委員長は知らなかった。
4) 固体素子量子コンピュータ
2003年2月20日、理化学研究所と日本電気は、世界で初めて固体素子で構成される2個の素子を結合した実験で、量子エンタングルメントを実現したと発表した。蔡 兆申(ツァイ・ヅァオシェン) NEC基礎研究所主席研究員/理研フロンティア研究システムチームリーダー(巨視的量子コヒーレンス研究チーム)が主導する研究グループの成果である。Natureの2月20日号に掲載された。(日本電気Press release 2003/2/20)(HPCwire 2003/2/21)
5) 高エネルギー加速器研究機構
2003年4月には、シミュレーション研究とコンピュータとを一体化するために、機構長の下に「大型シミュレーション研究推進委員会」を設立した。筆者も外部委員の一人に指名された。当初の外部メンバーは、宇川彰、岡眞、小柳義夫、常行真司、大原謙一、大川正典、東島清であった。
6) Tron
4月15日21:15からのNHK番組でTronの坂村健氏が取り上げられた。地球シミュレータ番組は教育テレビであったが、これは総合テレビのProject-Xであった。坂村氏がアメリカの圧力をはねのけてTronを組み込みOSとして再興した英雄として描かれていた。
7) ACS論文誌
2000年8月、「情報処理学会論文誌:ハイパフォーマンスコンピューティングシステム」(HPS)1号が発行されたが、これを発展させて、2003年度から「情報処理学会論文誌コンピューティングシステム」(IPSJ Transactions on Advanced Computing Systems)(ACS)が発刊された。本論文誌は,ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)研究会,計算機アーキテクチャ(ARC)研究会,システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS)研究会が編集/財務責任研究会となり,プログラミング(PRO)研究会が編集責任研究会として協力する形で刊行されている。
8) IBMメインフレーム互換機
「情報処理」の2003年4月号に掲載された『プラグコンパティブル・メインフレームの盛衰(2)』(高橋茂)では、例のIBM産業スパイ事件(1982年6月22日)に触れていた。日立は悪辣なおとりにひっかった被害者だという論調であった。ちょっとビックリしたのは、日立を裏切ってIBM社に通報したPalyn(ペイリン)社の社名は、社長のPaleyと副社長のFlynnの名前を組み合わせたものだということである。あの「Flynnの分類」のMichael Flynn教授であった。
9) 東京工業大学(Presto III)
HPCwireによると、東工大の松岡研究室はVoltaire社のInfiniBandを用いたPCクラスタPresto IIIを構築した。日本でのInfiniBandは初めて。(HPCwire 2003/11/14)
10) 『磁力と重力の発見』
大学の研究室の先輩である山本義隆氏が科学史に関する3巻にわたる大著『磁力と重力の発見』をみすず書房から5月に出版し、パピルス賞と毎日出版文化賞の両方を受賞した。11日15日、関係者が「つきじ植村」で受賞記念のパーティーを開いた。万有引力の法則というと今なら小学生でも知っているが、離れた物体の間に力が働くなんて「魔術」だ、というのがニュートン当時の常識であった。ニュートンが、当時唯一知られていた遠隔力である磁力とのアナロジーから万有引力の概念を構築する過程を、原典に即して記述している。『岩波キリスト教辞典』(2002)で「魔術」という項を執筆したが、この本を読んでいたらよかったのにと後悔した。それほど外れてはいなかったが。
国内会議
1) HPCS 2003(日本科学未来館)
第2回に当たるHPCS2003(2003年ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム)が、1月20日(月)~21日(火)に、東京台場の日本科学未来館 みらいCANホールで開催された。主催は情報処理学会HPC研究会。招待講演としては奥田洋司(東京大学)「GeoFEM開発の経験から」と、Charlie Catlett(ANL)「TeraGrid: A Case Study Customer for Global Grid Forum」があった。Catlett氏はGGFのChairでもある。実行委員長は関口智嗣(産総研)、副実行委員長は佐藤三久(筑波大)、プログラム委員長は福井義成(理研)、副プログラム委員長は須田礼仁(名大)であった。筆者は2003年~2008年のHPCSアドバイザリ委員を務めた。計算科学(computational sciences)と計算機科学(computer science)の交流を目指すシンポジウムなので、論文募集に際して以下のような注意を記した。
|
「本シンポジウムは「高性能計算」をキーワードの要と位置付け,計算科学と応用分野との間でのニーズ・シーズの情報交換や応用分野間での計算機利用技術の情報交換などを目的としております.論文を記述する際には以下の各点にご注意下さい. ・応用分野での成果に関する論文では,実装手法や評価条件(ハードウェア・ソフトウェア)について明確に記述して下さい. ・計算機科学に関する論文では,アプリケーションへの適用可能性や有用性について明確にして下さい.」 |
2) 21世紀COEプログラム(東大山上会館、湘南国際村)
東大情報理工学系研究科では、2002年に採択された21世紀COEプログラム「情報科学技術戦略コア」では、2003年1月21日~24日に東大山上会館において、 「応用離散数学シンポジウム — ロバスト最適化に向けて」を開催した。
2月28日~3月2日には、IPC生産性国際交流センター(神奈川県葉山町湘南国際村)において、国際シンポジウムWRSC2003: Workshop on Robust Software Constructionを開催した。
3) 第2回PCクラスタシンポジウム(日本科学字来館)
「日本の学界」で述べたように、PCクラスタコンソーシアムは、2003年2月20日~21日、日本科学未来館において、第二回PCクラスタシンポジウムを開催した。
 |
|
4) HOKKE 2003(イノベーションプラザ北海道)
HOKKE 2003(第10回「ハイパフォーマンスコンピューティングとアーキテクチャの評価」 に関する北海道ワークショップ)は、北海道大学キャンパスの北隣にできたばかりの科学技術振興事業団研究成果活用プラザ北海道「イノベーションプラザ北海道」セミナー室を会場として、2003年3月10日(月)~12日(水)に開催された。この会場は筆者が見つけてきたもので、タダの上、設備はよかったが、収容人員がイスを足しても120人で不足であった。2013年からは北海道立総合研究機構本部となっている。懇親会は、中島公園のキリンビール園。
これまでのHOKKEではHPC研究会とARC研究会の合同発表会という形を取っていたが、発表申し込みが予想外に多く、部屋も狭いので、開催期間を1日延長し、両研究会の連続開催という形を取った。すなわち、3月10日9:00から3月11日13:00は第144回計算機アーキテクチャ研究会(発表27件)、3月11日(火)14:00から12日(水)18:25は第93回ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(発表29件)となった。この間、札幌では最高気温が零下の日もあり寒かった。
ワークショップの最中に理化学研究所脳科学総合研究センター・グループディレクターの松本元氏(元、電総研)の訃報(亡くなられたのは3月9日)が伝えられた。会場ではこっそりメールを見ていた人が多く、同時にため息が漏れた。
5) グリッド研究会(高エネルギー加速器研究機構)
高エネルギー加速器研究機構では、2003年3月10日~11日に「高エネルギー物理データグリット研究会」を開催した。CERNなどの例からも分かるように、高エネルギー物理学はグリッドのheavy userである。HOKKE 2003と重なっていたが、松岡聡(東工大)、建部修見(産総研)らも長時間の発表(講義)を行った。
6) つくばWANシンポジウム(エポカルつくば)
3月13日、エポカルつつくばにおいて「第3回つくばWANシンポジウム」が開催された。
7) INSAMシンポジウム(広島大学)
広島大学理学部大規模非線形数値実験室(Institute for Nonlinear Sciences and Applied Mathematics: INSA)は、2003年3月14日、広島大学理学部において、INSAMシンポジウム2002を開催した。プログラムは以下の通り。
|
13:00-13:05 |
あいさつ |
|
|
13:05-14:00 |
『地球シミュレータが科学のパラダイムを変える』 |
佐藤 哲也(地球シミュレータセンター長) |
|
14:00-14:55 |
『地球シミュレータ上での大気・海洋結合モデルによる気候変動予測』 |
高橋 桂子(地球シミュレータセンター) |
|
14:55-15:10 |
休憩 |
|
|
15:10-16:05 |
『地球惑星科学と大規模数値シミュレーション』 |
濱野 洋三(東京大学) |
|
16:05-16:30 |
ポスターインデクシング |
|
|
16:30-18:00 |
ポスターセッション |
|
|
18:00-20:00 |
懇親会 |
|
8) HAS研(日立大森第二別館、ホテルエドモント)
HAS研(Hitachiアカデミックシステム研究会)は、2003年3月27日、日立大森第二別館において、第6回AT分科会(テーマ「3次元疑似空間に表現できる科学・教育・エンターテイメント」)・平成15年度総会を開催した。プログラムは以下の通り。
|
11:00 |
「没入型3次元可視化装置による科学コンテンツ -CAVE研究会より」 |
井門 俊治(埼玉工業大学) |
|
13:00 |
「コンピュータに地球と宇宙を再現:バーチャル地球磁気圏システムと分散データベース」 |
村田 健史(愛媛大学) |
|
14:00 |
「デジタルロストワールド:古代の生態系を電子空間に再現する」 |
宇佐見 義之(神奈川大学) |
|
15:10 |
「立体映像をみんなで見るための仕組み」 |
北村 喜文(大阪大学) |
|
16:10 |
「日立シミュレーションライドシステムの紹介」 |
松隈 信彦(日立) |
|
16:40 |
平成15年度総会 |
|
|
17:00 |
懇親会 |
|
また、8月29日には、ホテルエドモント(飯田橋)において第18回研究会を開催した。テーマは「仮想環境と実世界の橋渡し=最新の人工現実感技術とその高等教育への応用=」。プログラムは下記の通り。
|
11:00 |
「日立ウェアラブルIA - 高精細・大画面のウェアラブルコンピュータ」 |
海老名 修(日立) |
|
13:00 |
「バーチャル・リアリティによる教育手法の研究」 |
杉本 裕二(メディア教育開発センター) |
|
14:10 |
「現実世界と仮想世界を融合した複合現実型情報強化環境」 |
横矢 直和(奈良先端大) |
|
15:40 |
「実世界マルチメディア情報媒介システム」 |
坂内 正夫(東京大) |
|
17:00 |
懇親会 |
|
9) 数値解析シンポジウム(小涌園)
第32回の数値解析シンポジウムは5月21日~23日に箱根ホテル小涌園で開催され出席した。担当は東京理科大学矢部研究室で、参加者は107名。
10) SACSIS 2003(学術総合センター)
これまでのJSPP(1989年~2002年)に代わって2003年から新しいシンポジウム SACSIS (Symposium on Advanced Computing Systems and Infrastructures) が開催された。第1回のSACSIS 2003は2003年5月28日(水)から30日(金)まで、国立情報研と同じビルの、学術総合センター会議場で開催された。主催は、情報処理学会からは計算機アーキテクチャ研究会、システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会 、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会 、プログラミング研究会 、アルゴリズム研究会、電子情報通信学会からはコンピュータシステム研究専門委員会とデータ工学研究専門委員会、協賛は電子情報通信学会のディペンダブルコンピューティング研究専門委員会であった。組織委員長は中島浩(豊橋技科大)、副委員長は木村 康則(富士通研)、総務委員長は竹房あつ子(お茶の水)、プログラム委員長は横川三津夫(産総研)であった。
基調講演は、萩谷 昌巳(東大)「分子コンピューティング ─計算機科学者から見たナノテクノロジーと分子エレクトロニクス─」、招待講演はTim Kindberg (HP Lab.)「The next 700 billion smart physical objects」であった。チュートリアルは高田 広章(名大)「組込みシステム開発の現状と課題」と丸山 宏(日本IBM)「XMLとWebサービスにおけるセキュリティの最新動向」であった。口頭発表42件と、ポスター発表29件があった。ポスター発表のうちの5件はデモンストレーション付きで発表された。
11) NEC・HPC研究会(NEC本社ビル)
2003年7月3日に、NEC本社ビル地下1階講堂で、第17回NEC・HPC研究会が開催された。プログラムは大略以下の通り。
|
基調講演「超高速コンピュータ網形成プロジェクト(NAREGI)とナノサイエンス・シミュレーション」 |
(九州大、青柳睦) |
|
「Grid Computingの可能性- 星間分子の超精密計算とポリペプチドの量子分子動力学計算 -」 |
(産総研、長嶋雲兵) |
|
「自動車開発におけるCAE(CFD)の現状と今後」 |
(ダイハツ、栗山利彦) |
|
「NECのHPC向けGridソリューション」 |
(NEC、高原浩志) |
|
「並列Linuxクラスタの運用管理ソリューションのご紹介」 |
(NEC、中西浩一) |
12) 超並列計算研究会(日本HP市谷営業所)
2003年7月4日、第34回超並列計算研究会が日本ヒューレット・パッカードの市谷事業所で開催された。
13) SWoPP2003(松江テルサ)
16回目となるSWoPP松江2003(2003年並列/分散/協調処理に関する『松江』サマー・ワークショップ)は、2003年8月4日(月)から6日(水)まで松江テルサを会場に開催された。参加者募集には
「今年の開催地は宍道湖、怪談の小泉八雲、不昧公好みの和菓子で知られる山陰の古都、島根県松江市です。北は函館、南は那覇まで全国各地で開催されてきた SWoPP ですが、山陰地方で開催されるのは今回が初めてです。」
とあった。主催は、電子情報通信学会のコンピュータシステム研究会,ディペンダブルコンピューティング研究会、情報処理学会の計算機アーキテクチャ研究会、システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会、プログラミング研究会、システム評価研究会である。初日8月4日の前日には、松江の夏のイベント『水郷祭』の一環として、宍道湖上で6,000発の花火が打ち上げられ、38万人の人出で賑わった。船からの移動水中花火や、200本の手筒花火など見事であった。
14) IC2003(電気通信大学)
第8回目となるIC2003(インターネットコンファレンス2003)は、財団法人インターネット協会 (IAjapan)、日本学術振興会産学協力研究委員会インターネット技術第163委員会 (ITRC)、日本ソフトウェア科学会インターネットテクノロジー研究会 (JSSST)、日本UNIXユーザ会 (jus)、WIDEプロジェクト (WIDE)の主催により、2003年10月27日~28日に電気通信大学で開催された。プログラム委員長は砂原秀樹 (奈良先端科学技術大学院大学)と江崎浩 (東京大学)、実行委員長は楯岡孝道(電気通信大学)であった。2件の招待講演が行われた。
|
「ユビキタスコンピューティング ──次世代情報基盤の確立をめざして──」 |
坂村健 (東京大学) |
|
「次世代家電CoCoonのチャレンジ」 |
辻野晃一郎 (ソニー) |
15) SS研究会(汐留)
SS研究会(Scientific System研究会)は、1995年から開催してきた「HPCミーティング」を2003年から「HPCフォーラム」と名前を変え、非会員にも公開した。第1回のHPCフォーラムは、2003年10月3日、汐留シティセンター24階富士通本社大会議室において、開催された。参加者約90名のうち、31人が非会員(会員の組織に属さない参加者)であった。
|
開催趣旨 |
蕪木英雄 (日本原子力研究所) |
|
「高頻度金融データの解析とシミュレーション技法」 |
ソニーコンピュータサイエンス研究所 高安秀樹 |
|
「E-CELL Project : 細胞のコンピューターシミュレーション」 |
慶應義塾大学先端生命科学研究所 中山洋一 |
|
海外招待講演 「Recent Progress in Computational Science at NERSC」 |
Horst D. Simon, NERSC |
|
「OCTAプロジェクト : 物質の多階層シミュレーション」 |
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻 増渕雄一 |
|
富士通報告 「ナノデバイス開発のための原子スケールシミュレーション」 |
(株)富士通研究所シリコンテクノロジ研究所 金田千穂子 |
|
まとめ |
青柳睦 (九州大学情報基盤センター) |
|
懇親会 |
|
16) 河川情報シンポジウム(半蔵門)
何の縁か、財団法人河川情報センターから12月5日の河川情報シンポジウム(ベルサール半蔵門)でグリッドについて講演して欲しいと頼まれ「グリッドのめざすもの」と題して講演した。センサグリッドが洪水予測に使えるのではないか、などと指摘した。
17) 第3回PCクラスタシンポジウム(日本科学未来館)
PCクラスタコンソーシアムは、2003年12月11日~12日には、日本科学未来館において、「第三回PCクラスタシンポジウム業務に浸透するPCクラスタ」を開催した。
18) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所では1969年から毎年数値解析関係の研究集会を行っている。2003年は12月8日~10日に「数値解析と新しい情報技術」という課題で開催された。35回目である。代表者は筆者、キーパーソンは須田、西田、佐藤(東大)。講演内容は講究録:No. 1362に収録されている。
19) コンピュータシステムシンポジウム(つくば国際会議場)
情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会主催の「第15回コンピュータシステムシンポジウム」が、つくば国際会議場で12月11日~12日に開催された。基調講演は「次世代ITインフラストラクチャーとオートノミックコンピューティング」(岩野和生、日本アイ・ビー・エム)、招待講演は「VMwareの仮想化技術とユーティリティ・コンピューティング」(Lance Berc, VMware Inc.)であった。
次回は、日本の企業の動き、標準化、ネットワーク、性能評価など。富士通はPRIMEPOWER HPC2500を、日立はSR110000を、日本電気はSX-6の改良版を発売した。
 |
 |
 |

