HPCの歩み50年(第180回)-2010年(f)-
円周率5兆桁を自宅のPCで計算した近藤氏は、TBSの『情報7days ニュースキャスター』に登場した。スパコンはもう要らないなどと言ったら反論しようと身構えていたがそういう不用意な発言はなかった。情報処理学会が創立50周年を記念して日本将棋連盟に挑戦状を突きつけた。
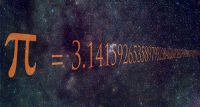
日本の学界の動き(続き)
4) 円周率
筑波大学・計算科学研究センターの高橋大介准教授らが、T2K筑波システムを使い円周率を2兆5769億8037万桁まで計算する世界記録を樹立したと発表したのは、2009年8月17日であった。検証計算も含め、計73時間36分かかっている。直後の2009年12月、フランスのFabrice Bellardは、Intel Core i7を搭載したデスクトップPCで2兆6999億9999万桁まで計算し、筑波大学の記録をわずかに上回った。検証を含め131日を要した。汎用CPUの飛躍的進歩、メモリやハードディスクの急激な価格低下により、時間さえかければスーパーコンピュータではなくPCで計算できるようになった。
2010年8月31日、円周率5兆桁を自宅のパソコンで計算したとの報道があった。長野県飯田市の会社員、近藤茂氏が、自宅のパソコンで円周率を小数点以下5兆桁まで計算し、昨年末にフランス人が達成した記録を大幅に更新した。使ったのはChudnovsky の公式という級数による方法で、筆者がやってみたら初項だけで小数点以下13位くらいまで正しかった。すごい公式である。
今回 5兆桁を計算したプログラムを作成したのは、アメリカの大学生のAlexander J. Yee 氏で、近藤氏はかれと連絡を取りながら計算したそうである。Yee氏はその後 UIUC の CS の大学院に入学した。
高橋大介氏の解説によると、級数を効率的に計算する Binary Splitting という手法が一般的になったのが大きいとのことである。これは、項の総和を順に小数で計算するのではなく、有理数のままトーナメント方式で足し合わせ、通分しながら計算する方式である。昨年までは、Chudnovsky の公式を Binary Splitting 法で計算すると、Gauss-Legendre の公式の 3 分の 1 程度の計算量であると考えられて来たが、フランスの Fabrice Bellard 氏が分母の共通因数の約分を効率良く計算する方法を考案したことから、計算量がさらに半分以下に削減され、ディスク I/O の量を大幅に削減することもできた。これが、パソコンで 2 兆桁を超える桁数を計算できるようになった大きな理由の一つとのことである。
今回パソコンで 5 兆桁を計算したのと同じ方法を T2K 筑波に実装すれば、恐らく 8 時間以下(パソコンの約 270 倍の速度)で計算できると推測される。したがって、T2K 筑波で 2 日程度で計算できる桁数はパソコンでは約 1 年半も掛かることになり、現実的にはかなり難しくなるであろう。
これまで円周率の計算の検証は複数の方式で独立に計算し、全桁の一致を確認してきたが、近藤氏の場合は、16進法の任意の桁以下を計算する公式で最下位の32桁をチェックしただけなので、完全な検証にはなっていない。実際上は正しいと思われるが。
マスコミが面白おかしく取り上げ、電気代が月2万円もかかったとか、(契約容量がぎりぎりなので)ヘアドライヤーをつけるとブレーカーが吹っ飛ぶとか、扇風機でPCを冷やしたとか話していた。2010年9月4日(土)の22時からTBSテレビの『情報7days ニュースキャスター』に出演するというので、「スパコンはもう要らない」なんて言ったら反論しなくてはと身構えていたが、そういう不用意な発言はなかった。
番組ではT2Kの映像が使われ、「筑波大学がスパコンの性能を検証するため」と紹介された。関係者は「安定性を検証するため」と伝えたが、やはり適当に解釈されてしまった。まあ、トーンは「普通のおじさんが頑張った」的な扱いで、スパコン云々という話ではなかったのと、ビートたけしが割と冷静に「これはスピードというよりも長時間かけているので」とコメントしていたので、胸を撫でおろした。たけしが、「円周率にはいろんな公式があって」などと一夜漬けを披露したのはご愛敬。「ギリシャ人が円周率をπという文字においたところが偉い」などというたけしのコメントがあったが、円周率にπというギリシャ文字を使ったのは17世紀のイギリス人William Oughtredが最初で、ギリシャ人ではない。
5) Grape-DR
2010年7月6日、東大は、東大情報理工学系研究科の平木敬 教授と国立天文台理論研究部の牧野淳一郎教授の共同開発したGRAPE-DRがLittle Green500でTopになった旨研究成果発表を行った。Green500は、Top500に入ったスーパーコンピュータの電力性能比をランク付けたリストであるが、Little Green500は、過去1年半(19か月)のどれかのTop500リストに入りうるLinpack性能をもつが、現在は入れないマシンの電力性能比をランク付けしたリストである。Little Leagueで優勝したようなものか。2009年のところに書いたように、Grape-DRは2009年6月のTop500に初めて登場し、Rmax=21.96 TFlops、Rpeak=84.48 TFlopsで279位にランクされている。プロセッサはGRAPE-DR 16C 330 MHzとあるので、32演算器を1コアとしているらしい。総コア数8192とあるので、動かしたチップ数は512で、2006年時点での計画の1/4と推定される。クロック周波数もかなり落としてある。その時は、Green500で5位であった。この時、GRAPE-DRとNECクラスタを除けば、20位までの18台はIBMのCellまたはBG/Pであった。2009年11月のTop500では447位でGreen500は7位であった。2010年6月のTop500の500位は24.7 TFlopsで、ぎりぎりで逃したようである。一説には、今回はメモリを増強できた64ノードだけを使い、Linpackの効率を上げて高い電力性能比を実現したそうである。これでは過去のTop500リストに入っていたマシンといえないのではないかと思ったら、“Run Rules for The Green500”によると、“a supercomputer must be at least as fast as the 500th-ranked supercomputer on the oldest Top500 List released within 19 months of the release date”とあり、Linapack性能としてそのレベルであればよいとのことである。
両教授は、GRAPE-DRの性能にはまだ向上の余地があるとして、今年度中により大規模なシステムの性能測定を行う予定だと述べた。
次の2010年11月のGreen500の当初の発表のトップ10件は以下の通りであった。
順位 Top500 MFlops/W 設置場所 マシン
| 順位 | Top500 | MFlops/W | 設置場所 | マシン |
| 1 | 116 | 1684.20 | IBM Thomas J. Watson Research Center | Blue Gene/Q Prototype 1 |
| 2 | 4 | 958.35 | 東京工業大学GSIC | Tsubame 2.0 |
| 3 | 405 | 933.06 | NCSA | EcoG – Hybrid Cluster Core i3 DC |
| 4 | 172 | 828.67 | 理研AICS | 「京」コンピュータ |
| 5 | 209 | 773.38 | FZJ | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 5 | 209 | 773.38 | U. Regensburg | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 5 | 209 | 773.38 | U. Wuppertal | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 8 | 22 | 740.78 | U. Frankfurt | Supermicro Cluster,QC Opteron 2.1 GHz,ATI Radeon GPU |
| 9 | 118 | 677.12 | Georgia Inst. Of Tech. | Keeneland – HP ProLiant SL390s G7 Xeon 6C X5660 2.8Ghz,nVidia Fermi |
| 10 | 103 | 636.36 | 環境研究所(日本) | GOSAT Research Computation Facility |
4位の「京」コンピュータは、4ラックのデータである。
12月22日に計算間違いがあったとしてGRAPE-DRを2+位とし、東工大のTsubame 2.0は2位のままとし、3位以下は一つ繰り下げた。その後、発表された表では、下記のように3位以下も元のままとなっている。筆者の見た限りweb pageに説明はなく、現在はどちらの表も載っていない。
| 順位 | Top500 | MFlops/W | 設置場所 | マシン |
| 1 | 116 | 1684.20 | IBM Thomas J. Watson Research Center | Blue Gene/Q Prototype 1 |
| 2+ | 385 | 1448.03 | 国立天文台 | GRAPE-DR accelerator Cluster 81 nodes |
| 2 | 4 | 958.35 | 東京工業大学GSIC | Tsubame 2.0 |
| 3 | 405 | 933.06 | NCSA | EcoG – Hybrid Cluster Core i3 DC |
| 4 | 172 | 828.67 | 理研AICS | 「京」コンピュータ |
| 5 | 209 | 773.38 | FZJ | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 5 | 209 | 773.38 | U. Regensburg | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 5 | 209 | 773.38 | U. Wuppertal | QPACE SFB TR Cluster,PowerXCell 8i |
| 8 | 22 | 740.78 | U. Frankfurt | Supermicro Cluster,QC Opteron 2.1 GHz,ATI Radeon GPU |
| 9 | 118 | 677.12 | Georgia Inst. Of Tech. | Keeneland – HP ProLiant SL390s G7 Xeon 6C X5660 2.8Ghz,nVidia Fermi |
| 10 | 103 | 636.36 | 環境研究所(日本) | GOSAT Research Computation Facility |
6)情報処理学会が日本将棋連盟に挑戦状
情報処理学会は創立50周年事業の一環として、2010年4月2日、将棋連盟に下記のような挑戦状をたたきつけた、と記者会見を行った。情報処理学会側出席者 は次の3名。
・白鳥則郎 情報処理学会会長/東北大学 電気通信研究所 客員教授
・佐々木元 情報処理学会創立50周年記念事業実行委員会委員長/日本電気(株) 特別顧問
・中島秀之 情報処理学会トッププロ棋士に勝つためのコンピュータ将棋委員会委員長/公立はこだて未来大学 理事長・学長
| 挑戦状
社団法人 日本将棋連盟 会長 米長 邦雄 殿 コンピュータ将棋を作り始めてから 平成ニ十ニ年四月二日 |
受けて立つとの返事が来た。将棋連盟側はまずは女流棋士でお手並み拝見といったところである。
| 社団法人 情報処理学会 会長 白鳥 則郎 殿
挑戦状確かに承りました 平成二十二年四月二日 |
対局では、複数のソフトを疎結合で並列計算させ、それらの意見を集約して次の一手を決める合議アルゴリズムを使う予定。「GPS将棋」「Bonanza」「激指」「YSS」「TACOS」「柿木将棋」などから、実験をもとに最適な組み合わせを採用する。合議より単独が強ければ単独の可能性もあるという
計算機には、東京大学、京都大学、筑波大学などの並列処理大規模計算機環境(T2Kであろう)のグリッドを使う方向。バックアップとして、複数のXeonマシンを並列につないだ環境も整備する予定だ。プログラムと計算機は、対戦1カ月前までに決定する。日本将棋連盟は2005年10月に、プロが公の場で許可なくコンピュータと対局することを禁止してきた。
 |
|
コンピュータ側が勝利すれば、半年から1年ごとにプロ4段からトッププロ、最終的には名人か竜王と対戦する計画である。
2010年10月11日、東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館において、将棋の清水市代女流王将に情報処理学会(白鳥則郎会長)のコンピュータ将棋システム「あから2010」が挑戦していた一番勝負で、11日午後7時、後手のあからが勝利を収めた。公の場で、コンピュータが日本将棋連盟(米長邦雄会長)の棋士を打ち破ったのは初めて。清水女流王将は歴代最多のタイトル獲得数43を誇る女流のトップ。その実力はアマチュアの五段以上のレベルといわれている。今後、あからは早ければ半年後にも日本将棋連盟が指名する男性棋士に挑み、さらに勝てば最高峰の羽生善治名人(王座・棋聖)か渡辺明竜王と対局する見通し。実際には、2011年7月24日、電気通史大学において、アマチュア2名の合議チームと対戦したが、ソフトの完勝であった。2011年9月、「あから2010」はCEDEC AWARDS 2011 プログラミング・開発環境部門の優秀賞を受賞した。2015年10月、コンピュータ将棋プロジェクトの終了が宣言された。図は『あから』のマスコットキャラクター(情報処理学会のページから)。
7) 「はやぶさ」帰還
宇宙科学研究所(ISAS)が2003年5月9日に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ」は、2005年夏に小惑星イトカワに到達して、表面を観測し、サンプル採取を試み、数々の苦難を経て2010年6月13日22時51分(日本時間)に地球(オーストラリア上空)に再突入した。筆者としては、7年前のコンピュータがちゃんと動いていることにも驚いた。データ処理コンピュータは日立製作所の組み込み用マイクロコンピュータSuperHシリーズのSH-3、リアルタイムOSはμITRONとのことである。
8) 重谷隆之氏死去
理研の重谷隆之氏は11月22日7時45分、心筋梗塞のため44歳の生涯を閉じられた。直前のSC10では筆者と同じホテル(Hotel Le Cirque)に泊まっており、SC10会議では元気にしておられた。日曜日に帰国して、翌月曜日に亡くなられたとのことである。12月20日に理研和光で「重谷さんを偲ぶ会」が催された。
9) 火山爆発
4月14日からアイスランドのEyjafjallajokull(エイヤフィヤトラヨークトル)火山が噴火し、風に乗ってヨーロッパ上空に火山灰が広がった。ヨーロッパの空域の多くが閉鎖され、航空便が大混乱となった。日本のHPC関係者の何人かもロンドンやパリに足止めになったようである。ドイツ東部のMüunchen空港がかろうじて動いたとか。
次回は、日本の国内会議。
 |
 |
 |

