新HPCの歩み(第116回)-1993年(f)-
|
SC会場近くのホテルでIEEE TCSAのSSS (Scientific Supercomputing Subcommittee)が開かれ、筆者は”Japanese Efforts”と題して、日本の状況について報告した。日本についての関心は高い。2回目のTop500が発表され、数値風洞が、並み居るCM-5に倍以上の差をつけて堂々のトップに躍り出た。 |
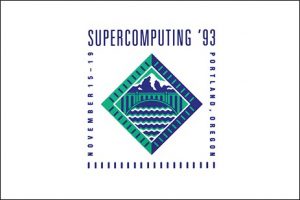 |
|
SC‘93
1) はじめに
第6回のSupercomputing国際会議(Supercomputing ‘93報告)はオレゴン州ポートランドのOregon Convention Centerで11月14日から19日に開かれた。参加者5196名、内technical session登録1886人の規模であった。展示は106件で初めての3桁。テーマがネットワークの方に広がった。Gigabit、ATM、NIIなどの話題が注目された。会場には45 Mb/sのバックボーンが引かれていた(Gb/sではないことに注意)。会場には、参加者のために数十台の端末を用意してtelnetのサービスを行っていた。日本への接続も快適であったが、漢字やかなが出ないのは困った。laptopを持ち歩く習慣はまだ一般的ではなかった。
2) 企業展示
展示会場は11000 m2で、目欲しいものもたくさんあった。ハードウェアベンダが十数社、大容量記憶システムが8社、ネットワーク関係が10社、ソフトウェアが十数社、出版関係が約10社であった。Cray-3のクロック2 nsのボード、CM-5X、KSR2、Convex、IBMのSP2とか。SequentやParsytecは出展していなかったが、SequentはE-mail serviceのスポンサーとして協力していた。日本からは富士通や日本電気。ソフトではFortran 90関係やHPFなど。HPFは標準化のところで紹介した。
研究展示にもリキが入っていた。アプリとしては、MPP上の並列化が進んでいた。種々の並列コンピュータをプラットフォームとして、流体や計算化学などのアプリが動いていた。Oracleデータベースなどの非数値計算の応用分野の重要性を各社とも強調していた。
3) HPC教育
もう一つの特徴は、教育とくにハイスクールでのコンピュータ教育の問題がクローズアップされたことである。HPCCの中には教育の問題も含まれている。前年から始まっているようであるが、K-12(幼稚園から高校3年まで)という標語で特別のプログラムや展示が企画され、ハイスクールの先生が多数参加していた。高校生が地理学から計算物理、計算化学などの問題を、スーパーコンピュータを駆使して解き、かなりレベルの高い発表を行っていた。日本では、パソコンすら高校に行き渡っていない。これでは日本はますます遅れてしまう、と筆者達日本からの参加者は焦りを感じた。
4) SSS
会議の主要部分の始まる前、14日か15日に、会場近くのホテルでIEEE Technical Committee on Supercomputing Applications (TCSA)のSSS (Scientific Supercomputing Subcommittee)が開かれた。これは1991年に始まった会議で、世界のスーパーコンピュータとHPCの進展を分析するためのもので、年に4回ほど会合を持っているようである。筆者は委員ではないが、今回依頼により出席し”Japanese Efforts”と題して、日本の状況について報告した。この後、1995年には、三浦謙一と筆者で、日本のHPCそのものをテーマとする会議を企画することになる。
5) 投稿論文
300件の論文が投稿され、査読により72件が採択された。採択率24%である。日本からの採択は1件だけであった。
|
Shin-ichiro Mori, Hideki Saito, Masahiro Goshima, Mamoru Yanagihara, Takashi Tanaka, David Fraser, Kazuki Joe, Hiroyuki Nitta, Shinji Tomita: |
A distributed shared memory multiprocessor ASURA: memory and cache architecture. |
電子版の会議録はIEEE Xploreに収録されている。
6) パネル
会議録によると以下のパネルやワークショップやミニシンポジウムが開かれている。
|
Workshop |
|
|
Uses of videoconferencing in the supercomputing environment |
Mary Stephenson, Larry Brandt, Eric Sills, Alex Ropelewski, B. Loftis, B. Buzbee |
|
Integrating task and data parallelism. |
Ian T. Foster, Carl Kesselman |
|
Scientific visualization of chemical systems |
Richard E. Gillilan, Bruce R. Land |
|
Debuggers for high performance computers |
Jeffrey S. Brown |
|
High performance Fortran: implementor and users workshop |
Alok N. Choudhary, Charles Koelbel, Mary Zosel |
|
Common runtime support for high-performance parallel languages |
Geoffrey C. Fox et al. |
|
CORPORATE The MPI Forum – MPI: a message passing interface. |
|
|
Minisymposium |
|
|
The heterogeneous computing challenge |
Francine Berman, Tom Kitchens |
|
Heterogeneous distributed computing |
Doreen Cheng |
|
Supercomputing around the world |
David X. Kahaner, Allen D. Malony: |
|
Panel |
|
|
Smart access to large scientific datasets |
Carol Christian, Robert F. Cromp, Carol L. Hunter, Lloyd Treinish |
|
National information infrastructure (NII) at Supercomputing ’93 |
Henry D. Shay, Vinton G. Cerf, Lansing Hatfield, Stacey Jenkins, Ed McCracken, John Rollwagen, Dale Williams |
|
Parallel C/C++: convergence or divergence |
Linda Stanberry |
|
What’s in the future for parallel architectures? |
David C. Douglas et al. |
|
Massively parallel vs. parallel vector supercomputers: a user’s perspective |
Gary Montry et al. |
7) Awards
1987年に創設されたGordon Bell賞は、5件のfinalistsの講演が行われた。
|
Barrier-breaking performance for industrial problems on the CRAY C916 |
Sara K. Graffunder (Cray) |
|
50 GFlops molecular dynamics on the Connection Machine 5. |
Peter S. Lomdahl, Pablo Tamayo, Niels Grønbech-Jensen, David M. Beazley |
|
Solving the Boltzmann equation at 61 gigaflops on a 1024-node CM-5 |
Lyle N. Long, Jacek Myczkowski |
|
Bispectrum signal processing on HNC’s SIMD numerical array processor (SNAP) |
Robert W. Means, Bret Wallach, David Busby |
|
Parallel execution of a Fortran 77 weather prediction model |
Gary Sabot (TMC), Skef Wholey, Jonas Berlin, Paul Oppenheimer |
本賞およびHonorable Mention(佳作)は以下の3件に与えられた。
|
Peak Performance |
|
Honorable Mention: Peter S. Lomdahl, Pablo Tamayo, Niels Gronbech-Jensen and David M. Beazley, Los Alamos National Laboratory; “Simulating the micro-structure of grain boundaries in solids,” 50 Gflops on a 1,024 processor CM-5 |
|
Price/Performance |
前年創設されたSidney Fernbach Awardの第1号は、「ベクトルコンピュータ上のFFT、行列乗算、多倍長計算に関する革新的アルゴリズムなどの数値計算上の寄与」に対して、David H. Bailey(当時NASA Ames Lab.)に授与された。SCの最中に授与式があったかどうか記憶はない。
8) Top500
第2回のTop500が、SC93に合わせて発表されたと思われるが、BoFはSC94からで今回はない。上位20位(同性能が続くので27件)は以下の通り。性能の単位はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
- |
航空宇宙技術研究所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
124.0 |
235.79 |
|
2 |
1 |
LANL |
CM-5/1024 |
1024 |
59.7 |
131.0 |
|
3tie |
2tie |
Minnesota Supercomputer C. |
CM-5/544 |
544 |
30.4 |
69.6 |
|
3tie |
2tie |
NSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
|
3tie |
2tie |
NCSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
|
6 |
5 |
日本電気(日本) |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
7 |
6 |
Atmospheric Environment Service (Canada) |
SX-3/44 343 MHz |
4 |
20 |
22 |
|
8tie |
- |
ORNL |
XP/S35 |
512 |
15.2 |
25.6 |
|
8tie |
- |
SNL |
XP/S35 |
512 |
15.2 |
25.6 |
|
10tie |
- |
アメリカ某政府機関 |
CM-5/256 |
256 |
15.1 |
32.77 |
|
10tie |
7 |
Naval Research Laboratory(アメリカ) |
CM-5/256 |
256 |
15.1 |
32.77 |
|
10tie |
- |
Thinking Machines |
CM-5/256 |
256 |
15.1 |
32.77 |
|
13 |
8 |
Caltech |
Delta i860 40 MHz |
512 |
13.9 |
20.48 |
|
14tie |
9tie |
Cray Research |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
Bettis Atomic Power Lab.(アメリカ) |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
Knolls Atomic Power Lab.(アメリカ) |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
ECMWF(イギリス) |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
- |
ERDC DSRC(アメリカ) |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
アメリカ某政府機関 |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tue |
9tie |
アメリカ某政府機関 |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
アメリカ某政府機関 |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
アメリカ某政府機関 |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
- |
KISTI(韓国) |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
NASA Ames |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
Naval Oceanographic Office |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
NERSC/LLNL |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
|
14tie |
9tie |
Pittsburgh Supercomputer C. |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.24 |
現在のTop500のリストでは、8位tieは両方ともORNLと書かれているが、一方はSNLである。Minnesota Supercomputer CenterのCM-5/544は、相変わらずまじめに測定してないようである。14位tieのKISTI(韓国)は、アジア・太平洋地区で最初のC90の導入である。日本設置のマシンで100位以内は以下の通り。(ただし58位tieのNECのSX-3はアメリカのHoustonに設置)
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
- |
航空宇宙技術研究所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
124.0 |
235.79 |
|
6 |
5 |
日本電気(日本) |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
30 |
21 |
核融合科学研究所 |
SX-3/24R 400 MHz |
2 |
11.6 |
12.8 |
|
31 |
22 |
NEC Daito Supercomputer C. |
SX-3/24 343 MHz |
2 |
10.0 |
11.0 |
|
43 |
(36) |
東京大学 |
S-3800/480 500 MHz |
4 |
7.0 |
32.0 |
|
51tie |
33tie |
日本原子力研究所 |
SX-3/41R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
51tie |
33tie |
大阪大学 |
SX-3/14R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
51tie |
33tie |
トヨタ中央研究所 |
SX-3/41R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
58tie |
40tie |
日本IBM |
SX-3/14 343 MHz |
1 |
5.0 |
5.5 |
|
58tie |
- |
航空宇宙技術研究所 |
SX-3/22 |
2 |
5.0 |
5.5 |
|
58tie |
40tie |
国立環境研究所 |
SX-3/14 343 MHz |
1 |
5.0 |
5.5 |
|
58tie |
- |
NEC Systems Laboratories Inc.(アメリカ) |
SX-3/22 |
2 |
5.0 |
5.5 |
|
67tie |
45tie |
富士重工 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
日本原子力研究所 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
日本原子力研究所 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
京都大学 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
九州大学 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
名古屋大学 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
航空宇宙技術研究所 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
動力炉・核燃料開発事業団 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
動力炉・核燃料開発事業団 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
67tie |
45tie |
大成建設 |
VP2600/10 312 MHz |
1 |
4.0 |
5.0 |
|
81tie |
57tie |
ATR |
CM-5/64 |
64 |
3.8 |
8.19 |
|
81tie |
57tie |
奈良先端科学技術大 |
CM-5/64 |
64 |
3.8 |
8.19 |
|
81tie |
57tie |
RWCP |
CM-5/64 |
64 |
3.8 |
8.19 |
|
95tie |
73tie |
NEC Scientific Information Systems Dev. |
SX-3/12R 400 MHz |
1 |
2.9 |
3.2 |
|
95tie |
73tie |
大林組 |
SX-3/21R 400 MHz |
2 |
2.9 |
3.2 |
東京大学大型計算機センターのS-3800/480のLinpack性能は、前回の5.71 GFlopsよりは改善されたが、まだフル性能を出していないようである。チューニングにより、1994年6月には27.5 GFlops、1995年6月には28.4 GFlopsを出している。
いよいよ次回はIBMとCray Researchが超並列スーパーコンピュータを発表した話題に移る。Cray-3はNCARに設置されたが、翌年Cray Computer社は倒産する。
 |
 |
 |

