新HPCの歩み(第153回)-1998年(b)-
|
高田俊和を中心とするグループは量子論的分子動力学に基づいて化学反応における分子の動きを可視化するバーチャル・マイクロスコープを発表する。日立、日本電気、日本IBM、富士通のユーザグループが多くの参加者を得てシンポジウムを開催する。PSCでは疎行列係数の方程式解放を出題した。 |
日本の大学センター等
1) 北海道大学(HITACHI MP5800/160+SUN/UltraEnterprise4000)
1998年3月、北海道大学大型計算機センターはベクトルスーパーコンピュータを並列汎用サーバに置き換えた。構成は、HITACHI MP5800/160(主記憶 256 MB)+SUN/UltraEnterprise4000(主記憶2 GB)となった。
2) 東北大学(SX-4/128H4)
東北大学大型計算機センターは、1998年1月、SX-4/128H4の運用を開始した。
3) 大阪大学(SX-4/64M2+Exemplar V2200/N)
1998年3月、大阪大学大型計算機センターは、ベクトルスーパーコンピュータSX-4/64M2に加えて演算サーバExemplar V2200/Nのサービスを開始した。
4) 茨城大学
1998年4月9日、省令施設として総合情報処理センターが設置された。
5) 琉球大学
1998年4月、情報処理センターから学内共同教育研究施設の総合情報処理センターへ省令化。
6) 工学院大学(VX-E/3)
工学院大学情報科学研究教育センターは、富士通 VX-E/3 システム、Sun ワークステーションに移行。 パソコンには富士通 FM/V シリーズを導入する。
日本の学界の動き
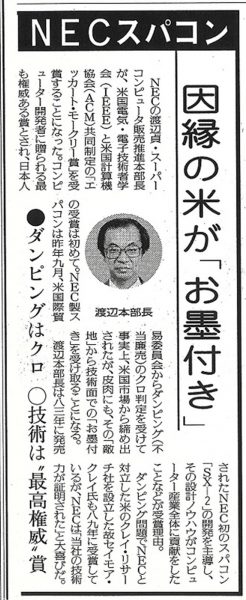 |
|
1) 渡辺貞氏、Eckert-Mauchly賞受賞
1998年のEckert-Mauchly Awardは、「多重ベクトルパイプラインとプログラム可能なベクトルキャッシュをもつスーパーコンピュータのアーキテクチャ設計」への寄与に対して、日本電気のSXシリーズの設計者である渡辺貞氏に授与された。日本人としては初めてであった。この賞は、ENIACを設計製作したJohn Presper Eckertと John William Mauchlyの名にちなんで、ACMとIEEE/CSが共同して「コンピュータとディジタルシステム分野への卓越した貢献」に対して贈るものである。
読売新聞4月22日号(写真)は、「NEC製スパコンは昨年九月、米国際貿易委員会からダンピング(不当廉売)のクロ判定を受けて事実上、米国市場から締め出されたが、皮肉にも、その「敵地」から技術面での「お墨付き」を受け取ることになる。」と書いているが、皮肉というよりもアメリカ国内には多様な考えがある(わかっている人はわかっている)というだけのことである。
2) GRAPE-5
牧野淳一郎らは、科研費特別推進研究の補助を受けて、GRAPE-5を完成させた。GRAPE-3の改良型で、理論演算性能は1 TFlopsである。日本天文学会で発表した。翌1999年のGordon-Bell賞を獲得する。
3)筑波大学
筑波大学計算物理学研究センター では、3月23日~24日、「並列・分散環境におけるハイパフォーマンスコンピューティング」という研究会を開催した。経緯は忘れたが、実行委員長を務めた。
岩崎洋一センター長は4月1日付けで筑波大学副学長(研究担当)に任命された(学長は北原保雄)。4月16日、宇川彰が後任のセンター長に就任した。ただし、未来開拓「計算科学」のリーダーは、岩崎のまま続けることとなった。
4) VRMS
高田俊和(日本電気基礎研究所、主席研究員)を代表とする日本電気、富士総合研究所、電子技術総合研究所、CRC総合研究所のグループは、情報処理振興事業協会の「創造的ソフトウェア育成事業およびエレクトロニック・コマース推進事業」の補助を受けて、バーチャル・マイクロスコープ(VRMS, Virtual Reality Microscope)を開発していたが、1998年3月に公表した(HPCwire 1998/3/27)。このソフトウェアは、量子論的分子動力学に基づいて化学反応における分子の動きをシミュレーションし、3次元グラフィックスにより目でみることができるのが特徴である。1996年に発足した産業基盤ソフトウェア/フォーラム(SIF)では、このソフトを開発段階から支援していた。
5) 量子アニーリング
このころ、西森秀稔東京工業大学教授らは「量子アニーリング」のアイデアをPhysical Review Eに発表した。このアイデアに基づき、翌1999年、カナダのベンチャー企業D-Wave Systems社が創業され、2010年、「世界初の商用量子コンピュータ」D-Wave One を発表する。
6) DNAコンピューティング
萩谷昌己(東大理学系)は、横森貴(早大教育)、陶山明(東大総合文化)、坂本健作(東大理学系)、伏見譲(埼玉大工)とともに、1996年から分子コンピュータに関する未来開拓研究プロジェクトを行ってきたが、生体分子のもつ計算能力を用いた情報処理機構の多様な可能性を示した(HPCwire 1998/1/19)。また9月には、アメリカのPrincetonにあるNEC Research Institute, Inc.が、DNAコンピュータの設計に関する特許をアメリカから取得している(HPCwire 1998/9/11)。E. Baumという人の成果とのことである。
7) ニュートリノ振動
1998年、梶田隆章らは、岐阜県神岡のスーパーカミオカンデを用いて、大気ニュートリノの観測からニュートリノ振動を実証した。この業績により梶田隆章は2015年にArthur Bruce McDonaldと共にノーベル物理学賞を受賞する。
8) 東京大学(新領域創成科学研究科)
東大では1998年、柏キャンパスに新領域創成科学研究科を創設した。筆者のいた理学系研究科コンピュータ科学専攻も、この研究科の複雑理工学専攻創設に協力した(つまり教員定員を献上した)。1999年から学生を受け入れる。
9) 学術誌電子化出版
1998年4月頃から、物理関係3学会(物理学会、応用物理学会、応用物理欧文誌刊行会)で学術誌の電子化(編集過程の電子化および電子ジャーナル化)についての議論に加わった。中心は五神真助教授(東大物工、2015~2021東大総長、2022から理化学研究所理事長)で、電子化のシステム作りの要求事項のまとめ作業を行った。結果的には、科学技術庁のJSTと文部省との縄張り争いに巻き込まれたりして要らぬ苦労を味わった。現在稼働している「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)の遠い祖先にあたる。
10) JCRN(研究ネットワーク連合委員会)
1990年に設立されたJCRN(Japan Committee for Research Networks)は、1995年の第2回JCRNセミナーの後大きな活動を行ってこなかったが、JPNICの法人化に伴い、所期の目的を達成したと判断し、1998年3月をもって解散することとした。JCRNが予定していたもう一つの重要な機能は、構成メンバである学会の情報化の支援である。特に、学術誌の電子出版の動きが急速に起こっているが、多くの学会では対応に苦慮している。
1996年から、TISN および JAIN の関係者が中心となり、日本学術振興会の産学協力研究委員会の一つとして「インターネット技術研究委員会」(ITRC、委員長 大阪大学 宮原秀夫教授)が発足した。この研究委員会は、分野間・産学間・世代間の密な交流を促進することにより、インターネットに関する技術研究およびその応用に携わる幅広い層の研究者・技術者に交流の場を提供し、ネットワーク技術の立ち遅れを一掃することを目的としている。学会の情報化については引続きITRCの部会として研究を進めていこうと考えていた。2022年3月2日(水)に、沖縄県市町村自治会館(沖縄県那覇市)において、ITRC 2021年度解散総会・記念研究会が開催され、ITRCも学振の活動としては解散し、4月からは産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会 として再出発する。
11) 有馬朗人氏、参議院議員に
東京大学在学中、隣の研究室の教授であり、理学部長、東大総長、理化学研究所理事長を歴任した有馬朗人(あきと)名誉教授は、1998年、当時の総理だった橋本龍太郎に請われて第18回参議院議員選挙に自由民主党の比例代表名簿1位に登載され当選した。報道によると、自民党は5月20日に方針を固め、22日に正式決定した。自民党がこの選挙で大敗、橋本内閣が敗北の責任を取って退陣した後、後任の小渕恵三から小渕内閣の文部大臣に抜擢、続く第1次改造内閣(1999年1月発足)でも文部大臣に留任した上で科学技術庁長官も兼務した。1999年10月の内閣再改造で退任する。この間、国立大学法人化の議論が進んだ。有馬朗人氏は、2020年12月7日に90歳で亡くなられる。
国内会議
1) HOKKE-98
第 4 回「ハイパフォーマンスコンピューティングとアーキテクチャの評価」に関する北海道ワークショップ(HOKKE-98)は、「計算機クラスタ技術の性能評価」をテーマとして(財)札幌エレクトロニクスセンター(2002年より(財) さっぽろ産業振興財団)の札幌テクノパークにおいて、3月5日~6日に開催された。主催は計算機アーキテクチャ研究会とハイパフォーマンスコンピューティング研究会。講演数23。実はこの会場は筆者が見つけてきたもので、前年1997年のHOKKE-97の前日に「NORTH 北海道地域ネットワーク協議会」のシンポジウムに顔を出した際、地元の企業家と親しくなり、このセンターのプレゼンテーションルームを、テクノパーク関係者が傍聴してもよいという了解で、無料で貸してもらえることになった。初日晩の懇親会は、これまでのサッポロビール園とは異なり、白石区のアサヒビール園で開催された。
2) INSAMシンポジウム ’97++
広島大学理学部大規模非線形数値実験室(Institute for Numerical Simulations and Applied Mathematics: INSAM)は、1998年3月30日、広島大学理学部において、INSAMシンポジウム ’97++を開催した。1997年度としては10月に続いて2回目の開催である。プログラムは以下の通り。
|
13:00-13:05 |
あいさつ |
|
|
13:05-14:05 |
『脳と神経回路の科学』 |
沢田康次(東北大学電気通信研究所所長) |
|
14:05-15:05 |
『計算過程としての自己複製・進化・遺伝につい』 |
池上高志 氏(東京大学) |
|
15:05-15:20 |
休憩 |
|
|
15:20-16:20 |
『地球規模の大規模計算』 |
矢川元基(東京大学) |
|
16:20-17:30 |
INSAM グループ活動報告会 |
|
|
18:00-20:00 |
懇親会 |
|
広島大学理学部大規模非線形数値実験室INSAMは、1998年度から英語名をInstitute for Nonlinear Sciences and Applied Mathematicsに変更した。
3) HAS研
HAS研(Hitachiアカデミックシステム研究会)は、1998年3月26日に第12回研究会を開催した。
|
第12回研究会 テーマ「アカデミックコンピューティング環境」 |
|
|
リアルワールドデータベースプロジェクトの現況と未来 |
横浜国立大学 有澤 博 |
|
知的生産のためのアカデミックコンピューティング |
埼玉大学 井門 俊治 |
|
アプリケーション層で考えるインターネットとデータ放送 |
北海道大学 山本 強 |
|
情報メディアを利用した教育支援環境 |
京都大学 美濃 導彦 |
7月28日には、10周年記念シンポジウムが行われた。
|
ご報告 |
|
|
日立のスーパーコンピュータのご紹介 |
株式会社日立製作所 小林 二三幸 |
|
10周年記念シンポジウム テーマ「21世紀に向けて、コンピュータテクノロジーの覇者たちは」 |
|
|
コンピューティングの動向とインテルの戦略 |
インテル株式会社 西岡 郁夫 |
|
マイクロソフトの製品戦略とエンタープライズ戦略 |
マイクロソフト株式会社 徳武 信慈 |
|
DBMSとネットワークコンピューティングの今後の展開 |
日本オラクル株式会社 佐藤 聡俊 |
|
総合討議 |
– |
11月26日には第13回研究会を開催した。
|
第13回研究会 テーマ「インターネットに安心が来る日」 |
|
|
インターネット上の不正アクセスとJPCERT/CCの役割 |
コンピュータ緊急対応センター 大林 正英 |
|
コンピュータ・セキュリティに対するKEKの取り組み |
高エネルギー加速器研究機構 馬渡 博司 |
|
忍びよるコンピュータウィルスの脅威 |
日本アイ・シー・エス・エー株式会社 |
4) NEC・HPC研究会
1998年5月15日に第7回NEC・ HPC研究会が開かれた。手元にプログラムはない。
第8回NEC・ HPC研究会は12月15日にNEC本社ビル地下1階講堂で開かれた。プログラムは以下の通り。
|
基調講演「ゲノム情報に基づく生命系シミュレーション」 |
金久實(京大) |
|
「DRAMA:並列アダプティブ有限要素法のための動的負荷分散ライブラリ」 |
Guy Lonsdale(NEC Europe) |
|
「Doacross ループのsandglass型並列化手法の有効性について」 |
高畠志泰(電通大) |
|
「MPIを使ったポータブルなコード作成について」 |
日置慎治(帝塚山大) |
|
「SMP型計算機を活用する軽量プロセス・ライブラリ」 |
小熊寿(電通大)、 |
|
「分散メモリ型並列計算機上での流体解析のための実時間可視化システム-地球シミュレータ上での実時間可視化に向けて-」 |
村松一弘(原研) |
|
「スーパーコンピュータSX-5シリーズのご紹介」 |
塚越 眞(NEC) |
5) JSPP’98
第10回並列処理シンポジウム(JSPP’98)は、1998年6月3日~5日に、名古屋市熱田区の名古屋国際会議場で開催された。実行委員長は石井光雄(富士通)、幹事は山名早人(早大)、高木浩光(電総研)、木村康則(富士通)、安藤 秀樹(名大)、プログラム委員長は瀧和男(神戸大)。主催は、情報処理学会の計算機アーキテクチャ研究会、システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会、アルゴリズム研究会、プログラミング研究会、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会、電子情報通信学会のコンピュータシステム研究会、データ工学研究会、日本ソフトウェア科学会のオブジェクト指向コンピューティング研究会、協賛は人工知能学会と日本応用数理学会と超並列計算研究会であった。
論文発表のほか、以下のプログラムが企画された。
|
基調講演 |
「脳を創る 」松本 元(理化学研究所) |
|
招待講演 |
“Performance Analysis of Parallel Systems: Approaches and Open Problems” Daniel A. Reed et al. (University of Illinois) |
|
チュートリアル |
「並列データベース技術」天野 浩文(九大) |
|
チュートリアル |
「命令レベル並列処理技術」安藤 秀樹(名大) |
|
10周年記念ワークショップ |
「超並列計算機のシステム技術」平木 敬(東大) 「低消費電力・高速LSI技術」花輪 誠(日立) 「オンチップマルチプロセッサの研究動向」西 直樹(NEC) 「インタコネクション技術」工藤 知宏(新情報) 「21世紀の分散処理に向けて -幾つかの素朴な疑問」後藤 厚宏(NTT) |
|
10周年記念パネル討論 |
「並列処理この10年・次の10年」モデレータ:坂井 修一(東大) パネリスト:天野 英晴(慶大), 加藤 努(ソフテック), 小長谷 明彦(北陸先端大), 中田 登志之(NEC), 福田 正大(航技研), 松岡 聡(東工大) |
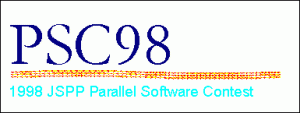 |
|
6) PSC 98
第5回JSPP並列ソフトウェアコンテスト(PSC 98)は、島崎眞昭(京大)を実行委員長として行われた。問題は疎行列連立方程式の並列解法であった。提供されたマシンは、NEC Cenju-3 128PE、Fujitsu AP3000 16PE、Hitachi SR2201 16PE ×2、Sun Enterprise 10000 64PEの4種類であった。Enterprise 10000は東大情報科学専攻のマシンをつかった。他は各社が研究者向けに設置したセンターのマシンを提供した。全エントリー数は69チーム。
|
|
Cenju-3 |
AP3000 |
SR2201 |
E10000 |
|
予選通過チーム |
12 |
11 |
15 |
21 |
|
Fortranチーム |
4 |
1 |
|
2 |
|
Cチーム |
8 |
10 |
|
18 |
|
本選通過チーム |
3 |
3 |
7 |
10 |
|
1位 |
黒田久泰(東大理) |
塙与志夫(東大理) |
吉本芳英(東大理) |
塙与志夫(東大理) |
|
2位 |
小菅哲也(筑波大) |
黒田久泰(東大理) |
黒田久泰(東大理) |
遠藤敏夫(東大理) |
|
3位 |
片桐孝洋(東大理) |
小菅哲也(筑波大) |
遠藤敏夫(東大理) |
黒田久泰(東大理) |
E10000では1チームが言語としてSchematicを用いた(上位入選せず)。上位入選者がだんだん固定化し、コンテストの意義が問題になり始めた。
7) 数値解析シンポジウム
第27回数値解析シンポジウムは、1998年6月15日~17日に浜名湖カリアックで開催された。担当は八巻直一(静岡大学工)を中心に、理科大・青山学院大が協力した。参加者95名、講演40件。特別イベントとして、夜20時から「数値解析夜話」(鳥居達生、南山大)と「数学関数の計算について」(二宮市三、元名古屋大)が企画された。
8) IBM HPC Forum
1998年7月16日、IBM HPC Forumが箱崎事業所IFAVホールで開催された。
|
9:30-9:40 |
開会の挨拶 |
川井 忠彦 IBM HP Cユーザーズフォーラム会長(東京大学名誉教授) |
|
9:40-11:00 |
基調講演 -IBM HPCシステムの最新動向 |
Joanne Martin (IBM, Senior Vice President) |
|
|
休憩 (15分) |
|
|
11:15-12:30 |
計算流体力学の今日、そして将来に向けて |
姫野 龍太郎(理化学研究所 情報環境室室長) |
|
|
昼食 (60分) |
|
|
13:30-14:45 |
ゲノムとHPC: 海外の動きを中心に |
八尾 徹、(三菱化学(株) 横浜総合研究所 技師長) |
|
|
休憩 (15分) |
|
|
15:00-16:15 |
基調講演 – 米国ASCI計画 最新情報 |
(LLNL) |
|
16:15-17:15 |
サイエンティフィック・ビジュアリゼーション ナウ |
藤川 泰彦((株)ヴァイナス 代表取締役社長 |
|
17:15-17:30 |
閉会の挨拶 |
宇陀 栄次(RS/6000製品事業部長、日本アイ・ビー・エム(株)) |
|
17:30-19:30 |
懇親会 (24階 特別食堂) |
|
このForumをもって筆者はIBM HPCユーザーズフォーラムの会長を川井忠彦前会長から引き継いだ。
9) SWoPP 98(別名SWoPP三尺玉)
1998年SWoPPは、8月4日~7日に長岡産業交流会館「ハイブ長岡」で開かれた。第11回目である。宿泊および懇親会はJTB長岡支店に委託した。主催は、電子情報通信学会のコンピュータシステム研究会(CPSY)とフォールトトレラントシステム研究会(FTS)、情報処理学会計算機のアーキテクチャ研究会(ARC)、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(HPC)、システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会(OS)、プログラミング研究会(PRO)であった。
SWoPP期間中、会場にISDN回線を引いて、インターネットのアクセスポート(10 BaseT)を用意した。日本ではまだそういう時代であった。
8月2日3日の夜には有名な長岡花火大会があり、宿が満員なので会期を4日からとした。3日晩の花火を見て、新潟市まで行って宿泊する計画の人もいた。ところが花火大会が豪雨で8月6日7日夜に延期となり、JTBの御陰でSWoPPとしても6日の晩に弁当付きの屋形船を急遽用意することができた。筆者は到着が1日遅れたので、申し込んだときは弁当が売り切れており、弁当なしで船に乗り、みんなから少しずつ食物を分けてもらった。屋形船といっても港に浮いているだけであり、屋根もなく、途中雨が降ってきて往生したが、有名な(正)三尺玉を見ることができた。ただし、電総研関係の方々と取った宿(三丸荘、温泉付き)では「泊まりたい方がたくさんいるので」ということで、その晩だけは少ない部屋に多人数押し込まれた。宿代を負けさせるべきだった。
10) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所において、杉原正顕(名古屋大)を研究代表者として、研究集会『数値計算における前処理の研究』が1998年11月9日~11日に開催された。講演は数理解析研究所講究録1084に収録されている。
11) SS研究会
SS研究会(Scientific System研究会)は、4回目となるHPCミーティングを、1998年11月20日、合同分科会(18日~19日)に続いて、神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ(六甲アイランド)で開催した。200名近くが参加した。会員外も11名参加しているので、このころからオープンにしたのであろうか。2000年頃には、はっきりオープンを謳っている。
|
挨拶 『富士通のHPCへの取組み』 |
富士通 取締役コンピュータ事業本部長 宮澤達士 |
|
【特別講演】 『The Role of High Performance Computing and Information Systems in Pharmaceutical Discovery and Development』 |
Frederick H. Hausheer, M.D., Founder Chairman and CEO BioNumerik Pharmaceuticals, Inc. |
|
【一般報告】 |
|
|
・『日本原子力研究所における計算科学研究の現状と課題』 |
日本原子力研究所 計算科学推進センター 蕪木英雄 |
|
・『建設業における気流シミュレーション技術の現状』 |
大成建設株式会社 技術研究所環境研究部 小野浩史 |
|
【富士通報告】 |
|
|
・『次期HPC』 |
富士通 コンピュータ事業本部HPC開発統括部 内田啓一郎 |
|
・『HPC環境における高速/大容量ファイルシステム』 |
富士通 ソフトウェア事業本部HPCソフトウェア統括部 杉山憲明 |
|
挨拶 |
富士通欧州情報技術センター 取締役社長 小坂義裕 |
|
【総合討論】 『ユーザが求める21世紀のHPC環境』 |
|
|
まとめ |
福田企画委員 |
12) インターネットコンファレンス’98
第3回となるインターネットコンファレンス’98は、日本インターネット協会(IAJ)、日本ソフトウェア科学会 インターネットテクノロジー研究会、 日本UNIXユーザ会、 WIDEプロジェクト の主催により、1998年12月15日~16日に国立京都国際会館で開催された。プログラム委員長は村井純(慶應大)、実行委員長は鈴木麗(奈良先端)であった。Internet Week’98(12月15日~18日) の一環として開催された。
次回は日本の企業の動き、標準化など。日本電気はSX-5を発表し、日立はSR8000を発表した。三好甫を中心としてJAHPFの活動が本格化し、成果をHUG‘98で公表した。
 |
 |
 |

