新HPCの歩み(第191回)-2002年(g)-
|
世界中でグリッド関係の国際会議が多数開催されている。例えばPRAGMAがSan DiegoとSeoulで開かれ、CCGridがBerlinで、iGrid 2002がAmsterdamで開催された。San Joseで開催されたMicroprocessor Forum 2002は、ITバブル崩壊にもかかわらず超高速CPUのラッシュであった。 |
国際会議
1) ApGrid(Phuket島、タイ)
1月頃、第1回ApGrid Core MeetingがタイのPhuket島で開催された。
2) LinuxWorld & Expo (New York、San Francisco)
2002年1月29日~2月1日に、New York市Manhattanにあるthe Jacob K. Javits Convention Centerにおいて、LinuxWorldが開催された(展示は30日から)。3年前最初に開かれた時と比べるとビジネスライクになり、スーツ姿が目立った。これまではLinuxを売る会社が中心だったが、今回は「隅の親石」がCompaq社、プラチナスポンサーはAMD社、Computer Associates社、Hewlett-Packard社、Intel社、IBM社であった。IBM社は「Linuxは現実のビジネスだ」を標語に乗り込んだ。(CNN 2002/1/29) (HPCwire 2002/2/8)
主催のIDG (International Data Grou)は1月31日に7件のOpen Source Product Excellence AwardsをUniForum Associationと共同して授与した。(HPCwire 2002/2/8)
8月12日~15日には、San FranciscoのMonscone Centerで開催された。Red Hat社やIBM社のようなLinux推進の主役だけでなく、やっとLinuxに入って来たSun Microsystems社や、いわば敵であったMicrosoft社まで多くの社が参加した。(HPCwire 2002/7/12)(HPCwire 2002/8/16)(HPCwire 2002/8/16) この席で、5件の2002 Enterprise Evolution Awardsが発表された。(HPCwire 2002/8/16) 来場者は20070人であった(HPCwire 2002/8/23)。
3) ISSCC 2002(San Francisco)
第49回目となるISSCC 2002 (2002 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、2002年2月3日~7日にSan FranciscoのMarriott Hotelにおいて開催された。電子版の会議録は、IEEE Xploreに置かれている。
John MarkoffがNew York Times紙掲載の記事で、この会議について報告している。「Mooreの法則」は(自然の)「公理」というより、「drag race(自動車の1/4マイルの短距離競争)」になっており、さらに加速している。Intel社は室温において1.66 Voltで10 GHzのクロックを実現し、これは数年後には商品で実用化されるであろうと述べた。IBM社は発熱が問題となるので、むしろ1 GHzでも状況に応じてクロックを調節できるPowerPCチップを開発している。(HPCwire 2002/2/8)
また、Intel社、IBM社や他の半導体企業は、将来のチップはより少ないエネルギーで高速に動作するようになるであろうと発表した。「エネルギーのことを考えなくてもいい時代は過ぎ、今はだれでもそれを考えるようになった」とIBM社のRussell Langeは語った。(HPCwire 2002/2/8)
4) PRAGMA(San Diego、Seoul)
PRAGMA (The Pacific Rim Application and Grid Middleware Assembly)の第1回が、2002年3月11日~12日にSan Diegoで開催された。ホストは、SDSCとUCSDのCatl-IT2。これはNPACI All Hands Meetingに併設して開催された。組織委員長はPhilip Papadopoulos (UCSD/SDSC/Cal(IT)2/CRBS)、副委員長はSangsan Lee (KISTI)。
第2回のPRAGMAは、2002年7月10日~11日に韓国ソウルで開催された。ホストはKISTIで、Grid Forum Koreaに併設されて開催された。組織委員長はSangsan Lee (KISTI)、副委員長は田中良夫(産総研)。
5) ARCS 2002(Karlsruhe)
第16回目となるARCS 2002 (International Conference on Architecture of Computing Systems 2002)が、“Trends in Network and Pervasive Computing”の副題で、2002年4月8日~11日にドイツのKarlsruheで開催された。General ChairはHartmut Schmeck、Program ChairはTheo Ungererである。共催はCEPISとEUREL、後援は、ACM、IEEE、およびIFIP TC10である。会議録はSpringer社からLNCS 2299として発行されている。
これ以前は、ドイツ語のタイトルなので、ドイツ語圏のいわば国内会議であったと思われる。これ以降は国際会議の形となっている。
6) IPDPS 2002(Fort Lauderdale、フロリダ州)
第16回目となるIPDPS 2002 (16th International Parallel and Distributed Processing Symposium)は2002年4月15日~19日にフロリダ州Fort LauderdaleのMarriott Marinaで開催された。主催はIEEE/CS TCPP、共催はIEEE/CS TCCA、IEEE/CS TCDP、ACM SIGARCHである。19件のWorkshopsと1件のTutorialが行われた。3件の基調講演が行われた。
|
Unknowing Research Subjects: Game Artists as Parallel Programmers |
Seamus Blackley, Microsoft |
|
Perspectives in Building Commercial Infrastructure for the Internet |
Daniel Sabbah, IBM |
|
SETI@home and Internet-Scale Distributed Systems |
David P. Anderson, United Devices, Inc. |
会議録がCD-ROMでIEEEから発行されている。
7) COOL Chips V(東京)
1998年から開催されているCOOL Chips(IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)は、5回目のCOOL Chips Vを2002年4月18日~20日に東京の機械振興会館で開催した。基調講演・招待講演・パネル討論は以下の通り。
|
Keynote:” Electronic Numbering of Products and Documents Using the μ-Chip, a Micro-rfID(radio-frequency IDentification) Backed by Networked Database, Brings About New Business and Life Styles, Innovating Manufacturing, Distribution, Consumption, Tracking, and Recycling” |
Shojiro Asai (Hitachi) |
|
Keynote:” Where Is the Next Silicon Valley for Chip and Related Industries?” |
Richard Dasher (Stanford U.) |
|
Invited:”Wireless Convergence Calls for Advanced Systems Level Designs” |
Nigel C. Dixon (TI Japan) |
|
Invited:” GRAPE Project–Future of High-performance Scientific Computing ?” |
Junichiro Makino (U. of Tokyo) |
|
Invited:” Challenge of System-in-a-package and MEMS Technology” |
Min-Shyong Lin and Chengkuo Lee (Asia Pacific Microsystems, Inc.) |
|
Panel: Do Game chips contribute to High Performance Computing? |
Chair and Organizer: Taisuke Boku (U. of Tsukuba) |
今回から3日間に増えたが、最終日は3件のLectureが行われた。
8) ICCS 2002(Amsterdam)
第2回となるICCS 2002 (The 2002 International Conference on Computational Science)は2002年4月21日~24日にオランダのAmsterdamにおいて開催された。参加者は約400人。共同議長はPeter Sloot (U. van Amsterdam), Jack Dongarra (U. of Tennessee), C. J. Kenneth Tan (U. of Western Ontario)の3名である。7件の招待講演が行われた。
|
e-Science, e-Business and the Grid |
Tony Hey (University of Southampton, UK) |
|
Computational Science on the Grid |
Francine Berman (SDSC) |
|
Computational chemistry |
Michiel Sprik (University of Cambridge, UK) |
|
Grid Computing: An Evolutionary Strategy for Industry |
Wolfgang Gentzsch (Sun Microsystems) |
|
Iterative Methods: a long history for fast convergence |
Henk van der Vorst (Universiteit Utrecht, The Netherlands) |
|
From peer-to-peer to community grids |
Geoffrey Fox (Florida State University, USA) |
|
The Virtual Laboratory on the Grid
|
Bob Hertzberger (Universiteit van Amsterdam, The Netherlands) |
会議録はSpringerのLNCS 2329~2331として出版されている。
9) ApGrid Workshop(台北)
第1回のAsia Pacific Grid Workshop 2001が2001年10月22日~24日に品川プリンスホテルで開催されたのに続いて、the 2nd ApGrid Workshop / Core Meetingが5月14日~17日台北で開催された。
10) ISHPC 2002(原研関西研究所)
4回目となるISHPC (International Symposium on High Performance Computing) 2002は、2002年5月15日~17日に原子力研究所関西研究所(京都府木津川市、現在は量子科学技術研究開発機構、関西光量子科学研究所)で開催された。参加者は147名。基調講演はThomas Sterling、Tony Heyおよび姫野龍太郎であった。 (International Workshop on OpenMP: Experiences and Implementations) 2002とHiWEP (HPF International Workshop: Experiences and Progress) 2002が併設された。会議録はLNCS 2377, Springerとして発行されている。
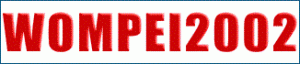 |
|
11) WOMPEI 2002(原研関西研究所)
WOMPEI (International Workshop on OpenMP: Experiences and Implementations)が5月15日に原子力研究所関西研究所において開催された。これは上記ISHPC 2002の一部として開催された。
12) CCGrid 2002(Berlin)
昨年に引き続きCCGrid 2002 (2nd IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, 2002)が5月21日~24日にベルリンのthe Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (formerly Prussian Academy of Sciences and Humanities)で開催された。General ChairsはAlexander Reinefeld (Zuse Institute and Humboldt Universität, Berlin, Germany)とKlaus-Peter Löhr (Freie Universität, Berlin, Germany)。Program Committee ChairはHenri E. Bal (Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands)。参加者は220名。以下の5件の基調講演が行われた。
|
Charlie Catlett |
“The Philosophy of TeraGrid: Building an Open, Extensible, Distributed TeraScale Facility” |
|
Chris Johnson |
“Visualization and VR for the Grid” |
|
Andrew Chien |
“Distributed Computing Technologies and Their Application to Drug Discovery” |
|
Reinhard Schneider |
“Drug Discovery on Cluster Farms” |
|
Hans Falk Hoffmann |
“From the “Higgs Particle” to Technology, From the Web to the Grid: Fundamental Science, Technology, and International Cooperation” |
13) ISCA 2002 (Anchorage)
第29回目となるISCA 2002 (29th International Symposium on Computer Architecture)は、2002年5月25日~29日にアラスカ州のAnchorageで開催された。委員長はYale Patt (The University of Texas at Austin)である。電子版会議録は、ACM、IEEE、IEEE/CSに置かれている。
14) ISC2002 (Heidelberg)
2002年6月19日~22日にHeidelbergで開催されたISC2002については別の章で記す。
15) ICS 2002(New York City)
第16回目となるICS 2002 (the 16th international conference on Supercomputing)は、2002年6月22日~26日にColumbia大学(New York市)で開催された。主催はACM SIGARCH、組織委員長はKemal Ebcioglu(IBM)、プログラム共同委員長はKeshav Pingali(Cornell University)とAlex Nicolau(University of California)であった。3件の基調講演が行われた。
|
Can the Earth Simulator Change the Way Humans Think? |
Tetsuya Sato, the Earth Simulator Center |
|
Challenges and Opportunities in Autonomic Computing |
Alfred Z. Spector, IBM |
|
Clustered Approaches to HPC via Commodity HW + Highly Evolved SW |
David Kuck, Intel |
会議録はACMから発行されている。
16) Lattice 2002(MIT)
第20回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 2002)は、2002年6月24日~29日に米国マサチューセッツ州のMITで開催された。会議録は、Nuclear Physics B – Proceedings Supplements 119 (2003)として出版されている。
17) VECPAR 2002(Porto)
第5回目となるVECPAR 2002(今回から会議名はInternational Conference on High Performance Computing for Computational Science)は、2002年6月26日~28日にポルトガルのPortoで開催された。会場は、Porto大学工学部の新建屋である。発表のうち49論文がSpringerのLNCS, volume 2565として出版されている。
18) HPDC-11(Edinburgh)
HPDC-11 (11th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing, 2002.)が、2002年7月24~26日にEdinburgh International Conference Centerで開催された。GGF5に接続して開催された。2件の基調講演が行われた。
|
Keynote |
|
Irving Waldasky-Berger, IBM |
|
Keynote Lecture |
Herding Cats, Mice and Elephants – Network resource implications for the Grid |
Jon Crowcroft, Cambridge |
19) WOMPAT 2002(Fairbanks、アラスカ州)
WOMPAT (Workshop on OpenMP Applications and Tools) 2002が2002年8月5日~7日にアラスカ州FairbanksのAlaska大学内にあるARSC (Arctic Region Supercomputing Center)で開催された。会議録は発行されなかったが、論文の一部はWOMPAT 2003の会議録に収録されている。
会議に参加した筑波大の朴泰祐氏によれば、8月8日、同センターに設置されたCray SX-6(写真は後の第196回の記事にある)を見学したとのことである。8プロセッサ、ピーク64 GFlopsのマシンである。筐体の形は地球シミュレータとは違うが、179回の記事にあるSX-6とはほぼ同じである。結局これがアメリカ国内の唯一のCray SX-6となった(あと6台はカナダに設置)。同センターには、そのほかにT3E、SV1ex、SP2などが設置されている。
20) HOT CHIPS 14(Stanford大学)
1989年から始まった高性能半導体の国際会議HOT CHIPSは14回目のHOT CHIPS 14 (2002)を、2002年8月18日~20日にStanford大学のMemorial Auditoriumで開催した。基調講演2件とパネル討論は以下の通り。
|
“Always On: Always Aware. Net Life 2005” |
Eric Schmidt (Google) |
|
“Incredible Challenges of the Air Traffic Control System” |
Tom Edwards (NASA) |
|
Panel: Embedded Systems Software : Visions of the Future |
Moderator: John Mashey (Sensei Partners) |
21) ICPP 2002(Vancouver)
第31回目となるICPP 2002 (31st International Conference on Parallel Processing)は、2002年8月20日~23日にカナダのVancouverのThe Renaissance Vancouver Hotel Harboursideで開催された。4年周期の4年目である。主催はIACC (The International Association for Computers and Communications)、共催はOhio State University他である。3件の基調講演が行われた。
|
Proteins, Petaflops and Algorithms |
William Pulleyblank, IBM |
|
The Cost of the Single System Image |
John Gustafson, Sun Microsystems |
|
An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration |
Ian Foster, ANL |
電子版会議録はIEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。
22) IFIP Congress 2002(Montréal)
第17回目のIFIP Congress 2002 (World Computer Congress 2002)は、2002年8月25日~29日に、カナダのMontréalで開催された。会議録は10巻にわかれてKluwer社から出版されている。
23) Euro-Par 2002(Paderborn、ドイツ)
第8回目のEuro-Par 2002, Parallel Processing, 8th International Euro-Par Conferenceは、2002年8月27日~30日にドイツのPaderbornで開催された。会議録は、Springer社からLNCS 2400として出版されている。
 |
|
24) CCGSC 2002 (Lyon)
CCGSC (Clusters and Computational Grid for Scientific Computing)は、1992年から隔年で、アメリカまたはフランスで開催されている。アメリカ側の主催者はJack Dongarra (U. Tennessee Knoxville)である。参加は招待者のみ。1992年は、Workshop on Environments and Tools for Parallel Scientific Computingと題して開かれた。今年も恒例により9月中旬(要確認)にLyonから東の、アルプスの山間いのFaverges(Annecy湖の反対側)で開催された。参加者写真はCCSGC 2006の記録から。参加した松岡聡の話によると、場外で地球シミュレータが話題になり、Ken KennedyはHPFが15 TFlopsも出したことに満足し、Tom Sterlingはコモディティより専用アーキテクチャがよいと言い出したり(BeowulfよりHTMTということか?)、いろいろ盛り上がったとのことである。
25) iGrid 2002(Amsterdam)
これは、高速ネットワークを活用して、世界中の様々な分野の研究者と、広域分散処理、バーチャルリアリティ、大型データベースなどの技術を使って共同研究を行うプロジェクトである。第1回はSC98の研究展示として出され、第2回はINET 2000(パシフィコ横浜)に併設して開催された。今回のiGrid 2002は2002年9月23日~26日にAmsterdam Science and Technology Center (WTCW)で会議に合わせて開催された。
26) Cluster 2002(Chicago)
第4回目となるCluster 2002 (2002 IEEE International Conference on Cluster Computing)は、2002年9月23日~26日にChicagoで開催された。会議録はIEEEから出版されている。
27) EuroPVM-MPI 2002(Linz、オーストリア)
9回目となるEuroPVM-MPI 2002(9th European PVM/MPI Users’ Group Meeting)は2002年9月29日~10月2日にオーストリアのLinzで開催された。9件の招待講演と2件のチュートリアルが行われた。
|
招待講演 |
|
|
High Performance Computing, Computational Grid and Numerical Libraries |
Jack Dongarra |
|
Performance, Scalability and Robustness in the Harness Metacomputing Framwork |
Vaidy sunderam |
|
Surfing the Grid – Dyanmic Task Migration in the Polder Metacomputer Project |
Dick van Albada and Peter Sloot |
|
Petascale Virtual Machine: Computing on 100,000 Processors |
Al Geist |
|
MPICH2: A New Start for MPI Implementations |
William Gropp |
|
Making Grid Commputing Mainstream |
Zoltan Juhasz |
|
Process Management for Scalable Parallel Programs |
Ewing Lusk |
|
A Security Attack and Defence in the Grid Environment |
Barton P. Miller |
|
Performance Analysis: Necessity or Add-onGrid Computing |
Michael Gerndt |
|
チュートリアル |
|
|
MPI on the Grid |
William Gropp and Ewing Lusk |
|
Parallel Application Development with the Hybrid MPI+OpenMP Model |
Barbara Chapman |
Proceedingsは、‟Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface”のタイトルで、Springer社からLNCS 2474として出版されている。
28) Microprocessor Forum 2002 (San Jose)
2002年10月14日~17日に、カリフォルニア州San Jose Fairmont Hotelで開催されたMicroprocessor Forum 2002は、ITバブル崩壊にもかかわらず超高速CPUのラッシュであった。冒頭の基調講演でIntel FellowのJohn Crawfordは、2007年頃には1B(109)個のトランジスタがチップに集積されると語った。 (HPCwire 2002/10/18) IBM社はPOWER4ベースの64bitプロセッサPowerPC 970の詳細を明らかにし、富士通の井上はSPARC64Vの詳細を発表した。(HPCwre 2002/10/11) (ASCII.JP 2002/10/17) (PC Watch 2002/1017)
29) The Linux HPC Revolution (フロリダ州St. Petersburg)
この会議は、2002年10月23日~25日に、The Linux Clusters Institute (LCI)の主催によりフロリダ州St. Petersburgで開催された。テーマはHPCのためのLinuxクラスタの利用である。協賛はMyricom社とthe Alliance (the National Computational Science Alliance)である。詳細は不明。(HPCwire 2002/5/10)
30) SC2002 (Baltimore)
SC2002(11月16日~23日、Baltimore)は別の章に記す。
31) HPC Asia 2002 (Bangalore, India)
HPC Asia 2002(12月16日~20日,Bangalore, India )は別の章に記す。
32) PRDC 2002(つくば市)
PRDC 2002 (Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing)は、2002年12月16日~18日、筑波国際会議場で開催された。この会議は1989年から始まり9回目である。1997年まではPacific Rim International Symposium on Fault-Tolerant Systemsと呼ばれており、隔年開催であった。1999年からは現在の名称に変え、毎年開催している。
33) ICPADS 2002(Zhongli、台湾)
ICPADS 2002 (Ninth International Conference on Parallel and Distributed Systems)は、2002年12月17日~20日に台湾のZhongli(中壢)で開催された。会議録はIEEE/CSから発行されている。
34) HiPC 2002(Bangalore)
HiPC 2002 (9th IEEE International Conference on High Performance Computing)は、2002年12月18日~21日にインドのBangaloreのThe Taj Residencyで開催された。12カ国から投稿された145編の投稿論文から57編採択した。基調講演等は以下の通り。会議録はSpringerから出版されている。
|
Keynote:”Protocols for Bandwidth Management in Third Generation Optical Networks” |
Imrich Chlamtac (Texas大学Dallas) |
|
Keynote: “Beyond FPGAs, Field Programmable Systems” |
Patrick Lysaght (Xilinx) |
|
Keynote: “Parallel Computations of Electron-Molecule Collisions in Processing Plasmas” |
B. Vincent McKoy (CalTech) |
|
Keynote: “Computational Science and Engineering — Past, Present, and Future” |
N. Radhakrishnan (Army Research Labs, USA) |
|
Keynote: “Collaboratory for Info-Bio-Nano Simulations” |
Priya Vashishta (USC) |
|
Industry Keynote: “Computing Environment for Large-Scale Interdisciplinary Applications” |
Raju R. Namburu (U.S. Army Research Lab.) |
|
Industry Keynote: “Redressing the Balance” |
Burton Smith (Cray Inc.) |
次回はISC2002である。Rick Stevensは、1990年代にアメリカで行われたPetaflopsへの議論を総括し、演算性能増大に伴い、メモリ総量とメモリバンド幅がどうスケールするかが問題であると述べた。Top500では地球シミュレータが堂々1位を占めた。
 |
 |
 |

