提 供
HPCの歩み50年(第53回)-1996年(a)-
筑波大学と日立が共同開発したCP-PACS (1024)が3月筑波大学で完成した。その商用版のSR2201 (1024)が東大に設置され6月のTop500では220.4 GFlopsで首位を占めた。筑波大学のCP-PACSは2048ノードに増強し、11月のTop500において368.2 GFlopsで首位を獲得した。富士通は超並列機AP3000を発表した。この年、NCARでの日米貿易摩擦が再び起こる。
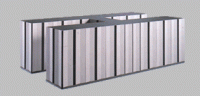
社会では、1/5村山首相が退陣表明、1/11橋本龍太郎内閣成立、2/1自衛隊、ゴラン高原へPKO派遣(2013/1/15まで)、2/9菅直人厚生大臣、厚生省エイズ研究班の資料発見を公表、2/10豊浜トンネルで岩盤崩落、2/28チャールズ皇太子、ダイアナ妃と離婚へ、3/14薬害エイズ訴訟でミドリ十字謝罪、5/10住専処理を含む予算成立、5/29岡山県で集団食中毒、O157と判明、7月堺市でも、7/20最初の「海の日」、7/20アトランタ五輪開幕、「自分で自分をほめたい」(有森裕子)、10/20小選挙区選挙、11/23バンダイから『たまごっち』発売、12/4厚生省汚職事件、前事務次官逮捕、12/17ペルー日本大使公邸がゲリラに占拠される、など。「援助交際」「ルーズソックス」「チョベリバチョベリグ」「アムラー」などが流行語トップテンに。ゴラン高原に派遣された自衛官については、筆者が1999年末にイスラエル北部のカルメル山に行ったとき、ジョギングしている隊員にばったり会った。眼下はゴラン高原であった。
学術振興会の国際交流委員会にいた関係で、3月10~16日にベトナム調査団に加わった。菊池健団長を含み総勢8名、前半はハノイ、後半はホーチミンシティ(昔のサイゴン)であった。共産国でアカデミーの研究所が研究の実質を握っていて、設備を持ち、大学は博士号授与権を持つという構造であった。訪問の目的は、研究教育の現状を視察するとともに、研究交流のパートナーを見定めることであった。詳細は筆者の「ベトナムの計算機事情」を参照してください。情報科学分野では非常に応用指向であるのが印象的であった。筆者にとってベトナムは初めてであり、驚くことばかりであった。ドイモイ(刷新)がどうにか軌道に乗ったところであったが、インフラがまだぼろぼろで、自動車もまばらであった。ハノイ市内には交通信号が1カ所だけ設置されていた。ただ、人々の復興への意欲は高く、今後の発展が期待できた。
珍しく情報処理学会年会(大阪工業大学)での原著講演の座長(9月6日)を依頼されたのでほいほい引き受けたが、発表者の一人である神奈川大学のY氏に年会後メールで絡まれて往生した。会場では筆者が一番好意的であったつもりであったが。
日本政府の動き
1) 科学技術基本計画
1995年11月に科学技術基本法が制定されたが、これに基づき、1996年7月2日、第1期の科学技術基本計画(5年間)が閣議決定された。「内外の諸問題に対応するため、また人類共通の知的資産である基礎研究を進めるため、我が国は自ら率先して未踏の科学技術分野に挑戦していくことが必要である。しかし、日本の研究開発投資額は1993年以来減少し、特に政府研究開発投資が対GDP比で欧米主要諸国を依然として下回っている。」と指摘し、科学技術振興における国の最優先課題を定めている。研究開発に関する情報化のために、高性能計算機の整備や応用ソフトウェア開発の必要を述べているのはいいとして、学内LAN等のATM(非同期転送モード)化を提唱している点は技術の方向性を見誤った。コンピュータネットワークとマルチメディア通信をATMによって統合するという方向性は結局実現せず、むしろIPが広範囲にわたって利用されるようになった。科学技術基本計画に基づき各大学にATMネットワークの予算が付いたが、活用されたであろうか。某大学ではその予算でATMとIPの両方の基幹ネットワークをキャンパス中に別々に引いたが、使われたのはIPの方だけであった。
2) 『地球変動予測の実現に向けて』
この科学技術基本計画に基づき、地球規模の諸現象の解明と予測に向けての研究開発の重要性が指摘された。1996年7月、科学技術庁の「航空・電子等技術審議会 地球科学技術部会」は、『地球変動予測の実現に向けて』と題する報告書をまとめた。地球規模で起きるさまざまな現象・問題を、科学技術を活用して解明し、その成果を活用して精度の高い将来予測を行おうとする戦略的なプログラムであった。 これを受けて1997年3月から7月にかけて、科学技術庁において「計算科学技術推進会議地球シミュレータ部会」(部会長、松野太郎)が開催された。これが後の地球シミュレータ開発のきっかけの一つとなった。
このコンピュータの名前として「ガイアシミュレータ」とか「地球環境シミュレータ」などの名前もあったが、「地球シミュレータ」という名称が定まったのは、1996年12月の「地球科学の推進と地球シミュレータ開発計画」(下書き)ではないかと『地球シミュレータ開発史』(p.41)は述べている。
3) 未来開拓事業
日本学術振興会は1996年度から未来開拓事業を始めた。これは、ピア・レビューではなくいわばトップダウンで助成を行うものであり、大崎仁日本学術振興会理事長のイニシアチブによるものと言われている。当初予算は110億円であった。この事業は、14人で構成される事業委員会があり、その下に、理工領域、生命科学領域、複合領域の研究領域の研究推進委員会がある。各領域でいくつかの研究分野を設定し、研究分野の選考委員会が研究プロジェクトを選定する。研究期間は5年間、研究経費はプロジェクト当たり5千万円から3億円程度とした。当時は気づかなかったが、科学技術基本計画に始まる流れのなかで生まれた事業であった。
初年度の助成117件について、東大に偏るなど選考過程がフェアでないと批判がなされた。とくに、選考委員会委員98人のうち34人は自分で助成金を受けるリーダーとなっているという(Nature, Vol. 383, October 3, 1996)。計算科学分野が始まるのは2年目からである。
4) TISN解散
東大理学部の運営するTISN(東大国際理学ネットワーク、1989年運用開始)は、大学や政府機関にネットワークサービスを行ってきたが、JST がIMnet(省際ネットワーク)を構築したので、文部省関係以外の組織はそちらに移った。文部省関係はSINETに移行。TISNは1996年7月24日に、TISN解散記念パーティーを挙行した。
日本の学界の動き
1) Gordon-Bell Prize
今年も SC’96 で Gordon Bell Awards が発表された。日本関係では、性能部門でNAL NWT (Simulation of 3-Dimensional Cascade Flow (in jet engines) with a Numerical Wind Tunnel)、 専用計算機部門でGRAPE-4 (N-body Simulation of Galaxy Formation on a Grape-4 Special-Purpose Computer)が受賞した。
2) Hokke 96
第3回「ハイパフォーマンス・コンピューティングとアーキテクチャの評価」に関する北海道ワークショップ(Hokke-96)は、この年も札幌ソフトウェア専門学校を会場として3月4日(月)~5日(火)に開催された。4日はHPC研究会、5日は計算機アーキテクチャ研究会の連続研究会であった。4日の夜には、サッポロビール園で懇親会が開催された。
3) JSPP 96
8回目の並列処理シンポジウムJSPP’96は、6月18日(火)~20日(木)に早稲田大学総合学術センター国際会議場を会場に開催された。情報処理学会の5研究会、電子情報通信学会の2研究会、人工知能学会の1研究会が主催、日本ソフトウェア科学会と日本応用数理学会が協賛であった。
続いて21日(金)には、同じ会場で国際ワークショップ HPMCC (High Performance Multimedia Computing and Communication)が開催された。
4) PSC 96
1994年に発足したJSPP並列ソフトウェア・コンテストは第3回を迎えた。使用できる並列コンピュータは、日本アイビーエムのSP2(統数研)、日本電気のCenju-3、日立製作所のSR2201、富士通のAP1000+の4種類であった。この年は筆者が委員長を務めた。日本クレイにはCS6400の提供をお願いしたが、もうすぐStarfireが出るので今年も見送るということで、例年通り委員だけを出してくださった。日本鋼管(Convex)にも声を掛けたが、ConvexはHP傘下に入ったばかりで今回マシンは提供できないが、将来の可能性を考えて、委員を出してくださった。両社とも副賞を提供してくださった。
問題はいろいろ議論した挙げ句、2^17 * 5^2 = 3,276,800個の1次元複素データの高速フーリエ変換および逆変換となった。精度は64ビット。3位までの入賞者がマシンごとに表彰された。4社合計の正味のチーム数は、エントリ103チーム、予選結果提出37チーム、予選通過27チーム、本選完走21チームであった。
| マシン | AP1000+ | SR2201 | SP2 | Cenju-3 |
| エントリチーム | 82 | 68 | 60 | 62 |
| 参加者数 | 163 | 125 | 117 | 137 |
| 予選結果提出 | 23 | 17 | 8 | 10 |
| 予選通過 | 15 | 14 | 7 | 8 |
| 本選完走 | 13 | 10 | 6 | 6 |
| 1位 | 牧野・長井・丹羽(東大理) | 高橋大介(東大理) | 高橋大介(東大理) | 荒木・馬場・大内・辻(東大工) |
| 2位 | 二上・植山・牧野(東大工) | 富松・黒田・渡辺(東大理) | 富松・黒田・渡辺(東大理) | 黒田洋介(早稲田理工) |
| 3位 | 富松・黒田・渡辺(東大理) | 荒木・馬場・大内・辻(東大工) | 荒木・馬場・大内・辻(東大工) | 佐藤敦他13名(北陸先端・山形大) |
5) SWoPP 秋田’96
1996年並列/分散/協調処理に関する『秋田』サマー・ワークショップ (SWoPP 秋田’96)は、1996年8月26日(月)-29日(木) に秋田県総合生活文化会館『アトリオン』(秋田県秋田市)で開催された。第9回である。主催は、電子情報通信学会の2研究会、情報処理学会の5研究会である。発表件数は149(110件大学、21件企業、18件国立機関)、参加者数は219(31大学160名、20企業35名、3研究機関24名)であった。
6) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所は、昨年に続き三井斌友(名古屋大)を代表者として、研究集会「科学技術における数値計算の理論と応用 II」を11月13~15日に開催した。報告は、講究録No.990に収録されている。
7) 数値解析シンポジウム
第25回数値解析シンポジウムは、5月29~31日に、湯沢パークリゾート(ホテル)で開催された。担当は前回に引き続き東京大学工学部森正武・杉原正顯研究室であった。参加者99名。
8) NEC HPC 研究会
5月28日に第3回NEC HPC研究会が開かれ、筆者は基調講演「並列処理と並列言語」を行った。また12月17日には第4回NEC HPC研究会が開かれ、Chul Park教授(東北大、航空宇宙工学)が基調講演を行った。
9) 日本IBM HPCユーザーズ・フォーラム
1996年のHPC Users’ Forumが7月24日に箱崎で開催された。「MPIとHPFによるプログラミングの方法」(寒川光)、「SPによるパラレル流体シミュレーション」(伊平尚志)、「仮想現実感とその将来、そしてSP」(中村維夫)、「並列処理計算法の計算化学・理論化学での応用」(橋本)などの他、JSPPのPSCのIBM部門優勝者高橋大介による「最高速FFTパラレル・プログラムはこうして開発した」という報告もあった。米国のIBMからは「米国での技術計算分野におけるSPの話題」(S. Clarke)という講演があった。筆者は「パラレルコンピューティングの最近の話題と今後について」という講演を行った。
また、「計算分子科学パラレル分科会」も計画された。
10) PCW’96
富士通研究所(川崎市中原)は、CAP-IIやAP1000を開発していた頃からPCW (Parallel Computing Workshop)を開いてきたが、その6回目のPCW’96が11月13日に開催された。招待講演 “Future Trend of Parallel Computing in Computational Sciences” を行った。
11) 科研費重点領域「超並列」
1992年に始まった文部科学省科学研究費重点領域研究「超並列原理に基づく情報処理体系」(代表田中英彦)は、1995年度が最終年度で、その最終の重点総括班の会議を、1996年1月5~6日に愛媛県松山市のKKR道後 泉南荘で開催し、最終報告や、今後の相談を行った。
1996年3月21~22日には、東京大学工学部11号館14号館において、重点領域研究の最終成果報告公開シンポジウムを開催し、成果のデモンストレーションを行った。
12) 並列・分散コンソーシアム(PDC)
1995年10月に発足したPDCは、上記重点領域シンポジウムに引き続き、3月22日午後、PDC賛助会員企業の方およびPDC研究推進会員を対象に、非公開の成果報告会およびデモンストレーションを行った。成果といっても今後の活動方針の提示で、デモも科研費「超並列」の成果が中心であった。企業3社からの発表もあった。
13) 筑波大学CP-PACSプロジェクト
CP-PACS (1024 PU, memory 64 MB/PU)は1996年3月25日完成設置され、翌年5月21日に完成披露式が行われた。
東京大学大型計算機センターには、2月、日立の商用版SR2201 (1024 PU, memory 256 MB/PU)が納入され、LINPACKベンチマークで220.4 GFlopsを達成し、6月のTop500の首位を占めた。この時点の筑波大学のCP-PACS (1024)は出さなかったが、メモリが小さい(64 MB/PU)のでLINPACK性能はこれには及ばなかったものと思われる。筑波大の目玉は、1993年に学術情報処理センターに設置したVPP500/30で27位であった。
CP-PACSはPU数を増強し、2048 PUのシステムが9月18日に完成設置された。9月27日にLINPACKベンチマークで368.2 GFlopsを達成し、10月4日から運用が行われた。11月18日付けのTop500の首位を獲得し、11月19日には完成記者会見を行った。表彰式の話はSC96の項で述べる。ちなみに、2位は航技研のNWT (229.7 GFlops)、3位は前回首位の東大大型センターのSR2201 (220.4 GFlops)であった。
このとき某新聞社科学部が、「NECのSX-4は1 TFlopsだから、その方が高性能だ。CP-PACSはチャンピオンではない。」などと珍奇なことを言い出した。カタログ性能と実機で実現した性能を比較しても意味ない、と強く反論したのだが、5月29日付け全国版紙面に「どちらがチャンプ」とかいう間の抜けた記事を載せていた。筆者の自宅にもその新聞社から電話があったが、さる懇親会で酔っ払っていて相手をしないですんだ。
1993年の記事で述べたが、1996年6月のリストの2位は航空宇宙研究所のNWT(数値風洞)で、166コア、Rpeak=279.58、Rmax=170.0となっている。1995年11月までは140コア、Rmax=170.0となっていて、コア(プロセッサ)を増強したのに、LINPACK性能は変更していない(再計測しなかったのであろう)。筑波大学のCP-PACSが首位をとる1996年11月では、167コア、Rpeak=281.3、Rmax=229と出ている。LINPACKを計り直したと思われる。コア数が増えているが、I/Oノード2台のうち1台を演算に駆り出したのであろう。上に書いたように、これにより、東大大型センターのSR2201(1024)の220.4を越えて2位を保った。なお、NWTのクロスバは56プロセッサが単位で、I/Oノードを含めて168は3単位の上限であった。
12月8~14日にはPDG(素粒子データグループ)の共同研究でLBNLに行く計画があったので、SC96においてNERSCのHorst Simonにそのことを話したら、適当な時間に彼のグループでCP-PACSの疑似ベクトル機構についてセミナーをやってくれということになった。内容は中村宏らがICS93などで講演した範囲にとどめたが、Simonは興味深そうに聞いていた。その後、NERSCの施設、特にESnet (Energy Science Research Net)関連の施設を案内していただいた。
CP-PACSは2005年9月29日にシャットダウンするまで2813日間稼動(Power-on)した。Top500に最後に載ったのは2003年6月で312位であった。
長くなったので、日本の学界の動きの続きは次回に。続いて日本の企業の動き、アメリカやヨーロッパの動きなど。
(タイトル画像: HITACHI SR2201 画像提供:日立製作所)
 |
 |
 |

