新HPCの歩み(第198回)-2003年(a)-
|
地球シミュレータ登場後1年が経ち、運用が順調に進むとともに、次期スーパーコンピュータ計画に向けてのRISTの調査研究会が動き出した。グリッド関係では、NAREGIが始まるとともに、産総研グリッド研究センター、アジアグリッドイニシアチブ、ビジネスグリッドコンピューティングプロジェクトなどが始まる。 |
社会の動き
2003年(平成15年)の社会の動きとしては、1/10北朝鮮、NPT脱退宣言、1/14小泉首相、靖国神社参拝、1/18天皇が東大病院で前立腺手術、1/20横綱貴乃花引退、1/29朝青龍が横綱昇進、1/31汐留シティセンター竣工、2/1ニース条約発効、2/1コロンビア号、大気圏突入で空中分解、2/18北京で日本人学校に脱北者駆け込み、2/18韓国で地下鉄放火事件、2/26ハウステンボスが会社更生法申請、3/2英国Observer紙はNSAからGCHQに送られたメールをリークした(Katharine Gun事件)、3/3りそな銀行発足、3/11国際刑事裁判所(ICC)がオランダのハーグに設置、3/12 WHOがSARSについて世界規模の警報、3/5三浦ロス疑惑に関し日本での無罪確定、3/20米軍英軍、イラクに侵攻、4/1郵政事業庁が日本郵政公社に、4/3韓国ドラマ「冬のソナタ」NHK BS2で放送開始、4/13第15回統一地方選挙、石原慎太郎圧勝、4/14ヒトゲノム解読終了、公開、4/25六本木ヒルズオープン、4/28岐阜県に白装束の集団(パナウェーブ)が現れ林道占拠、5/1ブッシュ大統領、イラクでの大規模な戦闘の終結を宣言、5/5アメリカでLinkedIn始まる、5/9小惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ(2010/6/13地球に帰還)、5/23個人情報保護法成立、5/26宮城県沖地震(M7.1)、6/2-3第29回首脳会議(フランス、エビアン)、6/6有事法成立、6/6-9廬武鉉大統領来日、6/22カリフォルニア州の高速鉄道BARTがサンフランシスコ国際空港に乗り入れ、7/5最後まで台湾に出されていたSARSの感染地域指定解除、7/18辻本清美逮捕、7/20九州で集中豪雨、7/22米軍がフセイン元大統領の息子2人を殺害、7/26イラク特措法成立(日本)、7/26宮城県北部地震(本震M6.4、M6を超える地震が3回)、8/10沖縄都市モノレール(ゆいレール)開業、8/14北米で大停電、8/29 Skypeのβ版が公開、9/9野中広務、引退表明、9/10外務審議官宅に発火物、9/15阪神、リーグ優勝、9/16名古屋で立てこもり男がガソリンまき放火、9/26十勝沖地震(M8.0)、9/26自由党が民主党に合流、10/1東海道新幹線、品川駅開業、10/7 Arnold A. Schwarzeneggerがカリフォルニア州知事に当選、10/15中国が初の友人宇宙船「神舟5号」の打ち上げに成功、10/19マザー・テレサがカトリック教会の福者に列せられる、10/21準惑星エリス(136199 Eris)が撮影された、10/23小泉首相が中曽根、宮沢元首相に政界引退勧告、11/4観測史上最も激しい太陽フレア、11/9衆議院総選挙、11/15武蔵丸引退、11/15土井たか子社民党党首、引責辞任、11/20マイケル・ジャクソン逮捕、11/24コロンビアで2001年に誘拐されていた日本企業の現地法人副社長が射殺遺体で見つかる、11/29イラクで日本人外交官2人殺害、11/29足利銀行経営破綻、一時国有化、12/1地上ディジタルテレビ放送、東京、大阪、名古屋で試験放送開始、12/13アメリカ軍、フセイン元大統領を拘束、12/26イランでバム地震(M6.6)、12/26航空自衛隊がイラクに派遣される、など。
 |
|
流行語・話題語としては、「毒まんじゅう」「マニフェスト」「SARS」「オレオレ詐欺」「世界に一つだけの花」「世界の中心で、愛を叫ぶ」(11月ミリオンセラー)など。(写真は神戸ポートアイランドにあるO2HIMAWARIより。筆者撮影)
チューリング賞は、Smalltalk の開発チームを指導し、現代のオブジェクト指向プログラミングの元となる多くの考えを開拓したことに対して、また、パーソナルコンピューティングへの基礎的貢献に対してAlan Curtis Kay(たぶん所属はHewlett-Packard社)に授与された。
エッカート・モークリー賞は、Multiflow Computerの共同創立者であり、VLIWアーキテクチャ、命令レベル並列性、Traceスケジューリングコンパイラの発明者であるJoseph A “Josh” Fisher(Hewlett-Packard Labs)に授与された。
スウェーデン王立科学アカデミーは10月7日、2003年のノーベル物理学賞をロシアと米国の国籍を持つ米アルゴンヌ国立研究所のDr. Alexei A. Abrikosov名誉研究員(75)、ロシア人でP・N・レベジェフ物理学研究所のDr. Vitaly L. Ginzburg前理論研究グループ長(87)、英国と米国の国籍を持つ米イリノイ大のAnthony J. Leggett教授(65)の3氏に授与すると発表した。授賞理由は「超伝導と超流動の理論に対する先駆的な貢献」。Leggett教授の晴子夫人は日本人であると報じられた。化学賞は、アクアポリンの発見に対しPeter Agreに、イオンチャネルの構造および機構の研究に対しRoderick MacKinnonに授与された。生理学・医学賞は、MRIの発明に対し、Paul LauterburとPeter Mansfieldに授与された。
SARSに明け暮れた1年であった。シンガポールから来た知人のセミナーが大学の命令でキャンセルされるなどの騒ぎもあった。FM電波の異常受信で地震が予知できるという串田嘉男氏の研究がマスコミに取り上げられ、9月半ばにM7クラスの地震が関東南部で起きる可能性があると報道された。有馬朗人氏と上田誠也氏が9月12日八ヶ岳で検討会を招集したので、「これは本当か」と色めき立った。9月20日、房総半島南部を震源とするM5.5(深さ80キロ)の地震があったが、それだったのか??
4月26日から日本テレビ系の特ダネで、白装束のカルト系団体について報じていた。スカラー(電磁)波が自然を破壊し、タマちゃんの方向感覚を失わせるという主張で、白い木綿の布はスカラー波を防ぐそうである。タマちゃんを捕獲しようとした「タマちゃんを想う会」はこの関連団体のようだ。物理の授業では、電磁波はベクトル波で、スカラー成分はないと習ったが。
筆者も還暦「癸未(みずのと ひつじ)」を迎え、本来ならば2003年度末で定年であったが定年逐次延長で2年延びた。私事ではあるが珍事件があった。「小柳義夫」(コヤナギヨシオ)教授という免疫学の研究者(筆者より15歳ほど若い)が当時東北大学医学部におられることは知っていたが、なんと、2003年に入ってから、東大から筆者に払われるべき旅費などがすべてコヤナギ先生の方に払い込まれていた。あちらが気づいてくださって発覚した。東大のある部局が、コヤナギ先生に旅費を払うために、東大の支払いデータベース上のオヤナギ(筆者)の銀行口座を勝手にコヤナギ先生の口座に書き換えて払ったようである。それで、その後何も知らない理学部から筆者へのすべての支払がコヤナギ先生の口座にredirectionされてしまったという次第。最近マイナンバーカードでも起こった初歩的なミスである。「小柳義夫」なんて珍しい名前は世界に一人と思ったのであろう。所属を見ればすぐわかるのに。理学部事務局の担当者が謝りに来たが、「医学部の教授の方が、理学部や工学部の教授より百倍えらいので、まずそっちに謝りに行ったら」とイヤミを言った。
地球シミュレータ
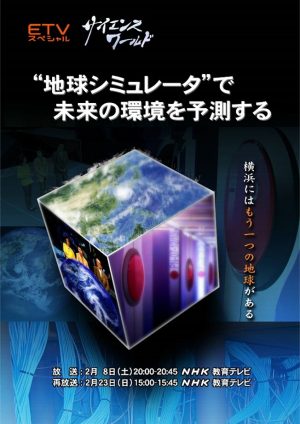 |
|
1) 地球シミュレータ番組
筆者は2月8日(土)20:00 ~20:45、NHK教育テレビのETVスペシャル サイエンスワールド『 “地球シミュレータ”で未来の環境を予測する』のメインプレゼンタとして出演した。シミュレーションの基本原理、ベクトルとスカラの違いなど、できるだけ分かり易く説明した。ベクトルをエスカレーターに、スカラ(並列)をエレベーターに例えた。
話は前年の10月ごろからあり、NHKではSC2002に出かけたり、日本やアメリカのスーパーコンピュータの歴史や気象シミュレーションの歴史などをかなり取材したりしたようである。「三好甫氏が並列とベクトルを合わせることを発明した」というので、「それは正しくない。流体力学や気象のためにこの二つを合わせて使うことを提唱した」に変えてくださいと頼んだ。
クロマキーを使うため配色がうるさく、靴も靴下もズボンもシャツも着るものは全部NHKで用意するので、「身一つで来てください」とのことであった。そのためサイズを通知した。知人からは、「小柳さん、あんな服持っていたの?」と不思議がられた。収録は1月21日(HPCS2003の日)であったが、昼過ぎから夜8時過ぎまで掛かった(出演料は7万円)。メークさんが付きっきりというのは新体験で、タレントにでもなったような気分がした。
担当者から「『プロジェクトX』ではないですから」と何度も念を押された。同じNHKでもチャンネルが違うと仲が悪いらしい。台本はもらっていたが、覚えるものだとはつゆ知らず(覚えろと言われても老化気味の筆者には無理だが)、適当にしゃべった。司会男性はアナウンサーの高市佳明氏、司会女性はサイエンスアイの司会をしていたタレントの中森友香さんであった。中森さんで感心したのは、半導体チップか何かを見せられて驚く場面で、リハーサルのときと、本番のときと、まったく同じように驚いていたことである。さすがプロ、と感心した。よく考えたら当たり前であるが。故三好甫氏の業績がたくさん紹介され、よい供養になった。2月23日(日)15:00~15:45に再放送。余談であるが、2024年4月から始まった「新プロジェクトX」でもスーパーコンピュータ(「京」)が2024年6月15日取り上げられた。
2) 共同プロジェクト公募
運用2年目に入った。2003年3月12日、「平成15年度の地球シミュレータ共同プロジェクト」の公募を開始した。2003年度から、「地球シミュレータ」 を用いて実施する研究課題の名称を、「利用課題」から「共同プロジェクト」 と改めた。利用可能な研究領域として、以下の4分野を定めた。
|
(1) 大気・海洋分野 |
|
(2) 固体地球分野 |
|
(3) 計算機科学分野 |
|
(4) 先進・創出分野 |
(3)(4)は、世界トップの計算資源を、狭義の地球科学以外の分野にも提供するものである。かつて関係者が私に「地球科学以外には一切使わせない」と息巻いていたが、この年から「計算機科学分野」と「先進・創出分野」にも提供されることになった。
前年は課題ごとにリソースの制限を付けなかったので、年度後半から高並列・長時間走行のプログラムが増え、リソースが逼迫したという経験から、課題選定委員会で採択課題ごとに計算資源の上限を定めることとなった。また、2003年度から海外機関等との共同研究も始まった。
3) 地球シミュレータセンター・シンポジウム
昨年に引き続き、第2回地球シミュレータセンター・シンポジウム「人と地球のやさしい関係 ~ もう一つの地球からのメッセージ」を、2003年6月19日、日本科学未来館みらいCANホールで開催した。プログラムは以下の通り。
|
10:30-10:40 |
開会の辞 |
平野拓也(海洋科学技術センター) |
|
10:40-10:50 |
来賓挨拶 |
文部科学省 |
|
10:50-11:00 |
ご挨拶 |
毛利衛(日本科学未来館) |
|
11:00-11:40 |
基調講演 「満1歳を迎えた地球シミュレータ」 |
佐藤哲也(地球シミュレータセンター) |
|
(先進・創出分野) |
||
|
11:40-12:05 |
「カーボンナノチューブの特性に関する大規模シミュレーション」 |
中村寿(高度情報科学技術機構) |
|
12:05-12:30 |
「タンパク質分子科学計算の将来」 |
佐藤文俊(東京大学生産技術研究所) |
|
12:40-14:00 |
昼食 |
|
|
(大気・海洋分野) |
||
|
14:00-14:15 |
「大気・海洋分野の概要」 |
佐久間 弘文 (地球シミュレータセンター) |
|
14:15-14:40 |
「地球温暖化予測の将来」- 温暖化したらどんな天気になるのだろうか? - |
住明正(東京大学気候システム研究センター) |
|
14:40-15:05 |
「地球温暖化は台風や集中豪雨にどのような影響を及ぼすだろうか?」 - 高精度・高分解能気候モデルの開発 - |
青木 孝 (気象研究所) |
|
15:05-15:30 |
「空と海との情報交換が決める気候変動メカニズム」 |
高橋 桂子 (地球シミュレータセンター) |
|
15:30-15:45 |
休憩 |
|
|
(固体地球分野) |
||
|
15:45-16:00 |
「固体地球分野の概要」 |
金田義行(固体地球統合フロンティア) |
|
16:00-16:25 |
「地球の磁場のシミュレーション」 |
浜野洋三(固体地球統合フロンティア) |
|
16:25-16:50 |
「大地震発生の予測可能性」 |
松浦 充宏 (東京大学理学系研究科) |
|
16:50-17:15 |
「日本列島の地震波の伝わり方と強い揺れの生成」-地球シミュレータで再現した日本の被害地震- |
古村孝志(東京大学地震研究所) |
|
17:15-17:30 |
休憩 |
|
|
17:30-18:30 |
招待講演「地球シミュレータがニューヨーク・タイムズトップ記事になって、日本の新聞のトップ記事にならない理由」 |
立花隆(ジャーナリスト) |
|
18:30-18:40 |
閉会の辞 |
木下肇(海洋科学技術センター) |
立花隆氏には、この後もスーパーコンピュータのサポーターとして発言をお願いすることになる。
4) 地球シミュレータセンターの移管?
夏頃、地球シミュレータセンターを理化学研究所に移管し、所管を環境エネルギー課(要確認)から情報課に変更するという可能性が検討されている記事が新聞に掲載された。これは地球環境だけでなくいろいろな分野に地球シミュレータを活用するには、現在の体制では対応できないからということであった。この話は、次世代スーパーコンピュータ開発計画の中でも実現することはなかった。
次世代スーパーコンピュータ計画
1) RIST「基礎研究における次世代高性能計算機環境に関する調査研究会」
RIST(財団法人 高度情報科学技術研究機構)はJSTから「次世代計算科学に関する調査研究」を2000年度頃から受託し、調査委員会を立ち上げている。2002年1月~3月には「次世代計算科学ソフトウェアに関する調査委員会」を3回開催した。(既報)
2003年末にも、JSTは「基礎研究における次世代高性能計算機環境に関する調査研究会」を企画し、RISTがこれを受託した。調査研究期間は2003年10月から2004年3月までで、3月15日には調査報告書をJSTに納入することになっていた。調査研究にあたっては、斯界の代表的な研究者が一同に会し、計算科学を積極的に用いて進もうとする、各々の最先端研究領域の現状を紹介しつつ、共通的に浮かび上がる課題を抽出し、そのために必須手段となる次世代高性能計算機環境の在り方を議論することが目的であった。
調査委員会のメンバーは、以下のとおり。
|
委員長:佐藤哲也 |
地球シミュレータセンター |
|
岩崎洋一 |
筑波大学 |
|
大澤映二 |
(有)ナノ炭素研究所 |
|
岡本征雄 |
核融合科学研究所 |
|
岡本祐幸 |
分子科学研究所 |
|
小柳義夫 |
東京大学 |
|
金田康正 |
東京大学 |
|
金田義行 |
海洋科学技術センター |
|
白山晋 |
東京大学 |
|
住明正 |
東京大学 |
|
高部英明 |
大阪大学 |
|
谷口伸行 |
東京大学 |
|
塚田捷 |
東京大学 |
|
中村壽 |
高度情報科学技術研究機構 |
|
西野哲郎 |
電気通信大学 |
|
平野恒夫 |
お茶の水女子大学 |
|
松本紘 |
京都大学 |
|
三浦謙一 |
情報学研究所/富士通 |
|
宮本良之 |
日本電気 |
|
渡邉国彦 |
地球シミュレータセンター |
文部科学省情報課の方々もオブザーバとして出席された。メンバーを見ると、ベンダーの委員を別にすれば、応用分野の研究者が多く、システムの専門家はほとんどいない。うがって見れば、応用分野から計算速度やメモリ容量などの要求事項を出してもらえば、あとはシステム側で汎用のスーパーコンピュータを設計すればよいという発想が背後にあるように思われる。現在強調されるco-designとは相反する考えである。筆者もメンバーであり、3回の研究会や座談会に出席していたらしいが、ほとんど記憶がない。
第1回研究会は2003年10月31日(金)に霞山会館で開かれ、ナノサイエンス分野から宮本委員が、バイオサイエンス分野から岡本(祐)委員が発題した。
第2回研究会は11月28日に海洋科学技術センター東京連絡所で開かれ、物質科学・物性物理の話題を塚田委員が、核融合プラズマの話題を岡本(正)委員が、CFDの話題を白山委員が、マクロ・ミクロ相互作用の話題を渡邉委員が、DEM (discrete element method)の話題を金田(義)委員が、量子色力学の話題を宇川(岩崎委員代理)が提供した。シミュレーションについては階層性が話題になり、そのための次世代計算機環境の性能、アーキテクチャなどが議論された。「30~40歳代の大規模計算機離れ」が話題に上り、教育や人材養成も議論された。
2) 古西氏の問題提起
古西真情報科学技術研究企画官はこの研究会にオブザーバとして陪席していたが、2003年11月28日の「基礎研究における次世代高性能計算機環境に関する調査研究会」の第2回研究会後、私信の形で「次世代のスーパーコンピュータ開発の必要性に関する検討」という文書をアカデミアの委員に送り、情報通信分野推進戦略(平成13年9月)においては、「スーパーコンピュータの高速化については、各分野の需要に応じて推進する」(つまり国家プロジェクトとはしない)こととされているが、地球シミュレータを越える規模のスーパーコンピュータを国家的に開発する必要はないか、と問い、もしyesならば、どの程度の規模のものを、何を目的として、どのような体制で整備するのがよいか、と問題提起している。筆者の知る限り、「京」コンピュータに向かう動きの発端であった。おそらく、情報課内部で予備的な議論が行われたのであろう。この直後の2004年1月5日付けで、岩崎洋一筑波大学教授は「我が国におけるスーパーコンピュータの開発の必要性について」という文書を公表した。これは2004年のところで詳しく述べる。
日本政府関係の動き
1) JAXA発足
2003年(平成15年)10月1日に航空宇宙技術研究所 (NAL)、文部科学省宇宙科学研究所(ISAS)、特殊法人宇宙開発事業団(NASDA)が統合され、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発足し現在に至る。旧文部省と旧科学技術庁にまたがる組織再編であった。
2) 情報科学技術委員会
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 情報科学技術委員会は、2001年に設置され、第一期は2001年2月1日~2003年1月31日であった。第二期が始まった。WARP(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業)により、会議日程を記す。(WARPについては村上弘氏にご教示いただいた)
|
第9回 |
平成15年2月26日(水) 10:00〜12:00 |
|
|
第10回 |
平成15年4月4日(金) 15:30〜17:30 |
|
|
第11回 |
平成15年8月21日(木) 13:30〜15:30 |
第11回会議では、ITBL評価ワーキンググループの設置が決まった。
3) JST改組
2003年10月、科学技術振興事業団は、独立行政法人科学技術振興機構に改組された。略号はJSTのままであった。
4) 日本学術振興会
特殊法人日本学術振興会は、独立行政法人となった。研究事業部は、2003年9月、地下鉄半蔵門駅近くの住友不動産一番町FSビルに移転した。2013年1月に麹町事務所に再統合する。
5) IMnet(SINETに統合)
1994年に国立研究所や関連の特殊法人などにおける研究のために省庁の枠を超えた研究情報基盤の共有化のために設立されたIMnet(Inter-Ministry netwoark、省際ネットワーク)は、JSTが運営していたが、2003年3月に大学等の情報基盤を担当するSINET2 (superSINET)に統合された。
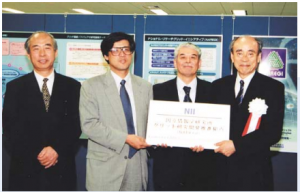 |
|
6) NAREGIプロジェクト
NAREGIは、国立情報学研究所が推進する最先端学術情報基盤(CSI:Cyber Science Infrastructure)整備の一つとして、広域分散型の最先端研究教育用大規模計算環境(サイエンスグリッド)を実現することを目的としている。 NAREGIは2003年4月から文部科学省の委託研究としてグリッドミドルウェアを研究開発するプロジェクト「超高速コンピュータ網形成プロジェクト(National Research Grid Initiative:通称NAREGI)」としてスタートし、2006年度から 2007年度までは「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用プロジェクトNAREGIプログラム」として推進される。2008年度にはNAREGIミドルウェアVer.1.0が公開される。
2003年7月1日、学士会館において「グリッド研究開発推進拠点(NAREGI)」の開所式,記念講演会,内覧会及び祝賀会が開催された(NII News No.17 なお写真は同記事よりNAREGI内覧会)。産学官の関係者が出席し、末松安晴国立情報学研究所所長からの式辞の後、石川文部科学省研究振興局長及び藤崎富士通(株)取締役CTOから挨拶を受け、その後、三浦謙一プロジェクトリーダーによるプロジェクトの概要説明が行われた。続いて、グリッドコンピューティング研究で著名なNASA Information Powergrid Project leaderのWilliam E. Johnston博士を迎え、今注目を集めている新技術であるグリッドコンピューティングについて記念講演が行われた。(Internet Warch 2003/7/1)
NAREGIプロジェクトでは、研究用グリッド基盤の確立から、グリッド技術の標準化、産業界へのグリッド環境の普及、グリッド分野における人材育成などを目的とした展開を行なっていくとともに、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所をアプリケーション開発拠点として、ナノアプリケーションを用いたグリッドミドルウェアの実証研究を行う。分子科学研究所では、アプリケーション開発のため、12月15日に日立のSR11000/H1と409台のHA8000/110Wからなるシステムを発注した。ピーク性能はそれぞれ約5 TFlopsである。SR11000は、POWER4+ 2C(1.7 GHz)を採用し、1ノードに16プロセッサ(正確には16コアであろう)を搭載する。OSはAIX 5Lで、ノード間通信は単方向4 GB/s×2である運用は2004年3月から。(日立ニュースリリース)(CNET 2003/12/15) なお2004年11月のTop500において、SR11000-H1/50は、コア数50、Rmax=2909.0 GFlops、Rpeak=5440.0 GFlopsで71位にランクしている。ここではノードをコアしてと数えている。
文部科学省でNAREGIを推進していた古西(ふるにし)真氏は、発足前の3月4日~6日に新宿京王プラザホテルで開催されたGGF7において、ドイツで開発されEurogridの基盤となっているUNICORE (Uniform Interfaces to Computing Resources) がNAREGIのグリッド・ミドルウェアになるであろうと述べ、ヨーロッパからは注目された(GRIDtoday 2003/4/28)。古西氏については、次世代コンピュータ開発のところでも言及した。
7) 産総研グリッド研究センター
電子ジャーナルGRIDtoday誌の2月3日号に、「あの有名な関口智嗣とのインタビュー」というAlan Beck編集長の記事が出た。SC2002で捕まえたものらしい。関口センター長を“visionary leader” として紹介している(「夢見るリーダー」か「先見的リーダー」か?)。センターの主要な目的として、Ninf、 ApGrid、Gfarmなどについて述べるとともに、国内の他のグリッドセンターとの連携についても語っている。
2002年4月に発足した産総研グリッド研究センターは、産総研本部の評価部からの評価を受けることになり、筆者もレビューボード委員を頼まれた(他には、後藤敏(早稲田)、下條真司(大阪大)、近山隆(東大)、坪田知己(日経新聞)、姫野龍太郎(理研))。2002年8月のプレ評価に続いて、2003年12月22日の午後2時からグリッド研究センターの上野オフィス(住友不動産上野ビル8号館)で成果ヒアリング評価委員会が開催された。
おおむね高い評価がなされたが、いくつかの指摘事項があった。ビジネスグリッドへの貢献の明確化に対しては、産業界への貢献として、同センターで開発した技術およびソフトウェアのビジネス展開、およびビジネスグリッドコンピューティングプロジェクトへの参画が示され、Grid ASPなどのアウトソーシングをビジネスモデルとして設定していることを了承した。アプリケーションに対するグリッド技術の優位性の実証としては、グリッド環境に適した分子動力学シミュレーションについてのツールキットを開発したことが示され、今後適用例を増やしていくことが報告された。また、世界標準化達成への戦略として、Ninf-GやGfarmなどの普及とde facto標準化を目指していることが述べられた。
8) アジアグリッドイニシアチブ
昨年のところで述べたように、2002年の文部科学省振興調整費に応募して採択された。文部科学省から推進委員会の設置を指示され、以下の構成となった。
|
外部有識者 |
姫野龍太郎(理研)、小西和憲(KDD)、合田憲人(東工大)、小柳義夫(東大) |
|
課題の研究分担者 |
後藤滋樹(早稲田)、下條真司(大阪大)、岡村耕二(九大)、小林克志(情報通信研究機構)、関口智嗣(産総研) |
日本でのGGF開催、PRAGMA開催、テストベッド整備などについて、当初の業務計画からの変更が必要になり、推進委員会として了承した。
2003年度に入って、4月9日に産総研上野オフィスで推進委員会を開催し、2002年度研究報告および2003年度研究計画について議論した。また、12月17日には第2回推進委員会を開き、2003年度上半期活動・成果報告について議論した。
9) ビジネスグリッドコンピューティングプロジェクト
報道によると、2003年度には、経済産業省が進める「ビジネスグリッドコンピューティングプロジェクト」に28億円の予算がつき、国内企業が連携してグリッドソフトウェアの世界標準化に向けた技術開発競争に加わる計画である。日本経済新聞3月6日号には「富士通・日立・NEC、超高速計算網の基幹ソフトを共同開発」という記事があり、グリッドを「超高速計算網」と紹介しているところが認識不足を如実に示している。2003年7月15日、村岡洋一(早稲田大)を委員長に第1回推進委員会を開催した。市場創造に向けた民間各社の取り組みが活発化し、日本電気や富士通は自社の研究所やデータセンターにグリッド環境を構築し、ユーザーが自由に検証実験できるようにした。(『情報処理』2006年9月号に特集がある)
日本IBM は2003年1月から、グリッドに関する世界共通カリキュラムを導入し、他国の実績・人材を活用して、システムデザインからコスト効果まで幅広く提案していくという。
次回は、日本政府関係の動きの続き。久しぶりにアメリカから二国間の議論をしようと言ってきた。今回のテーマは計算科学で、日本もアメリカも、大きな実験科学が幅を効かせている中で、どうやって計算科学を振興させようか、またそれに必要な計算リソースをどう確保しようか、ということを議論した。地球シミュレータを使わせろとの本音も。
 |
 |
 |

