新HPCの歩み(第226回)-2005年(d)-
|
バイオグリッドシンポジウムBioGrid2005は、日本科学未来館で開催された。SACSIS2005では、Grid Challengeが行われた。SWoPP2005では、姫野龍太郎が「異機種複合システムRSCC(Riken Super Combined Cluster)とその将来計画」について語った。 |
国内会議
1) 超並列計算研究会(理研和光)
2005年1月13日、理化学研究所 和光研究所 大河内記念ホールにおいて、第39回超並列計算研究会が開催された。
|
13:30-13:40 |
オープニング |
三木 光範(同志社大学) |
|
13:40-14:30 |
理研スーパー・コンバインド・クラスタ(RSCC)の紹介 |
重谷 隆之(理化学研究所・情報基盤センター) |
|
14:30-15:20 |
理研PCクラスタシステムの構築及び性能について |
久門 耕一 (富士通研究所) |
|
15:30-16:20 |
PACS-CS: 計算科学のための新しい発想の超並列クラスタ |
朴 泰祐(筑波大学) |
|
16:20-16:50 |
Condor超入門 |
西 克也(株式会社ベストシステムズ) |
|
16:50-17:30 |
RIKEN Super Combined Cluster Systemの見学 |
|
2) HPCS2005(東京大学山上会館)
HPCS 2005(2005年 ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム)は、1月18日~19日に東京大学山上会館で開催された。この会は、高性能計算機システムの研究者と,計算科学の研究者や高性能計算機システムのユーザとの合同の研究発表及び情報交換の場として企画された。主催は情報処理学会HPC研究会、協賛は情報処理学会 計算機アーキテクチャ研究会、 情報計算化学生物学会、日本応用数理学会、 日本化学会 情報化学部会、 日本計算工学会、日本シミュレーション学会、 日本物理学会、 日本流体力学会であった。実行委員会は、委員長が関口智嗣(産総研)、副委員長が佐藤 周行(東大)、その他、小柳義夫(アドバイザリ委員会委員長、東大)、佐藤三久(アドバイザリ委員会副委員長、筑波大)、須田礼仁(プログラム委員会委員長、東大)、片桐孝洋(プログラム委員会副委員長、電通大)、林亮子(プログラム委員会副委員長、北陸先端大)、高橋大介(財務担当、筑波大)、大嶋 裕子(会場担当、産総研)であった。招待講演は、井原茂男(東大)による“High Performance Computing in Systems Biology and Medicine”であった。月刊オープン・エンタープライズ・マガジン vol.3, March, 2005に紹介された。
3) ベストシステムズHPCフォーラム(産総研)
ベストシステムズ社主催、エンジニアス・ジャパン共催で、第二回ベストシステムズHPCフォーラムが2005年2月8日、産業技術総合研究所情報技術共同研究棟において開催された。
|
13:15-13:30 |
開会の辞 |
|
|
13:30-14:00 |
「統合化、自動化、最適化によるGrid EnablerソフトウェアiSIGHT」 |
エンジニアス・ジャパン株式会社 林 憲一 |
|
14:00-14:20 |
「自作最適化アルゴリズムをiSIGHTに組み込むメリット」 |
エンジニアス・ジャパン株式会社 |
|
14:20-14:50 |
「多目的遺伝的アルゴリズムの紹介と適用事例」 |
立命館大学 渡邉真也 |
|
14:50-15:10 |
休憩 |
|
|
15:10-15:40 |
「高信頼化に向けたロケットエンジン統合化設計手法の研究」 |
宇宙航空研究開発機構 青木宏 |
|
15:40-16:10 |
「人工関節の形状最適化」 |
北海道大学 石田 敏真 |
|
16:10-16:40 |
「PCクラスタとソフト技術の進歩」 |
(株)ベストシステムズ 西 克也 |
|
16:40-16:55 |
「HPC関連産学官連携推進情報連絡会の構想について」 |
(株)ベストシステムズ 後藤 和弘 |
|
16:55-17:00 |
閉会の辞 |
(株)ベストシステムズ |
4) 筑波大学計算科学シンポジウム(国際会議室)
日本の学界のところで述べたように、2005年2月16日~17日に、筑波大学大学会館国際会議室において、「第一回「計算科学による新たな知の発見・統合・創出」シンポジウム -PACS-CS プロジェクトと FIRST プロジェクト-」が開催された。
5) 「計算科学春の学校」(名古屋大学)
名古屋大学21世紀COEプログラム「計算科学フロンティア」は、2005年2月23日(水)名古屋大学VBLホールにおいて「計算科学春の学校」を開催した。
|
13:40-13:50 |
主催者挨拶 |
COEプログラム「計算科学フロンティア」拠点リーダー金田行雄(名古屋大学計算理工学) |
|
13:50-15:50 |
「専用計算機による計算科学」 |
牧野淳一郎(東京大学) |
|
15:50-17:00 |
質疑応答 |
|
|
17:30 – |
懇親会 名古屋大学レストラン 「花の木」 |
|
6) HOKKE 2005(北海道大学学術交流会館)
HOKKE 2005(第12回「ハイパフォーマンスコンピューティングとアーキテクチャの評価」 に関する北海道ワークショップ)は、第154回 計算機アーキテクチャ研究会と、第101回ハイパフォーマンスコンピューティング研究会との合同研究発表会として、3月7日~9日に北海道大学学術交流会館 小講堂で開催された。今回のHOKKEでは、グリッド、プロセッサ技術、ジョブスケジューリング、科学技術計算、数値計算アルゴリズム、クラスタと崇信・分散処理、回路およびチップ構成法、通信ライブラリに関する35件の発表が行われた。懇親会はキリンビール園(すすきの)。
7) 広島大学INSAMシンポジウム
広島大学数理シミュレーション科学研究センター(Institute for Simulation and Mathematical Sciences)は、2005年3月9日、広島大学理学部において、INSAMシンポジウム2004「粘菌:実験と理論からのアプローチ」を開催した。プログラムは以下の通り。
|
9:50-10:00 |
はじめに |
小林 亮 (広島大学数理シミュレーション科学研究センターセンター長) |
|
10:00-11:00 |
『粘菌による幾何学的パズル問題の解法』 |
中垣 俊之(北海道大学電子科学研究所) |
|
11:00-11:40 |
『アメーバ細胞運動のシミュレーション』 |
西村 信一郎(名古屋大学) |
|
11:40-13:00 |
昼食 |
|
|
13:00-14:00 |
『走化性情報伝達系の1分子解析』 |
上田 昌宏(大阪大学生命機能研究科) |
|
14:00-14:40 |
『ゆらぎを通して見る細胞の情報処理』 |
柴田 達夫(広島大学) |
|
14:40-15:00 |
休憩 |
|
|
15:00-16:00 |
『デタラメさをならす- 粘菌の時空間パターンと遺伝子フィードバック』 |
澤井 哲(プリンストン大学) |
|
16:00-16:30 |
ポスターインデクシング |
|
|
16:30-18:00 |
ポスターセッション |
|
|
18:00-20:00 |
懇親会 |
|
8) BioGrid2005(日本科学未来館)
文部科学省科学技術振興費主要5分野の研究開発委託事業におけるITプログラム「スーパーコンピュータネットワークの構築」として実施されるバイオグリッド・プロジェクトが主催するバイオグリッドシンポジウムBioGrid2005は、3月9日に日本科学未来館「みらいCANホール」で開催された。
|
9:40-12:00『バイオとITの融合領域に関する招待講演』 |
|
|
「生物情報資源の相互運用性」 |
国立遺伝学研究所 菅原秀明 |
|
「創薬現場からのバイオグリッドへの期待」 |
CBI学会会長 多田幸雄 |
|
「バイオのためのIT基盤とは」 |
バイオグリッド・プロジェクト代表 下條真司 |
|
13:00-17:40『文部科学省ITプログラム「スーパーコンピュータネットワークの構築」プロジェクト成果発表 |
|
|
「コンピューティンググリッド技術」 |
大阪大学蛋白質研究所 中村春木 |
|
「データグリッド技術」 |
大阪大学情報科学研究科 松田秀雄 |
|
「HTC(High Throughput Computing)」 |
神戸大学理学部 高田彰二 |
|
「TeleScience」 |
大阪大学サイバーメディアセンター 秋山豊和 |
|
「グリッド基盤技術」 |
NECシステムテクノロジー株式会社 仲川拓志 |
|
「NPOによる産学連携活動」 |
大阪大学サイバーメディアセンター 坂田恒昭 |
|
18:00-19:30 懇親会 |
|
9) 理研シンポジウム(理研和光)
理化学研究所情報基盤センターでは以前から「理研シンポジウム」を毎年開催している。2001年度以降はweb上に記録されている。2004年度理研シンポジウムは「RSCCからペタコンピューティングへ」をテーマに、2005年3月15日に理化学研究所 和光本所 鈴木梅太郎ホールで開催された。プログラムは以下の通り。
|
10:00 |
開会の辞 |
井上頼直、理研理事 |
|
10:10 |
RSCC運用紹介 |
重谷隆之、理研情報基盤センター |
|
10:30 |
ゲノム創薬研究とRSCCシステム |
佐藤万仁、理研ゲノム科学総合研究センター |
|
11:00 |
Bioポータルにおける占有利用 |
湯浅裕亮、理研横浜情報基盤センター |
|
11:30 |
RSCCにおける高エネルギー原子核実験データ解析 |
四日市悟、理研中央研究所 |
|
12:00 |
レプトン異常磁気能率の精密理論計算 |
仁尾真紀子、理研中央研究所 |
|
12:30 |
昼食 |
|
|
13:45 |
基調講演:Road Toward Peta Computing in USA |
David Kahaner, ATIP |
|
15:00 |
理研でのペタコンピューティングのニーズとRSCCの次期システム構想 |
姫野龍太郎、理研情報基盤センター |
|
16:00 |
理研における専用計算機への取り組み |
泰地真弘人、理研GSCゲノム情報科学研究グループ |
|
17:00 |
RIKEN BMT コンテスト表彰 |
|
|
17:20 |
RSCC見学 |
|
|
18:30 |
懇親会 |
|
最後のRIKEN BMTコンテストでは、以下の2種類のbenchmark test programを募集した。
(1)構造格子を用いた Poisson FDM-BMT
(2)非構造格子を用いた Poisson FEM-BMT
プラットフォームとして、計算機の種類・規模は問わない「無差別部門」と、使用する計算機を 1CPU だけを使った結果に限定し、Poisson FDM-BMT のみを対象とする「1CPU 部門」の 2 部門を用意したとのことである。だれが表彰されたかの記録はみつからない。
これとは別に、情報基盤センターでは2005年3月にベンチマークプログラム募集を行った。これは次世代計算システムの性能評価のためということである。募集の案内には、「現時点でLINPACKやFFT等の演算性能のベンチマークや計算機の基本要素を計測するベンチマークプログラム、CFD分野のベンチマークは目立ちますが、バイオやナノ分野のシミュレーションコードを元にしたベンチマークが少ないように見受けられます。」と書かれている。こちらの方には応募がなかったようである。
この募集に対して、筆者などとともに性能評価の研究を行ってきた関口智嗣は、実サイズアプリケーションを作ろうという動きは世界的にいろいろあるが、多くの困難があるとコメントしている。例えばSPEC HPG (High Performance Group)は、
(1) コードのメンテナンスにコストがかかること – MPI版とOpen MP版を作った
(2) なかなか測定データが集まらないこと
(3) 実アプリケーションだとベンチマークとして使っている間に、プログラムが進歩して、現実的な問題との差異が広がること。
(4) かといって、プログラムを改変するとそれまでのデータと比較ができなくなり、過去データの意味が失われこと
(5) 応用寄りのベンチマークにすればするほど計算機システムの性質が平均化されて特徴が見えなくなること
(6) 計算結果の正当性検証の問題
(7) ベンチマーク結果を解釈するためにプログラムの中身を説明しなければならず、それらのマニュアル等の整備が大変
などの問題を挙げている。筆者の私見であるが、逆にLinpackは、実アプリケーションでないが故に上記の困難を回避している面がある。
10) PCクラスタコンソーシアム(富士通関西システムラボ、日本科学未来館)
2001年に発足したPCクラスタコンソーシアムでは、2005年3月18日、富士通株式会社 関西システムラボラトリにおいて、SCoreワークショップin関西を開催した。プログラムは以下の通り。
|
10:00 |
コンソーシアム紹介 |
石川 裕 (東京大学) |
|
10:15 |
並列処理とMPI通信ライブラリ入門 |
石川 裕 (東京大学) |
|
11:00 |
SCore 入門 |
原田 浩 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) |
|
11:30 |
break |
|
|
13:00 |
SCore 6.0 概要 |
堀 敦史 (スイミー・ソフトウェア株式会社) |
|
13:30 |
メンバ企業によるSCoreクラスタ導入事例・応用事例・今後の取り組み |
|
|
13:30 |
日本HPのPCクラスタへの取り組みについて |
根本 雅樹 (日本ヒューレット・パッカード株式会社 Linux/HPTC推進本部Linux/HPTC推進部) |
|
13:50 |
ワークロード管理ソリューションPBS Proのご紹介 |
北邑 剛 (アルテアエンジニアリング株式会社 営業本部 シニアアプリケーションエンジニア) |
|
14:10 |
大規模PCクラスタシステム導入事例紹介 |
小川寛徳 (株式会社日立製作所 公共システム事業部) |
|
14:30 |
NECのHPCクラスタへの取り組み |
松岡 浩司 (日本電気株式会社 グリッド推進センター) |
|
14:50 |
break |
|
|
15:10 |
富士通のPCクラスタへの取り組み |
久門 耕一(株式会社富士通研究所 ITコア研究所 グリッド&バイオ研究部) |
|
15:30 |
Myrinetロードマップ |
小林 裕之 (住商エレクトロニクス株式会社 HPC事業部グリッドソリューション部) |
|
15:50 |
クラスタ構築・運用よろず相談所 住元 真司 (富士通研究所) 石川 裕 (東京大学) 堀 敦史(スイミー・ソフトウェア株式会社) |
|
|
17:00 |
懇親会 |
|
2005年12月15日~16日には、日本科学未来館において、第五回PCクラスタシンポジウムを開催した。プログラムは以下の通り。
12月15日テクニカルセッション
|
10:30 |
SCore入門 |
原田 浩 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) |
|
13:30 |
招待講演 「実効性能追求型超並列クラスタPACS-CSの概要」 |
朴 泰祐(筑波大学) |
|
14:30 |
break |
|
|
15:00 |
パネル討論: 「SCore 6.0 & Omni OpenMP 開発状況および今後の開発」 司会: 石川 裕(東京大学) パネリスト: 佐藤 三久(筑波大学) 堀 敦史(Allinea Software) 住元 真司 (富士通研究所) 清水 正明 (株式会社日立製作所) 亀山 豊久 (PC クラスタコンソーシアム) |
|
|
17:30 |
懇親会 |
|
12月16日一般セッション
|
10:00- |
SCore の節目 – SCore 10 年 |
石川 裕(東京大学) |
|
10:45 |
PCクラスタプラットフォームの動向 |
|
|
10:45 |
AMD プロセッサの最新情報ならびにクラスタに関する取り組みについて |
山野 洋幸 (日本AMD株式会社 エンタ-プライズビジネスデベロップメント部) |
|
11:15 |
HPC用インテル・プラットフォーマライゼーション |
池井 満 (インテル株式会社 分散並列技術部 シニア・アプリケーション・エンジニア) |
|
13:00 |
メンバ企業によるSCoreクラスタ導入事例・応用事例・今後の取り組み |
|
|
13:00 |
クレイドルにおけるパラレル製品情報 |
黒石 浩之 (株式会社ソフトウェアクレイドル 技術部) |
|
13:15 |
ワークロード管理ソリューションへの弊社の取り組みに関して |
松本 新一 (アルテアエンジニアリング株式会社 グリッドコンピューティング テクニカルスペシャリスト) |
|
13:30 |
HPCクラスタへの取組み |
竹内 義晴 (日本電気株式会社 グリッド推進センター) |
|
13:45 |
PCクラスタ性能への取り組み |
久門耕一 (株式会社富士通研究所ITアーキテクチャ研究部) |
|
14:00 |
休憩 |
|
|
14:10 |
Hitachi Technical Servers for HPC |
鈴木誠司 (株式会社日立製作所 エンタープライズサーバ事業部クラスタシステム部 主任技師) |
|
14:25 |
日本HPのPCクラスタへの取り組み |
根本 雅樹 (日本ヒューレット・パッカード株式会社 エンタープライズストレージ・サーバ統括本部 OpenSource& Linux推進部) |
|
14:40 |
AXEのScoreベースクラスタLinux axLinux/雷神 |
竹岡 尚三 (株式会社アックス代表取締役社長) |
|
14:55 |
休憩 |
|
|
15:00 |
パネル討論: 「PCクラスタの将来展望 -アプリケーションユーザからの視点-」 司会: 姫野 龍太郎(理化学研究所) パネリスト: 岡澤 重信(広島大学) 小西 史一(理化学研究所ゲノム科学総合研究センター) 白崎 実(横浜国立大学) 廣安 知之(同志社大学) 真鍋 篤(高エネルギー加速器研究機構) |
|
11) ナノ学会第3回大会(仙台)
2005年5月8日~10日に仙台市民会館で開催された。この連載では学会全国大会までカバーしてはいないが、この会議は次世代スーパーコンピュータがらみの匂いがする。
|
5月9日午後 |
特別セッション「Nanotech in Korea」 Hee Chul Lee氏、National Nanofab Center所長 |
|
5月9日午後 |
《パネルディスカッション》「ナノテクと今後の我が国の産業育成」 司会:川添良幸東北大学教授 パネリスト:尾身幸次衆議院議員、 浅野史郎宮城県知事、 黒川卓日経ナノテクノロジー編集長 |
|
5月8日午後 |
特別セッション「ナノ医療」 大内憲明東北大学教授、樋口秀男東北大学教授 他。 |
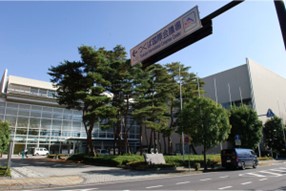 |
|
12) SACSIS 2005(つくば国際会議場)
3回目となるSACSIS 2005(2005年先進的計算基盤システムシンポジウム)は、5月18日~20日、つくば市のエポカルつくば・つくば国際会議場において開催された。写真は会議場のHPから。主催は、情報処理学会の計算機アーキテクチャ研究会、・システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会、・ハイパフォーマンスコンピューティング研究会、・アルゴリズム研究会、並びに電子情報通信学会のコンピュータシステム研究専門委員会、IEEE Computer Society Japan Chapterで、協賛は電子情報通信学会・ ディペンダブルコンピューティング研究専門委員会であった。基調講演は平木敬(東大)の「EFLOPS, 10Tbpsの世界を目指して」、招待講演はBarton Miller (University of Wisconsin)の“Binary Code Patching: An Ancient Art Refined for the 21st Century”であった。チュートリアルも4件行われた。今回はSACSIS2005はACS論文誌第11号と連携して論文募集が行なわれ、1件の論文を双方に同時投稿し、並行して査読を受けることができた。
今回の特別な企画としてGrid Challengeが行われた。国内のGrid研究の拠点の協力により、 1000プロセッサ規模の計算機資源を集め、それを企画開催中の一定期間、参加者に提供し、その環境で、与えられた問題を解く速度を競う「規定課題部門」ならびに与えられた資源を用いて興味深い実験を実行、報告してもらう「自由課題部門」を設け競った。資源を提供したのは、産業技術総合研究所 グリッド研究センター、電通大 弓場研究室・本多研究室、東工大 松岡研究室、徳島大 小野研究室、東大 近山・田浦研究室 21世紀COE科学技術戦略コアであった。
13) HAS研(日立システムプラザ新川崎)
日立アカデミックシステム研究会(HAS研)は2005年6月14日、日立システムプラザ新川崎において、HAS研臨時総会および研究会を開催した。
|
第19回研究会(2005年6月14日) |
|
|
セキュアPC |
株式会社日立製作所 プラットフォームソリューション事業部 |
|
ブレードコンピュータ |
株式会社日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 |
|
愛知万博 日立館のご紹介とμチップ |
株式会社日立製作所 トータルソリューション事業部 |
|
個人情報保護を取り巻く人間の意識 |
武蔵野大学 林 理 |
14) 数値解析シンポジウム(浜名湖)
第34回数値解析シンポジウムNAS2005は、6月28日~30日、浜名湖カリアックで開催された。実行委員長は八卷直一(静岡大学)。
15) NEC・HPC研究会(NEC本社ビル、芝パークホテル)
7月12日に、NEC本社ビル地下にて、第20回NEC・HPC研究会が開催された。主要な講演は以下の通り。
|
「超電導SFQ素子はCMOS素子の後継となるか」 |
超電導工学研究所、田中昭二 |
|
「不揮発性メモリMRAMの最新動」 |
NEC、田原修一 |
|
「地球シミュレータを使ったテラヘルツ発振」 |
RIST、立木昌 |
|
「量子コンピュータ実現に向けた超伝導デバイスの現状と展望」 |
NEC、蔡兆申 |
|
「エレクトロニクスの限界を打破するSiナノフォトニクス」 |
NEC、大橋啓之 |
11月9日には芝パークホテルにおいて、第21回NEC・HPC研究会が開催された。主要な講演は以下の通り、
|
“Advanced Supercomputing Concepts and Applications in Science and Engineering at HLRS” |
HLRS、Dr. Uwe Kuester |
|
「ペタフロップス時代の情報基盤センターの役割と東北大学情報シナジーセンターでの取り組み」 |
東北大、小林広明 |
|
「次世代スーパーコンピュータ構想と生命・生体シミュレーションへの挑戦」 |
理研、姫野龍太郎 |
|
「地球シミュレータを活用した自動車性能シミュレーションの研究及びペタフロップスコンピュータへの期待について」 |
日本自動車工業会、梅谷浩之 |
|
「材料シミュレーション分野からの期待」 |
東大、杉野修 |
|
「ペタコンに向けたNECの取り組み」 |
NEC、野口孝行 |
16) SWoPP 2005(武雄)
SWoPP武雄2005(2005年並列/分散/協調処理に関する『武雄』サマー・ワークショップ)は、8月3日~5日に佐賀県武雄文化会館で開催された。270名を超える参加があった。電子情報通信学会のコンピュータシステム研究会(CPSY)とディペンダブルコンピューティング研究会(DC)、情報処理学会の計算機アーキテクチャ研究会(ARC)、システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会(OS)、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(HPC)、プログラミング研究会(PRO)、システム評価研究会(EVA)の共催である。IEEE Computer Society Japan Chapterの共催となっている。招待講演はHoward Gobioff (Google)の“Google File System”と、姫野龍太郎(理研)の「異機種複合システムRSCC(Riken Super Combined Cluster)とその将来計画」であった。また夜のお楽しみセッションとして、「今後の日本のコンピュータ・サイエンス研究をどう盛り上げるか?」というパネルが開かれた。
17) SS研 HPCフォーラム2005(汐留)
SS研究会(Scientific System研究会)は2005年8月30日~31日に第3回となるHPCフォーラム「ペタスケールコンピューティングで何が変わるのか」を汐留シティセンター24階富士通本社大会議室において開催した。プログラムは以下の通り。
8月30日
|
13:30 |
開会挨拶 |
岩宮敏幸、 JAXA |
|
13:40 |
(海外招待講演)A New Paradigm for Large-scale Science:Computational End Stations |
Al Geist, ORNL |
|
14:50 |
HPC向けR&Dソリューションのご紹介 |
万谷 哲、 富士通 |
|
15:20 |
休憩<デモ展示> |
|
|
15:50 |
数値気象予測の現状と将来展望 |
室井ちあし、 気象研究所 |
|
16:50 |
地球シミュレータによる全球地震波伝播シミュレーション |
坪井誠司、 JAMSTEC |
|
18:10 |
懇親パーティ |
|
8月31日
|
10:00 |
ペタスケールコンピューティングへの期待~バイオ事例から~ |
藤田省三、 富士通研究所 |
|
11:00 |
休憩 <デモ展示> |
|
|
11:30 |
核融合から見たペタコンピューティング |
徳田伸二、 日本原子力研究所 |
|
12:30 |
昼食・休憩 <デモ展示> |
|
|
13:40 |
ナノサイエンスとペタコンピューティング |
岡崎 進、 分子科学研究所 |
|
14:40 |
休憩 <デモ展示> |
|
|
15:00 |
富士通のペタスケールコンピューティングへの取組み |
奥田 基、 富士通 |
|
16:00 |
閉会挨拶 |
上島豊、 日本原子力研究所 |
18) FIT2005
FIT2005(Forum on Information Technology、第4回情報科学技術フォーラム)が9月7日~9日中央大学後楽園キャンパスで開催された。FITは情報処理学会と電子情報通信学会の情報・システムソサイエティおよびヒューマンコミュニケーショングループとの共催で年1回(秋期)に開催するイベントで、2002年に始まった。『スパコン日本の時代は取り戻せるか』というパネルが9日に企画され、司会を依頼された。パネリストは、秋山泰(産総研)、奥田基(富士通)、菊池純男(日立)、住明正(東大)、姫野龍太郎(理化学研)、平木敬(東大)、渡辺貞(NEC)の7人であった。アメリカがASCIプロジェクトに力を入れてから日本製のスーパーコンピュータがじり貧状態となっているが、日本はどんな戦略をとればよいのか、という問題提起を行った。このパネルについて、マイナビニュースの大塚実が記事で詳しく紹介している(現在リンク切れ)。
19) IC2005(東京大学山上会館)
第10回目となるIC2005(インターネットコンファレンス2005)は、財団法人インターネット協会 (IAjapan)、日本学術振興会産学協力研究委員会インターネット技術第163委員会 (ITRC)、日本ソフトウェア科学会インターネットテクノロジー研究会 (JSSST)、情報処理学会 高品質インターネット研究会(QAI)、情報処理学会 ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(HPC)、日本UNIXユーザ会 (jus)、WIDEプロジェクト (WIDE)の主催により、2005年10月27日~28日に東京大学山上会館で開催された。プログラム委員長は植原啓介 (慶應義塾大学)と永見健一 (インテック・ネットコア)、実行委員長は関谷勇司(東京大学)であった。2件の招待講演が行われた。
|
「WiMAXの現状と期待」 |
竹井淳(インテル) |
|
「ブロードバンドトラフィックの現状」 |
福田健介(NTT未来ねっと研究所) |
20) ナノサイエンスワークショップ(笹川記念会館)
第3回目となる「ナノサイエンス&テクノロジにおける次世代計算科学に関するワークショップ」はRIST(高度情報科学技術研究機構)の主催により、2005年11月24日に港区三田の笹川記念会館で開催された。プログラムは以下のとおり。
|
9:00 |
開会&挨拶 |
|
|
9:10- 9:50 |
「ナノ計算科学の限界突破への期待:ナノテクそしてドラッグデリバリなど」 |
Dr. D. Tomanek(ミシガン州立大学教授) |
|
9:50-10:30 |
「ナノ超伝導物質における新奇機能発現シミュレーションモデルとテラヘルツ連続波発振」 |
Prof. Dr. M. Tachiki(東北大学名誉教授) |
|
10:30-10:50 |
Coffee Break |
|
|
10:50-11:30 |
「欧州における分子シミュレーションモデルの現状と今後」 |
Prof. Dr. G. Cuniberti (独:レーゲンスベルク大学教授) |
|
11:30-12:10 |
「ドラッグデリバリと物理エネルギとのシナジーに関する研究について」 |
Prof.Dr.M. Uesaka(東京大学工学系大学院教授) |
|
12:10-13:30 |
昼食 |
|
|
13:30-14:10 |
「密度汎関数強結合分子動力学モデルの現状と今後」 |
Dr. T. Heine(ドレスデン工科大学助教授) |
|
14:10-14:50 |
「第一原理電子輸送モデルの現状と今後」 |
Prof. Dr. S. Skelboe(コペンハーゲン大学教授) |
|
14:50-15:00 |
Coffee Break |
|
|
15:00-15:30 |
「複雑系に関する大規模シミュレーションへの新しいアプローチ」 |
Dr. T. Sato (地球シミュレータセンター長) |
|
15:30-16:00 |
「ナノカーボン類の新奇機能シミュレーションモデルの現状」 |
Dr.Y. Miyamoto(NEC) |
|
16:00-16:30 |
「ナノ炭素系に関する大規模シミュレーションモデル」 |
Dr. S. Tejima (RIST) |
|
16:30-16:40 |
まとめ |
|
21) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所では1969年から毎年数値解析関係の研究集会を行っている。2005年は37回目で、11月30日~12月2日に「計算科学の基盤技術とその発展」という課題で開催された。37回目である。代表者は櫻井鉄也(筑波大)。講演内容は講究録 No. 1505に収録されている。地球シミュレータを用いた大規模計算としては「地球シミュレータ上での18テラフロップス級及び1590億次元行列の厳密対角化計算:トラップされた強相関フェルミ原子ガスの基底状態探索(計算科学の基盤技術とその発展)—」(今村、山田、町田)がある。
22) 日本SGI HPC Open Forum(ウェスティンホテル東京)
日本SGI HPC Open Forum(会長 小林敏雄)は、2005年11月30日、ウェスティンホテル東京において、『HPC Open フォーラム -日本の防災研究の最前線-』を開催した。
|
13:30-14:20 |
《基調講演》 揺れる日本列島 ~兵庫県南部地震後10年~ |
防災科学技術研究所 石田 瑞穂 |
|
14:30-15:20 |
高密度地震観測網で見る日本列島の揺れと大規模コンピュータシミュレーションによる強震動の予測 |
東京大学地震研究所 古村 孝志 |
|
15:20-15:40 |
休憩 |
|
|
15:40-16:30 |
津波の破壊力とシミュレーション |
港湾空港技術研究所 有川 太郎 |
|
16:40-17:30 |
CFDに基づく市街地火災の延焼総合シミュレーション |
東京大学生産技術研究所 加藤 信介 |
|
17:30-19:00 |
意見交換会 |
|
23) IPAB(産総研CBRC)
並列生物情報処理イニシアティブ(IPAB)は1999年に設立され、シンポジウムや研究会を開催している。2005年12月9日、2月にBlueGene/Lの設置された臨海副都心センター(CBRC)において第3回IPAB公開セミナー「最新HPC事情」を開催した。筆者が基調講演を行った。
|
13:00-13:10 |
ご挨拶 |
理事長 小長谷明彦 |
|
13:10-14:20 |
基調講演:「最新HPC事情」 |
東京大学 小柳 義夫 |
|
14:20-14:35 |
アップル・コンピュータ |
ソリューションエキスパーツ部長 坂野 勝美 |
|
14:35-14:50 |
クレイ・ジャパン・インク |
代表取締役社長 中野 守 |
|
14:50-15:05 |
富士通株式会社 |
科学ソリューション本部 奥田 基 |
|
15:05-15:20 |
休憩 |
|
|
15:20-15:35 |
株式会社日立製作所 |
エンタープライズサーバ事業部 熊洞 宏樹 |
|
15:35-15:50 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
エンタープライズストレージ・サーバ統括本部 根本 雅樹 |
|
15:50-16:05 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 |
ディープコンピューティング研究所 清水 茂則 |
|
16:05-16:20 |
日本電気株式会社 |
第一コンピュータ事業本部 笹倉 孝之 |
|
16:20-16:35 |
日本SGI株式会社 |
アドバンスドテクノロジーコミッティ 田坂 隆明 |
|
16:35-16:50 |
サン・マイクロシステムズ株式会社 |
未定 |
|
16:50-17:00 |
ご挨拶 |
副理事長 秋山泰 |
|
17:00-17:30 |
産総研CBRC見学 |
|
|
17:30-19:00 |
懇親会 |
|
24) 第5回PCクラスタシンポジウム(日本科学未来館)
PCクラスタコンソーシアムは、2005年12月15日~16日に日本科学未来館において、第五回PCクラスタシンポジウムを開催した。
次回は日本の企業の動きと標準化関係の動き。富士通研究所は「ペタスケールコンピューティング推進室」を設置し、「ピーク性能で3 PFlops、実効性能で1 PFlops超を目標とする」と発表した。2005年も3回のGGF (Global Grid Forum)が開催された。
 |
 |
 |

