新HPCの歩み(第230回)-2005年(h)-
|
ISCは2001年からHeidelbergで開催されてきたが20回目の今回がHeidelbergでの最後となった。初日の基調講演ではHorst Simonが20年のHPCを回顧した。2日目の基調講演は「破壊の時代におけるペタスケール・コンピューティング」という”disruptive technology”の話であった。 |
ISC2005
 |
|
 |
|
ISC2005 (International Supercomputer Conference)は、Heidelberg Kongresshaus(写真は外観と会場)で2005年6月21日~24日に開催された。今回は家内同伴で参加した。2002年に続き2回目の参加である。
1) 全体の印象
今回は20回目ということで盛り上がっていた。参加者は650人、展示は43件。参加者リストによると、ドイツから228人、アメリカから120人などで、日本からは10人となっていた。この会議はシングルセッション形式で、招待によるreview talkが中心である。審査による論文投稿はないようである。会議で示されたスライドの多くは、webで公開されていたが現在は残っていない。
2) Sun HPC Consortium Europe 2005
ISC2005に先出ち、6月20日~21日の2日間、Heidelberg市中心部のCrowne PlazaホテルでSun MicrosystemsのHPC Consortium Europe 2005が開かれた。
まず、Marc HamiltonからHPC全体の報告があった。Sun社はCray社やIBM社とともにDARPAのHPCSのPhase IIを受注しており、HPCに積極的に取り組んで行くという心強い表明があった。近い将来50-200 TFlopsのマシンが登場するが、Top500のうちHPC用のマシンは10%以下という現状も認識すべきという指摘があった。筆者のメモによる主なプログラムは以下のとおり。
|
6月20日(月) |
|
|
(9:00) |
Marc Hamilton: Delivering HPC Innovation |
|
(9:45) |
Steve Furtado: Solaris and OpenSolaris |
|
|
Thomas Nau (Ulm): Time for changes |
|
|
Bernd Dammann (Denmark): Using ThinLinc in an HPC environment — some experiences |
|
午後 |
分科会(Parallel Programming & Performance |
|
|
Nick Maclaren (Cambridge): Parallel models |
|
|
Mick Pont (NAG): High Performance Math Libraries on Multi-core Systems |
|
|
Henry Fong (Sun): Grid-Based Opteron Solutions for MCAE |
|
|
C. J. Kenneth Tan (Optima Numerics): HPC Software |
|
|
Cos Ierotheou (Parallel Software Ltd.): A parallelization environment for the generation of efficient and scalable parallel code on Sun HPC systems |
|
|
Michael Rudgyard (Allenea Software Ltd.): HPC Development Tools for Linux and Solaris |
|
16:20 |
Jim Pepin (USC): “Building and Benchmarking a 7 TF Linux Cluster |
|
|
Ruud van der Pas (Sun): A Performance Scalability Study of UltraSPARC IV+ Systems |
|
|
John Fragalla (Sun): Sun Chip Multithreading Systems |
|
7月21日(火曜日) |
|
|
8:45 |
分科会(Grid and Portal Computing) |
|
|
John Darlington (Imperial College): Economic Models of the grid |
|
|
Simon See (Sun): The Asia-Pacific Science and Technology Center (APSTC) |
|
|
Steven Newhouse (OMII): OMII 1.0 and beyond: Architecture & Process |
|
|
Philip Bull (Sun): Utility Grid |
|
|
Michal Kosiedowski (Poznan): Handling workflow grid jobs in N1 Grid Engine |
|
|
Fritz Fersti (Sun): Advances in N1GE |
|
|
Stephen Perrenod (eXludus Technologies, Inc.): RepliCator: A different Approach to Data-Intensive Cluster computing |
|
|
Kevin Stratford (EPCC): Cosmology using MPI on the Grid |
|
|
Mark Jessop (York): World University Network Grid |
|
|
Christian Haeberli (Bern): The Swiss ATLAS Computing Prototype |
|
午後 |
基調講演 Steve Campbell (Sun): Innovation Matters in HPTC |
|
|
Francesco Torricelli (AMD): AMD’s challenge in EMEA HPC |
|
|
Jan Fisher, Sr. (Sun): Future NSG Platforms |
|
|
Panel: “Bringing the Gap between CIO and Scientist” |
Sun社のOSであるSolaris 10が紹介され、multi-platformであることが強調された。UltraSparcはもちろん、AMDでも、Intelでも動く。Solarisは誰でもタダで、現在までに160万件のライセンスを出している。Solaris 10は軍用のTrusted Solarisを統合したので、軍レベルのセキュリティがあると述べた。7年間のバイナリ互換性を保証する。
このあと、ユーザの報告が続いた。初日夕方には、次世代のプロセッサUltraSPARC IV+や、multi-threadingのNiagaraやRockの話があった。
2日目もユーザの報告があり、Steve Campbellの基調講演“Innovation Matters in HPTC”やパネルなどがあった。
3) 展示
ISC本会議の方であるが、22日朝から24日11時まで企業や大学・研究機関センターの展示が会議場の2階の廊下で開かれていた。あまり広くないスペースであったが、46の組織が55のブースで盛大に展示を示していた。ハードウェアが20件、ソフトウェアが8件、接続網が4件、問題解決が3件、記憶装置が2件、HPC センターが9件である。日本関係では、日本電気と富士通が出していた。IBMはこの会議のメインスポンサーだそうで、多くのブースを使いなかなかにぎやかだった。BG/Lのラックを設置し動かしていた。SC2004にも出ていたが、ClearSpeedというベンチャーが、CSX600というマルチコアのコプロの実演をやっていた。1チップに搭載されている96個のprocessing coresが250 MHzで動き、全体では50 GFlopsのピーク速度を持つ。しかも(クロックが低いので)5 Wしか食わないということである。今後このような低消費電力・マルチコアの製品がいろいろ出てくることであろうと思った。
4) 開会式
7月22日10時から開会式が行われた。まず主催者のHans Meuer教授が歓迎の言葉とともに、この会議の歴史を紹介した。引き続いてHeidelberg大学のWilli Jägerと、European Media LaboratoryのAndreas Reuterが歓迎のことばを述べた。
5) Top500(2005年6月、世界)
SCにおいてTop500はBoFの一つに過ぎないが、ISCでは開会式に続くメインイベントである。Erich Strohmaier (NERSC) は、”20 Years of Supercomputer Market Analysis at ISC” と題して、25回目となる今回のリストを発表するとともに、歴史を回顧し、現状を分析した。Strohmaier氏は、1950年頃のEDSAC1やUNIVAC1(1 kFlops弱、でもそのころLINPACKはなかった)から今日までの計算機の進歩を示し、55年間、年率1.608で進歩していることを示した。いわゆるMooreの法則「18ヶ月毎にトランジスタ数は倍増する」は年率1.587に相当するから、これにほぼ等しい。今年のTop500の参入条件はすでに1.166 TFlops以上となり、テラフロップスないとスーパーコンの仲間に入れないということである。1993年のTop500の速度の合計が1.167 TFlopsであったから、12年前の500台の計算機がまとめてかかっても、今の500番目にやっと入れるという事である。なかでもショックだった図は、アジア諸国のTop500に含まれる台数のグラフで、日本は1993年には110台あったのに、2005年には20台強にまで減ってしまっていることである。反面、中国の進出が著しい。日本製のスーパーコンが少ないことと合わせて、ゆゆしき事態と言わなければならない。(HPCwie 2005/6/24)
Top500の栞が配られていた。表と裏はこんな感じであった。裏のTop5では地球シミュレータが4位となっている。
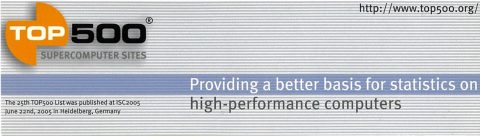 |
 |
まず、Top20を示す。トップ10は 1, 2, 6, 8 位(8位は2件)の5件が BG/L という結果となった。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
システム |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
(1) |
LLNL |
BlueGene/L |
65536 |
136.8 |
183.5 |
|
2 |
- |
IBM T.J.Watson |
BGW |
40960 |
91.29 |
114.688 |
|
3 |
2 |
NASA Ames |
Columbia – SGI Altix 1.5 |
10160 |
51.87 |
60.98 |
|
4 |
3 |
海洋研究開発機構 |
地球シミュレータ |
5120 |
35.86 |
40.96 |
|
5 |
4 |
Barcelona SC |
MareNostrum – JS20 Cluster |
4800 |
27.91 |
42.144 |
|
6 |
- |
ASTRON(オランダ) |
Stella – Blue Gene |
12288 |
27.45 |
34.4064 |
|
7 |
5 |
LLNL |
Thunder – Itanium 2 1.4 – Quadrics |
4096 |
19.94 |
22.938 |
|
8 tie |
- |
産総研CBRC |
Blue Protein – Blue Gene |
8192 |
18.2 |
22.9376 |
|
8 tie |
- |
EPF Lausanne(スイス) |
Blue Gene |
8192 |
18.2 |
22.9376 |
|
10 |
- |
SNL |
Red Storm – Cray XT3, 2.0 GHz |
5000 |
15.25 |
20.0 |
|
11 |
- |
ORNL |
Cray XT3, 2.4 GHz |
3748 |
14.17 |
17.99 |
|
12 |
6 |
LANL |
ASCI Q – AlphaServer SC45, 1.25 GHz |
8192 |
13.88 |
20.48 |
|
13 |
- |
LLNL |
pSeries p5 575 1.9 GHz |
2048 |
13.09 |
15.5648 |
|
14 |
7 |
Virginia Tech |
System X – 1100 Dual 2.3 GHz Apple |
2200 |
12.25 |
20.24 |
|
15 tie |
- |
Air Force Research Lab. |
SGI Altix 3700 Bx2 1.6 GHz |
2048 |
11.814 |
13.107 |
|
15 tie |
- |
日本原子力研究所 |
SGI Altix 3700 Bx2 1.6 GHz |
2048 |
11.814 |
13.107 |
|
17 |
8 |
IBM Rochester |
BlueGene/L DD1 Prototype |
8192 |
11.68 |
16.384 |
|
18 |
- |
中国気象局 |
pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) |
3200 |
10.31 |
21.76 |
|
19 |
9 |
NAVOCEANO |
pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) |
2944 |
10.31 |
20.0192 |
|
20 |
10 |
NCSA |
Tungsten – PowerEdge 1750 |
2500 |
9.819 |
15.3 |
18位の中国気象局のIBM p655は、19位と比べると、Rmaxはもう少し大きいと思われる。No. 1, 2, 3とNo.5 (ヨーロッパでトップ)に表彰状が授与された。この時はアジアのトップという表彰はなかったようである。
6) Top500(2005年6月、日本)
100位以内の日本設置のマシンは以下の通り。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
システム |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
4 |
3 |
海洋研究開発機構 |
地球シミュレータ |
5120 |
35.86 |
40.96 |
|
8 tie |
- |
産総研CBRC |
Blue Protein – Blue Gene |
8192 |
18.2 |
22.9376 |
|
15 tie |
- |
日本原子力研究所 |
SGI Altix 3700 Bx2 1.6 GHz |
2048 |
11.814 |
13.107 |
|
29 |
14 |
理研 |
RIKEN Suer Combined Cluster |
2048 |
8.728 |
12.534 |
|
41 |
- |
名古屋大学 |
PRIMEPOWER HPC2500 (2.08 GHz) |
1664 |
6.86 |
13.844 |
|
46 |
28 |
産総研グリッド研究センタ |
AIST Super Cluster P-32 |
2200 |
6.155 |
8.8 |
|
55 |
32 |
JAXA |
PRIMEPOWER HPC2500 (1.3 GHz) |
2304 |
5.406 |
11.98 |
|
62 |
- |
ニイウス |
Blue Gene |
2048 |
4.713 |
5.734 |
|
67 |
33 |
京都大学 |
PRIMEPOWER HPC2500 (1.56 GHz) |
1472 |
4.552 |
9.185 |
7) Horst Simon, “Progress in Supercomputing: The Top Three Breakthroughs of the Last 20 Years and the Top Three Challenges for the Next 20 Years”
二つの基調講演の一つはHorst Simon (Associate Laboratory Director, LBNL)で、20年間の変化を分析した。計算速度やメモリの飛躍的増大を述べた後、以下のような変化を指摘した。
|
1985年 |
2005年 |
|
注文生産のベクトル計算機 |
汎用チップのMPP |
|
ベクトル化FORTRANでプログラム |
Fortran/CとMPIでプログラム |
|
自社製のOS |
共有のUnix/Linux |
|
リモートバッチでの利用 |
会話的利用 |
|
数字の出力だけ |
可視化 |
|
人手によるチューニング |
並列デバッガやチューニングツールの利用 |
|
テキスト端末 |
高性能デスクトップ |
|
9600 baudのアクセス |
10 Gb/sのアクセス |
|
ベクトル用アルゴリズム |
並列アルゴリズム |
10の主要なブレークスルー(タイトルでは3つの予定だったようだ)としては、以下の10件を挙げた。
|
No. 10 |
Top 500 List(ジョークか?) |
|
No. 9 |
NAS Parallel Benchmark |
|
No. 8 |
The “Grid” |
|
No. 7 |
Hierarchical Algorithms: multigrid and fast multipole methods |
|
No. 6 |
HPCC Initiative and Grand Challenge Applications |
|
No. 5 |
The “Attack of the Killer Micros” |
|
No. 4 |
Beowulf Clusters |
|
No. 3 |
Scientific Visualization |
|
No. 2 |
MPI (Message Passing Interface) |
|
No. 1 |
Scaled Speed-Up(Amdahlの法則に「反して」) |
最後に今後の20年のチャレンジとして、3つの時期にわけて論じた。2010年までの課題はペタフロップスまで応用プログラムをスケールさせることである。2010年~2018年の課題は、HPCの新しいエコシステムを開発することである。2015年~2025年の課題は、Mooreの法則がいよいよ飽和して、性能向上が終わりを告げることである。産業界は「ゼロ成長」のシナリオに耐えられるか、と結んだ。
8) Thomas Sterling, “Looking Back over the Last Year in HPC”
恒例になっているTom Sterlingによる最近1年間のHPCの回顧である。Tomはこの一年を”High Density Computing”と総括した。トレンドのハイライトとして、2年以上地球シミュレータが占めていたTop500の首位の座をBlueGene/Lが奪還したことである。もう一つのトレンドはコモディティのクラスタが相変わらずHECの主流を占めていることである。3つめのトレンドは(Fortran 2008やUPCなど)次世代のHEC言語の研究が進んでいることである。
9) Steve Louis and Alan Gara, “Peta-Scale Computing during Disruptive Times”
23日の基調講演は「破壊の時代におけるペタスケール・コンピューティング」であった。まずSteve Louis (LLNL)が 破壊的技術革新とは何かについて語り
1) 現行の製品とは異なるものが市場にもたらされる。
2) 以前より簡単(多くの場合、より安い)もの
3) 市場の主流でないところに根をおくもの
4) 後には、主流のニーズを横取りするように改良される
5) 占有ではなく差別化によって市場の破壊者になる
というようなことを述べた。要は、「Blue Geneこそ破壊的革新技術だ」と言いたいらしい。続いてAlan Gara (IBM)が、今後のアーキテクチャの動向について述べ、技術革新のためには、アプリの専門家とシステムの専門家のアグレッシブな協力が必要だと結んだ。
 |
|
10) Hot Seat
これも恒例のベンダをいじめるセッション。各ベンダが10分のプレゼンを行い、壇上のInquisitors(異端審問官)が5分間厳しい質問を浴びせる。Myricom社のChuck Seitzは短パン、Tシャツ姿で現れ、10 GbのMyrinetは10 GbEと技術を共有すると述べた。QuadricsのMoray McLarenも次の10 GbのQuadricsは下位の層に10 GbEと同じ技術を使うと述べた。
日本関係の会社では、NEC HPCE GmbHからドイツの人がしゃべり、富士通からは奥田基氏が講演した。NECは2010年までにペタを出すと豪語し、奥田氏は、2006Q1までに、Montecito (2 coreのItanium)を使ったPRIMEQUEST/HPCを出すと豪語した。帰国後知ったことであるが、富士通は同じ6月23日付けで「富士通は2010年度末までに、ピーク性能3 PFlopsを持つ次世代スパコンの稼働を目指して研究開発を進める。」と公式発表したようである(既出)。
11) Gala Event
この日の夜はIBMによるイベントとして、Castle Neckarbischofsheimでのパーティーがあった。Neckarbischofsheimは、ハイデルベルクからネッカー川をバスで1時間(直線距離24 km)ほど上流に上ったあたりの小都市で、そこのお城の一つ(たぶんノイエ・シュロス)が会場であった。名前からして、元々司教の館(やかた)だったと思われる。7時半というのにまだ日が高く、暑いほどであった。すばらしい食事(とビールやワイン)とともに、暗くなった頃盛大な花火が上がった(写真)。
12) Wolfgang Gentzsch, “Grid Computing in Research and Business around the World”
24日はI/OやData Managementのセッションのあと、最終日の基調講演があった。昼過ぎで終了し、筆者は家内の運転するベンツでアウトバーンをぶっ飛ばして、ローテンブルクまで遊びに行った。
次回と次々回は11月シアトルでのSC|05である。直前のSun HPC Consortium USA 2005では、東工大のTSUBAMEが大きく取り上げられた。富士通のUser’s Meetingでは、Tony Heyが招待講演を行なった。
 |
 |
 |

