新HPCの歩み(第255回)-2007年(h)-
|
HPC Asia 2007はソウルのロッテホテルで開催された。情報処理学会のHPC研究会はこの国際会議を協賛するとともに、同会場でHPC研究会を開催した。4年に1度開催されるICIAM 2007がチューリッヒで開催された。36回目のICPP 2007は中国の西安で開催された。 |
国際会議
1) HiPEAC 2007 (Ghent、ベルギー)
第2回となるHiPEAC 2007(High Performance Embedded Architectures and Compilers)は、2005年11月に続き、2007年1月28日~30日にベルギーのGhent(ヘント)で開催された。基調講演は下記の通り。
|
Thomas M. Conte, Georgia Institute of Technology, |
Insight, Not (Random) Numbers: An Embedded Perspective |
会議録は、LNCS 4367としてSpringer社から出版されている。
2) ISSCC 2007 (San Francisco)
第54回目となるISSCC 2007 (2007 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、2007年2月11日~15日にSan Francisco Marriot Hotelにおいて、“The 4 Dimensions of IC Innovation”のテーマで開催された。主催者は、IEEE Solid-State Circuits Society, IEEE San Francisco Section, Bary Area CouncilおよびPennsylvania大学である。3件の全体講演があった。
|
Foundry Future: Challenges in the 21st Century |
Morris Chang, founder of TSMC |
|
Analog and Mixed-Signal Innovation: The Process-Circuit-System-Application Interaction |
Lewis Counts of Analog Devices |
|
Toward A New Nanoelectronic Cosmology |
Joël Hartmann, of Crolles2 Alliance |
電子版の会議録はIEEE Xploreに置かれている。PC WatchのISSCC 2007レポートリンク集にいくつかの話題が紹介されている。
3) HPC User Forum (IIT Delhi, India)
インドでの初めてのHPC User Forumが、2007年2月28日~3月2日に、DelhiのIIT (Indian Institute for Technology)で開催された。(HPCwire 2007/1/5)
 |
|
4) 次世代気候モデル開発 (Hawaii)
RIST(高度情報科学技術研究機構)の主催による最先端並列計算機における次世代気候モデル開発に関わる国際ワークショップは、1999年のハワイ会議から(2012年まで)日米欧を会場に毎年開かれている。昨年はAlbuquerqeであったが、2007年はハワイに戻り、第4回共生ワークショップとの併催で3月1日~3日に第9回ハワイ会議”The 9th International Workshop on Next Generation Climate Models for Advanced High Performance Computing Facilities”としてSheraton Princess Kaiulaniホテル(写真はWikipediaから)開催された。Sustainabilityがテーマということで、筆者は”Sustainable Society and Information Technology”という講演を行った。
5) CGO-2007 (San Jose)
第5回目となるCGO-2007 (2007 International Symposium on Code Generation and Optimization)は2007年3月11日~14日にカリフォルニア州San JoseのHotel Valencia Santana Rowで開催された。主催はIEEE/CS TC-uARCHとACM SIGMICROとACM SIGPLANである。昨年と同様にPPoPP’07 (Principles and Practice of Parallel Programming)との同時開催である。2件の基調講演と1件のパネルが行われた。
|
Keynote |
GPU Computing: Programming a Massively Parallel Processor |
Ian Buck, NVIDIA |
|
Keynote |
Parallel Programming Environment: A Key to Translating Tera-Scale Platforms into a Big Success |
Jesse Fang, Intel |
|
Panel |
Are new languages necessary for multicore? |
Chairs: Michael Paleczny, Sun and Carol Eidt, Microsoft |
6) ARCS 2007 (Zurich)
第20回目となるARCS 2007 (International Conference on Architecture of Computing Systems 2007)は、2007年3月12日~15日にスイスのZurichで開催された。会議録はSpringer社からLNCS 4415として出版されている。
7) IPDPS 2007 (Long Beach)
IPDPS 2007 (21st IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium)は、2007年3月26日~30日にカリフォルニアのRenaissance Long Beach Hotel, Long Beachで開催された。主催はIEEE/CS TCPP (Technical Committee on Parallel Processing)、共催はACM SIGARCH、IEEE/CS TCCA、IEEE/CS CDPであった。PCGrid 2007 (Workshop on Large-Scale, Volatile Desktop Grids)が併設された。招待講演は下記の通り。
|
TCPP Reception Talk |
“Reinventing Computing” |
Burton Smith, Microsoft |
|
Keynote I |
“Large-Scale Bioimaging and Visualization” |
Christopher Johnson, U. of Yutah |
|
Keynote II |
“Avoiding the Memory Bottleneck through Structured Arrays” |
Michael J. Flynn, Stanford U. |
|
Banquet Talk |
“Why Peta-Scale is Different: An Ecosystem Approach to Predictive Scientific and Engineering Simulation” |
Mark Seager, LLNL |
|
Keynote III |
“Quantum Physics and the Nature of Computing” |
Umesh Vazirani, UCB |
8) Teraflops Workshop (HLRS、Stuttgart、東北大学)
第6回目となるTeraflop Workshopは、2007年3月26日~27日に、StuttgartのHLRSで開催された。プログラムは以下の通り。
3月26日
|
9:15 |
Welcome |
|
|
9:30 |
Teraflop Workbench – Results & Future Petaflop Architecture |
Wolfgang Bez |
|
10:15 |
Coffee |
|
|
10:45 |
A Year with TSUBAME and its Possible Future Petaflops Extensions |
Prof. Satoshi Matsuoka, TITECH |
|
11:30 |
The Path to Petascale |
Jay Boisseau, Texas Advanced Computing Center, The University of Texas at Austin |
|
12:15 |
Lunch |
|
|
13:30 |
ISC plans and update |
Hiroaki Kobayashi, Tohoku University, Japan |
|
14:15 |
Ionic liquids from Car-Parrinello molecular dynamics – exceeding TFLOPS on NEC SX-8 at HLRS |
Ari P. Seitsonen, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France |
|
14:45 |
Performance Assessment and Parallelisation Issues for Large-Scale Applications of the CFD Code NSMB |
Jörg Ziefle, Institute of Fluid Dynamics, ETH Zürich |
|
15:15 |
Coffee |
|
|
15:45 |
Supernova Simulations with the Radiation Hydrodynamics Code PROMETHEUS/VERTEX |
Bernhard Mueller, MPA Garching |
|
16:15 |
Simulations of Premixed Swirling Flames using a Hybrid Finite-Volume / Transported PDF Approach |
Stefan Lipp, Institut fuer Technische Thermodynamik (ITT), Universität Karlsruhe (TH) |
|
16:45 |
FSI simulations on vector systems – Development of a linear iterative solver (BLIS) |
Malte von Scheven, IBB, University of Stuttgart / Sunil Tiyyagura, HLRS, University of Stuttgart |
|
17:15 |
Wrap up and discussion |
|
|
19:00 |
Social Event |
|
3月27日
|
9:00 |
French-Japanese collaborations on the Earth Simulator |
Sebastien Masson, University Pierre and Marie Curie, Paris, France |
|
9:45 |
Ensemble SimulationS of Extreme weather events under Nonlinear Climate changE (ESSENCE) |
Henk Dijkstra, Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht, Utrecht University, The Netherlands |
|
10:30 |
Coffee |
|
|
11:00 |
Application Performance on Commodity-class Computers: The Impact of Cluster Architecture |
Martyn Guest |
|
11:45 |
Blood flow simulations |
Uwe Küster, HLRS, University of Stuttgart |
|
12:15 |
Coupled Problems in Computational Modeling of the Respiratory System |
Lena Wiechert, TU München |
|
12:45 |
Lunch |
|
|
13:30 |
High Performance Computing Towards Silent Flows |
Wolfgang Schroeder, Aerodynamisches Institut, RWTH Aachen |
|
14:15 |
Fluid-Structure Interaction: Simulation of an tidal current turbine |
Ivana Buntic-Ogor, IHS, University of Stuttgart |
|
14:45 |
Coffee |
|
|
15:15 |
Aeroelastic Simulations of Isolated Rotors Using Weak Fluid-Structure Coupling |
Markus Dietz, IAG, University of Stuttgart |
|
15:45 |
Large-scale Computations of Flow around a Circular Cylinder |
Dr. Jan Wissink, IfH, Uni Karlsruhe |
|
16:15 |
Closing remarks and end |
|
会議録は“High Performance Computing on Vector Systems 2007”として、Springer社から出版されている。
なお第7回は11月21日~22日に東北大学で“計算科学の可能性と次世代スーパーコンピュータ研究開発動向を探る”をテーマに開催された。主要な招待講演は以下の通り。
|
Supercomputing Aerospace CFD – Glance Back the Past and Consider the Future |
宇宙航空研究開発機構 藤井 孝藏 |
|
HPC in Academia and Industry – Synergy at Work |
HLRS Michael Resch |
|
Multi-Objective Design Exploration (MODE) – Finding Design Tradeoff, Sweet Spot, and Knowledge |
東北大学 大林 茂 |
|
Large Scale Particle-in-Cell Plasma Simulation |
核融合科学研究所 石黒 静児 |
|
The Development Project of a Next-Generation Supercomputer System and Application Software |
理化学研究所 花村 光泰 |
|
Some Lessons from the Earth Simulator Project |
海洋研究開発機構 大淵 済 |
9) ICCM2007(広島)
ICCM2007 (International Conference on Computational Methods)は、2007年4月4日~6日、平和記念公園内の広島国際会議場で開催された。この会議は2004年にProf. G.R. Liuによって始められ、2回目である。その後は二三年間隔で開催されている。
10) COOL Chips 2007(横浜)
10回目にあたるCOOL Chips X (IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)は、2007年4月18日~20日、横浜情報文化センターで開催された。主要ブログラムは以下の通り。
|
Keynote |
“Introduction of the Japanese Supercomputer Project and its Technical Challenges” |
Tadashi Watanabe, RIKEN |
|
Keynote |
“Toshiba’s Strategy in Semiconductor Business and NAND Flash Memory” |
Shozo Saito, Toshiba Corp. |
|
Invited |
“A 65nm SPE for a 1 Petaflop Super Computer” |
Brian Flachs, IBM |
|
Invited |
“EXREAL Platform : SOC Design Challenges for Embedded Systems” |
Toshihiro Hattori, Renesas Technology Corp. |
|
Panel |
“Microprocessor for 10-PetaFLOPS supercomputer” |
Organizer & moderator: Ryutaro Himeno, RIKEN |
|
Special Sessions |
“Novel Architectural Techniques to Mitigate Processor Errors due to Design Defects and Parameter Variation” |
Josep Torrellas, University of Illinois |
|
“Architectural Integration of Software Protection” |
Gyungho Lee, University of Illinois |
11) Computing Frontier 2007 (Ischia)
第4回目となるACM International Conference on Computing Frontiers 2007は、2007年5月7日~9日に前3回と同じくイタリアのIschia島で開催された。以下の3件の基調講演が行われた。
|
Keynote 1 |
Recent Technological Trends and their Impact on System Design |
Pratap Pattanaik, IBM |
|
Keynote 2 |
Models for Parallel and Hierarchical Computation |
Gianfranco Bilardi, Padova大学 |
|
Keynote 3 |
The Quantum Challenge to Computer Science |
Philippe Jorrand, CNRS |
12) CCGrid07 (Rio de Janeiro)
CCGrid07 (7th IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid)は、2007年5月14日~17日にブラジルのRio de Janeiroで開催された。IEEE/ACMが主催した。発表の一部はWiley発行のConcurrency and Computation: Practice and Experienceの特別号として発表された。ワークショップGP2PC’07 (The 7th International Workshop on GLOBAL AND PEER-TO-PEER COMPUTING” Observation, Experience and Application”が併設された。参加者は331人。
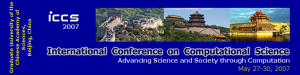 |
|
13) ICCS 2007 (北京)
ICCS 2007 (International Conference on Computational Science 2007)は2007年5月27日~30日に中国の北京にある中国科学院大学(Graduate University of the Chinese Academy of Sciences)で開催された。ICCSは2001年San Franciscoに第1回が開催され、これは7回目である。今回のテーマは”Advancing Science and Society through Computation”であった。会議議長はYong Shi(石勇、中国科学院大学)、プログラム委員長はDick van Albada、Scientific Co-chairはJack DongarraとPeter Slootであった。基調講演は以下の通り。
|
“Efficient Scalable Algorithms for Large Scale Computations” |
Vassil Alexandrov, Reading大学(英国) |
|
“Computational Modeling of Huge Tsunamis from Asteroid Impacts” |
Hans Petter Langtangen, Oslo大学(スエーデン) |
|
“Research Frontiers in Advanced Data Mining Technologies and Applications” |
Jiawei Han, UIUC(米国) |
|
“Knowledge Engineering and Knowledge Ware” |
Ru-qian Lu(陸汝鈴)中国科学院数学与系統科学研究院 |
|
“Computational epidemiology and emergent disease forecast” |
Alessandro Vespignani, Indiana大学(米国) |
|
“Scalable Solver Infrastructure for Computational Science and Engineering” |
David Keyes, Columbia大学(米国) |
|
“Think before coding: static strategies (and dynamic execution) for clusters and grids” |
Yves Robert, Ecole Normale Supérieure de Lyon(仏) |
会議録は、SpringerからLNCS 4487~4490として出版されている。
14) IWOMP 2007 (北京)
IWOMP 2007 (International Workshop on OpenMP (2007))” A Practical Programming Model for the Multi-Core Era”は2007年6月3日~7日に北京の清華大学で開催された。
15) COMPUTEX 2007(台北)
COMPUTEX 2007は、2007年6月5日~9日に台北市信義路にあるthe Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hallを中心に開催された。
16) ISCA 2007 (San Diego)
ISCA 2007 (The 34th Annual International Symposium on Computer Architecture)は、2007年6月9日~13日、San Diegoにおいて2007 Federated Computing Research Conferenceの一部として開催された。主催はACM/SIGARCHとIEEE/CSで、共同組織委員長はDean M TullsenとBrad Calderである。会議録はACMから出版されている。HPでは会議名にAnnualが付いていないが、会議録には付いているなど不統一である。
17) ICS 2007 (Seattle)
ICS 2007 (21st International Conference on Supercomputing)は2007年6月16日~20日にSeattleのCrowne PlazaホテルでACM/SIGARCHの主催により開催された。議長はBurton Simth (Microsoft)。この会議は1987年から開催されている。基調講演は以下の通り。
|
Current trends in computer architectures: Multi-cores, Many-cores and Special-cores |
Avi Mendelson, Intel |
|
Harnessing Massive Parallelism in the era of Parallelism for the Masses |
Craig Stunkel, IBM |
17日、ワークショップALPS (2nd International Workshop on Advanced Low Power Systems)が併設された。会議録はACMから出版されている。
18) ISC2007 (Dresden)
2007年6月25日(月)~7月1日(日)にDresdenで開催された ISC2007 については別項で述べる。
19) HPDC-16 (Monterey)
第16回目となるHPDC-16 (The 16th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、2007年6月27日~29日、カリフォルニア州MontereyのMonterey Hyatt Regencyで開催された。3件の基調講演が行われた。
|
Keynote |
Michael Franklin, UCB |
|
Keynote |
Satoshi Matsuoka, Titech |
|
Keynote |
Urs Hölzle, Google |
会期中7件のワークショップが開催された。IEEEは主催者であるが、会議録はこれまでとは異なり、ACMから出版されている(以後も同様)。
20) ICIAM 2007 (Zurich)
応用数理学会連合が4年に1度開催するICIAM 2007 (The International Council for Industrial and Applied Mathematics)は2007年7月16日~20日にスイスのZurichで、Zurich ETHとZurich大学を会場に開催された。
21) Lattice 2007 (Regensburg)
第25回となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 2007)は、2007年7月30日~8月4日にドイツのRegensburgで開催された。会議録はオンラインでPoS上に公開されている。
 |
|
22) HOT CHIPS 19 (2007) (Stanford)
1989年から始まり、Stanford大学またはその周辺で開催されて来た高性能半導体の国際会議HOT CHIPSは、19回目のHOT CHIPS 19 (2007)をStanford大学のMemorial Auditoriumにおいて、2007年8月19日~21日に開催した。基調講演2件とパネル討論は以下の通り。
|
Keynote: “Digital Gaia” |
Vernor Vinge, Computer scientist, science-fiction writer |
|
Keynote: “Multicore and Beyond: Evolving the x86 Architecture” |
Phil Hester, AMD |
|
Panel: What’s Next After CMOS? |
Moderator: Norm Jouppi (HP) |
この「CMOSの次に来るのは何か」というパネルについてはAndo Hisaによる報告がある。Kubiatowicz教授が、来年(2008年)には実用的な計算ができる最低限と言われる30qubitをイオントラップで実現できると述べ、量子コンピューティングはCMOS以後の候補になり得ると述べた。本当か。(MyNavi News 2007/9/9)
23) Euro-Par 2007 (Rennes)
Euro-Par 2007 (The 13th International Euro-Par Conference, European Conference on Parallel and Distributed Computing)は、2007年8月28日~31日にフランスRennesのIRISAで開催された。The First CoreGRID European Network of Excellence Symposiumとの合同開催である。展示会も併設された。基調講演は以下の通り。
|
Keynote: Transactions are back: but are they the same? |
Rachid Guerraoui – EPFL (Switzerland) |
|
Keynote: Virtualizing the Data Center with Xen |
Steve Hand – University of Cambridge (United Kingdom) |
|
Keynote: 15mm x 15 mm: the new frontier of parallel computing |
André Seznec – IRISA (France) |
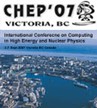 |
|
24) CHEP 2007 (Victoria)
第16回目となるCHEP 2007 (International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics 2007)は、2007年9月2日~7日にカナダのBritish Columbia州のVictoriaで開催された。会議録は、Journal of Physics: Conference Series CHEP 07 Proceedings(Volume 119)として出版されている。写真はProceedingsの表紙である。
25) ParCo 2007 (Jülich/Aachen)
1983年からほぼ2年ごとにヨーロッパで開催されている(1987年は開催せず)が、ParCo2007 (PARALLEL COMPUTING 2007)は、2007年9月4日~7日にドイツのJülichの研究センター(FZJ)とAachen大学のRWTHを会場に開催された。6日以外はFZJが会場で、Aachenから朝晩のバスで連絡した。FZJはかなりの田舎にある。前日の9月3日にはAdvanced OpenMP and MPI Tutorialsが開催された。招待講演は以下の通り。
|
European E-Infrastructure: Promoting Global Virtual Research Communities |
Maria Ramalho-Natario, European Commission, INFSO |
|
Programming in the Multicore Era |
Barbara Chapman, University of Houston, Texas |
|
Simulation of Heart-Assist Devices |
Marek Behr, RWTH Aachen University |
|
Towards Petascale Grids as a Foundation of E-Science |
Satoshi Matsuoka, Tokyo Institute of Technology |
26) HPC Asia 2007 (Seoul)
HPC Asia 2007 (The 9th International Conference on High Performance Computing, Grid and e-Science in Asia Pacific Region)は、KISTIの主催で、2007年9月9日~13日にソウルのロッテホテルで開催された。情報処理学会のHPC研究会はこの国際会議を協賛するとともに、9月9日に同会場で第112回HPC研究会を開催した。HPC研究会登録会員は参加費が$100割引された。筆者はこれまでのHPC Asiaは皆出席であったが、今回は所用で欠席した。
27) ICPP 2007 (西安)
36回目のICPP 2007 (2007 International Conference on Parallel Processing)は2007年9月10日~14日に中国の西安 (Xi‘ An)の西安電子科技大学(Xidian University)で開催された。3回目の4年周期の1年目である。主催はIACC (The International Association for Computers and Communications)とNSF (US National Science Foundation)。共催はXidian University (西安電子技科大學)とOhio State Universityであった。電子版会議録はIEEE XploreとIEEE/CSに置かれれている。基調講演は以下の通り。
|
Reflections on Failure in Post-Terascale arallel Computing |
Garth Gibson (Carnegie Mellon U.) |
|
Computational Challenges in Multiple Adversarial Multi-agent Teams |
Jose Cruz (OSU) |
|
Data-parallel Abstractions for Irregular Applications |
Keshav Pingali (U. of Texas, Austin) |
13日には始皇帝の兵馬俑などの見学ツアーがあった。
28) Cluster 2007 (Austin)
第9回目となるCluster 2007 (2007 IEEE International Conference on Cluster Computing)は、2007年9月17日~21日にテキサス州AustinのOmni Austin Hotel Downtown Austinで開催された。会議録はIEEEから出版されている。
29) iWAPT2007 (東大)
iWAPT2007 (The Second international Workshop on Automatic Performance Tuning)は2007年9月20日~21日に東大の小柴ホールで開催された。プログラム委員長は片桐孝洋(東大)、副委員長は直野健(日立)である。招待講演は以下の通り。
|
Keynote: “Advances in Self-Tuning Database Systems” |
Vivek Narasayya (Microsoft Research) |
|
“ATLAS Version 3.8 : Overview and Status” |
R. Clint Whaley (University of Texas, San Antonio) |
|
Can We Teach Computer To Write Fast Libraries? |
Markus Püschel (Carnegie Mellon University) |
30) HPC User Forum (Santa Fe)
IDCが主催するHPC User Forumは、2007年9月26日~27日にニューメキシコ州Santa Feで「HPCにおけるエネルギー問題」をテーマに開催された。基調講演はDOEのSenior Advisor, Office of the SecretaryのVictor Reisであった。(HPCwire 2007/10/12)
31) EuroPVM-MPI 2007 (Paris)
14回目となるEuroPVM-MPI 2007(14th European PVM/MPI User’s Group Meeting)は、2007年9月30日~10月3日にフランスのParisで開催された。6件の招待講演と3件のチュートリアルが行われた。
|
招待講演 |
|
|
The X-Scale Challenge |
George Bosilca |
|
Sustained Petascale: The Next MPI Challenge |
Al Geist |
|
MPI: Past, Present and Future |
Tony Hey |
|
New and Old Tools and Programming Models for High-Performance Computing |
Ewing Lusk |
|
The TSUBAME Cluster Experience a Year Later, and onto Petascale TSUBAME 2.0 |
Satoshi Matsuoka |
|
To Infinity and Beyond?! On Scaling Performance Measurement and Analysis Tools for Parallel Programming |
Bernd Mohr |
|
チュートリアル |
|
|
Using MPI-2: A Problem-Based Approach
|
William D. Gropp, Ewing Lusk |
|
Verifying Parallel Programs with MPI-Spin |
Stephen F. Siegel |
|
Advanced MPI Programming |
Julien Langou, George Bosilca |
32) I-SPAN 2007
9回目のI-SPAN 2007 (The International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks) は2007年10月11日~13日にオーストラリアのSydneyで開催された。IEEEのリストではこの回は無視されているようである。1回目は1994年12月14日~16日に金沢で開催された。
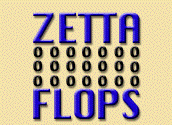 |
|
33) Frontiers of Extreme Computing 2007
第3回目となるFrontiers of Extreme Computing 2007/Zettaflops workshopは、2007年10月21日~25日にカリフォルニア州Santa Cruzで開催された。サマリーによると、議論された主要な問題は
a) 伝統的アプリと新しいアプリ
b)増大する並列性
c) メモリと記憶装置
d) 相互接続
e) 信頼性
f) プログラミングモデル
g) 消費電力
h) ヘテロなアーキテクチャと演算加速装置
i) 新しいデバイスの可能性(可逆計算、量子計算)
などであった。2008年からは、Zettaflopsより宇宙空間で故障しないコンピュータ技術の方に関心が移っている。
34) The Grace Hopper Celebration of Women in Computing (GHC)(Orlando)
第7回のThe Grace Hopper Celebration of Women in Computing 2007は、2007年10月17日~20日にフロリダ州Orlandoで“I Invent the Future”をテーマに開催された。主催はAnita Borg Institute。参加者は1430人。
35) SC07
11月12日(月)~18日(日)のSC07(Reno, Nevada)については別記する章を改めて記す。
36) Teraflop Workshop
3月にStuttgartで開催された第6回に引き続き、第7回Teraflop Workshopは2007年11月21日~22日に東北大学で開催された。主催は、東北大学情報シナジーセンター、HLRS、GSIS、NECである。プログラムは以下の通り。
11月21日
|
10:30 |
Greeting |
|
|
10:45 |
Greeting and HPC update at ISC |
Hiroaki Kobayashi (ISC, Tohoku University) |
|
11:00 |
HPC in Academia and Industry – Synergy at Work |
Michael Resch (HLRS, Stuttgart University) |
|
11:45 |
Multi-Objective Design Exploration (MODE) – Finding Design Tradeoff, Sweet Spot and Knowledge |
Shigeru Obayashi (IFS, Tohoku University) |
|
12:30 |
Lunch |
|
|
1:30 |
Large scale Particle-in-Cell Plasma Simulation |
Seiji Ishiguro (National Institution for Fusion Sience) |
|
2:15 |
Tera-flops Quantum Simulation for Superconducting Nano-device: High-Performance Eigenvalue Solver on the Earth Simulator |
Susumu Yamada (Japan Atomatic Energy Agency) |
|
2:45 |
Transient Thermal Stress Simulation of a Curved Steam Generator Tubesheet |
Osamu Hazama (Japan Atomic Energy Agency) |
|
3:15 |
Coffee Break |
|
|
3:45 |
Complex Numerical Simulations in Production Techniques |
Jörg Niemann (Institute of Industrial Manufacturing and Management, Stuttgart University) |
|
4:30 |
MPI in the Light of Multi-core Architectures: Thread-Safety |
Rainer Keller (HLRS, Stuttgart University) |
|
5:00 |
Performance |
Uwe Küster (HLRS, Stuttgart University) |
11月22日
|
10:00 |
The Development Project of a Next-Generation Supercomputer System and Application Software |
Mitsuyasu Hanamura (RIKEN Next-Generation Supercomputer R&D Center) |
|
10:45 |
An Application of the NAREGI Grid Middleware to a Nationwide Joint-Use Environment for Computing |
Eisaku Sakane (CMC, Osaka University) |
|
11:15 |
Innovative Technologies for the SX-9 Architecture |
Takayuki Sasakura (NEC) |
|
11:45 |
X Software for the Next Generation Supercomputer |
Masashi Ikuta (NEC) |
|
12:15 |
Lunch |
|
|
1:15 |
Supercomputing in Aerospace CFD – Glance back the past and consider the future |
Kozo Fujii (Japan Aeorspace Exploration Agency) |
|
2:00 |
Some Lessons from the Earth Simulator Project |
Wataru Ohfuchi (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology / The Earth Simulator Center) |
|
2:45 |
Coffee Break |
|
|
3:15 |
Heterogeneous Parallelism in Aero-Acoustic Simulations using PACX-MPI |
Harald Klimach (HLRS, Stuttgart University) |
|
3:45 |
Prerequisites for the Productive Usage of Hybrid Systems |
Danny Sternkopf (NEC Europe) |
|
4:15 |
Closing/Remarks |
Toshiyuki Furui (NEC) |
37) ICPADS 2007
ICPADS 2007 (2007 International Conference on Parallel and Distributed Systems)は2007年12月5日~7日に台湾の新竹(Hsinchu)で開催された。会議録はIEEEから発行されている。
38) HiPC 2007
HiPC 2007 (14th IEEE International Conference on High Performance Computing)は2007年12月18日~21日にインドのGoaのthe Cidade de Goaで開催された。アメリカなどに多くいるインド出身のコンピュータ研究者がクリスマス休暇に帰省するチャンスを狙っているとのことである。基調講演5件が行われた。会議録はSpringerから出版されている。
|
Keynote:“The future is parallel but it may not be easy” |
Michael J. Flynn (Stanford大学他) |
|
Keynote:” Petaflop/s, Seriously” |
David Keyes (Columbia大学) |
|
Keynote:” High Performance Data Mining – Application for Discovery of Patterns in the Global Climate System” |
Vipin Kumar (Minnesota大学) |
|
Keynote:” The Transformation Hierarchy in the Era of Multi-Core” |
Yale Patt (Texas大学Austin) |
|
Keynote:” Web Search: bridging information retrieval and microeconomic modeling” |
Prabhakar Raghavan (Yahoo! Research) |
次回はDresdenで開催されたISC2007について述べる。
 |
 |
 |

