新HPCの歩み(第66回)-1982年(a)-
|
この年の動きは日本とアメリカで対照的である。日本では、富士通がFACOM VP-100/200を、日立がHITAC S-810を発表し、ベクトルコンピュータ全盛時代を予感させていた。他方アメリカでは超並列コンピュータ・ベンチャーがまさに「雨後の竹の子」のごとく登場しはじめた。後の高並列・超並列の時代を予感させる。 |
社会の動き
1982年(昭和57年)の社会の動きとしては、2/8ホテル・ニュージャパン火災、2/8ロンドン郊外のMuswell Hillの下水から多数の惨殺死体発見(犯人はDennis Nilsen)、2/9日航350便羽田沖墜落(いわゆる「逆噴射」事故)、3/29メキシコのエルチチョン火山が大噴火、4/1五百円硬貨発行、4/2フォークランド紛争勃発(6/14終結)、4/8家永教科書裁判、第二次訴訟、最高裁で破棄差戻、5/12ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世、ファティマ巡礼中に剣で襲われる、軽傷、5/28ローマ教皇がイギリス訪問、イングランド国教会と和解、6/4-6第8回サミット(ベルサイユ)、6/8橋本登美三郎、佐藤孝行に実刑判決、6/17イタリアAmbrosiano銀行総裁Roberto Calviの死体がロンドンの橋で発見される(バチカン銀行の闇)、6/22 IBM産業スパイ事件、アメリカにおいておとり捜査で日本人6人逮捕、6/23東北新幹線開業(大宮・盛岡間)、7/14レフチェンコ事件、7/23長崎大水害発生、7/26歴史教科書について中国政府から日本政府に抗議、8/2台風10号上陸、8/17フィリップス社が世界初のCDを製造、8/29三越「古代ペルシア秘宝展」出展物の大半がニセであることが判明、9/2国鉄のリニアモーターカーが世界初の有人浮上走行、9/14モナコのグレース・ケリー大公妃事故死、9/22岡田三越社長を解任、10/1西ドイツでコールが首相に、10/12鈴木善幸首相退陣表明、10/18竹久みち逮捕、10/29岡田三越前社長特別背任で逮捕、11/10ブレジネフ書記長死去、11/15上越新幹線開業(大宮・新潟間)、11/27中曽根康弘、首相に、12/4「E.T.」が日本公開、12/13戸塚ヨットスクール事件、12/23電電公社がテレホンカードの使える公衆電話1号機設置、など。
流行語・話題語としては、「逆噴射」「ネクラ」「ルンルン」「なぜだ!」(岡田三越社長)「おしりだって洗ってほしい」など。
チューリング賞は、計算複雑性への理解を高めさせた貢献に対してStephen A. Cook(Toronto大学)に授与された。授賞式は、1982年10月25日Dallasで開催されたACM年次総会において行われた。
エッカート・モークリー賞は、PDP-5やPDP-8などのミニコンピュータの設計に貢献したC. Gordon Bellに授与された。
ノーベル物理学賞は、相転移に関連した臨界現象に関する理論に対しKenneth G. Wilsonに授与された。Wilsonは格子ゲージシミュレーションの元祖であるが、そのことは授賞理由に入っていない。化学賞は、電子線結晶学の開発と核酸・タンパク質複合体の立体構造の研究に対しAaron Klugに授与された。生理学・医学賞は、プロスタグランジンおよびそれに関わる生物学的活性物質の発見に対し、Sune Bergström、Bengt I. Samuelsson、John Robert Vaneの3名に授与された。
わたくし事であるが、2/6に学内において自転車で転倒して左腕を骨折し、4週間のギプス生活を送った。活動はしていたが、左手を吊っていたので不自由であった。「小柳さん、その格好は何ですか」と私を笑った某社のSEは、その直後、バイクで自動車と衝突して大けがをした。「救急車の中で小柳さんの顔が浮かびました。」と言っていた。人のことを笑うものではないですね。筆者は12月に、筑波大学電子・情報工学系助教授にやっと昇任した。万年講師を覚悟していたが、39歳で脱出した。
日本政府関係の動き
1) 第五世代コンピュータプロジェクト
1982年4月、第五世代コンピュータプロジェクトが開始された。このプロジェクトは10年の予定であったが、当初の予定から1年延長され、1992年度まで11年間継続した。プロジェクトの委託先として、民間8社により財団法人新世代コンピュータ開発機構(ICOT)を設立した。電総研、NTT、コンピュータメーカ等から、若手研究者や技術者を集め、約30名でスタートした。92年度予算は4億円であった。電総研の渕一博は、6月に開設されたICOT研究所の所長となってこのプロジェクトを取り仕切った。
ICOTの会員には二種類あり、一口45万円の年会費を納め、ICOTの研究発表会に出席して情報提供を得られる一般賛助会員と、一定数口以上の会費を納め、ICOTへ研究員を出向させるとともに、理事として運営にも参加する特別賛助会員である。後者は、ICOTの設立準備段階から参加した富士通、日立、三菱電機、日本電気、沖電気、東芝、松下電器、シャープの8社であった。
技術目標を「知識情報処理を指向した新しいコンピュータ技術の研究開発」と定め、技術目標に含まれる多くの要素技術の実証・評価を行うために、並列推論型コンピュータのプロトタイプシステムの試作を行うことになる。
2) 電電公社
日本電信電話公社が1970年から開始していたプッシュホンを使った電話計算システムDIALSは、1982年10月の東京センターの廃止を最後に、サービスを終了した。
3) 航空宇宙技術研究所(M-380)
航空宇宙技術研究所(NAL、JAXAの前身の一つ)は、1982年頃(要確認)、それまで使っていたFACOM 230-75/230-75 APUをFACOM M-380に更新した。
日本の大学センター等
1) 利用料金の省令化問題
1982年ごろ、総務庁の行政監察において、「(大型計算機センターの)計算機の利用料金は、現行の負担金制度を廃して、費用省令により定義した上で実施すべきである」という指摘があり、7大型計算機センターは大騒ぎになった。当時の二三のセンターニュースに記事が載っている。
1984年にかけて、センター長会議や事務長会議などが何度も開かれ、当時の有馬朗人東京大学大型計算機センター長と丹羽義次京都大学大型計算機センター長を中心としてセンター側の意見をまとめ、負担金制度を死守した形となった。相手は、田保橋彬学術情報課長であった。何が論点であったが承知しないが、おそらく、料金を国庫収入とせよ、ということではなかったかと思う。東大大型計算機センターを例に取ると、東大の学内からは校費移管なのでセンターの収入になるが、学外の利用が国庫収入になると直接センターには入らなくなり、差別が生じることになる。科研費による計算機利用でも同様な問題が生じたことがある。
2) 東北大学(ACOS 1000)
東北大学大型計算機センターは、1982年1月ACOS1000の運用を開始した。
3) 東京大学(HITAC-280H×6)
東京大学大型計算機センターでは、1982年、HITAC M-280H(IAP付)を6台に更新した。メモリは192 MB。また、1983年10月に日立製作所製のHITAC S810の1号機を導入することを、1982年11月12日に決定した。
4) 東京学芸大学(M-150H)
1982年4月、東京学芸大学はデータステーションを設置し、M-150Hを設置。
5) 千葉大学(HITAC M-180)
千葉大学情報処理センターでは、HITAC M-170をM-180にアップグレードし、主メモリも2 MB増設して8 MBとした。
6) 神戸大学
1982年4月、総合情報処理センターを設置した。
7) 青山学院大学
1982年4月、開学した厚木キャンパスに情報科学研究センター厚木分室を開設し、ACOS 350および日本電気スーパーミニコンMS-140を導入した。
8) 九州産業大学(ACOS 700S)
九州産業大学情報処理センターは、1982年、ACOS 700Sを導入した。
9) 分子科学研究所(HITAC M-200H×2)
分子科学研究所電子計算機センターは、1982年4月に、M-200HとM-180それぞれ1台の構成から、M-200H 2台の構成に更新した。
10) 統計数理研究所(HITAC M-280H)
統計数理研究所は、HITAC M-180+8400を、1982年までにHITAC M-280Hに更新した。メモリは10 MBである。HITAC 10を中心としたハイブリッド計算機S-300は継続して利用されている。
日本の学界の動き
1) EVLIS
実験的なコンピュータとしては、安井裕(大阪大)らが並列LISPマシンEVLISを稼動させた。大阪大学EVLISマシンは、2012年3月6日、情報処理学会により2011年度情報処理技術遺産に認定されている。
2) FACOM α
1982年、富士通研究所はLISP言語の高速処理専用コンピュータ“α(Alpha)”を開発した。その後、1984年7月9日に商用LISPマシンFACOM αとして発表した。同社汎用コンピュータMシリーズ、またはスーパーミニコンS-3000シリーズをホストとして稼働する。
3) 筑波大学星野グループ
筆者はこのころからPAX-32が物理(スピン系や格子ゲージ理論)に使えるのではと直感し、星野研究室に入り浸っていた。筆者は知らなかったが、星野力先生が心配してくださり、筆者の上司(講座制ではないので、数値解析研究室の教授という意味で)の森正武教授に、「お宅の小柳という若手がうちに入りびたっていますが、いいんですか」と聞いたそうである。森教授は何でそんなことを心配するのか不思議に思ったと言っておられた。筑波大学は講座制を廃し、若手が自由に活動し、分野を越えて連携する環境を作ることを目指していたからである。
星野らはこのころPAX-128を計画していたが(完成は1983)、計算科学に使えるもっと本格的な並列コンピュータを製作するべく種々の可能性を探っていた。そのためにはやはり億単位の予算が必要であり、当時の科研費の枠を越えていた。星野氏によると(「情報処理」2002年2月号)、「つてを頼り、スポンサーを探して東京中を歩き回り、1日に4、5カ所も訪問した」とのことである。筆者も、1982年6月24日には星野、川合に随行して文部省(当時)に陳情に行った。筆者は元高エネルギー研管理部長の重藤学二氏や元筑波大研究協力部長の大山超氏などを省内で見つけ相談を持ちかけた。なかなか名案はなかった。
でもこのとき、ある文部省幹部が、「でも先生方、消費税が始まればそういうお金はどんどん出ますから」と、消費税をまるで打ち出の小槌のように話していたのが記憶に残っている。消費税は1989年4月から導入される。
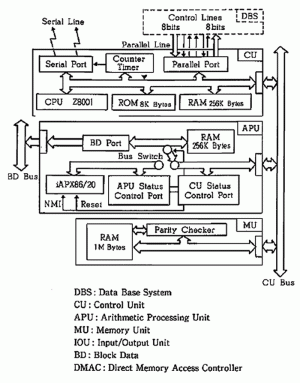 |
|
|
大阪大学 LINKS-1 |
|
4) LINKS-1
筆者がおもしろいと思うのは、大阪大学で大村皓一らが製作したコンピュータグラフィックス(レイトレーシング)用のマルチプロセッサLINKS-1である。10月末に試作完成した。各UC (Unit Computer)はRCもNCも同一のハードウェア構成であり、1台のRC(Root Computer)と最大256台のNC (Node Computer)が星状接続で疎結合されている。UCはCPUとしてZ8001が、数値プロセッサとしてiAPX86/20を搭載している。
レイトレーシングは光線ごとに自然な並列性をもっている。LINKS-1は単なる実験的なマシンではなく、多数の動画製作において実用的に用いられた。有名なのは、筑波科学博(1985)の富士通パビリオンで上映された全天周ドーム型3D映像である。筆者も見に行って感激した。筆者の記憶では画像制作のために、FACOM VPも合わせて使用したと思う。
1985年4月9日、PAXグループの星野力、川合敏雄、白川友則と筆者は、大阪に行き、このマシンが稼動している東洋リンクスという会社(当時)に大村氏を訪問し、マシンを見学したが、並列処理はもちろん、コンピュータも知らないアーチストでも使えるようにユーザ用ソフトが整備されていることに感心した。
5) HYPHEN C16
この頃九州大学の末吉らは、16個のZ80からなるHYPHEN C16を開発した。階層的なバス結合により接続している。
6) SALS
最小二乗法解析プログラムSALSの開発はほぼ終了していたが、1982年5月30日に中川徹・小柳義夫共著で『最小二乗法による実験データ解析 プログラムSALS』が東京大学出版会から出版された。この書は、その後版を重ねていたが、2018年9月に14刷りとして新装版が発行された。
7) 『プレイボーイ』誌
たまたまコピーを持っているが、週刊プレイボーイ誌の1982年2月23日号が「スーパー・コンピュータ最前線リポート」という5ページもの記事を載せている。「人間の脳細胞利用の生体コンピュータ、水槽に浸った超高速高性能コンピュータ」とか「SFを超えた!21世紀の巨大科学がいま実現」「光が3センチ進むまでに計算を終える(要するに10 GFlops)」「キミは脳にコンピュータを埋め込まれたいか?」など扇情的な文が並んでいる。驚くべことに、コンピュータの動作速度一覧などという表が出ている。業界紙も顔負けである。
この記事によると、1982年1月25日付の『日経コンピュータ』に「日立製作所はスーパーコンピュータの開発に成功。早ければ今夏にも発表する。機種名はHAP-1。」と書かれているのを見て、プレイボーイ誌の記者が日立製作所に問い合わせたが、日立製作所は「そんなコンピュータを開発した事実もなければ、今年度の当社の事業計画にも上がっていない。」と剣もほろろの対応だったそうだ。日立がS810を発表したのは8月30日であった。HAP-1は開発コード名であろう。
この年に出たアメリカのLax Reportは、アメリカの大学の研究者がスーパーコンピュータをふんだんに使える環境を作れと力説している。この年、日本では情報処理学会「数値解析研究会」が発足する。また、IBM産業スパイ事件が起こる。
(アイキャッチ画像:大阪大学 LINKS-1 出典:一般社団法人情報処理学会Webサイト「コンピュータ博物館」)
 |
 |
 |

