新HPCの歩み(第156回)-1998年(e)-
|
6月のTop500では、256ノードのSX-4が2台(東北大とカナダ)に登場した。CP-PACSも6位まで降下。LANLのグループは通信販売で買った自作のクラスタでTop500に登場した。HPC Asia 1998の基調講演でSDSCのSid Karinは、コンピュータ性能は今や連続スペクトルで、スーパーコンピュータも他のコンピュータと連続していると指摘した。 |
国際会議
1) HPCA 1998
第4回目となるHPCA 1998 (the Fourth International Symposium on High-Performance Computer Architecture)は、1998年1月31日~2月4日にネバダ州Las Vegasで開催された。主催はIEEE/CS TCCAである。委員長はKai Hwang, University of Hong Kong/USCである。電子版会議録はIEEEおよびIEEE/CSにある。
2) ISSCC 1998
第45回目となるISSCC 1998 (1998 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1998年2月5日~7日に、San Franciscoにおいて開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section, Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである(要確認)。組織委員長はJ. Trnka (IBM)、プログラム委員長はJohn D. Cressler (Auburn Univ)であった。3件の全体講演が行われた。
|
Challenges in semiconductor technology for multi-megabit network services |
M. Nakamura (Central Res. Lab., Hitachi Ltd.) |
|
GSM and beyond-the future of the access network |
J. Danneels (Alcatel Telecom) |
|
The Global Positioning System: challenges in bringing GPS to mainstream consumers |
Kanwar Chadha (SRF Technol. Inc.) |
IEEE Xploreに会議録が置かれている。
3) IPPS/SPDP 1998
IPPS 1998 (12th International Parallel Processing Symposium)とSPDP 1998 (9th Symposium on Parallel and Distributed Processing)の合同会議が、1998年3月30日~4月3日にフロリダ州Delta Orlando Resortで開催された。IEEE/CS TCPPの主催、ACM SIGARCHの共催である。共同組織委員長は、Viktor K. Prasanna (USC)とBehrooz Shirazi (U. of Texas at Arlington)、プログラム委員長はSartaj Sahni (U. of Florida)であった。18件のWorkshopsが開催された。会議録はIEEEから発行されている。
4) COOL Chips I
第1回のCOOL Chips I (IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)が、1998年4月15日、東京の機械振興会館で開催された。1989年から開催されているHOT CHIPSを意識して、省電力だからCOOLと名乗ったと思われるが、coolには「かっこいいという」意味もある。基調講演はなかったが、下記のパネル討論会が行われた。
|
Panel Session: “Future Trends in Microprocessors” |
Moderator: Toshiyasu L. Kunii (Hosei U.) |
5) HPCN Europe 1998
High-Performance Computing and Networking, International Conference and Exhibition, HPCN Europe 1998は、1998年4月21日~23日にオランダのAmsterdamで開催された。会議録はLecture Notes in Computer Science 1401としてSpringer 1998から出版されている。プログラムの一部として”HPF+ Workshop”があり、日本からHPF/JA仕様を発表予定であったが、会議録にはない(要確認)。HPCN Europe会議は2001年まで継続する。
6) Mannheim Supercomputer Seminar
Hans Meuer教授の主催するMannheim Supercomputer Seminar(2001年からはISC)は、第13回目を6月18から23日にMannheim市内で開催した。参加者は183名。基調講演はLarry Smarr (UIUC)であった。
7) Top500(世界)
11回目となる1998年6月のTop500が発表された。上位20位は以下の通り。性能はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。10件は新顔でほとんどT3Eである。クロックが約600 MHzのT3E1200も多数登場した。日本製のマシンでは、カナダの気象環境局と東北大学に128ノードのSX-4が登場した。なお、東北大学のSX-4は、前回の表では4台に分割してリストされていたものと思われる。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
1 |
SNL |
ASCI Red – Pentium Pro 200 MHz |
9152 |
1338.0 |
1830.4 |
|
2 |
- |
アメリカ政府某機関 |
T3E1200 – EV56 598 MHz |
1080 |
891.0 |
1296.0 |
|
3 |
2 |
アメリカ政府某機関 |
T3E900 – EV5 450 MHz |
1248 |
634.0 |
1123.2 |
|
4 |
(3) |
英国気象庁 |
T3E900 |
840 |
450.0 |
756.0 |
|
5 |
- |
NASA/Goddard Space Flight Center |
T3E – EV5 300 MHz |
1024 |
448.6 |
614.4 |
|
6 |
4 |
筑波大学計算物理学研究センター |
CP-PACS/2048 |
2048 |
368.2 |
614.4 |
|
7 |
- |
Max-Planck-Gesellschaft |
T3E – EV5 300 MHz |
784 |
342.0 |
470.4 |
|
8tie |
5 |
NERSC |
T3E900 |
512 |
321.0 |
460.8 |
|
8tie |
- |
Naval Oceanographic Office |
T3E900 |
512 |
321.0 |
460.8 |
|
8tie |
- |
Stuttgart大学(ドイツ) |
T3E900 |
512 |
321.0 |
460.8 |
|
11 |
- |
ドイツ気象庁 |
T3E900 |
400 |
251.0 |
360.0 |
|
12tie |
- |
Atmospheric Environmental Service(カナダ) |
SX-4/128M4 |
128 |
244.0 |
256.0 |
|
12tie |
- |
東北大学 |
SX-4/128H4 |
128 |
244.0 |
256.0 |
|
14 |
6 |
東京大学 |
SR2201/1024 |
1024 |
232.4 |
307.2 |
|
15 |
7 |
航空宇宙研究技術所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
167 |
229.0 |
281.3 |
|
16tie |
(9tie) |
FZJ(ドイツ) |
T3E – EV5 300 MHz |
512 |
222.0 |
307.2 |
|
16tie |
(9tie) |
Pittsburgh Supercomputing C. |
T3E – EV5 300 MHz |
512 |
222.0 |
307.2 |
|
16tie |
(9tie) |
SGI社(元Cray社) |
T3E – EV5 300 MHz |
512 |
222.0 |
307.2 |
|
19 |
8 |
ECMWF |
VPP700/116 |
116 |
213.0 |
255.2 |
|
20tie |
- |
アメリカ政府某機関 |
T3E1200 |
256 |
211.8 |
307.2 |
|
20tie |
- |
US Army HPC Research C. |
T3E1200 |
256 |
211.8 |
307.2 |
「世界の学界」のところで述べたように、LANL(Los Alamos国立研究所)の理論天文学グループは68台のAlpha EV56搭載のPCを通信販売で買い、Avalonという名のクラスタを自作し、今回のTop500で314位にランクした。Top500史上はじめてのLinuxクラスタであった。この年のGordon Bell賞の価格性能比部門で2位を獲得している。
8) Top500(日本)
日本国内設置のマシンで100位以内は以下の通り。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
6 |
4 |
筑波大学計算物理学研究センター |
CP-PACS/2048 |
2048 |
368.2 |
614.4 |
|
12tie |
- |
東北大学 |
SX-4/128H4 |
128 |
244.0 |
256.0 |
|
14 |
6 |
東京大学 |
SR2201/1024 |
1024 |
232.4 |
307.2 |
|
15 |
7 |
航空宇宙研究技術所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
167 |
229.0 |
281.3 |
|
31tie |
- |
核融合科学研究所 |
SX-4/64M2 |
64 |
122.0 |
128.0 |
|
31tie |
27 |
大阪大学 |
SX-4/64M2 |
64 |
122.0 |
128.0 |
|
37 |
28 |
九州大学 |
VPP700/56 |
56 |
110.0 |
123.2 |
|
38 |
29 |
高エネルギー物理学研究所 |
VPP500/80 |
80 |
109.0 |
128.0 |
|
41 |
30 |
日本原子力研究所 |
XP/S-MP 125 |
2502 |
103.5 |
125.1 |
|
55 |
(46) |
防災科学技術研究所 |
T3E |
160 |
69.3 |
96.0 |
|
56tie |
47tie |
国立環境研究所 |
SX-4/32 |
32 |
61.7 |
64.0 |
|
56tie |
47tie |
日本電気府中工場 |
SX-4/32 |
32 |
61.7 |
64.0 |
|
62tie |
54tie |
日本原子力研究所 |
VPP500/42 |
42 |
59.6 |
67.2 |
|
62tie |
54tie |
名古屋大学 |
VPP500/42 |
42 |
59.6 |
67.2 |
|
65tie |
56 |
RWCP(日本) |
SR2201/256 |
256 |
58.7 |
76.8 |
|
65tie |
- |
東京大学ヒトゲノムセンター |
SR2201/256 |
256 |
58.7 |
76.8 |
|
70tie |
58tie |
遺伝研 |
VPP500/40 |
40 |
56.9 |
64,0 |
|
70tie |
58tie |
東京大学物性研 |
VPP500/40 |
40 |
56.9 |
64,0 |
|
73tie |
(71tie) |
北陸先端科学技術大学院大学 |
T3E – EV5 300 MHz |
128 |
55.7 |
76.8 |
|
87 |
74 |
航空宇宙研究技術所(日本) |
SX-4/25 |
25 |
48.3 |
50.0 |
|
88 |
75 |
オングストローム技術組合(日本) |
VPP500/32 |
32 |
46.1 |
51,2 |
|
91 |
80 |
理化学研究所 |
VPP500/28 |
28 |
40.4 |
44.8 |
|
99 |
- |
京都大学 |
Origin2000 |
128 |
40.2 |
49.9 |
9) VECPAR’98
VECPAR’98 (Third International Conference on Vector and Parallel Processing)は、1998年6月21日~23日にポルトガルのPortoで開催された。会場は、Fundação Dr. António Cupertino de Mirandaという非営利団体の設備(美術館、名称の銀行家が設立)であった。発表のうち52件がSpringerのLNCS, volume 1573として出版されている。HPFのところで述べたように、第2回HPF User Group meeting HUG’98が併設して開催された。
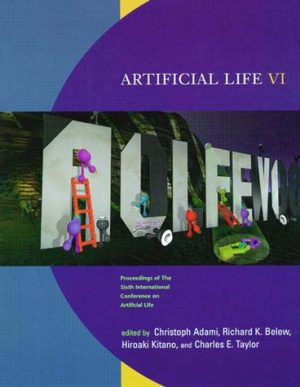 |
|
10) ALIFE VI
人工生命に関する国際会議ALIFE VI (the 6th International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems)は1998年6月26日~29日にLos Angelesで開催された。主催はUCLAである。有田隆也が報告を書いている。そこでも触れられているが、筆者の研究室の大学院生佐山弘樹は、Langtonの自己増殖ループに構造解消機構を組み込むことにより進化が早まることをシミュレーションにより示した。会議録はMIT Pressから発行されている。
11) ISCA 1998
第25回となるISCA 1998 (the 25th Annual International Symposium on Computer Architecture)は、1998年6月27日~7月1日にスペインのBarcelonaで開催された。主催はIEEE/CS TCCAとACM SIGARCHである。委員長はMateo Valero。電子版会議録は、ACM、IEEE、IEEE/CSに置かれている。ACMからは25周年を記念して記念誌(25 years of the international symposia on Computer architecture)が出版されている。これにはテーマごとの回想や、主要論文のリプリントが掲載されている。
12) ICS 1998
ACM SIGARCHが主催するICS (International Conference on Supercomputing)の第12回目は、オーストラリアのMelbourneで1998年7月13日~17日に開催された。共同組織委員長は Greg Egan(Monash大学)、Richard Brent(Oxford 大学)、Dennis Gannon(Indiana 大学、プログラム委員長)の3人である。論文投稿数は116編で、日本から相当数の投稿があったとのことである。ACMからプロシーディングスが発行されている。なお、ICS’98という別の会議が12月に台南で開催されている(後述)。
13) Lattice 98
第16回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 98)は1998年7月13日~18日に米国コロラド州Boulderで開催された。会議録は、Nuclear Physics B – Proceedings Supplements 73 (1999)として出版されている。
14) HPDC-7
第7回となるHPDC-7 (Seventh IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、1998年7月28日~31日にChicagoのDrake Hotelで開催された。2件の基調講演が行われた。
|
How Distributed Computing Changes Science |
Larry Smarr, NCSA |
|
Peering into the Future |
Richard F. Rashid, Microsoft |
会議録はIEEEから発行されている。
15) ICPP 1998
第27回目となるICPP 1998 (1998 International Conference on Parallel Processing)は、1998年8月10日~14日にミネソタ州Minneapolisで開催された。主催はIACC (The International Association for Computers and Communications)とThe Ohio State Universityである。電子版会議録はIEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。
16) HOT CHIPS 10
1989年から開催されている高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、第10回目のHOT CHIPS 10 (1998)を、1998年8月16日~18日、Stanford大学のMemorial Auditoriumで開催した。基調講演1 件とパネル討論会は下記の通り。
|
Keynote: ? |
Greg Papadopoulos (Sun Microsystems) |
|
Panel: Confronting the Microsoft Challenge |
Moderators: John H. Wharton |
17) IFIP Congress 1998
第15回目となるIFIP Congress 1998は、1998年8月31日~9月4日に、オーストリアのViennaとハンガリーのBudapestで開催された。会議録は衛星会議を含め7分割で出版されている。
Austrian Computer Societyから出版されたのは:
1. Global IT Security (SEC’98), IFIP World Computer Congress 1998
2. Fundamentals – Foundations of Computer Science, IFIP World Computer Congress 1998
3. Computers and Assistive Technology – ICCHP’98, IFIP World Computer Congress 1998
4. KnowRight ’98 – 2nd Int. Conference on Intellectual Property Rights and Free Flow of Information,
5. Teleteaching ’98 – Distance Learning, Training and Education, IFIP World Computer Congress 1998 Schriftenreihe der Österreichischen Computer Gesellschaftの巻として出版されたのは:
6. Telecooperation, IFIP World Computer Congress 1998, Vol 121 7. Informations Technology And Knowledge Systems, IFIP World Computer Congress 1998, Vol 122
ある。
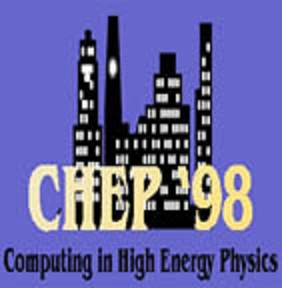 |
|
18) CHEP 1998
第10回目となるCHEP 1998 (International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics)は、1998年8月31日~9月4日に、ChicagoのHotel Inter-Continentalで開催された。この回から正式会議名に”Nuclear”が入っている。主催はANL (Argonne National Laboratory)である。ポスター写真はCHEP 2016のページから。
19) Euro-Par’98
4回目となるEuro-Par’98 Parallel Processing: 4th International Euro-Par Conferenceは、1998年9月1日~4日に英国Southamptonで開催された。会議録はSpringer社のLNCS 1470として出版されている。
20) EuroPVM-MPI’98
5回目となるEuroPVM-MPI’98(5th European PVM/MPI Users’ Group Meeting)は、1998年9月7日~9日にイギリスLiverpoolで開催された。Proceedingsは、‟Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface”のタイトルでSpringer社からLNCS 1947として出版されている。
21) HPC Asia 98
International Conference & Exhibition HPC ASIA 98 は、シンガポールのRaffles City Convention Centre において、1998年9月22日から25日まで開かれた。1997年4月末にSeoulで開かれた第2回に続く第3回である。2月17日~19日にMaui HPC CenterでSteering Committeeが開かれたが、筆者は学年末の仕事の関係で出席できなかった。会場はシンガポールの中心部に位置し、Westin Plaza Hotel および Westin Stamford Hotelと会議場とが一体の建物を構成している。今回は、スーパーコンピュータセンターのiHPCが主催し、かなりの力を入れていたことが感じられたが、参加費が750S$(約62000円)と高く、学生料金もなく、会場といい、食事といい、バンケットといい贅沢な会議であった。19カ国から276人に出席者があり、176編の論文が発表された。このほかに、パネリストや座長のために地元の研究者を100人ほど非登録で参加させたようである。
Keynote Address では、Dr. Sid Karin (Director of NPACI, San Diego) が “The Computing Continuum”と題して講演した。従来、スーパーコンピュータはそれ以外のコンピュータから隔絶した性能を持っていたが、いまやコンピュータの性能は連続スペクトラムで、そのうち比較的上位のものをスーパーコンピュータと呼んでいるに過ぎない、というようなことを述べた。
Industrial Keynote Address としては、R. E. Belluzzo (new CEO of SGI) が”Big Data: The Big Picture and the Long View” と題して講演した。組織委員会は事前に、会社の promotion talk ではなくscientific talkをするようにと念を押し、アブストラクトはそうなっていたが、「SGIの strategic direction は、graphic & media と、cc Numa & supercomputerとの融合である。その証拠が ASCI Blue Mountain である。」というような全くのセールストークで評判はよくなかった。
アジア全体の不景気ということもあって、展示は前回の半分ほどの面積である。出展数は前回よりかなり少ない。大きなブースを占めたのが国際的大企業で、SGI、IBM、Hewlett-Packard、Sun、Fujitsu、Compaq の6社であった。ソフトウェアでは、Portland Group、NAG、Pallas の3社。 地元の企業としてはTechSourceという会社が出展した。研究展示が5件、日本の航技研、Centre for Development of Advanced Computing (India)、Interactive Visual Simulation Laboratory (Singapore)、Sydney Vislab (Australia)、The Cooperative Research Centre for Advanced Computational Systems (Australia)であった。
会議の中で、北京の中国科学院の研究所がSR2201を所有し、日立と共同研究を行っているという発表があり、少々驚かされた。そういう時代になったのか。
バンケットは、オーチャードロード北西端の少し先の超高級ホテル「シャングリ・ラ」で、前回と同じく、中国・マレー・インドの3文化を代表するダンスがあった。
会議のあと、NUS(シンガポール国立大学)で非公式セミナーをやって何人かの人と討論したが、Rice大学から来ている人で、OpenMP から Message Passingコードを生成する研究をしている人がいた。OpenMPが並列性を記述しているのなら、このような道もあるとかねがね考えていたのでおもしろかった。
22) SC98
第10回目となるSC98はフロリダ州Orlandoで1998年11月9日から13日まで開催されたが、これについては別の章で記す。
23) ICPADS 1998
第6回となるICPADS 1998 (1998 International Conference on Parallel and Distributed Systems)は1998年12月14日~16日に台湾の台南で開催された。会議録はIEEE/CSから発行されている。
24) ICS’98
上記会議に引き続き、1998 International Computer Symposium (ICS’98)という会議が、台南の国立成功大学(National Cheng Kung University)で12月17日~19日に開催された。主催は台湾教育省、共催は台湾学術会議、台湾コンピュータ学会、IEEE台北セクション、ACM台湾チャプターであった。会議名が紛らわしい。
25) HiPC’98
5回目のHiPC’98 (International Conference on High Performance Computing)は、1998年12月17日~20日にインドのChennai(昔のMadras)で開催された。基調講演は以下の通り。
|
“Technologies for Building a Teraflop Windows NT Cluster” |
Andrew A. Chien (UCSB and NCSA) |
|
“Critical Issues in Design and Implementation of Interconnects for Workstation Clusters” |
Jose Duato (Universidad Politecnica de Valencia) |
|
“Custom-Fit Processors” |
Joseph A. Fisher (HP) |
|
“Recent Trends in Networking Including ATM and Its Traffic Management” |
Raj Jain (Ohio State University) |
|
“Teaching Parallel Algorithms Using the Cilk Multithreaded Programming Language” |
Charles E. Leiserson (MIT) |
|
“Data-centric Program Restructuring” |
Keshav Pingali (Cornell大学) |
次回はSC98である。第1回と同じOrlandoに戻ってきた。10年目ということで歴史展示が設けられた。SC98では、LANとして初めて1 Gbps ethernetを設置した。
 |
 |
 |

