新HPCの歩み(第215回)-2004年(f)-
|
グリッドの標準化が進み、実用化の段階に進んできた。折も折、GGFとは別に、企業を中心にEnterprise Grid Allianceが設立され驚いたが、両者の協議が行われ、2年後合併してOGFとなる。ホワイトハウスは「最先端コンピューティング再生タスクフォース」構成し、アメリカが技術の主導権を回復するための方策を議論した。「打倒!地球シミュレータ」 |
標準化
1) GGF10
第10回Global Grid Forum (GGF10)は、2004年3月9日~13日、ベルリンのHumbordt大学で開催された。グリッド協議会のサイトには会議概要や詳細な参加報告がある。大学での開催は初めてであった。参加者は約600人。GGFの中心は、専門家が種々の分野での標準を実際に決定するWG (Working Group)やRG (Research Group)であるが、多くのGGFでは一般参加者向けのプログラムが用意されている。今回はWGやRGの他に全体会議が開催されたが、tutorialはなかった。GGF議長は「OGSAをGGFのmain architectureとする」ことを明言し、すべてのWG/RGにOGSA対応を勧告した。下位のレイヤとして、新しいweb serviceの仕様WSRF (Web Service Resource Framework)がGlobusWorldで発表されたが、その後初めてのGGFであった。(HPCwire 2004/3/19)
4件のワークショップが開催された。
・The Future of Grid Data Environments
・Workflow in Grid Systems
・Case Studies on Grid Applications
・Grid Services for Particle and Nuclear Physics Applications – Experience and Requirements
多数のRGやWGがあるが、APME (Applications and Programming Models Environments)領域では特定の分野(天文、生命科学、原子核素粒子など)に特化したRGが増えている(RGが10、WGが2)。RGやWGの活動の詳細については「平成15年度グリッドコンピューティング標準化調査研究成果報告書」の付録に収録した。
日本からの参加者の活躍も目立つ。2002年にのべたように、GFSC (GGF Steering Group)には松岡聡(東工大)が、GFAC (Grid Forum Advisory Council)には村岡洋一(早稲田大)が加わっている。GROC (Grid Research Oversight Committee)では松岡聡(東工大)がリーダーを務め、広報活動のためのGMAC (GGF Market Awareness Committee Leadership Council)には関口智嗣や伊藤智が加わり、岸本光弘(富士通)がOGSA-WG Chairに、中田(日本電気)と伊藤智(産総研)がBusiness Grid RGのChairとSecretaryに、田中良夫(産総研)がGridRPC-WGのChairに、大石雅寿(天文台)がASTRO-RG Chair候補など。これまで、日本の国際標準化への参加は、いち早く情報をキャッチして製品に生かそうという意識が強く、標準策定そのものに寄与するという意識は強くなかった例が多かったが、Gridについては、標準化への積極的寄与がなされた。
GGFの創立者であり、GF以来約5年間GGFを引っ張ってきたCharlie Catlett(ANL)は会長を退任する予定であることを発表した。8月9日、GGFはMark Linesch (Hewlett-Packard)を次期GGF会長に選出したことを発表した(HPCwire 2004/8/9)。Lineschは、HPのAdaptive Enterprise Programの副会長としてグリッドや次世代分散コンピューティングアーキテクチャの開発を主導している。GGF12から会長の任に就く。
2) Enterprise Grid Alliance
2004年4月20日、NEC、富士通、インテルなど世界のIT大手19社は共同で、EGA (Enterprise Grid Alliance)を発足させた。EGAは企業向けグリッド・ソリューションの開発および推進に焦点をあてたオープンなコンソーシアムである。初期に重点的に取り組む分野として、「参照モデル」「プロビジョニング」「セキュリティ」「課金」などを想定している。EGAの発足時の理事会は、EMC、富士通・シーメンス・コンピュータズ、ヒューレット・パッカード、インテル、NEC、ネットワーク・アプライアンス、オラクル、サン・マイクロシステムズで構成。その他の設立会員として、AMD、Ascential Software、Cassatt、Citrix Systems、Data Synapse、Enigmatec、Force 10 Networks、Novell、Optena、Paremus、Topspinの各社が参画する。(GRIDtoday 2004/4/26)(CNET Japan 2004/4/23)
ただ、GGFから見ればもう一つのグリッド標準化関連の組織ができたことになり、ただ事ではない。GGFにも100社の企業を含む30カ国の数百の組織が参加しており、グリッド技術のビジネスへの適用も当然視野に入れている。4月26日付けのGRIDtodayによると、GGFは早速EGAと協議を開始し、企業とアカデミアのグリッド・コミュニティー全体にとって最善となるような協力体制を検討することとなった。
2004年7月5日、EGA日本運営委員会が設立されたことが発表された。これはアジア太平洋地域におけるグリッドの普及促進を目的とし、日本グリッド協議会を初めとするグリッド関連団体との連絡業務も視野に入れている。当初EGA日本運営委員会の運営は、EMCジャパン株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、日本ネットワーク・アプライアンス株式会社、日本電気株式会社、日本オラクル株式会社、サン・マイクロシステムズ株式会社の6社により行なわれる。日本グリッド協議会の関口智嗣会長は今回の発表を歓迎し、グリッド技術の研究開発への促進及び研究成果の普及とともに新たな応用と産業分野への導入を期待すると述べている。
2006年6月26日、GGFとEGAは合併してOGF (Open Grid Forum)を設立すると発表する。
3) GGF11
GGF11 (第11回Global Grid Forum)は、2004年6月6日~10日、ホノルルのHilton Hawaiian Resort Beachで開催された。参加者は600人以上。グリッド協議会のサイトに会議概要および詳細な参加報告がある。GGFの最も重要な部分であるRGやWGについてはこれらを参照してください。GGF10での計画では今回Enterprise Gridを主要テーマとする予定であったが、これは次回のGGF12に延期した。この延期はEGA設立と関係があったのではないかと推測される。会議でもEGAとの協力について議論された。(GRIDtoday 2004/6/14)
基調講演は以下の3件、招待講演は12件が行われた。9件のtutorialsが予定されていたが、3件はキャンセルされた。
|
Hiro Kishimoto and Ian Foster |
Open Grid Services Architecture: Status and Futures |
|
Jamie Clark |
|
|
Yoshio Tanaka |
Experiences with Production Research Grids |
Workshopは4件開催された。
|
Building Service based Grids Workshop |
|
Management of Services in Production Grid Workshop |
|
Social Factors, Humanities, Arts and Social Sciences: Old Challenges and New Disciplines for Grid Computing Workshop |
|
1st International Semantic Grid Symposium Workshop |
4) GGF12
GGF12(第12回Global Grid Forum)は、”Grids Deployed in the Enterprise”とのテーマの下に、2004年9月20日~23日、ベルギーのBrusselで開催され、約600人が参加した。全体会議はホテルで、通常セッションは大学で開催された。Mark Linesch新会長の下での初めてのGGFである。新会長は、前会長のCharlie Catlettが研究分野に重点を置いていたのに対し、ビジネスや企業のグリッドに重点を移す方針を示した(GRIDtoday 2004/10/11)。日本関係の人事では、関口智嗣がGFACに加わり、岸本光弘がGFSG (At-Large)に加わり、松岡聡がGFSG (APME AD)に再選された。グリッド協議会のサイトに総括報告および報告集がある。WGやRGについて詳細な報告が掲載されている。
テーマにあるように企業に於けるグリッドの活用事例に焦点が置かれ、基調講演やパネルも企業グリッドのテーマが目立った。4月に設立されたEGA (Enterprise Grid Alliance)とは協力体制が強調された。基調講演は3件行われた。
|
J. Mark Cates (Corporate Investment Banking) |
From the Glass House to the Grid: Have we come Full Circle? |
|
Girumehar Bhatia (Intel) |
Intel IT Grid History, Strategy and Challenges: Using Grid for Product Design |
|
Manuel C. Peitsch (Novartis) |
The GRIDs @ Pharma The Novartis Example |
全体会議の一環として、3件のパネルが開催された。
|
Automotive Panel |
Chiar: Mark Parsons, Panel: Heinz Mayer and Clemens-August Thole |
|
Role of Standards in Entergprise Grids |
Mark Linesch (GGF) and Bernd Kosch (EGA) |
|
Telecom Industry Panel |
Alessandro M. Aiello (Telecom Italia) |
Workshopは4件開催された。
|
Grid Application Programming Interfaces Workshop |
|
CDDLS of Grid Services Workshop |
|
Operational Security for the Grid Workshop |
|
Enterprise Grid Solutions and Deployments Workshop |
Tutorialも10件開催された。
5) グリッドコンピュ-ティング標準化調査研究委員会
2002年10月からINSTAC(日本規格協会情報技術標準化研究センター)において、グリッドコンピューティングについて標準化の調査研究が始まったことは述べたが、2004年3月、その第2年度が終了し、報告書「平成15年度グリッドコンピューティング標準化調査研究成果報告書」を公表した。世界に於けるグリッド標準化に関する詳細なレポートになっている。
最終年度である2004年度が始まったが、調査研究と言っても、いつまでも勉強ばかりしているわけにもいかないので、GGFがカバーしていない標準化への提言を行う方向で議論を進めた。各委員会の議論の概略は以下の通り。「グリッドガイドライン」をまとめ、成果物とする方向で議論がまとまった。
|
日付 |
主な議論 |
|
第1回5月19日 |
EGAとGGFの関係。INSTACは何を目指すか。 |
|
第2回6月23日 |
GGF11参加報告(OGSAが標準として確立した。実ビジネスでの実用が進んできている。EGAとは協調の方向)。Grid World 2004報告。Grid Today 04参加報告。 |
|
第3回7月26日 |
ビジネスグリッドプロジェクトの事例紹介。本委員会の方向性として、グリッドのガイドラインの作成を検討する。 |
|
第4回9月8日 |
ガイドラインについての議論。ユースケースと要件項目との対応。 |
|
第5回10月12日 |
ガイドラインについての議論。 |
|
第6回11月22日 |
グリッドガイドラインの検討 |
|
第7回12月21日 |
報告書の検討。グリッドシステムガイドラインの検討 |
|
第8回1月17日 |
報告書の検討 |
|
第9回2月16日 |
報告書まとめ |
6) Fortran 2003
新しいFortran言語の規格である通称Fortran 2003は、ISO/IEC 1539-1:2004として、2004年11月15日に公表された。Fortran 2003は、Fortran 95と比較して大幅に改訂されており、とくに、オブジェクト指向プログラミングを大幅に取り入れている。また、C言語との相互運用性の機能が付加され、FortranからのC手続きの呼び出し、C言語からのFortran手続きの呼び出し、両言語間のグローバル変数共有、またCと共有できるFortran要素を宣言するためのBIND(C)構文などが規定されている。新しい機能については、WG5の文書に詳細に記されている。2009年にJIS X 3001としてJIS化された。かつてはFortran遣いを自認していた筆者であるが、使ったことはない。この規格の次は、2010年10月15日に公表されるFortran 2008 (ISO/IEC 1539-1:2010)である。Fortran 2008ではco-arrayがサポートされる。規格が利用よりずっと先に行ってしまっている感じである。
7) 高性能Fortran推進協議会
2001年発足したHPF推進協議会は、2004年3月12日、京都大学学術情報メディアセンターにおいて、第2回総会を開催した。
8) OpenMP
The OpenMP Architecture Review Board (ARB)は、11月、OpenMP 2.5の仕様案を公表し、パブリックコメントを求めた。Version 2.5の目標はFortranとC/C++に関する仕様を1つの文書に統合し、不統一を防ぐことである。(HPCwire 2004/11/26) 決定版は2005年に公表される。
9) OpenMPI
Jack DongarraらTennessee大学、Indiana大学、LANLのグループによりOpenMPIが開発され、SC2004で公表された。これはLAM/MPI (Indiana), LA-MPI (LANL), FT-MPI (Tennessee), PACX-MPI(Stuttgart)などのプロジェクトの成果を総結集したMPI-2の実装である。この開発がいつから始まったかは不明である。
10) CentOS Project
CentOSはRed Hat Enterprise Linuxと機能的に互換性があることを目指したフリーなLinuxディストリビューションであり、最初の版は2004年5月14日にリリースされた。名前は、Community ENTerprise Operation Systemに由来する。2014年からRed Hat社が支援している。
11) Ubuntu
2004年10月20日、Debian GNU/Linuxから派生したOSとしてUbuntuがリリースされた。2005年7月8日、南アフリカ共和国の実業家Mark Shuttleworthと彼の設立したCanonical社は、Ubuntu財団を創設し、初期投資として$10Mを提供したと発表した。
アメリカ政府の動き
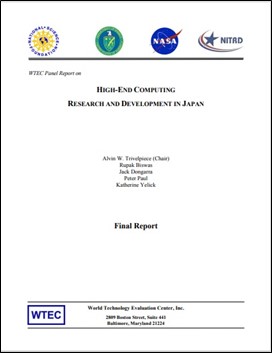 |
|
1) 米国訪日視察団
WTEC (World Technology Evaluation Center, Inc.)は世界の技術を評価する非営利組織であり、2001年にLoyola University (メリーランド州)内のセンターから組織変更し、独立組織に変わった。この組織が2004年3月29日~4月3日にアメリカ政府諸機関(NSF, NITRD, DOE, NASA)の支援のもと、“High-End Computing Research and Development in Japan”という調査活動のため、視察団を日本に派遣し下記の22の研究所、大学、企業等を訪問した。駐日アメリカ大使館がサポートしていた。
筆者のところには、3月30日(火)午後2時にJack Dongarra, Rupak Biswas, Peter Paulの3人が来訪した。訪日メンバーとしては、他に、Al Trivelpiece (chair)と Katherine Yelicがいたようである。報告書(写真)が公開されている。2003年のところに書いたように、アメリカ科学アカデミー(NAS)の訪日調査が2004年3月23日~26日に行われたが、別の活動である。Dongarra教授は両方に参加していたので、継続して日本に滞在していたと記憶している。
|
研究機関: 地球シミュレータセンター 地球フロンティア研究システム 高エネルギー加速器研究機構(KEK)計算研究センター 超高速コンピュータ網形成プロジェクト(NAREGI) 国立核融合研究所 理論・シミュレーション研究センター 理化学研究所 情報基盤センター 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 情報技術センター 原子力研究所 計算科学技術推進センター 高度情報科学技術研究機構(RIST) 産業技術総合研究所 グリッド技術研究センター |
|
大学: 東京大学 理学部情報科学科 東京大学 工学部矢川研 東京工業大学 GSICセンター 筑波大学 計算物理学研究センター |
|
企業: 富士通 日立製作所 IBM-Japan NEC Sony Computer Entertainment社 |
|
官界: 総合科学技術会議、 文部科学省、 経済産業省 |
 |
|
2) HECRTF(最先端コンピューティング再生タスクフォース)
既に述べたように、2003年3月、ホワイトハウスのNSTC(National Science and Technology Council、国家科学技術会議、1993年11月発足)は、特別プロジェクトとしてHECRTF(High End Computing Revitalization Task Force、最先端コンピューティング再生タスクフォース)を設立し、アメリカが今後科学技術でのリーダーシップを確保するための計画“Federal Plan for High-End Computing”を作成した。2004年5月に計画の策定が完了し、報告書“Report of the High-End Computing Revitalization Task Force”が5月10日付けで出版された(写真はその表紙)。これに基づき“Department of Energy High-End Computing Rivitalization Act of 2004”が2004年11月に成立した。(野村稔著『米国政府の高性能コンピューティングへの取り組み』、「科学技術動向」2005年2月号参照)
それによると科学技術の多様な分野における目標達成には現在のリソースの100倍~1000倍の能力が必要であり、今後のハードウェア、ソフトウェアにおけるコア技術の研究開発、科学・工学コミュニティーでいつでも利用可能なHECのcapability(最高性能)とcapacity(計算量)の向上、ユーザ要求を満たすHECシステムの政府機関での効率的な調達の戦略に関する今後15年のロードマップを示している。そのためには年度当たり$900Mの予算が必要である。研究開発については、科学技術におけるニーズと商用システムの性能とに乖離があり、量産されるプロセッサではHEC向けのプログラム開発が非常に難しくなっていることを指摘している。このために以下の3つの勧告を行っている。
|
a) 最先端の研究開発 このタスクフォースの第一の目的は最先端コンピュータシステムの有効な利用を制限する主要な技術障壁を克服するために10年~15年の継続する研究開発プログラムを整備することである。今日、貧弱な信頼性、価格の上昇、ソフトウェア開発の機器、アーキテクチャ上の問題(たとえばプロセッサとメモリに不均衡など)は、すべて科学技術や国家安全保障の性能を制限するものとなっている。これらの障壁を解決するためにHECRTF計画は基礎研究、高度な開発、プロトタイプの開発、検証と評価などを含む総括的な戦略を含んでいる。この計画は、ハードウェア、ソフトウェア、システムの開発の技術的ロードマップを含み、現行のプログラムと提案するプログラムとの比較を行っている。これにより、今後何十年にもわたる世界一の地位が可能にする、最先端コンピューティングや科学技術の分野で確実なリーダーシップをもたらすのである。 |
|
b)最先端資源 国家的な使命に最先端のコンピューティング資源を提供するには3つの課題がある。まず、科学技術的な使命をもついくつかの機関は最先端コンピュータへのアクセスを欠いている。次に、ある分野では最先端コンピューティングは研究開発に非常に有効に働いているが、資源が目一杯である。最後に、現在の資源は多くの重要な大規模問題を解くには不十分である。これらの3つの問題に対処するため、機関間の協力戦略を打ち出す。 |
|
c) 調達 HECRTF計画は、連邦の調達プロセスの効率を改良するためにいくつかのパイロットプロジェクトを提案する。これは政府にも産業界にも利益となるであろう。この中には、ベンチマーク、トータルコスト(導入から維持まで)のモデル、機関間での共同調達、調達に決定的に重要な問題を可視化することなどが含まれる。 |
この計画は現行のプログラムとは違う新しいアプローチを提案している。現在のプログラムでは、最先端コンピューティングにおいてある程度の漸進的な進歩はできるかも知れないが、現在の厳しい[日本との]競争でアメリカのリーダーシップを確保することもできないし、最先端コンピューティングへの加速する要求とペースを合わせることもできない。
3) High-End Crusaderの批判
2月頃からHPCwireにHigh-End Crusader(「最先端計算十字軍」というような意味であろうか?)と名乗る匿名のコメンテータがしばしば登場して論陣を張っていた。3月にはHECRTFは死んだとして、PC-Cluster や Blue Gene で高速に処理できるような問題だけではないと主張し、SMPクラスタではペタフロップスはできない、LINPACK がすべてであるかのような議論は人を誤らせると批判していた。(HPCwire 2004/3/12)
High-End CrusaderはHPCwire上の長文の記事(HPCwire 2004/6/4)で、このHECRTFのPlanに対しても鋭い批判をあびせた。この著者は、この報告書がHECの重要性を述べたことを高く評価しながらも、計画に不明瞭な点が多く、緊急性の認識に欠けており、予算の目途が立っていないと述べている。そして、このHECRTF計画と、以前に出た二つのレポート、”Report on High Performance Computing for the National Security Community”(IHEC Report, July 2002, U.S. Department of Defense)とと “Workshop on: The Roadmap for the Revitalization of High-End Computing“(June 16-18, 2003, Computing Research Association)とを比較している。確かにHECRTF計画は、HECの研究開発に連邦政府の予算を要求し、先進システムの必要性を論証し、「持たざるもの」にも最先端コンピューティングの恩恵を及ぼすこと、合理的なベンチマークの必要を述べ、調達の改善を示唆している。これは高く評価される。しかし1990年代初頭にCOTS(汎用製品)に基づく先進的コンピュータを推進した[ASCIなど]ことにより、アーキテクチャの研究が廃れてしまったことを指摘している。COTSによる疎結合のシステムはスケールせず、真に大規模な問題を取り扱えないと、high-end computingのためのより専用的なアーキテクチャを推奨している。
High-End Crusaderは、2005年2月の記事(HPCwire 2005/2/4)において、3つの抵抗勢力を指摘している。「DOEおよびDODの旧守派」「ベンダの一部(社名は挙げなかった)」「議会予算局(HECRTFを骨抜きにしようとした)」である。議会予算局がHECRTFを批判した話は承知していないが、1993年(d)に書いたように、議会予算局は保守的観点からHPCCを批判している。
この論者は、Cray社の関係者(Burton Smith?)であろうか。
4) High-End Computing Revitalization Act of 2004
第108回アメリカ連邦議会には、revitalizationを法案名に掲げた法案が少なくとも3件審議された(H.R.4516, S. 2176, H.R. 4218)(H.R.=House of Representatives 下院、S.=Senate 上院)。
このうち、“H.R.4516 – Department of Energy High-End Computing Revitalization Act of 2004” 「2004年エネルギー省高性能コンピューティング再生法」は、2004年11月17日に可決され、11月30日Bush大統領の署名をもって法律となった(CRA 2004/11/17)。この法律はエネルギー小委員会の議長Judy Biggert (R-IL)が提案し、下院は7月に採択していた。上院は科学委員会との交渉結果を反映させて修正し、10月に全会一致で可決した。今回、修正案が下院で再可決され、署名のため大統領に送られたものである。
この法案は、スーパーコンピューティングのためにDOEに対し2005年度(2004年10月~2005年9月)に$50M、2006年度に$55M、2007年度に$60Mと合計$165Mの資金の支出権限を認めている。DOEはこの資金をつかって、HECの研究、スーパーコンピュータの開発・購入、リーダーシップ・システム関連施設の設置と運営、ソフトウェアの開発・保存センターの設立、民間への技術移転などを行う。(CNET Japan 2004/11/19)(HPCwire 2004/11/19)
連邦下院には、2004年4月27日に同種の別の法案“H.R. 4218, the High-Performance Computing Revitalization Act of 2004”が提出され、科学委員会で審議されて可決されたが、上院に送られたままのようである。6月22日には、IBM社のDeep Computing 担当副社長のDavid Turekが上院の「エネルギーと天然資源委員会」で、スーパーコンピューティングの国家的重要性について陳述した。(HPCwire 2004/7/9)
連邦上院に3月8日提出された“S. 2176: High-End Computing Revitalization Act of 2004”は、エネルギー省(DOE)に対し、Ultrascale Scientific Computing Capabilityの設立を許可し、エネルギー省長官に対して、今後5年間にわたって毎年最低$100Mの予算を研究施設の設立のために使うことを許可し、また今後5年間、最先端ソフトウェア開発センターのために毎年最低$10Mの予算を使うことを許可するものである。テネシー州選出上院議員Lamar Alexander(共和党)は、3月にWashington DCで開催されたフォーラムで、この法案の共同提出者になると発表した。(HPCwire 2004/3/19) その後この法案自体は廃案となったようである。
5) The Future of Supercomputing
米国のNational AcademiesのNRC (National Research Council)はCommittee on the Future of Supercomputingを組織し、提言書“Getting Up To Speed: The Future of Supercomputing”を11月にNational Academy Press社から出版した。編集者は Susan L. Graham、Marc Snir、Cynthia A. Pattersonである。その中で、政府機関はスーパーコンピュータの発展の加速と国内の強力なメーカ育成に第一責任を持つべきであり、アメリカがスーパーコンピュータのリーダーの地位を保つためには行動が必要であると述べている。
6) First Annual HPC User Conference
2004年7月13日、Washington D.C.のCapital Hilton Hotelにおいて表記の会議“The First Annual HPC User Conference — High Performance Computing: Supercharging U.S. Innovation and Competitiveness”が開かれた。共同主催者は、the Council on Competitiveness、DARPAおよび DOEの National Nuclear Security Administration および Office of Scienceであった。The Council on Competitivenessはレーガン政権下の1986年にできたアメリカの非営利団体である。200人ほどが参加した。(HPCwire 2004/7/16)
次回は、アメリカ政府各省庁の動きである。DOEは大幅な予算増で最先端コンピューティングとそれによる科学研究に取り組む。NASAはColumbiaを建設し、NSFのTeraGridが発足する。
 |
 |
 |

