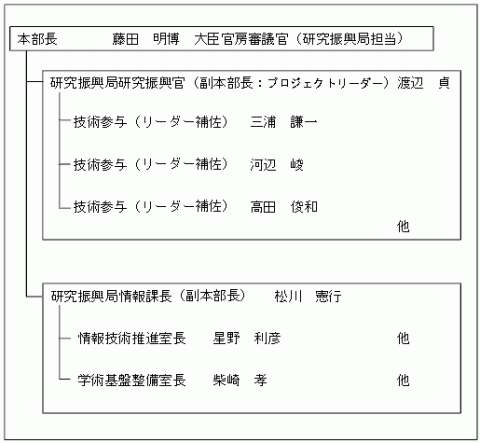新HPCの歩み(第235回)-2006年(a)-
| 理化学研究所は次世代スーパーコンピュータ開発実施本部を設置し、ターゲットアプリの検討とともに、「概念構築に関する共同研究」を募集したところ、16の組織から提案があった。それを基に概念設計が進められる。 |
社会の動き
2006年(平成18年)の社会の動きとしては、1/1三菱東京UFJ銀行発足、1/10ソウル大学調査委員会が、黄禹錫教授の研究チームが世界で初めてヒトクローン胚からES細胞を作製したと発表した論文について捏造であると断定、1/12メッカ巡礼のイスラム教徒が将棋倒し、1/16ライブドアを証券取引法違反容疑で強制捜査、1/18東京証券取引所システム故障で一時取引停止、1/19 NASAが冥王星など太陽系外縁天体の探査機New Horizonsを打ち上げ(2015年冥王星を観測、2019年太陽系外縁を通過)、1/20米国産牛肉、日本再び全面禁輸、1/21首都圏平野部で大雪、1/23堀江貴文ら、証券取引法違反容疑で逮捕、1/23日本郵政株式会社発足、2/2神戸ポートライナーが神戸空港まで延伸、2/5在ベイルートデンマーク大使館をムハンマド風刺画に抗議して放火、2/10トリノ冬季オリンピック開幕(2/23荒川静香、イナバウアーで金メダル)、2/10日本で預金者保護法施行、2/11表参道ヒルズがオープン、2/16神戸空港開港、2/16堀江メール問題、2/22初めての「竹島の日」、3/3アメリカ合衆国でWBC (World Baseball Classic)が開幕(3/21日本優勝)、3/16北九州空港、開港、3/21アメリカでTwitter始まる、3/27近鉄けいはんな線開業、ゆりかもめが豊洲まで延伸、3/31南公園にあった神戸ポートピアランド閉園、4/1ワンセグ放送開始、4/7小沢一郎、民主党代表に、4/26構造計算書偽造問題(姉歯事件)で8名逮捕、5/12キトラ古墳の白虎が公開される、5/24映画『不都合な真実』アメリカ公開、5/25エンロン社の不正会計事件で、元会長らに有罪判決、5/27インドネシアのジョグジャカルタで地震発生(M6.3)、6/3セルビア独立宣言、6/3シンドラー社製エレベータ誤作動、高校生死亡、6/5村上世彰が証券取引法違反で逮捕、6/7平成電電、破産手続き開始、事業は日本テレコムに譲渡(6/16)、6/9 FIFA World Cupドイツ大会開幕、6/20イラクからの自衛隊撤収方針表明、7/4 NASAがSpace Shuttle “Discovery”を1年ぶりに打ち上げる、7/5北朝鮮がテポドン2号など7発の弾道ミサイルを発射、安保理緊急協議、14日非難決議、7/9ムンバイ列車爆破事件、7/15-17第32回主要国首脳会議サンクトペテルブルクで開催、7/15-24「平成18年7月豪雨」、7/17インド洋地震・津波(M7.7)、7/31ふじみ野市の市民プールで、女児が流水プールの吸水口に吸い込まれ死亡、8/7米国産牛肉再開第一便到着、8/14首都圏停電(クレーン船のブームが送電線に接触)、8/15小泉純一郎総理大臣靖国神社参拝、8/24冥王星が準惑星に格下げ、9/6秋篠宮家に悠仁(ひさひと)親王誕生、9/15竹中平蔵議員辞職を表明、9/17台風13号が九州に上陸し延岡市などで竜巻発生、9/19タイ軍事クーデター、9/26安倍晋三が内閣総理大臣に指名される、第1次安倍内閣、9/28タイでスワンナプーム国際空港開港、10/1阪急と阪神が経営統合、10/9北朝鮮が初めての核実験、10/23福島県の佐藤栄佐久前知事を逮捕、11/7アメリカの中間選挙で、民主党が上下両院で多数派を奪還、11/15 千島列島沖地震(M7.9)、12/9米映画『硫黄島からの手紙』日本公開、12/30フセイン元イラク大統領死刑執行、など。
 |
|
流行語・話題語としては、「イナバウアー」「品格」「エロカッコイイ」「格差社会」「耐震偽装」「ハンカチ王子」「メタボ」「お金儲けは悪いことですか?」「千の風になって」など。(写真は神戸ポートアイランドにあるO2HIMAWARIより。背後は神戸市民農園。遠景のビルは港湾技術研修センター) 1月に打ち上げられたNew Horizonsは2015年には冥王星を観測し、その後は太陽系外縁天体を観測し、太陽系外に向かった(冥王星は打ち上げ7か月後に「準惑星」に格下げになった)。制御用と観測用に、それぞれMIPSのR3000アーキテクチャの耐放射線マイクロプロセッサMongoose-V(12 MHz、Synova製)を正副2基(合計4基)搭載している。過酷な環境の中で20年近く動いていることは驚異である。もちろん通信距離も驚異的だ。2019年1月1日には、カイパーベルト天体のUltima Thule(2019年11月6日、IAUはArrokothと命名)に接近し撮影した。地球への通信速度は1-2 kb/sなので、観測データをダウンロードするためには20ケ月掛かると予想されたが、2022年7月現在、まだ10%のデータが残っていた(Wikipedia)。2030年代まで活動を続けることができ、新たな観測対象をすばる望遠鏡で探している。
チューリング賞は、最適化コンパイラ技術の理論と実践への先駆的な貢献に対してFrances Elizabeth Allen(IBM)に授与された。女性として初めての受賞である。なお受賞が発表されたのは、2007年2月下旬である。(HPCwire 2007/2/23)
エッカート・モークリー賞は、PrincetonのIASの開発に関わった後、IBM社において、IBM 7030やHarvestの開発に関わり、キャッシュ、メモリ、信頼性、パイプライン処理、分岐予測などコンピュータアーキテクチャに関する先駆的な研究を行ったJames H. Pomereneに授与された。
ノーベル物理学賞は、宇宙マイクロは背景放射の発見とその非等方性の発見に対し、John C. MatherとGeorge F. Smootに授与された。化学賞は、真核生物における転写の研究に対しRoger David Kornbergに授与された。生理学・医学賞は、RNA干渉-二重鎖RNAによる遺伝子サイレンシング-の発見に対し、Andrew FireとCraig Melloに授与された。
私事では2006年3月末をもって東大を定年退職し、4月からは、創設に協力していた工学院大学情報学部の初代学部長になった。3月15日には東大で最終講義「素粒子から情報まで」を行った。4月からは日本応用数理学会会長に任命された。日本数学会との相互交流企画で、数学会年会(中央大学)において招待講演「スーパーコンピュータの歩み」を行った。関係者のご尽力により、4月18日、文部科学省より「科学技術計算の高度化のための超並列計算の研究」が、我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究・開発であると認められ、文部科学大臣表彰「科学技術賞(研究部門)」を受賞した。これも私事であるが、1998年から教皇庁文化評議会の顧問を務めていて、この年11月26日~30日にインドネシアのバリ島で汎アジア会議が開かれ参加した。筆者は”The Challenge of Sects and Indifference to the Faith”という題をいただいたので、オウム真理教について講演し、オウムに向けられている批判は、既成宗教であるキリスト教にも当てはまると論じた。「バチカンでは聞けない話だ」と言われたので評価されたと思っているが、果たして?
次世代スーパーコンピュータ開発
1) 開発体制構築
1月4日、文部科学省に次世代スーパーコンピュータ整備推進本部が設置され、プロジェクトリーダー(研究振興官)として渡辺貞(日本電気支配人)が着任した。体制は以下の通り。なお渡辺貞プロジェクトリーダーは2年の任期であったが、1年も経たない8月に理研に移った。
| 文部科学省 スーパーコンピュータ整備推進本部 | |
|
|
|
|
平成18年4月14日現在 |
 |
|
また、理化学研究所は、1月1日 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部を設置した。丸の内の明治生命館6階に丸の内拠点を設けた。組織は図の通り。写真はWikipediaから。
次世代スーパーコンピューティング技術は、閣議決定した第3期科学技術基本計画において「国家基幹技術」と位置づけられ、文科省が2006年度(平成18年度)から「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用プロジェクト」を開始し、理研が開発主体となった。4月、横川三津夫が産総研グリッド研究センター副センター長からハードウェア開発チームチームリーダーとして移籍した。
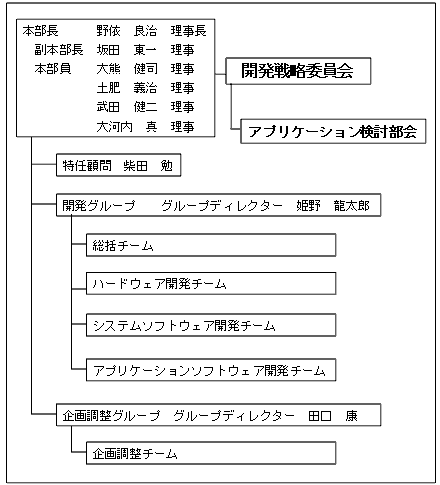 |
| 平成18年4月14日現在 |
次世代スーパーコンピュータ開発戦略委員会の構成は以下の通り。特記ない所属は理化学研究所。
| 委員長 坂田 東一 | 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 副本部長 |
| 副委員長 茅 幸二 | 和光研究所長 |
| 平尾 公彦 | 東京大学工学部 工学部長 教授 |
| 延與 秀人 | 延與放射線研究室 主任研究員 |
| 米倉 実 | 経営企画部 部長 |
| 渡辺 貞 | 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 プロジェクト・リーダー |
| 姫野 龍太郎 | 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 開発グループ グループディレクター |
| 田口 康 | 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 企画調整グループ グループディレクター |
2006年には以下のように開催された。
| 日付 | 議事内容 | |
| 第1回 | 2006年1月24日 | 1.次世代スーパーコンピュータ開発戦略委員会について
2.アプリケーション検討部会の設置について |
| 第2回 | 2006年4月10日 | 1.ターゲット・アプリケーションの優先順位付けについて
2.ハードウェアの検討状況について (1)今後の開発手順について (2)ハードウェア研究会の開催状況 |
| 第3回 | 2006年7月11日 | 1.ターゲット・アプリケーションによる性能評価について
2.システム開発の進捗状況と今後の進め方 3.立地検討部会の設置について |
| 第4回 | 2006年9月1日 | 1.システム開発: 進捗状況と今後の進め方
2.総合科学技術会議への対応について 3.立地検討部会の開催状況について 4.19年度予算 概算要求について |
| 第5回 | 2006年12月27日 | 1.総合科学技術会議フォローアップと結果
2.概念設計中間報告結果について(内容と今後の予定) 3.COEの構築について 4.立地について 5.平成19年度予算について |
文部科学省の整備推進本部と理研の開発実施本部との共同で、日本国内のスーパーコンピュータの設置状況、利用状況、将来計画などについて調査を行い、「スーパーコンピュータ調査報告書」(2006年6月6日)を発行した。
2006年度国家予算案は、2006年3月27日、与党の賛成多数により、参議院議員本会議で可決成立した。5月17日に公布された「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の新法が7月1日施行された。理研が次世代スーパーコンピュータの設置者と規定され、理研は設置者として正式に開発・建設・維持管理・共用の業務を行うこととなった。立地検討部会を設置し検討を開始した(後述)。
2) ターゲット・アプリケーション・ソフトウェア候補の選定
2005年の総合科学技術会議の評価検討会において、筆者らが「汎用だからどんなアプリにも対応できる、という考えは間違っている」と主張したこともあり、システム開発のターゲットとなる具体的なアプリケーションの選定が必要になった。2004年10月ごろから、文部科学省では大学、研究機関、産業界などからのヒアリングを精力的に行った。
理化学研究所次世代スーパーコンピュータ開発実施本部では、2006年1月24日の第1回開発戦略委員会において、次世代スーパーコンピュータ開発戦略委員会の下に「アプリケーション検討部会」を設置した。メンバーは以下の通り。
| 氏 名 | 所 属 | |
| (部会長)平尾公彦 | 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 教授 | |
| (副部会長)中村春木 | 大阪大学 蛋白質研究所 教授 | |
| 宇川 彰 | 筑波大学 計算科学研究センター センター長、数理物質科学研究科 教授 | |
| 梅谷 浩之 | 日本自動車工業会 | |
| 大峯 巌 | 名古屋大学大学院理学研究科 教授 | |
| 加藤 千幸 | 東京大学生産技術研究所計算科学技術連携研究センター、センター長 教授 | |
| 川田 裕 | 三菱重工業株式会社 高砂研究所 技監・主幹研究員 | |
| 北浦 和夫 | 産業技術総合研究所 計算科学研究部門 総括研究員 | |
| 木寺 詔紀 | 横浜市立大学 大学院総合理学研究科 教授 | |
| 阪口 秀 | 地球内部変動研究センター地殻ダイナミクス研究グループグループリーダー | |
| 住 明正 | 東京大学気候システム研究センター 教授 | |
| 泰地真弘人 | 理化学研究所 ゲノム科学総合研究センター 高速分子シミュレーション研究チーム チームリーダー | |
| 高田 彰二 | 神戸大学理学部 助教授 | |
| 寺倉 清之 | 北海道大学 創成科学共同研究機構 特任教授 | |
| 土井 正男 | 東京大学大学院 工学系研究科 教授 | |
| 中村振一郎 | 株式会社三菱化学科学技術研究センター 計算科学研究所 所長 | |
| 西島 和三 | 持田製薬 開発本部 主事 | |
| 平田 文男 | 自然科学研究機構分子化学研究所 教授 | |
| 平山 俊雄 | 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター 次長 | |
| 姫野龍太郎 | 理化学研究所 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 開発グループ グループディレクター |
|
| 樋渡 保秋 | 金沢大学大学院自然科学研究科 教授 | |
| 藤井 孝蔵 | 宇宙航空研究開発機構情報・計算工学センター センター長 | |
| 古村 孝志 | 東京大学地震研究所 助教授 | |
| 牧野内昭武 | 理化学研究所 ものつくり情報技術統合化研究プログラム プログラムディレクター |
|
| 松本洋一郎 | 東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 教授 | |
| 觀山 正見 | 自然科学研究機構国立天文台 教授・副台長 | |
| 山形 俊男 | 地球フロンティア研究センター気候変動予測研究プログラム プログラムディレクター | |
| オブザーバー | ||
| 渡辺 貞 | 文部科学省スーパーコンピュータ整備推進本部副本部長・プロジェクトリーダー | |
| 高田 俊和 | 文部科学省スーパーコンピュータ整備推進本部リーダー補佐 | |
検討の経緯は下記の通り。
| 日付 | 会議 | 議事内容 |
| 1月24日 | 第1回開発戦略委員会 | アプリケーション検討部会の設置 |
| 1月25日 | 第1回アプリケーション検討部会 | 設置趣旨の確認及びと今後の活動の審議 |
| この間 | [各委員によるターゲット・アプリケーション候補の調査及び提案] | |
| 3月 1日 | 第2回アプリケーション検討部会 | 提案アプリケーション(107種)のリスト及び優先順位付けの方法の審議、分野別会合の開催 |
| この間 | [各委員による提案アプリケーションの評価] | |
| 3月30日 | 第3回アプリケーション検討部会 | 提案アプリケーションの評価結果のとりまとめ、分野別の審議、優先順位の決定 |
| 4月10日 | 第2回開発戦略委員会 | ターゲット・アプリケーション候補の選定 |
| 5月 | 計算機仕様検討チームとターゲットアプリケーション検討チームとの第1回合同検討会 | |
| 6月 | 計算機仕様検討チームとターゲットアプリケーション検討チームとの第2回合同検討会 | |
| 7月 | 計算機仕様検討チームとターゲットアプリケーション検討チームとの第3回合同検討会 | |
| 7月5日 | 第4回アプリケーション検討部会 | BMTコードの開発について、BMTコードによる性能評価について、ペタフロップス超BMTコードの作成について |
| 12月7日 | 第5回アプリケーション検討部会 | 概念設計進捗状況およびBMT結果の中間報告について、運用検討案、グランドチャレンジおよびCOE構築に向けて |
| 2007年
1月23日 |
第6回アプリケーション検討部会 | 概念設計中間報告に関する評価結果案、システム概要、BMTによる性能評価 |
| 3月1日 | 第7回アプリケーション検討部会 | ターゲット・アプリケーションについて、システム構成案、COE形成について |
検討部会では、5つの分野から候補アプリ21種と次候補4種を定めた。ライフ分野から候補6+次候補1、物理分野から候補2、ナノ分野から候補6+次候補1、地球科学分野から候補3+次候補1、工学分野から候補4+次候補1である。今後、これらのアプリケーション・ソフトウェアの所有者等からソースコード等のデータを収集し、分析を行った上で、次世代スーパーコンピュータのアーキテクチャを評価するためのベンチマークテストプログラムを作成する。2007年4月9日に、選定した21本のアプリケーションプログラムを公表する。
3) グランドチャレンジアプリケーション研究
2つのグランドチャレンジアプリケーション(正式には「次世代スーパーコンピュータを最大限活用するためのソフトウェアの開発・普及」)研究が始まった。まず「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」(代表平田文男)が2006年4月から始まった。拠点は分子科学研究所。 もう一つの「次世代生命体統合シミュレーションソフトウエアの研究開発」(代表茅幸二)は半年遅れ、2006年10月から始まった。拠点は理化学研究所中央研究所。いずれも期間は5年間。
4) 共同研究
アーキテクチャの基本は2006年中に方向が決まった。2006年4月6日、理研次世代スーパーコンピュータ開発実施本部は、アプリの検討とともに、「次世代スーパーコンピュータ:概念構築に関する共同研究」を4月21日締め切りで募集していたところ、16組織から17提案があった。このうち具体的なアーキテクチャ提案のあった6組織(日立製作所、東京大学、筑波大学、国立天文台、日本電気、富士通)および2組織(九州大学、海洋研究開発機構)と共同研究を行うと6月20日発表した。理研側としては、アーキテクチャ検討と同時に、21本のターゲットアプリケーションからベンチマークテスト(BMT)コードを開発する。相手機関は、アーキテクチャを提案し、その上でもBMTコードの性能を予測する。(HPCwire 2006/4/21)
どのような共同研究が行われたかは、企業秘密もあり一切公表されず、筆者も知らなかった。翌2007年3月から始まった情報科学技術委員会 次世代スーパーコンピュータ概念設計評価作業部会において委員には経緯が開示され筆者も知ることになった。しかし、その資料は会場限りとされ、一切持ち出すこともできなかった。しかし、2012年6月に秘密指定が解除されweb上で公開された。
次回は概念設計である。F案とNH案の2案に収束して行った。
 |
 |
 |