提 供
新HPCの歩み(第246回)-2006年(l)-
|
かねてから経営が危ぶまれていたSGIは5月に遂にChapter 11の保護を申請したが、10月には立ち直った。Intel社とAMD社のx86-64をめぐる競争はますます激化した。Intel社がTerascaleのアクセラレータのようなものを開発しているという発表があった。 |
アメリカの企業の動き
1) IBM社(Cell)
アメリカIBM社は、2006年2月8日、Cellプロセッサ(正式にはCell Broadband Engine)を採用したブレードサーバーを開発したと発表した。これはBladeCenter QS20と名付けられ、発売は2006年9月。1U程度のサイズの筐体に2基の2.3 GHzのCellプロセッサ、1GBのメモリ、40 GBのHDDなどを搭載している。(ZDNET Japan 2006/2/6)(PC Watch 2006/2/9) BladeCenterとしては、Intel Xeonを搭載したHSシリーズ(2002年~)、PowerPCを搭載したJSシリーズ(2004年~)、AMD Opteronを搭載したLSシリーズ(2005年~)につぐ機種である。2008年には、64ビット演算を強化したIBM PowerXCell 8iを搭載したBladeCenter QS22が登場し、Roadrunnerに用いられる。
PLAYSTATION 3以外のCell搭載システムとしては、これまで2005年6月に米Mercury Computer Systems社がサーバー/ワークステーションの開発を表明し((HPCwire 2005/7/1)(Wikipedia: Cell (processor))、 (ITmedia 2005/10/17)(HPCwire 2006/8/4) 2006年1月には、最初のCTES (Cell Technology Evaluation System)を出荷した。(HPCwire 2006/1/13) SIGGRAPH 2006でデモを行っている。 2006年12月の報道によると、Mercury Computer Systems社はこれをMentor Graphics社に提供し、EDA (Electronic Design Automation)に使うと発表した。また、2005年9月に東芝がディジタル家電向けの開発キットを発表している(PC Watch 2005/9/20)。
日本では、2月28日、日本IBM大和事業所において、「第一回 Cell ブレード セミナー」が開催された。大阪でも3月7日に開催された。
LBNLのSamuel Williams, John Shalf, Leonid Oliker, Parry Husbands, Shoaib Kamil and Katherine Yelickは科学技術アプリのカーネルを走らせてCellの可能性を分析した。その結果は、5月2日~5日にIschia島で開催されたComputing Frontier 2006で発表された。(HPCwire 2006/5/26)
LANLのところに書いたように、2006年9月にはRoadrunnerシステムのアクセラレータにCellを使うことが発表された。Roadrunnerのテスト版はとりあえず現在の32bit版のCellを使い、実用版には64bitのCell を開発するとのことであった。(HPCwire 2006/9/15)
この頃議論になったのは、CellがHPCの新しい潮流を作れるのかということであった。もちろん、PowerPCベースのSPEが8個も搭載されているので、その潜在能力がすごいことに疑いはない。ヘテロな構成になるが、それだってHPC業界では既に経験を積んでいる。しかし、Cellのヘテロ構造は、従来のものと違ってる。一つの見方によると、ある意味でCellはSeymour Crayの設計をひっくり返したものなっている。つまり、CDC 6600は1つの高速なプロセッサに計算を担当させ、他の10個の遅いシステムにメモリ管理をやらせた。しかしCellは逆に、8個のSPEが計算をやり、中央のプロセッサ(PPE)はそれにデータを供給する。(HPCwire 2006/6/2)
2006年10月、Terra Soft という会社がCellをつかったスーパーコンピュータを発売すると報道された。その名前がE.coli(大腸菌)で、ちょっと中毒しそうである。当時、アメリカでもO157が騒がれていた。(HPCwire 2006/10/13)(OSNews 2006/10/10)なおTerra Soft社は2008年11月、日本のフィックスターズ社に買収される。
アメリカIBM社は、Cell B.E.の利用を促進するために大学からの提案を選考していたが、2006年12月、10の大学に対しIBM Shared University Research (SUR) awardsの受賞者を発表した。(HPCwire 2006/12/15)
2) IBM社 (POWER/PowerPC)
IBM社は、2月5日~9日に開かれたISSCCにおいて、現在開発を進めているPOWER6プロセッサの動作周波数が4~5 GHzになると発表した。開発は困難に遭遇しており、2006年リリースの予定が2007年になるとのことである。(ZDNet Japan 2006/2/27)(HPCwire 2006/2/10) 実際には、2007年5月21日に正式に発表され、2007年6月8日に3.5, 4.2, 4.7 GHzのチップが発売される。
POWER搭載マシン関係では、2006年2月にPOWER5+を16コア搭載した新しいIBM System p5 570サーバを発表した。これに加えて、2.2 GHzのPOWER5+を16コア搭載したp5 575サーバも発売した。(HPCwire 2006/2/17)
2006年7月には、最大64コアのp5 595サーバを発表した。これは16 コアのPOWER5または5+ processor bookを1~4接続したものである。(HPCwire 2006/7/28)
2006年10月3日、米IBM社は低消費電力のPowerPCプロセッサ(PowerPC 750CLおよびPowerPC 970GX)を発表した。これらを搭載したBladeCenter JS21も発表された。
同時に新しい32ビットプロセッサコア3種も発表した。これらは90 nmテクノロジで製造される。
3) IBM社(BladeCenter)
IBM社は、2005年にAMDのOpteronを搭載したBladeCenter LSシリーズの発売を開始した。2005年のsingleまたはdual coreのOpteronを2ソケット搭載したLS20に続き、2006年には1個または2個のdual core Opteron(Santa Rosa)を搭載できるLS21を発売した。(Wikipedia:BladeCenter)
4) IBM社 (Blue Geneロードマップ)
IBM社は、Blue Geneの最新の最新の開発ロードマップを公表した。これまで次期機種Blue Gene/Qの目標ピーク性能を3 PFlops程度としていたが、今回10 PFlopsを目指すと述べた。2010年までにピーク性能1 PFlopsのBlue Gene/Pを開発し、2010年~2012年には10 PFlopsのBlue Gene/Qを開発するとのことである。IBM社は、2006年6月8日に東京都内で“IBM Deep Computing Innovation Forum”を開催し、Tilak Agerwala(IBM社研究担当副社長)が明らかにした。(日経Biztech 2006/6/8)筆者もこの会には参加したが、遅刻したのでこの講演は聞きそこなった。実際にはBlue Gene/Pは2007年に出荷されるが、Blue Gene/Qは2012年に登場する。
5) IBM社(ClearSpeed)
既述のように、2003年3月26日、xSeries 335または345などのIBM製品や、非IBM製品を含む様々なクラスタ技術を統合した製品、IBM eServer Cluster 1350を発表した。2003年11月、Opteronを最大48個搭載したIBM eServer 1350スーパークラスタを発表していた。
2006年6月27日(英国時間)、英国ClearSpeed Technology社と米IBM社は、クラスタ向けブレード・サーバーIBM System Cluster 1350に、演算処理用アクセラレータ・ボードClearSpeed Advanceを搭載すると発表した。ClearSpeed Advance搭載Cluster 1350は、2006年11月7日に発売された。ClearSpeed Advanceは、高速演算用プロセッサCSX600を2個搭載するPCI-X対応アクセラレータ・ボードで、東京工業大学が使っているものと同じであろう。同プロセサは96個の演算コアを内蔵し、64ビット長の浮動小数点演算で最大25 GFlopsを出す。動作周波数が250 MHzと低いので、消費電力は10Wを切る。 ClearSpeed Advance全体としては、最大50GFlopsで連続して倍精度実数行列乗算(DGEMM)を処理できるという。平均消費電力は25W未満。(ITpro 2006/6/28)(HPCwire 2006/6/30) Cell Broadband Engineを搭載した版も発売された(PressBox 2006/8/11)。
IBMまでがClearSpeed搭載のサーバを出すというのでビックリした。
6) SGI社(破産と復活)
SGI社は2006年5月にChapter 11(連邦破産法第11章)を申請し、会社更生手続きに入ったが、早くも10月には抜け出した。
昨年の所に書いたように、SGI社は2005年5月9日にNYSE(ニューヨーク証券取引所)から、株価が上場基準を下回ったことを通告されていた。上場を続けるためには30営業日連続で終値の平均が$1.00以上となる必要があるが、このレベルには戻らなかった。かつて1995年ごろには$50にも上昇したことを思うと、昔日の感がある。2005年11月1日SGI社に上場廃止の通告があり、SGI社は11月7日付けでNYSEの上場が廃止になると発表した。取引はthe OTC Bulletin Boardで続けられる。
2006年1月31日、Dennis McKennaが取締役会議長、CEO、会長に即日で就任したことが発表された。前任のRobert Bishopは取締役に止まり、副議長を務める。McKenna会長は、今後もサーバ、ストレージ、可視化の分野で技術革新を続けていくと力強く宣言した。2006年3月には従業員の12%を解雇した。新体制で苦境を脱出できるか?(HPCwire 2006/2/3)(HPCwire 2006/2/17)
SGI社は2006年5月8日、ついに連邦破産法第11章(いわゆるChapter 11)に基づく会社更生手続きの適用を、ニューヨーク州南部地区の米国破産裁判所(bankruptcy court、連邦地方裁判所に置かれ、連邦破産法に関する事件を取り扱う)申請したと発表した。(ITmedia 2006/5/9)(PC Watch 2006/5/9)(ASCII.JP 2006/5/8)(ITpro 2006/5/9)
同社の資産は$369.4Mに対し、債務は$664.3Mであり、$294.9Mの債務超過である。同社は、主要な債権者3社に対し、$250Mを資産に変え、$70Mの借款により会社を浮上させる計画を提案した。Dennis McKenna CEOは、今後も事業を継続し、製品およびサポートは従来通り継続すると述べた。6ヶ月以内に破産法の保護下から脱却すると豪語した。(HPCwire 2006/5/12) 正直「まさか」という感想であった。
ただし、日本などアジア太平洋、欧州、カナダ、メキシコ、南米など米国外の子会社は対象とならず、今後も業務を継続する。
2006年8月4日、SGI社は、破産裁判所が重要事項説明書(Disclosure Statement(よく分からないが、資産や負債や再建計画に関する開示情報であろう)を承認した、と発表した。これによって9月末にも破産法の保護から脱出できる見通しが立ったとした。(HPCwire 2006/8/4)(SGI Press Release 2006/7/5)(Silicon Valley Business Journal 2006/7/28)
2006年10月17日、破産後6ヶ月以内で、SGI社は連邦破産法の保護から脱却した。10月16日、SGI社は2006年3月末までの四半期に対する10-Qと呼ばれる報告書と、2006年6月30日までの1年に対する10-Kと呼ばれる年間報告書を提出していた。かつて主流であったMIPSプロセッサと自社のUNIX系OSのIRIXの組み合わせで動作するワークステーションの製造を中止し、代替としてIntel社のXeonやItaniumといったプロセッサとLinuxの組み合わせで動作する機種の開発へとシフトする予定である。(HPCwire 2006/10/20)(Outlook Series 2006/10/23) 多くのChapter 11事件(航空会社なども)と同様、破産は一種の徳政令と見ることもできる。その背後にはアメリカ政府への「忖度」があったのではないか。
本当に破綻したのは2009年4月1日で、Rackable Systems社に買収された。
7) Cray社(XT4、XM、CUG2006)
2006年5月、Cray社はAdaptive Supercomputingという新しいパラダイムを提唱し、今後の製品計画を示した。
まず、XD1の後継技術として、DRC Computer Corportion社のFPGAモジュールを採用すると発表した。DRC社は標準的なAMD Opteronソケットに刺さるコプロセッサを作っている。これにより、このモジュールはHyperTransportのスピードとレイテンシにより、DDRメモリやOpteronプロセッサにアクセスすることができる。後のConveyを連想させる。(The Register 2006/5/3)(HPCwire 2006/5/6)
Hoodというコード名で開発され、NERSCに納入される予定であったシステムは、2006年11月18日にCray XT4として発表された。これもAdaptive Supercomputingの一環である。Dual-core Opteronを搭載するMPPで最大1 PFlopsのピーク性能が可能である。相互接続もXT3のSeaStarからSeaStar2に更新され、1個のプロセッサが1つの通信インタフェースを占有する。
Cray社は複数の製品ラインの技術をXTラインにまとめるRainierプログラムを推進中で、XT4はこのプログラムに基づく最初の製品である。XT4はFPGAコプロセッサを組み込むこともできる。ちなみにMount Rainierはワシントン州にある4392mの火山である。日系人は「タコマ富士」と呼んでいる。
Top500から主要なCray XT4の設置状況を示す。
|
設置場所 |
システム |
コア |
Rmax |
Rpeak |
初出と順位 |
|
SNL |
Red Storm, XT3/4 2.4/2,2 GHZ DC/QC |
38208 |
204.20 |
284.00 |
2008/11 10位 |
|
ORNL |
Jaguar-Cray XT4/XT3 |
23016 |
101.70 |
119.35 |
2007/6 2位 |
|
Jaguar-Cray XT4, QC 2.1 GHz |
30976 |
205.00 |
260.20 |
2008/6 6位 |
|
|
NERSC |
Franklin-Cray XT4, 2.6 GHz |
19320 |
85.37 |
100.44 |
2007/11 9位 |
|
Franklin-Cray XT4, QC2.3 GHz |
38442 |
266.30 |
355.51 |
2008/11 8位 |
|
|
ERDC DSRC(アメリカ) |
Jade-Cray XT4, QC 2.1 GHz |
8464 |
56.25 |
71.10 |
2008/6 29位 |
|
Tennessee大 |
Athena-Cray XT4, QC 2.3 GHz |
17956 |
125.13 |
165,20 |
2008/11 16位 |
|
Edinburgh大(英国) |
HECToR-Cray XT4, 2.8 GHz |
11328 |
54.65 |
63.44 |
2007/11 17位 |
|
Cray社 |
Cray XT4, 1.8 GHz |
4304 |
12.86 |
15.49 |
2007/11 103位 |
|
Cray XT4, 2.2 GHz |
2728 |
9.85 |
15.30 |
2007/11 161位 |
|
|
CSC(フィンランド) |
Louhi-Cray XT4, 2.6 GHz |
2024 |
8.88 |
10.53 |
2007/6 109位 |
|
Cray XT5/XT4, QC 2.3 GHz |
10816 |
76.51 |
99.51 102.00 |
2008/11 32位 2009/6 49位 |
|
|
Bergen大(ノルウェー) |
Cray XT4 QC 2.3 GHz |
5550 |
40.59 |
51.06 |
2008/11 66位 |
|
国立天文台(日本) |
Cray XT4 QC 2.2 GHz |
3248 |
22.93 |
28.58 |
2008/6 77位 |
(QC:quadcore)
 |
|
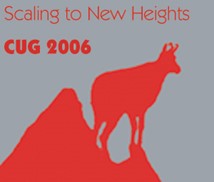 |
|
2006年11月13日、Cray XMT(Cray eXtreme MultiThreading、コード名Eldorado)も発表された。MTA (Multi-threaded Architecture)の創始者であるBurton Smithは前年2005年にCray社を去っているのにもかかわらず発表されたことは驚異的である。MTAに基づくCray MTAやCray MTA-2は余り売れなかったが、これを改良したThreadstormというカスタムチップを開発した。各プロセッサは128スレッドを並行して動作させることが可能である。最大8000個のプロセッサが搭載可能で、その場合100万スレッドに達する。
これもRainierプログラムの一環となるものであり、Opteronのソケットと通用性があり、XT4と同じ筐体に組み込むことができる。FPGAと同様、一種のコプロセッサらしい。主たる目的はデータマイニングやデータ解析であり、マルチスレッド技術が活躍する。他の応用も考えられるということであった。ユーザ環境としては、自働並列化を含むCとC++のクロスコンパイラを開発した。出荷は2007年初めの予定。筐体の写真はWikipediaより。HPE社によると公開されている最初の顧客はPNNLである(SciDac Review Fall 2008)。5筐体からなるシステムで、2007年に設置される。他に売れたとの話は聞こえて来ないので、全体でどの程度売れたかは不明。
Cray User Groupは、2006年5月8日~11日に、スイスのLuganoにおいて、“Scaling to New Heights”と題したCUG 2006 meetingを開催した。
8) Cray社(株式併合)
2006年6月7日、Cray社は4対1の株式併合(reverse stock split)が6日の株主総会で承認され、6月8日から有効になると発表した。これにより株式の総数は9200万株から2300万株に減少する。(Cray Annual Report 2006, F-5)混乱を避けるため20営業日はCRAYDという略号で取引されるが、7月10日以降は元のCRAYに戻る。
9) Hewlett-Packard社(Superdome SX2000)
2003年のSuperdome SX1000に続いて、2006年にはSuperdome SX2000を発表した。アーキテクチャはSX1000に似ているが、様々な改良により、高速化されている。SX1000と同様に64-wayまで。
10) Sun Microsystems社(UltraSPARC T1)
2006年3月、Sun Microsystems社は、UltraSPARC T1プロセッサのハードウェア仕様を公開した。これは2005年11月14日まではNiagaraというコード名で知られていたプロセッサである。省電力を重視し1.4 GHzで72 Wである。
T1は全く新しく設計されたSPARCマイクロプロセッサの実装で、完全なSPARC V9命令セットをサポートする。これはCMT (chip multi-threading)を実現し、Sun社にとって初めてのマルチコア、マルチスレッドのチップである。4コア、6コア、8コアのチップがあり、各コアは4スレッドを並列に実行する。すなわち最大32スレッドを処理できる。これはWebサーバやトランザクションサーバなど多数のアクセスを処理する用途に向いているが、FPUは1個が全コアで共有されていてHPC用ではない。
T1はHypervisor権限による実行モードをサポートする最初のSPARCプロセッサであり、Solarisはもちろん、LinuxやBSDなど複数のOSをチップ上で同時に動かすことができる。(HPCwire 2006/3/24)(Wikipedia: UltraSPARC T1)
11) Sun Microsystems社(Sun Blade、Sun Fire)
2006年7月、Sun Microssystems社は、3種類のAMD Opteronを搭載したサーバを発表した。4~16基のX64 を搭載したサーバSun Fire X4600、24 TBのデータサーバ、新しいブレードプラットフォームの3つである。Sun Fire X4600サーバは、8ソケットまたは4ソケットで、Opteronのsingle coreまたはdula coreを選ぶことにより、4~16コアを搭載できる。(HPCwire 2006/7/14)
2006年8月18日、Sun Fireファミリーの新しい製品を発表した。これらはSolaris 10で走る。一つは1.8 GHz UltraSPARC IV+を搭載したサーバで、もう一つは次世代AMD Opteronプロセッサを搭載したサーバである。(HPCwire 2006/8/18)
2006年9月10日、Sun社はQuad-Core Opteronを搭載したブレードサーバSun Blade X8440を発表した。同時に、4ソケットの2U quad-core serverも発表した。年末には発売する予定。(HPCwire 2006/9/10)
Sun社は2005年12月からOpenSPARCと呼ばれるオープンソースのハードウェアプロジェクトを始めたが、2006年10月、OpenSPARC Community Advisory Boardを設立したと発表した。(HPCwire 2006/10/6)
SC06では東京工業大学のSun Fireを要素とするTSUBAMEが話題になったが、Sun社のHPCおよび統合システム部長であるBjorn Anderssonは「HPCに戻ってきた(‘Sun is back in HPC’)」と高らかに宣言した。具体例として、以下の成果を語った。(HPCwire 2006/11/18)
|
・東工大のTSUBAMEがTop10に入った ・IDCの調査では、HPC市場でのシェアが増えた ・オレゴン州HillsboroにTop500 HPC Benchmark and solution centerを設立した ・HPCに対するSunのパートナーのコミュニティを始めた ・Sun Fire x64製品により、HPC製品の完全なポートフォリオを市場に提供した ・Scaliのような主要なHPC ISVとx86/x64上のSolarisに関する協定を結んだ ・TeraGrid上の汎用システムの入札に勝った(TACCの話であろう) ・x64サーバやWSで125もの世界ベンチマーク記録を打ち立てた ・HPCでのSIerとして日本電気との関係を深めた |
次回は、アメリカ企業(その二)、その他の企業、企業の創業、終焉など。Amazon Web Service社(AWS社)は、Amazon S3 Cloud Storageを開始した。
 |
 |
 |

