新HPCの歩み(第163回)-1999年(e)-
|
日本電気は、ITCのダンピング判定を不服として連邦最高裁判所に上告したが、最高裁はコメントなしに上告を退けた。CSCSの評価委員会はマッジョーレ湖畔AsconaのCastello del Soleという瀟洒なリゾートホテルで6日間にわたって開かれ、連邦予算による継続的な支援が不可欠であると答申した。インターネットに接続されたPCの遊休時間を使って地球外知的生物を探索するSETI@homeが公開される。 |
日米貿易摩擦
1) 連邦最高裁判所(上訴棄却)
日本電気は、ITC (International Trade Commission)のダンピング判定を不服として、1998年11月、連邦巡回区控訴裁判所に続き連邦最高裁判所に上告したが、2月26日、最高裁はコメントなしに上告を退けた(HPCwire 1999/2/26)。
2)「スーパーコンピュータ」の定義
アメリカのスーパー301条の恫喝を受けて、1990年4月19日に日本政府のアクションプログラム実行推進委員会は、「スーパーコンピュータ導入手続き」を改正したことは既に述べた。これによって、300 MFlops以上の「スーパーコンピュータ」の政府調達に際して、資料招請、仕様書の作成、官報公示を含む入札手続、技術審査、苦情処理などのやり方を定めた。スーパーコンピュータの定義はその後1995年に5 GFlops以上とされている。1999年4月には50 GFlops以上に引き上げられた(5月1日付)。日本は100 GFlopsを主張し、アメリカが25 GFlopsを主張したとのことであるが、その幾何平均をとったように見える。もし、Rmax=50 GFlopsのコンピュータがあれば、直前の1998年11月のTop500では113位にランクする。
3) 2度目のITC裁決(再度被害を認定)
昨年の日米貿易摩擦のところに書いたように、1998年12月、米連邦国際通商裁判所(The U.S. Court of International Trade)は、日本電気と富士通がダンピングによってアメリカの産業に害を与えているという1997年9月の連邦政府ITCの判定を差し戻した。これに対し1999年3月、米国ITC (International Trade Commission)は日本のスーパーコンピュータ販売はアメリカの製造会社に損害をもたらすと再び判断した(HPCwire 1999/3/5)。
日本電気のスポークスマンは、「ITCがこの件について再度こういう決定を行ったことは遺憾である。我々はこの訴えを継続するために、我々の意見を30日以内に書面で提出する予定である。」と述べた。
富士通の鳴戸道郎副会長は、「(日本はダンピングを行っていないし、米国の業者にとって脅威になってもいないという)われわれの主張は正当であり、法廷の判断を見守っている。」と述べた。鳴戸道郎は富士通の国際派の草分けと呼ばれていた人物であり、1980年代にはOSの著作権をめぐってIBMと渡り合った。富士通も30日以内に署名で意見を提出すると述べた。
両社は、3月、連邦国際通商裁判所(The U.S. Court of International Trade)に再び訴えた。
4) SX-4による温暖化予測
これとは別に、NCARは、異なるシナリオの下での地球温暖化のシミュレーションを、日本にあるSX-4/32を用いて実行した。おそらく、1998年のところに書いた、日本電気の遠隔計算サービスであろう。料金はCPU時間当たり$100である。資金は、アメリカ、日本、オランダの電力研究所およびNSが提供した。NCARのCSM気候モデルを用い、まず1870年~1990年までの地球の気候をシミュレートして、モデルと計算の正しさを検証したのち、2種類のシナリオのもとでの気候変動を1990年から2100年に対してシミュレートしたものである。「通常通りのビジネス」のシナリオでは、2100年の降水量は、地域と季節で大きく異なる。アメリカ合衆国では、冬期に、南西部と中西部平原において40%増加し、通常の変動範囲を超える。全世界の平均気温の上昇は華氏3~4度(摂氏1.5~2度)である。他方、「CO2放出を制限する」シナリオでは、降水量の増加が顕著ではなく、平均気温の上昇も華氏2~3度と予測される。(HPCwire 1999/6/4)
アジア太平洋の政府関係の動き
1) シンガポール(iHPC外部諮問パネル)
シンガポール政府が1998年4月iHPC (Institute for HPC)を設立したことは既に述べた。1999年6月に所長のDr. Lam Khim Yongから外部諮問パネルのメンバとなることを要請された。会合は1年に1回程度ということであった。メンバは下記のとおり。
 |
|
David Kahaner |
ATIP |
|
David Roger Lones Owen |
Swansea University, UK |
|
Alfred Brenner |
Inst Defense Analysis, USA |
|
Richard S. Hirsh |
NSF |
|
Jean L. Lambla |
Thomson |
|
Yoshio Oyanagi |
University of Tokyo |
9月14日~16日に第1回が開かれた。秋分近くで、赤道直下のシンガポールでは昼間の太陽は真上から射していた。会議のドレスコードが指定されていて、”Coat & Tie”ということであった。アメリカの某委員はジャケットを忘れて誰かの上着を借りていた。写真は、委員の集合写真。当時は、シンガポールにおける唯一のHPC資源提供機関であり、大学、研究所、軍などのスーパーコンピュータを利用した研究全部がここに集まっていた。運営方針から、研究テーマまで広く議論を行った。所長への勧告として、シンガポール国内への有用性を証明することにより予算の増額を要求すること、長期戦略を立てること、シンガポール国内の他の組織との連携を強めること、アメリカ、ヨーロッパ、アジアとの国際協調を進めることなどを提示した。メンバの一人が、「外部評価をやって、“予算を増額せよ”という答申が出なかったら、委員の選択を誤ったのだ。」と言ったので、大笑いした。
毎晩色々なホテルで豪華な夕食会が催された。夕食会のドレスコードは ”Smart Casual”とあったので、何を着ていくべきか迷った。筆者は写真のようにインドネシアで買ったバティックのシャツを着ていった。
 |
2) 台湾(中央気象局)
台湾中央気象局は、1983年にCyber 205を、1990年にCray Y-MPを導入したが、1999年には富士通VPP5000/15を設置した。このマシンは、1999年11月のTop500において、Rmax=139.0 GFlops、Rpeak=144.0 TFlopsで66位にランクしている。2001年にはVPP5000/25に増強し、2001年11月のTop500では、Rmax=232.00 GFlops、Rpeak=240.00 GFlopsで129位にランクしている。
3) オーストラリア(Melbourne大学)
1999年5月、NEC Australiaは、Melbourne大学および私立Melbourne大学とSX-4をA$3M(当時のレートで約2.2億円)で導入する契約を結んだ。すでにSX-5が発表されているのに、なぜSX-4なのかは不明である。性能は3.6 GFlopsとあるので2ノードか。余った計算資源はビジネス関係者に提供する。(HPCwire 1999/5/14)
ヨーロッパの政府関係の動き
1) CSCS外部評価
スイスのCSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, Swiss Centre for Scientific Computing, 現在はSwiss National Supercomputing Centre)は外部評価を行うことになり、筆者も外部委員を依頼された。電総研の関口智嗣氏の紹介だったと思う。CSCSは1991年創立のスイス全国共同利用のコンピュータセンターであり、ETH Zürich の一組織である。所在地はアルプスの麓、イタリア語圏Lugano地方のMannoであったが、その後2012年にLuganoのダウンタウンのCornaredo地域に移転する。なぜイタリア語圏かというと、2つの連邦立大学は、ETH Zürichがドイツ語圏で、EPFLがフランス語圏のLausanneなので、バランスを取ったとのことである。多言語国では言語圏のバランスは微妙な政治問題である。
諮問委員は以下の通り。
|
Dr. Stephan Bieri(委員長) |
ETH Zürich理事会副理事長 |
|
Prof. Th. Stocker |
Bern大学(スイス) |
|
Dr. W. Peters |
Baden-Württemberg州科学文化大臣(ドイツ) |
|
Prof. Knut Faegri |
Oslo大学(スウェーデン) |
|
Dr. Mario Arioli |
イタリア数理解析研究所 |
|
Prof. Sid Karin |
SDSC所長(アメリカ) |
|
Dr. Irene Qualters |
元Cray Research(アメリカ) |
|
小柳義夫 |
東京大学 |
委員会はマッジョーレ湖畔AsconaのCastello del Soleという瀟洒なリゾートホテルで5月30日から6月4日まで開催された。筆者はZürichで前後に各1泊した。ZürichとAsconaの間は1時間に1本の割合で特急が走っていた。筆者やSidは夫人同伴であった。
会議では、CSCSからのプレゼンとともに、ユーザ8人のヒアリング、ベンダ(NEC, IBM, HP and SUN)からのプレゼンもあった。一日はCSCSを訪問した。このときはNEC SX-4(12プロセッサ、8 GB)とHP Exemplar(4 GB)が稼動していた。
分かったことは、CSCSの発足に際してシステムを購入する予算は連邦政府が出したが、運用の費用はETHが用意せよという方針で、ユーザからの利用料金でまかなうことになった。ところが全国共同利用にもかかわらず、利用料金について、連邦立のETHおよびEPFLの2大学と、他の県立大学(cantonal universities)とのあいだに差別があり、県立大学の研究者から大きな不満が出ていた。Geneve大学にいたRoberto Car教授(Car-Parrinello法で有名)が1999年に頭脳流出しPrinceton大学に移ったのはそのためとも言われる。「新HPCの歩み(第35回)-1965年(a)-」に書いたように、日本でも同様な経験がある。東大大型計算機センター設立時に「(国費によって設置したものなので)私学等の利用負担金は30%増しにする」という案が出て、反対の大騒ぎになり、結局取り下げられた。
評価委員会は連邦予算による継続的な支援が不可欠であると答申し、4月末までに新しいコンセプトに基づいた利用料金体系を策定するよう求めた。多くの委員からはもうベクトルの時代ではないので、SX-4の次はスカラ高並列コンピュータを入れるべきとの意見も出た。筆者は反対した。実際には1999年末に8プロセッサのSX-5/8Aが導入された(2000年6月のTop500で236位tie)。あと議論になったのは、CSCSの研究機能である。CSCSは「サービスセンターから研究センターへ」というスローガンを掲げ、単なる計算サービスを提供するだけでなく、研究を推進する機能を持とうとしていたが、現実には人材不足で、人材育成とともに現実的な事業計画が必要であることを強調した。筆者はここで、日本の大型計算機センター群についても同様な議論が必要であることを痛感した。CSCSのセンター長が当時空席で、その決定も大問題であった。(HPCwire 1999/12/10)
夜な夜な豪華な夕食やおいしいワインが出された。でも食後夜10時に再集合なんていうこともあり欧米人のタフさに驚いた。またスイスはユーロを導入していないのに、あらゆる領収書にスイスフラン表記と並んでユーロ表記が並んでいたのでビックリした。下の写真は、ディナーのひと時。
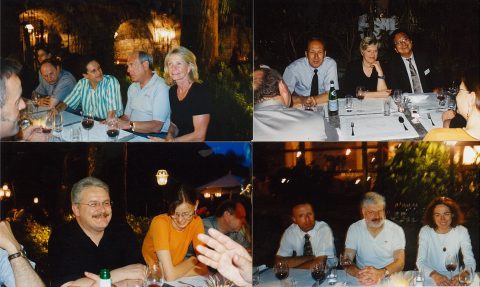 |
余談であるが、このときワインの(ホスト)テイスティングなど不用意にやるべきでないと痛感した。ディナーで出された数本の赤ワインは同じ種類であったが、足りなくなったので、追加でまた同じワインが出て来た。開栓され「誰かテイスティングしないか」との声が。そこでイタリアの陽気なMario(左下の写真中央)が「俺がやる」と、一口飲んで「OK」。皆のグラスに注がれたが、直後、ETHのStephan Bieri副理事長(右上の写真の左側)が、「皆、飲むな」と制止。何事かと思ったら、そのボトルのワインが酢になりかけていたのであった。栓に傷があって空気(雑菌?)が入ったらしいとか。セラーに並んでいたワインを順に持ってきたのだと思うが、そういうこともあるようだ。テイスティングで酸化を検知できなかったMarioは赤恥をかいた。自分でなくてよかった。グラスは全部新しくされ、ちゃんとしたワインが注がれた。
8月にはイギリスで最終答申策定の会議が開かれたが、筆者は出席しなかった。2000年にCSCSは組織再編を行い、再出発する(HPCwire 2000/9/15)。」
2) CINECA(イタリア)
BolognaにあるスーパーコンピュータセンターCINECAは、1999年、SGI/CrayからT3E1200(コア数268、Rmax=221.8 GFlops、Rpeak=321.6 GFlops、6月のTop500で36位tie)およびOrigin 2000 300 MHz(コア数64、Rmax=31.3 GFlops、Rpeak=38.4 GFlops、6月のTop500で326位tie)を導入した。
世界の学界の動き
1) LAPACK 3.0
LAPACK 3.0が1999年6月30日にリリースされた。
2) Cornell Theory Center (CTC)
NSFのPACIプロジェクトに採択されなかったCTCは8月、500 MHzのIntel Pentium III Xeon 4個から構成されるDellのPowerEdge serversを64台接続したクラスタを設置した。OSはWindows NTであった。Cornell関係者によると、これにより、金のかからないスーパーコンピューティングのための使いやすい環境を提供し、大きなプロジェクトも容易に管理できるようになる、とのことであった(HPCwire 1999/8/20)(HPCwire 1999/10/15)(Cornell Chronicle 1999/10/4)。
3) Tennessee大学(キャンパスグリッド)
第1回のGrid Forumが、1999年6月18日にNASA Ames Research Centerにおいて開催されたところであるが、NSFは10月、University of Tennessee, Knoxville (UTK)に対し、5年間総額$2Mを提供して、キャンパス内にグリッドthe Scalable Intracampus Research Grid (SInRG)を構築することとなった。“computational power grid”として、電力グリッドとの類比で説明されている。(HPCwire 1999/10/15)
4) Pittsburgh Supercomputing Center(実アプリでのTFlops達成)
ORNL、NERSC、PSCなどのグループは、1998年、LSMS法(locally self-consistent multiple scattering method)で磁性体のシミュレーションを行い、1024プロセッサのT3E1200で、657 GFlopsを実現したが、1998年11月9日には、SGI/Cray社内にある1480プロセッサのT3Eを用いて、1.02 TFlopsを実現していた、と1999年になって公表した。彼らは、ベンチマーク問題ではなく、現実問題を取り扱うアプリケーションにおいて、TFlopsの壁を破ったのは初めてであると主張している。(HPCwire 1999/10/15)
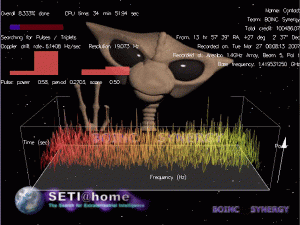 |
|
5) SETI@home
インターネットに接続されたPCの遊休時間を使うvolunteer computingのソフトの代表格であるSETI@homeはUC BerkeleyのSpace Science Laboratoryから1999年5月17日に公開された。SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)は地球外知的生命体からの信号を検出するための観測データの分析であり、SETI@homeはそれを有志のPCの遊休時間を使って実行するものである。スクリーンセーバの動画はWikipediaから。
Volunteer computingは、1996年に始まったMersenne素数の探索GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search)プロジェクトが最初と言われ、その後いくつかの研究プロジェクトが始まったが、SETI@homeはメディアの関心を引き一番有名な例となった。Volunteer gridとかcommunity computingとも呼ばれる。これがあまりに有名になったので、”Grid”と言えば”Volunteer grid”だという誤解も生じた。
6) クラスタvs.ベクトル
1999年3月下旬、CSCS(前述)のあるスイスのLuganoで「演算の高速化」をめぐるワークショップが開かれ、COWBOY(Cluster-of-Workstation派)とVectorian(ベクトル派)が激突した。アメリカではクラスタが普及し、価格性能比も良好である。もちろん、ヨーロッパにもクラスタはたくさんあるが。アメリカのCOWBOYたちは、ヨーロッパに来て、死んだはずだと思っていた恐竜(ベクトル計算機)が使われ、新規購入もされていることにびっくりした。
アメリカには、ベクトルとしては、高性能だが超高価なT90か、安いが低性能のJ90しかない。しかし、ヨーロッパには富士通のVPP300や日本電気のSX-4があって、CMOSでも性能が高い。AudiやMercedesなどの自動車会社ではCFDや構造解析や衝突解析にベクトル計算機を高効率で使っている。プログラムの移行も容易で、クラスタに比べて数倍も価格性能比がよい。しかしアメリカではダンピング関税で日本のスーパーコンピュータは数倍の価格となるので、クラスタと競争にならない。というような議論となった。21世紀はどうなるのか?(HPCwire 1999/5/14)
7) 微細化限界
HPCの性能向上は、Mooreの法則に象徴されるように、チップの微細化によるところが大きいが、微細化には限界がある。もちろん、これまで多くの壁が破られてきたが、原子の大きさはいかんともしがたい。Bell研究所のGreg Timpらは、現在の材料を使う限り、SiO2の絶縁膜の最小の厚さは5原子であると予測した。これは一様性を前提としているので、実際にはこの倍の厚さが必要であろう。現在(1999年)の酸化物被膜の厚さは25原子なので、もう10年は微細化を進めることができると結論している。(HPCwire 1999/6/25)
8) Computer History Museum完全移転
1996年の記事に書いたように、1984年にBostonのダウンタウンで開館したThe Computer Museumのいわば西海岸支所として、1996年、カリフォルニア州Moffett Fieldの元NASAの建物で、The Computer Museum History Centerが開設され、多くの展示物が移された。国道101号線の近くである。1999年にBostonのThe Computer Museumが閉鎖され、すべての収蔵品がこちらに移された。2000年、名称をComputer History Museumに変える。2002年には、SGIの使っていたMountain Viewのランドマークビルに移転する。『情報処理』(2008年)に発田弘の見学記がある。
次回は国際会議である。Santa Barbaraのホテルで開かれた第2回Petaflops会議では、Thomas Sterlingの提案したHTMTに度肝を抜かれた。RISTはハワイを会場にNext Generation Climate Modelsのワークショップを開催する。
 |
 |
 |

