提 供
HPCの歩み50年(第74回)-2000年(c)-
WCC2000 (IFIP 16th World Computer Congress)ではなんと江沢民国家主席本人が登場して開会演説を行った。SC2000の基調講演では、Steve Wallachが2009年までにPetaflopsを実現する方法について論じた。また同じSC2000でBlueGeneと地球シミュレータに関する講演が多くの聴衆を集めた。
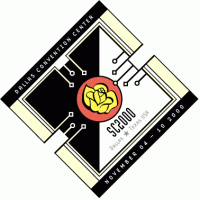
世界の学界の動き(続き)
5) Top 500
Mannheim Supercomputer Seminarにあわせて、2000年6月版のTop 500が発表された。top 10 は
| 順位 | マシン名 | Rmax |
| 1 | ASCI Red (SNL) | 2379.6 |
| 2 | ASCI Blue-Pacific (LLNL) | 2144 |
| 3 | ASCI Blue-Mountain (LANL) | 1608 |
| 4 | SP Power3/1336 (NAVOCEANO) | 1417 |
| 5 | SR8000-F1/112 (Leibniz Rechenzentrum) | 1035 |
| 6 | SR8000-F1/100 (KEK) | 917.2 |
| 7 | T3E1200 (米国、政府機関) | 891.5 |
| 8 | T3E1200 (米国、Army HPC Research Center) | 891.5 |
| 9 | SR8000/128 (東大) | 873.6 |
| 10 | T3E900 (米国、政府機関) | 815.1 |
であった。今回の傾向として、PC/WSクラスタが減少し、スーパーコンピュータの逆襲とも言える現象が目立っている。今回500位までに入ったクラスタはわずか3件で、どれも256 nodes以上である。
6) WOMPAT 2000
第1回目のWOMPAT 2000 (Workshop on OpenMP Applications and Tools)が7月6~7日にSan Diego Supercomputer Centerで開催された。
7) WCC2000/AEARU
1998年のところで触れた東アジア研究型大学協会 AEARU (The Association of East Asian Research Universities)の第3回Computer Science Workshopは、8月21~25日のWCC2000 (IFIP 16th World Computer Congress)に併設して開かれた。WCCの会場となった北京国際会議場は3回目で若干飽きた。少しずつは便利になって来たが、田舎という感じである。2008年の北京オリンピックが隣で開かれてからは、地下鉄も通り、便利になったようであるが。
WCC2000の出席者は2000人で、半分は中国から、次に多いのは日本からの160人。基調講演を行った長尾真京大総長(情報処理学会会長)やIFIP副会長の三浦武雄日立顧問など多くの方とお会いした。開会式には江沢民国家主席が現れ、開会講演をおこなった。最初は中国語で(同時通訳付)「地下資源には限りがあるが、情報資源は無限である。中国はまだ工業化の途中でITには大いに期待している。」などと述べたあと、原稿を下に置いて、「これからは英語で話します。私自身も電気工学者である。1982-85には通信大臣を務めた。私が大学(上海交通大学)で勉強していたころはトランジスタなどというものはなかった。1952年にアメリカのベル研究所を訪れたが、まだ秘密になっていた。今や、0.15μまで小さくなっているのはすごい進歩だ。」などと流ちょうな英語で述べた。あまりの迫力に、情報通信大臣や北京市長の挨拶などはかすんでしまった。三浦さんの話では、1980年に日本で開いた時には、当時の皇太子(現天皇)が挨拶されたとのことである。ただ、分科会は低調で、筆者の出たParallel Computingのセッションでは、筆者の他は発表者と座長しかいなかったのでビックリした。開会後少し来たが。
さて、AEARU CS Workshopは23日に国際会議場から徒歩7分ほどのCATIC Plaza Hotelで開かれた。参加者は20名ほど。日本からは李頡(筑波大)と加藤直樹(京大)と筆者。まずいくつかの大学が現在の状況や問題点について報告した。筆者は、東大で理学系の情報科学専攻と工学系の計数専攻・知能機械専攻が合併して情報理工学系研究科を作った話をした。「それはshot-gun marriageか?」という質問があったが、筆者はこの言葉を「いやがる二人をピストルで脅して結婚させる」と誤解していた。Shot-gun marriageとは要するに「できちゃった婚」のことであった。全体としては、企業に行ってしまう学生をどうして大学院に行かせるか(給付型奨学金とか)、大学教授が会社を創業することは許されているか、知的財産権はどうなっているか、などが議論された。
翌24日には希望者だけが北京大学を訪問した。昔は、理工系の清華大学に対し、北京大学は文科系の大学という印象があったが、巨大な8階建てのビル全体がComputer Science学科と聞いてうらやましく思った。GIS Lab.、Computer Linquistic Lab.、Architecture Lab.、Software Engineering Lab.、Database and Information Lab.、Network and Distributed System Lab.などを見学した。
このあとAEARU CSに関する東大の連絡担当は、筆者から今井浩教授に代わった。
8) SC2000
Supercomputing 2000については別に章を設ける。
9) Next Generation Climate Models
高度情報科学技術研究機構は、昨年のハワイでの会議に引き続き、“The Second International Workshop on Next Generation Climate Models for Advanced High Performance Computing Facilities”をフランスのToulouseで2月23~25日に開催した。
10) 集積回路でノーベル賞
ノーベル賞に「コンピュータ科学」部門はないが、2000年のノーベル物理学賞は、Texas Instruments社に勤務していたときに集積回路を発明したJack St. Clair Kilby博士に与えられた。博士は2005年に亡くなられた。
11) APEmille
イタリアの国立原子核物理学研究機構INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)は1980年代からQCD計算(格子ゲージ理論)のためのSIMD専用計算機を製作するプロジェクトを推進してきた。初代は1988年に完成したAPEでWeitek演算チップ12個を組合わせたノード16個をループ接続したものであった。次のAPE100 (APE cento)は1994年に完成し、2048ノードを3次元トーラス接続したもので、ピーク100 GFlopsであった。APEmilleは3代目に当たり、66 MHzのASICプロセッサで528 MFlopsの演算性能をもつ。クロックは100 MHzまで上げる予定で、ノード当たり800 MFlopsとなり、2048ノードでピーク1.6 TFlopsを持つ。
12) SSQ II Computer Science Workshop
個人的なことであるが、Templeton財団が支援し、BerkeleyのCTNS (Center for Theology and the Natural Sciences)が主宰するプロジェクトSSQ II (Science and Spiritual Quest II)のcomputer science部門に招請された。このプロジェクトは科学と宗教との対話を目的とし、Group 1: Physics and Cosmology, Group 2: Genetics and Evolution Biology, Group 3: Sciences of the Human PersonとわれわれのGroup 4: Computer Science and Information Technologyの4グループから構成されている。
12月9~12日にニューヨークでComputer Scienceグループのワークショップがあり家内と出席した。詳細は報告参照。滞在中に大統領選挙のフロリダの票数が確定しブッシュの勝利がやっと決った。ニューヨークは久しぶりであったが、以前と違って街はきれいで華やいでいた。人々は楽しそうにクリスマスの買い物を楽しんでいた。われわれもレストランで豪華なディナーを楽しんだり、深夜にエンパイア・ステート・ビルに登ったりした。このとき家内が「もしかしたらこれはニューヨークの最後の栄光かもしれない」と言ったのをはっきりと覚えている。まさかと思ったが、翌年9.11の同時多発テロが起こり家内の予言は不幸にも的中した。Canal Streetのそばのホテルに泊まっていたが、9.11のときの非常線はその辺りに張られることになる。
標準化
1) XML標準化調査
XML(Extensible Markup Language)はW3C (World Wide Web Consortium)においてSGMLを基に開発されたマークアップ言語で、1998年2月10日にXML1.0がW3Cの勧告になった。これに対し日本規格協会のINSTAC (情報技術標準化研究センター)ではJIS標準化の可能性を考えるため調査研究を行うことになり、どういうわけか全く不適な筆者がとりまとめを依頼された。実際の中心は大野邦夫氏(INSエンジニアリング)。企業と大学から委員を出していただき委員会を構成した。これはXML規格とその応用について世界や日本の動きを調査し、日本が今後どう取り組むべきかを提言することが目的で、XMLの規格制定そのものを行う予定はなかった。もちろん、単なる勉強会でなくアウトプットが必要であった。第1回を7月12日に開催し、ほぼ月1回の会合をもった。様々な分野におけるXMLの応用について調査したが、XBRL (Extensible Business Report Language)については国際的に活躍している渡辺榮一氏(東京商工リサーチ)に委員になっていただき、その結果実際の規格制定にも関与することになった。その間、10月24日には、W3CがCanonical XMLとXML Schemaを勧告候補として公表するなど、様々な動きがあった。応用についても議論が白熱し、とくに電子政府については現在の政府の方針が「あるべき姿」から乖離していることが指摘された。
2) XHTML
Webを記述する新しいプロトコルXHTML 1.0が標準化された。これはHTML 4.01をXMLにより再定義したもので、HTML 4.01と同様にStrict、Transitional、Framesetという3種類のDTDが存在する。2000年1月26日に勧告となり、2002年8月1日に改訂版であるSecond Editionが勧告された。
3) ICANN
第32回に書いたように、1990年にJCRNが設立され、これからDomain NameやIPアドレスなどのインターネット資源の割り当てのための組織JNICが生まれた。筆者も多少関係した。その後(株)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)に進化した。
世界的には、米国政府の援助も受けつつ技術者や研究者のボランティアで運営されてきたIANA (Internet Assigned Numbers Authority)がインターネット資源管理の責任を負っていた。1993年からはNSFがIANAの活動の一部を支援し、拡大し続けるインターネットに対応しようとした。1990年代後半になると、インターネットが社会に急速に浸透し、当時NSFからの委託でドメイン名等の管理を行ってきたNSI社(Network Solutions Inc.)に対し独占という批判が高まり、今後インターネット資源の世界規模での調整をどうすべきかについて活発な議論が行われ、1998年10月の民間の非営利法人ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)の設立につながった。IANAはその下部機関となった。詳しくはJPNICの「ICANNの歴史」を参照のこと。
世界中でICANNの一般会員を広く募集し、会員の投票によって理事を決めることになり、2000年5月18日、「ジャパンICANNフォーラム」という会が発足した。このフォーラムはICANNの活動の重要性を日本に広く広報し、その理事に日本から選出するための環境を整えることを目的としていた。ことになる。これを母体としてAt Large委員会が設立され、ICANNに対して日本を代表する組織となった。筆者も委員の一人となった。実際にはほとんど出席できなかったが、6月2日、6月13日、6月15日と急いで議論をまとめ、6月30日、第2回 ジャパンICANNフォーラム会合を如水会館で開催し、理事候補者が紹介された(筆者も出席)。第4回のAt Large委員会を9月7日、第3回ジャパンICANNフォーラム会合を9月20日に開催し、10月1~10日の理事選挙に備えた。これらの努力のかいあって、富士通の加藤幹之(かとう まさのぶ)氏がアジア・太平洋地域の理事として当選した。なお、慶應義塾大学の村井純氏は初代At Large理事として、1998年10月から就任している。
4) Global Grid Forum
2000年10月に、北米のGrid Forumと、ヨーロッパのeGridと、アジア太平洋地域のAP Gridとが合併してGlobal Grid Forumが結成された。2001年3月、最初のGGF-1がアムステルダムで開催される。2006年からはOpen Grid Forum。
5) Fortran 2000
Fortran言語の規格を議論しているISO/IECのJTC1/SC22/WG5は、Fotran 95の改訂を議論していた。このころFortran 2000の新しい規格案がまとまりつつあった。実際に公表された規格名はFortran 2003 (ISO/IEC 1539-1:2004)である。
SC2000
詳しくは筆者の報告を参照。電総研研究速報の報告、福井義成の報告などもあったが現在は見当たらない。12周年目にあたるSC2000: High Performance Networking and Computing Conference国際会議(通称 Supercomputing 2000)は、テキサス州 DallasのDallas Convention Center で11月6日から10日まで開催された(educational program やtutorialは4日から)。ケネディーを撃ったとされるオズワルドのいた元教科書倉庫のビルの”The Sixth Floor Museum” を見に言った。また今回ちょうど火曜日がElection Dayなので、Bushが勝ったらお膝元で戦勝パレードぐらいあるかと期待していたが、それどころではなかった。今年の参加者は例年より若干少ないのではないかという感じであったが、主催者発表によるとだいたい例年並とのことで、世界の32カ国から集まっている。
1) 企業展示
この会議の目玉の一つは大規模な企業展示である。本年も広大な会場に多くの企業の展示がにぎやかに設営された。クラスタを含むハードウェアベンダを始めとして、ソフトウェア、大容量記憶装置、ネットワーク、E-commerce、出版、学会など約90の企業等が出展した。Applied Metacomputing, Knowledgeport Alliance, Entropia, ParabonのようないわゆるMegacomputingの企業の参入は今年の新傾向であろう。
正直言って、今年はあまり目新しいものはなかった。IBMはPower4やBlue Geneを宣伝していた。Compaqは、ASCI Q(30+ Tera OPS)を受注したばかりで意気が上がっていた。これは、375台のGS320 (32 CPU)を結合したものである。原子力研究所(関西)からもかなり大きなシステムを受注していて、”Strongest computer in Japan” だとか電光表示で自慢していた。strongかどうかは主観の問題だが。Sun Microsystemsのブースのシアターでは、会社のセールストークの他に、8日(水)の昼には理研の成見君がMDGrape-WINE systemによるNaClのシミュレーション(Gordon Bell賞の候補になった仕事)を発表し、実演していた。
SGIはOrigin 3200/3400/3800などを出展していた。モジュール性を重視したNUMAflexというコンセプトを打ち出し、来年にはIA-64 ItaniumやPCI-Xなどにも繋げていくらしい。なんでも、Ohio Supercomputer CenterにはIA-64を使った機械のprototype systemが設置されたとのことである。
Teraに吸収されてCray Inc.となった旧Cray Divisionは、SV1の増強版SV1exを発表した。8M gatesのASICがtape outしたとのことである。450MHzでプロセッサ当たり1.8 GFlops、ノード当たり7.2 GFlopsと50%増強された。SV1は既に100台以上販売しているそうだ。SV2の噂もいろいろ流れているがどうなたのか?
日本の3社もは、例年通り大きなブースで出展していた。NECはSX-5を、富士通はVPP5000を、日立はSR8000を軸に出展した。ニュースによると、HitachiはSR8000のデバッガとして、EtnusのTotalViewを選択したとのことで、日本の代理店Softekの武田喜一郎社長のコメントが出ていた。
会議と平行して Exhibitor’s Forum が開催され、展示を出した各社が30分弱ずつ講演したが今年は聞く時間がなかった。
2) 研究展示 Research Exhibits
大学・研究所などの展示は、年毎に盛んになっている。今年は、合計69の展示があった。そのうちなんと13件は日本からの出展であった。電総研、原子力研究所計算科学推進センター、JAMSTEC海洋科学研究センター、科学技術振興事業団、航技研、大阪大学サイバーメディアセンター、RWCP、RIST、埼玉大学、理研、Adventure(東大)、GRAPE(東大)、早稲田大学。このうち、Adventure、GRAPE、早稲田大学の3つは学術振興会の未来開拓研究推進事業関連である。中でも、JAMSTECは地球シミュレータの1/100模型とCPUボードとを展示していた。
3) 基調講演
今回の基調講演はConvexの共同創立者の一人 Steven J. Wallach(CenterPoint Vecture Partners / Chiaro Networks)の “Petaflops in the Year 2009″であった。かれは2009年までにPetaflops計算機を製作する方法は何かと問い、高密度化したシリコンチップを光接続する、というスキームを提示した。
4) The Earth Simulator
11月7日(火)のMasterworksは、Computing Platformsと題して、”Blue Gene” by Monty Denneau (IBM) と、”Status of the Earth Simulator Project in Japan” by Kenji Tani (Japan Atomic Energy Research Institute) とがあった。いずれも今後のHigh Endのコンピュータであり、多くの聴衆を集めていた。谷氏は地球シミュレータのハード、ソフト、応用について全体的な解説をし、CPUボードと建物全体の模型が展示会場に出展されていることを述べた。「総予算は?」という質問が出て、谷氏が一瞬たじろぐ場面もあった。
5) Technical Program
オリジナルな論文は 179編の投稿があり、審査の上63件が発表された。今回は、村岡洋一氏(早稲田大学)と三浦謙一氏(富士通)がプログラム委員会に参加している。両氏ともIlliac IVのころイリノイ大学で活躍された方々なのは偶然か。日本からはGordon Bell finalistsの2件の他、”PM2: A High Performance Communication Middleware for Heterogeneous Network Environments” by Toshiyuki Takahashi, Shinji Sumimoto, Atsushi Hori, HIroshi Harada, Yutaka Ishikawa (RWCP) がCluster Infrastructureのセッションに採択された。来年は松岡聡氏(東工大)がプログラム委員会に加わる。
Tutorialは24件(Full Day:9件,Half Day 15件)、Panelは7件であった。SC96の頃はHPFやPVMのTutorialがあったが,最近はMPI,OpenMP,Java,XMLなどの内容が目立つ。VisualizationやClusterはここでも人気があり複数のTutorialが開催されている。今年の新しい試みとしては,Mesh Generationに関するTutorialが開催されていた。
6) 大統領選挙
11月7日火曜日は大統領選挙の日であった(11月第1月曜の翌日)。候補者は共和党のジョージ・W・ブッシュと民主党のアル・ゴア(と緑の党のラルフ・ネーダーはじめ5人の泡沫候補)であった。火曜日は開会式のある日で、夜はいくつかの会社のパーティーが催される。夕方何人かのアメリカ人の友人に話を聞くと、「ゴアが勝ちそうだ」と嬉しそうな顔をしていた。会議参加者のアメリカ人には民主党支持が多いこともあるが、ゴアは情報分野への支援に積極的だからであろう。
夜遅くなってからSGIのパーティー会場に行った。大広間では飲んだり食べたりだべったりしていたが、脇の小さな部屋2つにそれぞれ別のテレビニュースを投影して、皆見入っていた。票数伯仲で“Too close to call”となり、フロリダ州の勝者が決まらず、もやもやしたままホテルに帰った。
その後はご存知の通り、票を数えなおすとか再チェックするとかいうことになり、アメリカの投票システムの弱点が明らかになった。日本人の筆者にとって不思議だったことは、「人間が判定するとバイアスがかかるから、機械に任せるのが一番公正だ」と誰も信じていることだった。日本なんか全部人間が判定するのに。
結局、上に書いた通り、筆者が12月中旬、SSQIIのComputer Science Workshopでニューヨークに滞在しているとき、ブッシュの勝ちに決定した。当時のジェブ・ブッシュ知事(ブッシュ候補の弟)が、フロリダ州の票はもうこれ以上は数え直さないと断を下したからだそうである。
SC名物のAward Sessionについては次回。パネルではPataflopsやGridやMegacomputingの話題が踊った。
(タイトル画像: SC2000ロゴ 出典:UCARホームページ)
 |
 |
 |

