HPCの歩み50年(第177回)-2010年(c)-
2009年にまとめた「次世代スパコンを念頭においた人材育成のあり方について」に基づき「HPC人材育成のための教育のあり方検討会」を設置し、人材育成や教育利用についての議論を始めた。2つのグランドチャレンジはまとめの段階に入った。
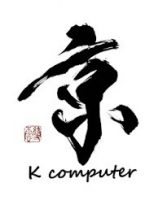
次世代スーパーコンピュータ開発(続き)
9) 「京」初出荷
2010年8月26日、理化学研究所と富士通との間で、計算機システムの製作契約が締結された。
9月28日午後2時、富士通は理化学研究所に納入する次世代スーパーコンピュータ「京」(けい)の第一号筐体出荷セレモニーを、石川県かほく市の富士通ITプロダクツ(FJIT、富士通とPFUの合弁会社)で行なった。同日、神戸市ポートアイランドにある理化学研究所の計算科学研究機構に向けて初荷(8ラック)が出荷され、翌日搬入された。これを皮切りに順次出荷する予定とのことであった。
富士通の佐相秀幸執行役員副社長は、「スパコンプロジェクトは、富士通の技術を牽引しているものである。半導体、PC、携帯電話、サーバといった富士通の製品群の信頼性を高め、これらのトータルな基盤の上で総合サービスを提供する。富士通は、これまでに30年近くスパコン事業に取り組んでおり、1993年には性能世界ナンバーワンを獲得した実績もある。性能の追求だけでなく、これをきちっと安定稼働させるという点にも力を注いでおり、365日間に渡り、低消費電力で安定稼働させることができるのが大きな特徴だ」などと述べた。佐相副社長のほか、富士通ITプロダクツの高田正憲社長、文部科学省研究振興局情報課長の岩本健吾氏、理化学研究所次世代スーパーコンピュータ開発実施本部プロジェクトリーダーの渡辺貞氏、石川県の山岸勇副知事などが出席し、出荷を祝ってテープカットを行なった。
| 理研AICSに到着した京初出荷のトラック (背景は花鳥園、現在の神戸どうぶつ王国) |
また、来賓を代表して挨拶した文部科学省研究振興局情報課長の岩本健吾氏は、「今回の初出荷により、3年間に渡る努力に一区切りがついたことには意義がある。これから出荷が本格的に始まっていくことになるが、理化学研究所の収容施設はすでに準備万端である。多額の投資をしたスパコンであり、世界最高水準の性能を目指すとともに、国民に対していかに成果を出すかといったことにも取り組んでいく。ライフイノベーション、グリーンイノベーションといったこれまでに成しえなかったものが実現されるようになるだろう。政府としても未来につながる投資として期待したい」とコメントした。理化学研究所次世代スーパーコンピュータ開発実施本部プロジェクトリーダーの渡辺貞氏は、「スパコンは国家基幹技術であるとされたものの、システムの大幅な構成変更や、新政権発足の事業仕分けにより一時凍結にあうなどの状況にあった。だが、国民や科学技術関係者の支援もあり、計画通りに今回の出荷を迎えることができた。富士通の総力にも感謝したい。これからの生産に向けて、より品質を高めてもらうことを期待したい」と述べた。
また、セレモニーでは、地元かほく市の小学校6校から12人の児童が参加して、出荷を記念した「くす玉」を割り、関係者によるテープカットののちに、地元関係者および社員で、第1号筐体を積載したトラックを拍手で見送った。[以上Impress誌による]PC Watchの写真を見ると、トラックの側壁に大きく書かれた「次世代スーパーコンピュータ初出荷」の「初」の「衣へん」に点がなく、「示へん」になっている。ところが、翌日理研AICSに到着したトラックには写真のように「点」が付いていた。ちょっとした珍事件(?)であった。
HPCwire紙の10月1日号は、「今後GPUなどを用いたヘテロなアーキテクチャが主流となるので、この『京』は、CPUだけでできた最後のホモジニアスなスーパーコンピュータとなるであろう」と書いているが、この予言は外れたようである。
10月1日には、ポートアイランドの理化学研究所計算科学研究機構において、計算科学研究機構設立式典が行なわれ、今回出荷した筐体第1号の見学会や、京の愛称の命名者の表彰などが行なわれた。また、書家の武田双雲先生によるロゴマークも披露された。
10) HPC人材育成
2009年4月24日の第11回次世代スーパーコンピュータ戦略委員会から、スーパーコンピュータの教育利用や人材育成についての議論が始まった。6月10日の第13回において、それまでの議論を基に、「次世代スパコンを念頭においた人材育成のあり方について」をまとめた。これに基づき「HPC人材育成のための教育のあり方検討会」を設置し、メンバーを決めたところまでは2009年の記事に書いた。会議は2010年から始まった。
| 主要な議題 | ||
| 第1回 | 2010年3月10日 | ・ HPC 人材育成のための教育のあり方検討会設置について ・ 学際計算科学・工学人材育成について(米澤明憲、中島研吾) ・ 神戸大学システム情報学研究科(薄井洋基) ・ 今後の検討事項 |
| 第2回 | 2010年4月16日 | ・ 今後の検討事項 ・ 計算科学の学際性と求められる人材像(青柳睦) ・ 計算理工学専攻、21世紀COEプログラム「計算科学フロンティア」、計算科学連携教育研究センター(金田行雄) ・ 兵庫県立大学の新研究科(佐藤哲也) ・ 育成すべき人材像について |
| 第3回 | 2010年5月26日 | ・ 今後の検討事項 ・ 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)とこの構築を主導するコンソーシアムのグランドデザイン ・ 産業界での人材育成について(伊藤聡) ・ 計算科学領域での人材育成(美濃導彦) ・ 「大学連合による計算科学の最先端人材育成」の活動報告(賀谷信幸) ・ 育成すべき人材像について |
| 第4回 | 2010年6月21日 | ・ これまでの議論のまとめと提言に向けた検討 |
| 第5回 | 2010年7月6日 | ・ これまでの議論のまとめ 応用系のカリキュラム(青柳睦、賀谷信幸) 情報系のカリキュラム(中島研吾) 企業のカリキュラム(伊藤聡) 欧米の事例と名古屋大学の事例(金田行雄) |
| 第6回 | 2010年8月11日 | ・ これまでの議論のまとめ |
| 2010年11月 | HPC人材育成のための教育のあり方について(中間報告) |
委員に予定していた神戸大学の井洋基学長補佐から、4月から担当任務が変わるということで、第2回からは賀谷信幸教授に交代した。中間報告にはいろんな場合を想定したカリキュラムの例が示されている。問題は、HPCの人材には、コンピュータ科学の知識と各分野(物理とか化学とか機械工学とか)の知識の両方が求められるので、限られた時間内にどう教育するか、ということであった。
11) 情報科学技術委員会
2010年には情報科学技術委員会が4回開催された。HPCIや次世代IT基盤関係の議題が多くを占めた。
| 日付 | 主要な議事 | |
| 第65回 | 2010年4月21日 | 1.平成22年度の情報科学技術予算について 2.平成22年度に実施する研究開発課題の評価の進め方について 3.革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)及びコンソーシアム構築について 4.その他 (配付資料)(議事要旨) |
| 第66回 | 2010年5月28日 | 1.「次世代IT基盤構築のための研究開発 情報基盤戦略活用プログラム(e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの研究開発)」中間報告会 2.「次世代IT基盤構築のための研究開発 イノベーション創出の基盤となるシミュレーションソフトウェアの研究開発」中間報告会 3.情報科学技術に関係する政府の基本政策等について 4.その他 (配付資料)(議事要旨) |
| 第67回 | 2010年6月24日 | 1.「次世代IT基盤構築のための研究開発 情報基盤戦略活用プログラム(e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの研究開発)」中間評価について 2.「次世代IT基盤構築のための研究開発 イノベーション創出の基盤となるシミュレーションソフトウェアの研究開発」中間評価について 3.平成23年度における情報科学技術分野の取り組みについて 4.HPCIの構築に係わる平成23年度新規課題の事前評価の進め方について 5.その他 (配付資料)(議事要旨) |
| 第68回 | 2010年8月20日 | 1.「次世代IT基盤構築のための研究開発 グリーン・サイバー・フィジカル・システム基盤技術開発」事前評価について 2.「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ計画」事前評価について 3.「グランドチャレンジアプリケーション開発 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」中間評価について (報告) 4.その他 (配付資料)(議事要旨) |
8月20日に金融庁9階903会議室で開催された第68回情報科学技術委員会では、筆者がHPCI計画推進委員会主査代理として出席し、HPCI計画の事前評価について報告した。
12) 賠償請求
2009年11月13日(金)の事業仕分けにおいて「日本電気と日立に契約違反の損害賠償を請求するか」という質問があり、準備中との回答があったが、文部科学省の中川正春副大臣は2010年7月28日の記者会見で、次世代スーパーコンピュータの開発プロジェクトから途中で撤退したNECに対して、理化学研究所が損害賠償を求める民事調停を7月14日付で東京地裁に申し立てたことを明らかにした。日本電気の参加を見込んで、スパコンの収容施設の建設を進めたため、無駄な投資をさせられたとして賠償を求めたと見られるが、請求額などの詳細は明らかにしていない。
NECコーポレートコミュニケーション部は「和解に向けて話し合いを進めたい」としている。
2011年12月22日、理化学研究所は「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトに係る調停事案の処理について、という発表を行い、「双方の請求を考慮し、その差額としての2億円をNECが理研に支払うことおよびNECが保有する同プロジェクト関係の知的財産権を理研他に無償許諾等することを主な内容とする調停が成立し、本事案は円満に終結しました。」と明らかにした。「理研によると、NECと結んだ四つの設計契約に絡んで損害が生じたと主張していたが、地裁はうち三つについては契約が履行されたと判断。残りの一つも途中までは契約通りに設計が進められていたとして、理研の請求額を大幅に減額した和解金を提示した。記者会見した理研の古屋輝夫理事は『満足したわけではないが裁判所の判断でやむを得ない』と説明した。」(共同通信2011年12月23日)
13) 駅名変更
各紙の報道によると、2010年10月29日、ポートライナーを運行する神戸新交通は「来年7月、施設近くの駅名を『ポートアイランド南駅』から『京コンピュータ前駅』に変更する」と発表した。同社は「世界的な施設とともに、新しい駅名も市民に浸透してほしい」と語っている。これは、市立医療センター中央市民病院の移転に伴い、従来の「市民病院前駅」を「みなとじま駅」に、移転先の「先端医療センター前駅」を「医療センター駅 市民病院前」に変更するのに合わせたものである。券売機の改修など、駅名変更に伴う経費は約5千万円であるが、3駅同時なので経費節減になっているそうである。1981年の開業後、駅名変更は初めて。2011年7月の変更直後にAICSで国際会議が開かれたが、外国からの参加者が「スーパーコンピュータの名前のついた駅は世界でここだけだ」と記念写真を撮っていた。
理研側からの強い要望があったとのことであるが、筆者などは、「京」の賞味期限は数年なので、次のコンピュータになったら「垓(がい)コンピュータ前?」になるのか、などと心配した。東京都立大学のない「都立大学駅」、東京学芸大学のない「学芸大学駅」は、住民投票で存続したそうである。現在は東京都立大学という名前自体がなくなった(復活しそうな形勢であるが)。
14) スーパーコンピューティング技術産業応用シンポジウム
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会は、2010年11月25日に東京大学生産技術研究所で「スーパーコンピューティング技術産業応用シンポジウム」を開催した。講演を頼まれたので、「計算科学の発展と人材育成」という話をした。
15) グランドチャレンジ
グランドチャレンジ「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」では、「第4回公開シンポジウム」を2010年3月3日~4日に岡崎コンファレンスセンターにおいて開催した。プログラムは以下の通り。
3月3日
| 13:00 | 挨拶等 | (分子研) 中村 宏樹 (文部科学省) 井上 諭一 (理研) 茅 幸二 |
| 13:20 | 次世代スーパーコンピュータプロジェクトの進捗状況 | (理研) 渡辺 貞 |
| 13:30 | スーパーコンピューティング技術産業応用協議会報告 | (産応協議会) 高棹 滋 |
| 13;40 | 休憩 | |
| 14:00 | ナノ分野グランドチャレンジ研究開発報告 | (分子研) 平田 文男 |
| 14:20 | プログラムの高度化 | (名大院工) 岡崎 進 |
| 14:40 | 実証研究(物性科学WG) | (東大院理) 常行 真司 |
| 14:50 | 実証研究(分子科学WG) | (京大院工) 榊 茂好 |
| 15:00 | 次世代ナノ統合ソフトウェア | (分子研) 江原 正博 |
| 15:20 | 休憩 | |
| 15:40 | パネルディスカッション「次世代スパコンでの新しい挑戦」 | モデレータ (分子研) 平田 文男 |
| 18:10 | 懇親会 |
3月4日
| 9:30 | 「招待講演」分光イメージングSTMを用いた非従来型超伝導の研究 | (理研) 花栗 哲郎 |
| 10:10 | 「招待講演」高次機能性単分子量子磁石と単一次元鎖量子磁石の現状と展望 | (東北大院理) 山下 正廣 |
| 10:50 | 休憩 | |
| 11:10 | 生命・生体シミュレーションの進捗状況 | (理研) 姫野龍太郎 |
| 11:20 | 大規模分子シミュレーションと溶液理論の融合によるナノ不均一溶液系の自由エネルギー解析 | (京大化研) 松林 伸幸 |
| 11:40 | 第一原理材料シミュレータQMASの開発状況と適用計算例 | (産総研) 石橋 章司 |
| 12:00 | 二次元有機導体における電荷秩序の光誘起ダイナミクス | (分子研) 田中 康寛 |
| 12:20 | 昼食 | |
| 13:50 | 「招待講演」電流および電圧による磁化の操作 | (阪大基礎工) 鈴木 義茂 |
| 14:30 | 「招待講演」蛋白質表面化学から細胞内有機化学へ | (京大院工) 浜地 格 |
| 15:10 | ポスターセッション | |
| 17:10 | 大規模系輸送現象のオーダーN2計算 | (阪大理) 赤井 久純 |
| 17:30 | 高精度電子状態理論による理論精密分光と光物性化学 | (分子研) 江原 正博 |
| 17:50 | 閉会挨拶 | (分子研) 平田 文男 |
グランドチャレンジ「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」では、「第2回 バイオスーパーコンピューティングシンポジウム」を2010年3月18日~19日に東京のMY PLAZAオールで開催した。参加者は約200名であった。プログラムは以下の通り。
3月18日
| 10:00 | Opening address | 茅幸二(理研) |
| Keynote lecture:High performance and distributed computing in biomedical research | Prof. Peter Coveney (University College London) | |
| 11:15 | Break | |
| 11:30 | Flash Talks for Poster Presentation I | |
| 12:30 | Lunch and Poster Session | |
| 14:00 | Invited: Simulations of lipid nano-containers mimicking primitive cells | Prof. Siewert Jan Marrink (University of Groningen) |
| Invited: Forces and Conformatoinal Dynamics in Biomolecular Nanomachines | Dr. Helmut Grubmüller (Max Planck Institute for Biophysical Chemistry) | |
| Simulations of biomolecular functions by a simultaneous use of three levels of molecular simulations, QM, MM, and CG | 木寺詔紀(理研) | |
| 16:15 | Break | |
| 16:30 | Invited: Towards the Systems Biology of Tissues: Predicting liver regeneration and tumor growth | Dr. Dirk Drasdo (INRIA) |
| Research and Development of Cell Scale Simulation Team | 横田秀夫(理研) | |
| 18:30 | Reception |
3月19日
| 10:00 | Invited: Toward Useful Biomedical Models | Dr. Grace C. Y. Peng (NIH) |
| Toward the multiscale simulation for organs and whole-body scale | 高木周(理研) | |
| 11:30 | Break | |
| 11:45 | Flash Talks for Poster Presentation II | |
| 12:45 | Lunch and Poster Session | |
| 14:15 | Invited: Issues in Management and Analysis of Genomic Data at Large Scale | Mr. Matthew Trunnell (Broad Institute of MIT and Harvard) |
| Can supercomputer hack cancer systems? | 宮野悟 (理研) | |
| 15:45 | Break | |
| 16:00 | Invited: Integration and Differentiation: Changing Scientific Publication and Communication with Models | Prof. James M. Bower (University of Texas Health Science Center) |
| Simulations of single neurons and large-scale neural networks | 石井信(理研) | |
| 17:30 | Report on the Poster Sessions | 中村春木 (バイオスーパーコンピューティング研究会 会長) |
| 17:45 | Closing address | 姫野龍太郎(理研) |
次は、「京」関係以外の日本政府関係の動きである。日本学術振興会では、G8の国際協力で新しい事業多国間国際研究協力事業(G8 Research Councils Initiative)が始まった。文部科学省研究開発局では、「気候変動予測に関する計算機検討会」を設置し、次の地球シミュレータの検討を始めた。
 |
 |
 |


