HPCの歩み50年(第192回)-2011年(d)-
「京」のテスト利用が始まり、5つのHPCI戦略プログラムと、2つのグランドチャレンジが「京」上でプログラムを流し始めた。HPCIコンソーシアムの組織が固まり、人材育成の議論も始まった。
「京」コンピュータ開発(続き)
30) 戦略プログラム
HPCI戦略プログラム推進委員会は2010年12月に設置され第1回の会合が2010年12月28日に開催された。第2回は3月29日に予定されていたが、事情により何度か延期され6月24日に文部科学省で開催された。各分野の状況報告、「京」の一部稼働の報告、AICSの活動状況などが報告され、計算資源の配分案が示された。また、分野を超えた取り組みについても議論された。なお、文部省のwebには、2012年10月31日の第5回委員会以降の記録しか残っていない。
2月24日には理研東京連絡事務所で第3回戦略プログラム連携推進会議があり、「京」のリソース配分の案が示された。第4回連携推進会議は5月13日に理研AICSで開かれ、研究連携、支援体制、サマースクール、シンポジウム、「京」の試験利用などについて議論した。
10月3日には、理研AICSにおいて、第3回HPCI戦略プログラム合同研究交流会が開催された。
31) 戦略分野5
筆者は、HPCI戦略プログラム(分野5)「物質と宇宙の起源と構造」の分野マネージャとなったので、作業部会メンバを決め、戦略分野5の作業部会を発足させた。2月2日に第1回分野5作業部会を開催し、3時間半の長い時間をとり、各課題責任者からの説明を聞き、十分議論した。マネージャとしては、次のような一般的な方向を提示した。
(a) この分野は、5分野の中で基礎科学をカバーする唯一の分野であり、応用的な諸分野とは異なる説明責任が求められていること。
(b) 科研費のように、この分野全体を万遍なく進歩させるのではなく、これはという大きな成果に向けて戦略を立てること。
(c) ヨーロッパやアメリカではスーパーコンピュータのかなりの資源をQCD(量子色力学)の計算が利用しているが、だからといって日本でもそれが当然というわけではなく、多くの資源を要求するにはそれなりの説明責任があること。
(d) 合わせて、この分野の研究者への利用支援も必要である。
(e) 計算科学として比較的長い歴史をもっているので、他の分野にとって模範となる利用形態を示すこと。また、その経験を他の分野に示すことにより、貢献すること。
各研究開発課題について、「具体的な達成目標と達成時期」・「選定プロセスおよび判断基準」・「京でしかできない定量的な理由」の説明、および分野全体としての「萌芽的研究開発課題への支援」の説明が提示された。作業部会で問題となったのは、各研究開発課題において選定に漏れた課題の方が、学問的に面白いのではないかということである。課題としては、次世代スパコン稼働5年後に具体的な一つの課題解決(ブレークスルー)を目指すものでなければならず、「京」を使って確実に成果が出て学術的なインパクトの強い3~5の研究開発課題に絞り込まざるをえなかった。従って「標準模型を超える物理の探索」や「超巨大ブラックホールの成長シミュレーション」などチャレンジングなテーマはこの基準に合わず、「萌芽的研究課題」として支援していくこととした。基礎科学分野としては歯がゆい思いであった。
作業部会からの指摘について、統括責任者、分野マネージャ、文科省が4月21日に会合し、対応方針について意思統一を行った。
第2回HPCI戦略プログラム作業部会(分野5)は、5月20日、文部科学省で開催され、作業部会からの指示事項への対応の説明と、計算科学技術推進体制構築について議論した。様々なコメントが出たが、以下の3点にまとめて課題担当者に示された。
(a) 課題について、評価されることを考慮し、達成目標を、数値などを使いより明確に具体化すること。また、関連する研究などへの成果の波及効果を明示すること。
(b) 萌芽的研究課題について、評価方法及び基準を明確化すること。
(c) 計算科学技術推進体制構築について、達成目標、期待される成果、課題の成果との結びつき、評価基準を明確にすること。
分野5の研究交流活動としては、3月21日~22日に「第3回 素核宇宙融合レクチャー シリーズ」、3月23日に「物質と宇宙の起源と構造」ワークショップを筑波大学計算科学研究センターで予定していたが、大震災のため延期となった。
延期された分野5「物質と宇宙の起源と構造」ワークショップは、5月19日に筑波大学で開催され、4つの研究開発課題と計算科学技術推進体制について紹介された。筆者は午後と懇親会だけ参加した。
「第3回 素核宇宙融合 レクチャー シリーズ――高エネルギー天体物理の基礎」は、2011年6月8日~9日に東京大学理学部4号館で開催された。
 |
|
7月26日には、分野2との交流として、「HPCI戦略プログラム 分野2×分野5 異分野交流研究会— 量子系の固有値問題と大規模計算 —」が筑波大学で開催された。写真はこの研究会風景。
8月4日(木)~8日(月)に京都大学基礎物理学研究所においてサマースクール「クオークから超新星爆発まで」―基礎物理の理想への挑戦―が開催された。
12月19日~21日にはKEKつくばキャンパスにおいて、HPCI戦略プログラム分野5研究会「計算的手法による素粒子論研究の広がり」— Expanding the Horizon of Theoretical Particle Physics through Computational Methods —が開催された。
32) グランドチャレンジ
ナノ・グランドチャレンジ(正式名:「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」は、2011年2月22日~23日、神戸市の甲南大学ポートアイランドキャンパス(「京」コンピュータに隣接)において、第5回公開シンポジウムを開催した。初日の第1セッションは、バイオ・グランドチャレンジ(正式名:「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」)との合同セッションであった。プログラムは以下の通り。
2月22日(火)
|
11:00~12:00 |
次世代スパコン施設見学会 |
|
|
|
昼休み |
|
|
13:00-13:05 |
開会の辞 |
ナノ統合拠点長 平田 文男 |
|
13:05-13:10 |
挨拶 |
バイオ・プログラムディレクター 茅 幸二 |
|
13:10-13:15 |
挨拶 |
分子科学研究所・所長 大峯 巖 |
|
13:15-13:25 |
挨拶 |
総合科学技術会議・常勤議員 奥村 直樹 |
|
13:25-13:30 |
挨拶 |
文部科学省大臣官房審議官(研究振興局担当)戸渡 速志 |
|
13:30-13:35 |
挨拶 |
理化学研究所・計算科学研究機構・機構長 平尾 公彦 |
|
13:35-13:40 |
挨拶 |
理化学研究所・次世代スーパーコンピュータプロジェクト・プロジェクトリーダー)渡辺 貞 |
|
|
休憩 |
|
|
13:55-14:00 |
事務連絡 |
(分子研) 斉藤 真司 |
|
14:00-14:20 |
ナノ分野グランドチャレンジ研究開発報告 |
(分子研) 平田 文男 |
|
14:20-14:35 |
プログラムの高度化 |
(名大院工) 岡崎 進 |
|
14:35-14:55 |
次世代ナノ統合ソフトウェア |
(分子研) 江原 正博 |
|
14:55-15:15 |
次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム(分野2 新物質・エネルギー創成) |
(東大院理) 常行 真司 |
|
15:15-15:25 |
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会報告 |
(産応協議会)高棹 滋 |
|
|
休憩 |
|
|
15:40-18:00 |
パネルディスカッション 2010年度テーマ:「社会に役立つナノ統合ソフト -次世代スパコンで、何か良い事をやっていただけるのですか?-」 モデレータ (分子研) 平田 文男 パネリスト(物性科学) (東大院工) 押山 淳 (物性科学) (京大基研) 遠山 貴巳 (分子科学) (名大院工) 岡崎 進 (分子科学) (分子研) 永瀬 茂 (物性科学実験)(筑波大物理) 上殿 明良 (分子科学実験)(神戸大院工) 近藤 昭彦 (計算機科学) (筑波大計算セ)佐藤 三久 (スパコン開発)(富士通) 追永 勇次 (企業研究者) (ダイセル) 柴田 徹 |
|
|
18:20~19:50 |
懇親会(ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター1F レストラン) |
|
2月23日
|
9:00- 9:30 |
実空間第一原理ナノ物質シミュレータ(HP-RSDFT) |
(東大院工) 押山 淳 |
|
9:30-10:00 |
高並列汎用分子動力学シミュレーションソフト(Modylas) |
(名大院工) 岡崎 進 |
|
10:00-10:30 |
動的密度行列繰り込み群法 |
(京大基研)遠山 貴巳 |
|
|
休憩 |
|
|
10:50-11:20 |
3D-RISM/RISMプログラムの開発と応用 |
(分子研) 平田 文男 |
|
11:20-11:50 |
大規模並列量子モンテカルロ法(ALPS/looper) |
(東大院工)藤堂 眞治 |
|
11:50-12:20 |
高速量子化学計算ソフト |
(分子研)永瀬 茂、(産総研)北浦 和夫 |
|
|
昼食 |
|
|
13:50-15:50 |
ポスターセッション |
|
|
15:50-16:10 |
付加機能ソフトM2TDの紹介 |
(鳥取大工)吉本 芳英 |
|
16:10-16:30 |
レプリカ交換法を実現する付加機能ソフト REM |
(名大院理)岡本 祐幸 |
|
16:30-16:50 |
磁性半導体中の磁気相関 |
(原子力機構)前川禎通 |
|
|
休憩 |
|
|
17:10-17:30 |
ermodの開発状況と環境調和型化学過程への適用事例 |
(京大化研)松林 伸幸 |
|
17:30-17:50 |
クラスタ動的平均場理論を用いたプログラム開発と有限温度モット転移への応用 |
(阪大院理) 大橋 琢磨 |
|
17:50-17:55 |
閉会の辞 |
(分子研) 平田 文男 |
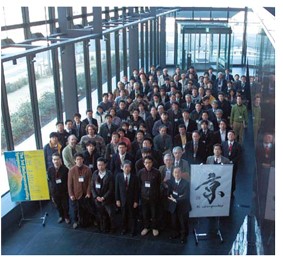 |
|
他方、バイオ・グランドチャレンジでは、2011年1月6日~7日に、神戸市にあるニチイ学館神戸ポートアイランドセンターにおいて、「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェア研究開発(ISLiM)」生命体統合シミュレーションウィンタースクール2011を開催した。2月21日~22日には、理化学研究所計算科学研究機構において、第3回バイオスーパーコンピューティング・シンポジウムが開催された。写真はニュースレターから。
また、2011年9月26日~27日には、淡路夢舞台国際会議場において、「バイオスーパーコンピューティングサマースクール2011」を開催した。
2011年12月21日~22日、東京大学武田ホールにおいて、「ISLiM成果報告会2011」を開催した。プログラムは以下の通り。
12月21日
|
10:00-10:15 |
オープニング |
茅幸二 プログラムディレクター |
|
10:15-10:45 |
プロジェクト総合報告 |
姫野龍太郎副プログラムディレクター |
|
10:45-11:35 |
分子スケール研究開発チーム成果報告(1/2) |
|
|
|
・チーム成果総括報告とPlatypus MM/CGの開発 |
木寺詔紀チームリーダー |
|
|
・タンパク質カノニカル分子軌道法プログラムProteinDFの京コンピュータへの実装 |
佐藤文俊 (東大生研) |
|
|
□ ランチタイム ◆ポスター展示説明 および休憩 |
|
|
13:30-14:45 |
分子スケール研究開発チーム成果報告(2/2) |
|
|
|
・Platypus-QM/MMの開発と並列性能 |
中村春木 (阪大蛋白研) |
|
|
・全原子分子動力学計算ソフトウエアMARBLEの開発と多剤排出トランスポーターAcrBへの応用 |
池口満徳 (横浜市立大) |
|
|
・粗視化分子ソフトウエアCafeMolによる多剤排出トランスポーターと遺伝子動態のシミュレーション研究 |
高田彰二 (京大) |
|
14:45-15:35 |
細胞スケール研究開発チーム成果報告 |
|
|
|
・チーム成果統括報告 |
横田秀夫チームリーダー |
|
|
・ 組織化された細胞代謝シミュレーションの開発と応用 |
末松 誠 (慶大 医) |
|
|
◆ポスター展示説明および休憩 |
|
|
16:20-18:00 |
臓器全身スケール研究開発チーム成果報告 |
|
|
|
・チーム成果統括報告 |
高木周チームリーダー |
|
|
・UT-Heartの進捗状況報告 |
鷲尾 巧 (東大) |
|
|
・大規模並列計算に適した流体構造連成手法(ZZ-EFSI)の開発と血栓シミュレーションへの適用 |
杉山和靖 (東大) |
|
|
・超音波治療器設計に向けたHIFUシミュレータの開発 |
沖田浩平 (日大) |
|
18:10-19:30 |
◯懇親会 |
|
12月22日
|
10:00-10:15 |
●DAY2オープニング |
|
|
10:15-12:00 |
データ解析融合研究開発チーム成果報告 |
|
|
|
・チーム成果統括報告 |
宮野悟チームリーダー |
|
|
・全ゲノム解析の超並列化による疾患研究の加速 |
角田達彦 (理研) |
|
|
・大規模遺伝子ネットワーク推定ソフトウェアSiGNとデータ解析融合プラットフォームSystems Biology integrative Pipeline (SBiP) |
宮野悟チームリーダー |
|
|
・網羅的タンパク質間相互作用予測ソフトウェア MEGADOCKの開発と応用 |
秋山泰 (東工大) |
|
|
・ LiSDAS:データ同化計算技術に基づく生体情報シミュレーション |
樋口知之 (統数研) |
|
|
□ ランチタイム |
|
|
13:00-14:00 |
◆ポスター展示説明および休憩 |
|
|
14:00-15:45 |
脳神経系研究開発チーム成果報告 |
|
|
|
・チーム成果統括報告/シミュレーションにより神経系の情報処理基盤を探る |
石井信チームリーダー |
|
|
・大規模並列計算で探る大脳局所神経回路の機能 |
深井朋樹 (理研) |
|
|
・視覚―眼球運動系の実時間シミュレーションをめざして |
銅谷賢治 (沖縄科技大) |
|
|
・モデル生物の全脳シミュレーションにむけて -カイコガ嗅覚・運動系シミュレーション- |
神崎亮平 (東大先端研)
|
|
15:45-16:30 |
◆ポスター展示説明および休憩 |
|
|
16:30-17:45 |
生命基盤ソフトウェア開発・高度化チーム成果報告 |
|
|
|
・チーム成果統括報告: MDコアソフトウェアおよびソフトウェア高度 |
泰地真弘人チームリーダー |
|
|
・アプリケーションミドルウェア SPHEREと大規模データ可視化 LSV |
野田茂穂 (理研) |
|
|
・ 創薬プラットフォーム-大規模バーチャルライブラリの開発- |
西村拓朗 (東大工) |
|
17:45-18:00 |
●クロージング |
|
33) HPCI計画推進委員会
2010年に発足したHPCI計画推進委員会は、2011年中、以下の通り6回開催された。主要なテーマは、「HPCIコンソーシアムの立ち上げ」「共用法対応や登録機関の選定」「ポスト「京」研究開発」などであった。
|
|
日付 |
主要な議事 |
|
第2回 |
2011年1月27日 |
(1)平成23年度HPCI計画政府予算について (2)HPCIコンソーシアムの状況について (3)HPCI戦略プログラムの進捗状況について |
|
第3回 |
2011年4月7日 |
(1)HPCIコンソーシアムの検討状況について (2)特定高速電子計算機施設の共用の促進に関する基本的な方針の改正等について (3)今後のハイパフォーマンス・コンピューティング技術の研究開発の検討ワーキンググループについて |
|
第4回 |
2011年6月17日 |
(1)利用促進業務実施機関審査基準について |
|
第5回 |
2011年7月14日 |
(1)HPCIコンソーシアムの検討状況について (2)今後のハイパフォーマンス・コンピューティング技術の研究開発の検討について (3)HPCI戦略プログラムの進捗状況について |
|
第6回 |
2011年9月14日(非公開) |
(1)平成24年度新規課題について |
|
第7回 |
2011年11月28日 |
(1)今後のハイパフォーマンス・コンピューティング技術の研究開発の検討状況について |
34) 情報科学技術委員会
科学技術・学術審議会のもとにある情報科学技術委員会は、2011年は5回開催された。
|
|
|
議題 |
|
第69回 |
2011年4月8日 |
|
|
第70回 |
2011年5月18日 |
1. 第4期科学技術基本計画を踏まえた今後の情報科学技術分野の研究開発推進方策の検討について |
|
第71回 |
2011年6月29日 |
|
|
第72回 |
2011年7月20日 |
|
|
第73回 |
2011年9月16日 |
|
35) HPCIコンソーシアム
昨年10月8日の国立情報学研究所における第1回「HPCI検討総会」に続いて、第2回「HPCI検討総会」が、2011年3月30日、国立情報学研究所で開催され、中間報告案について議論した。5月30日には霞山会館において、第1回「HPCI検討に関する意見交換会」が開催された。第3回「HPCI検討総会」が、7月5日に国立情報学研究所で、開催された。以上の議論に基づき中間報告「HPCIとその構築を主導するコンソーシアムの具体化に向けて」が7月5日付で発表された。
9月7日には理研AICSにおいて、第2回「HPCI検討に関する意見交換会」が開催された。9月26日には、第4回「HPCI検討総会」が国立情報学研究所で開催された。9月29日には、エムプラスグランド(三菱ビル内)において、「HPCIシステム基盤詳細設計中間報告&意見交換会」が開催された。12月14日には、東海大学校友会館(霞が関ビル)において、第5回「HPCI検討総会」が開催された。この時の配布資料には、スーパーコンピュータ計画をクソミソにけなす長文の「決算行政監視委員会行政監視に関する小委員会 -関連資料-」とともに、「京」の開発状況に関する貴重な資料もあり、面白い。
この間、多くのHPCI計画検討委員会が開かれ、次項の人材育成の関係で、一部には参加した。
法人としてのHPCIコンソーシアムは、2012年4月に正式に発足した。
36) HPCI人材育成
2009年にHPCI計画推進委員会の下に設置した「HPC人材育成のための教育のあり方検討会」(主査は筆者)は、2010年11月に中間報告「HPC人材育成のための教育のあり方について」をまとめた。これに基づき、HPCI事務局は、2011年4月27日の第9回HPCI検討委員会に「人材育成に係る検討の考え方」を提案し、2011年度末までに「HPCIを活用した人材育成の具体的な取組を示す」ことを目標に,HPCI検討委員会の下にWGを設置することを了承した。6月14日の第11回HPCI検討委員会に検討課題とメンバを提案した。6月24日の第12回HPCI検討委員会で検討。最終案を8月4日の第13回HPCI検討委員会に提示した(TV会議で出席)。メンバは若手中心(というほどでもないが、実務的に動ける人を中心)とした。経緯については、筆者の資料を参照。
|
(代表)小柳義夫 |
神戸大学システム情報学研究科特命教授 |
|
関口智嗣 |
産業技術総合研究所情報技術研究部門長 |
|
伊藤聡 |
理化学研究所計算科学研究機構企画部コーディネータ |
|
今田正俊 |
東京大学工学系研究科教授 |
|
金田行雄 |
名古屋大学工学研究科教授 |
|
賀谷信幸 |
神戸大学システム情報学研究科計算科学専攻長 |
|
斎藤峯雄 |
金沢大学自然科学研究科教授 |
|
中島研吾 |
東京大学情報基盤センター教授 |
|
兵頭志明 |
兵庫県立大学シミュレーション学研究科 |
2011年9月6日~2012年2月22日まで4回開催した。
|
第1回 |
2011年9月6日 理研東京連絡事務所(富国生命ビル) |
1. WGの検討項目について 2. 大学及び企業におけるHPC人材育成について 3. その他 |
|
第2回 |
2011年11月25日 理研東京連絡事務所(富国生命ビル)、TV経由で理研AICS |
1. HPCIの環境を活用した人材育成の考え方について 2. 企業のための人材育成とHPCIへの期待について 3. 大学におけるHPC・計算科学教育への課題とHPCIへの要望について 4. その他 |
|
第3回 |
2011年12月22日 理研AICS、TV経由で東大情報基盤センター |
1. 戦略分野における人材育成とHPCIコンソーシアムへの期待、提言について 2. 大学のHPC人材育成の観点からのHPCIコンソーシアムへの期待、提言について 3. 企業におけるHPC人材育成とHPCIコンソーシアムについて 4. その他 |
|
第4回 |
2012年2月22日 東京大学工学部6号館、TV経由で理研AICS |
1. HPCIを活用した人材育成の取組について 2. その他 |
|
|
2012年3月30日 |
第1回の会議で、このWGがどこまでを守備範囲とすべきかが問題となった。会議後、委員にアンケートを取ったところ、全体的には
b1:計算科学的手法を使い始めようとする人の教育
b2:現在すでに使っている人への教育
b3:ソフトウェア作成者、開発支援環境の開発者、チューニング専門家の育成
を中心に考えることとなった。このほか、
a4:学部・大学院での教育(とくに計算科学以外の学生への)
a5:理解増進、社会人へのアウトリーチ
を対象とするべきだと意見もおおかったが、a4については前年度までに検討会で精力的に検討したので、必要に応じて考慮するにとどめ、アウトリーチ活動についてはある程度検討することとした。従って早急に対応すべきテーマとしては、
a5関連:高校生へのアウトリーチプログラム
企業に対するアウトリーチ
b1関連:大学間の連携
AICS、情基センターなどへの若手研究者のインターシンップ制度、e-Learning教材の整備
b2関連:産学での情報交換・議論の場
並列化ライブラリ、環境などの講習会、e-Learning教材、インターンシップ制度
b3関連:大規模データ解析に関するトレーニング
その他:国産ソフトの教育現場での活用・普及
AICS、情基センターなどでの教育枠の設定
などが挙げられた。そのため、HPCIの機能として「計算科学教育センター」(仮称)を設置する方策についても検討した。
第2回は、もともと11月10日に予定していたが、前記の「事業仕分け」のために延期を余儀なくされた。
2012年3月には報告書を提出し、2012年4月に発足予定のHPCIコンソーシアムに提言を行なった。ここでは、「早急に具体化の検討を始めるべき事項」と「中長期的に検討を進めるべき事項」とに分けて提言している。その後はHPCIコンソーシアムの責任で検討を進めることになる。
次回はポスト「京」開発。「京」の完成を待たず、次のコンピュータシステムの要求要件やどう開発するかについての議論が始まっていたが、多数の若手が参加して、計算科学と計算機科学について、膨大なロードマップをまとめた。
 |
 |
 |

