提 供
HPCの歩み50年(第4回)-1966~7年-
IBM社のSystem/360のショックは大きかった。通産省は、1966年大型プロジェクト「超高性能電子計算機プロジェクト」を発足させ、System/360に対抗できるコンピュータの開発を計った。日本の各社は論理素子にICを用いた汎用コンピュータを続々開発した。アメリカのANSIはこの年FORTRANの米国規格を制定したが、これは後にFORTRAN 66と呼ばれた。日本も翌年「電子計算機プログラム用言語FORTRAN」の規格を制定した。
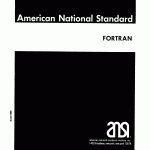
1966年の日本は飛行機事故の一年であった。全日空機が2/4に東京湾に墜落したと思ったら、1月後の3/4にはカナダ太平洋航空機が羽田で着陸に失敗して爆発炎上した。何とその翌日(3/5) BOAC航空機が富士山上空で空中分解した。11/13には全日空機が松山沖で墜落している。1/15「常磐ハワイアンセンター」オープン(現在の「スパリゾートハワイアンズ」)、6/29ビートルズ来日、6/30にいわゆる袴田事件、7/4は新東京空港を成田に建設することを閣議決定、8/5田中彰治逮捕、10/16「ベトナムに平和を!市民連合」発足、12/27黒い霧解散。一方世界に目を転じると、1/19インド首相にインディラ・ガンジーが選出、2/3米ソ同時の探査機月面軟着陸など。
筆者はこの年の4月に、東大の大学院理学系研究科物理学専門課程(当時は「専攻」とは言わなかった)修士課程に進学した。指導教官のM先生は1年間アメリカに行ってしまい、我々は孤児となった。その間、中村誠太郎先生(湯川秀樹先生の弟子)には大変お世話になった。
ついでに1967年を見ると、3月非核三原則決定、4/15美濃部亮吉が都知事当選、6月、富士通信機製造が富士通に社名変更、6/10東京教育大、筑波への移転決定、6/23家永三郎、教科書訴訟提訴、9月、不忍池の底が抜け建設中の千代田線トンネル冠水、10/8羽田デモ、10/18ツイッギー来日、10/31吉田茂国葬。世界では、6/5第3次中東戦争勃発、6/17中国、水爆実験、7月EC成立、8月ASEAN結成など。
筆者ら研究室の若手は1965年に設置されたHITAC 5020Eを愛用した。筆者は1967年に修士2年になり、当時ヨーロッパから帰国したK先生の示唆によるSU(3)対称性の現象論的研究や、I先生の指導によるRegge pole理論による高エネルギー実験データの解析などを行った。その際、不可欠だったのは、非線形最小二乗法のプログラムである。ほとんど参考書がなかったので、いろいろ工夫して自分で作成し、他の研究者にも提供した。このときの勉強が、後のSALSの開発に役立った。
しかし、われわれの研究室のM先生(当時助教授)は、アメリカ帰りというのに、コンピュータにのめり込む若手にこう嫌みを言った。曰く「一流の物理学者はコンピュータを使わない。」と。しかし先生の言うことに従っていては東大の学生は勤まらない。そんな批判はどこ吹く風と筆者等は計算物理への道を歩み始めたのである。後日談であるが、M先生は東大定年後、さる私学の何と「情報科学科」の教授となられた。
FORTRANの規格化
1966年の大事件は、ANSI (American National Standards Institute)がFORTRANの米国規格を制定したことである。2つの言語が制定されたが、一つはFORTRAN IIを基にしたBasic Fortranであり、もう一つはFORTRAN IVを基にしたFORTRANである。後者は後にFORTRAN 66と呼ばれることになる。この規格は1967年、JIS C 6201(水準7000)として「電子計算機プログラム用言語FORTRAN」という日本規格となった。同時に水準5000および3000も規定された。
FORTRANの歴史は10年以上前にさかのぼる。1953年末、John Backusは、IBM 704のためにアセンブリ言語に代わるものを開発するよう上司に提案し、開発チームが発足した。最初のコンパイラは1957年4月に開発された。1958年にはFORTRAN IIが、1962年にはFORTRAN IVが開発された。
筆者に言わせれば、FORTRANこそ、最初の「数式処理」言語、最初の「高級」言語、最初の「オブジェクト指向」言語であった。名前がformula translation(数式変換)に由来するからである。演算子のオーバーロードなどは、オブジェクト指向っぽいところと言えよう。カプセル化は不十分であるが。
日本の動き
 |
|
| HITAC 8700(画像出典:一般社団法人 情報処理学会 Web サイト「コンピュータ博物館」) |
1) 通産省大型プロジェクト
通産省は「大型工業技術研究開発制度」(通称大型プロジェクト)を新設した。これは、補助金のように開発費の一部を補助するのではなく、技術院が自ら開発を行う一方、一部をメーカに委託するものである。
コンピュータ関係では、1966年、大型プロジェクト「超高性能電子計算機プロジェクト」を発足させ、System/360に対抗できるコンピュータの開発を計った。通産省として最初のコンピュータ関連の大型プロジェクトであった。5年間に101億円が投入された。工業技術院電気試験所の指導の下、日立が全体を統括し、日本電気、富士通、東芝、三菱電機、沖電気の5社が集積回路や周辺装置の開発を担当した。プロジェクトは1972年まで続いた。このプロジェクトでは、仮想記憶(ページング方式)、キャッシュ、共有メモリ型マルチプロセッサ(4プロセッサ)、パイプライン処理などが開発された。1972年8月に試作機が完成し、成果はHITAC 8800/8700 (1972)として製品化された。
日本の企業の動き
このころ日本の各社は、ICを論理素子とするコンピュータの開発にしのぎを削った。
1) 三菱電機
1966年1月、三菱電機は、ファミリー形態を採用したMELCOM 3100シリーズ(18ビット語長、磁気ディスク採用)を発表した。1967年9月、三菱電機は、科学技術オンライン用コンピュータMELCOM 9100/30を完成した。
2) 日立
1966年8月、日立は全面IC採用の中型汎用機HITAC 8210(磁気ディスク採用)発表。また、月は不明だが、日立は1966年、高速化したHITAC 5020E/Fを開発し、東大大型センターの2台の5020の一方をこれに更新した。
3) 日本電気
1966年10月、日本電気は大型機NEAC 2200/500(全面IC採用)が完成した。大阪大学にmodel 500を納入した。また、1967年2月、日本電気はICを用いたNEAC-1240(コアメモリ採用)を発表した。
4) 沖ユニバック
1966年12月には、沖ユニバックがOUK 9400(全面IC、ディスクOS採用)が完成。
 |
 |
|
| MELCOM 3100 (画像提供:三菱電機株式会社) |
NEC NEAC 2200 (画像提供:日本電気株式会社) |
世界の学界の動き
1) Flynnの分類
Stanford大学のMichael J. Flynnは、1966年、並列コンピュータをinstruction streamとdata streamの観点からSISD, SIMD, MISD, MIMDの4種に分類した。現在の視点からは、データが共有か分散かについて考慮されてないのは不思議であるが、恐らく共有メモリしか頭になかったのであろう。また、multiple instruction stream(複数命令流)についても、命令間の同期が配慮されていないので、MIMDというと今で言うchaotic algorithmのようなものが連想され、のちにわれわれがPAXはMIMDだと言った時、激しい拒否反応を受けた。従って、現在この4分類は並列処理の分類として枕詞としてしか言及されないが、このうちSIMDだけはプロセッサ内の浮動小数演算高速化の技術の名称として使われている。
アメリカの企業の動き
1) IBM社(IBM 360/91, Amdahlの法則)
IBM社は1967年、System/360シリーズの中で、科学技術計算向けに設計したmodel 91を発表した。これはTomasuloのアルゴリズムを採用し、浮動小数演算においてout-of-order実行を行う最初のマシンである。ビジネス利用を想定していないので、十進演算命令は用意されていない。
また、IBM社のGene M. Amdahlは、1967年8月のAFIPS Spring Joint Computer Conferenceにおいて、”Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities”においていわゆるAmdahlの法則(Amdahl’s law)を発表した。並列処理による速度向上の限界については、本文中にはあまり明確に書いてないが、Guihai Chenが補足を加えて有名な公式を提示している。
(タイトル画像出展:GCC Wiki)
 |
 |
 |

