新HPCの歩み(第52回)-1974年(b)-
|
アメリカではベクトルコンピュータSTAR-100がLLLに納入されたが、思ったほど性能は出なかった。Motorola社は8ビットマイクロプロセッサMC6800を開発した。Dongarraらは線形計算ライブラリLINPACKをこのころ公開した。他方、日本ではSystem/370対抗の通産省の補助金の成果が出つつあった。 |
日本政府関係の動き
1) 文部省
文部省は、1949年からおかれていた大学学術局を、1974年、大学局と学術国際局に分離し、学術研究の振興は学術国際局が担当することとなった。とくに、研究機関の設置及び運営指導に関する行政事務の充実を図るため学術課の一部を研究機関課として独立させた。大学局は、1984年、高等教育局に改組した。
2) コンピュータ自由化
1973年4月に決定された第5次資本自由化および輸入自由化方針により、電子計算機の技術導入の自由化が1974年7月1日に行われた。このあと、1975年12月1日には資本自由化、12月24日には輸入自由化が実施され、1976年4月1日にソフトウェア業の資本が自由化される。
日本の大学センター
1) N-1ネットワーク
文部省科学研究費特定研究「広域大量情報の高次処理」が日本学術会議の推薦により1973年から3年間の計画で進められ、1974年4月からはN-1ネットワークの開発が始まった。システム構成の検討、プロトコルの整備、ソフトウェア開発・デバッグなどが1976年5月まで続けられた。N-1ネットワークの特徴として、以下の項目が示されている。
a) 分散型コンピュータネットワークである(互いに対等)
b) 日本電信電話公社の新データ網(回線交換およびパケット交換)に接続できる
c) 異機種計算機間を接続
d) 同一回線で複数業務
e) 障害対策を持つ
今から見れば当たり前のことも多いが、当時としては斬新な計画であった。
2) 北海道大学(FACOM 230-75)
北海道大学大型計算機センターは1970年に発足したが、1974年11月にFACOM230-60をFACOM230-75に機種変更した。
3) 東京大学(研究会)
東京大学大型計算機センターでは、「乱数と最適化問題研究会」を1974年2月22日~23日に開催した。記憶は定かではないが、当時、大型計算機センターで研究会を開くことは珍しかったと思う。この研究会は、ライブラリ開発に関連して企画されたもので、筆者も自分が直前に開発したサブルーチンの性能評価について論じている。研究会のプログラムを報文集の目次より記す。
|
乱数 |
||
|
擬似乱数の生成と評価 |
計量研究所 |
栗田良春・森村正道 |
|
神経インパルス系列のランダムネスについて |
東北大医 |
中浜・石井・山本・藤井 |
|
位相体積とモンテカルロ法 |
早稲田理工 |
力久正憲 |
|
有限数列のrandom度 |
高エネルギー研 |
苅田幸雄 |
|
最適化 |
||
|
非線型最適化の方法 |
東大工 |
山本善之・本間康之・松原典宏 |
|
Variable metric法による極小化法 |
京大大型センター |
星野聡 |
|
非線型最小二乗法における誤差評価 |
東大理 |
金久実 |
|
非線型最小二乗法プログラムPOW1について |
高エネルギー研 |
小柳義夫 |
|
制約条件付非線型最適化問題とその解法 |
早稲田理工 |
力久正憲 |
|
特異値分解を用いた二乗和の最適化 |
東大理 |
大岩元 |
|
人工衛星の軌道解析における最小化問題 |
宇宙開発事業団 |
加藤武彦 |
|
P-P Phase shift analysisにおける最小二乗法 |
大阪市立大 |
亘和太郎 |
当時これらの分野では参考書も乏しく、非常に勉強になった記憶がある。筆者がモンテカルロ法に興味を持つようになったのもこのころである。1975年から最小二乗法標準プログラムSALSの開発を始めたとき、力久(りきひさ)氏はその有力メンバーの一人となったが、早く亡くなられた。大岩元の研究は、その後電子光学系の設計で大活躍した。ちなみに星野聡(聰)氏は、PAXの星野力氏の兄である。聰氏は最適化だけでなく、日本を含む東洋の古文書のコンピュータ処理においても貢献された。2020年10月に89歳で亡くなられた。
4) 京都大学(FACOM 230-75)
京都大学大型計算機センターは、1969年に2台のFACOM 230-60を設置したが、1974年、そのうちの1台をFACOM 230-75 (1 CPU, 512 KW, 5 MIPS)に機種変更した。
5) 九州大学(FACOM 230-75)
九州大学大型計算機センターは、仮設センターの時代から稼働していたFACOM 230-60を、1974年9月、FACOM 230-75に更新した。
6) 筑波大学(計算センター発足、情報処理教育)
筑波大学は1973年10月、茨城県新治郡桜村に設置されたが、1974年4月に学内共同利用のための計算センターを設置した。当初のマシンはおそらくTOSBAC 5600(要確認)である。研究や事務処理のため運用を開始した。
また、筑波大学では新構想の一つとして、文系を含め必修の全学情報処理教育(1年次)を企画した。当初は、実習はなく講義だけで済ます予定であったが、畳の上の水練では意味がないということで、講義とともに2コマの実習も行うことになり、以下のような構想を立てた(『筑波大学第三学群20年誌』の宇都宮公訓の記事による)。
(1)コンピュータを対話形式で利用させる
(2)利用技術を優先し,プログラミング実習は半分以下に押さえる
(3)講義と実習を連係させ,コンピュータの利用とその社会的インパクトを正しく深く理解させる
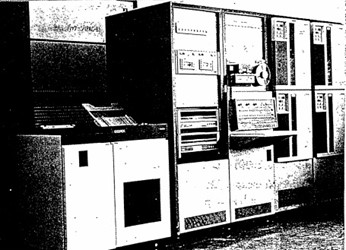 |
|
当時大型機でも対話型のOSは少なく、大学で行われていた情報処理教育は、FORTRANやCOBOLでプログラムを書き、カードにパンチしてclosed batchで処理するのが普通であった。しかし、担当者は「コンビュータの利用形態の基本は対話型であるべきと考え、検討の末、3台のTOSBAC-40C(写真は『筑波大学第三学群20周年誌』より)により情報処理実習を始めた。複数台のミニコンによるTSSは東芝と筑波大学の共同開発によるもので、わが国初である。1台のCPUが保守や故障で使えない場合も他でカバーできる。21台のディスプレイ端末により、一度に多数の学生が利用できた。と言っても1クラス40人なので、占有とはならず2人で1台の割り当てであった。それでも当時は画期的であった。システム開発が終わって、実習が開始できたのは第3学期(1974年12月~1975年2月)であり、一部の1期生の情報処理教育は1975年のゴールデンウィークまでずれ込んでしまった。
実は、筆者も、1978年8月に筑波大学に転勤し、この情報処理教育の一端を担うことになる。ちょうとそのころ、教育用計算機はMELCOM COSMO 700IIIに変わっていたので、実習中は一人一台占有できるようになっていた。TOSBAC-40Cの時代は話に聞くだけである。
7) 富山大学
1974年2月、計算センターを増築し、FACOM 230-45Sを設置し、3月よりサービス開始。
8) 九州工業大学(IBM 370/115)
1974月4月、九州工業大学は工学部に情報処理教育センターを設置し、10月にはセンター専任教官3名を発令した。翌年4月から、全学科一年次に入門教育を開始した。6月情報処理教育センターの建物が完成し、OKITAC4500-OKITAAC4300システムを移設。2月に情報工学科に暫定設置したIBM 370/115も移設。
9) 青山学院大学(IBM 370-135)
世田谷キャンパスのIBM 7040-1401をIBM 370-135に更新。
10) 東京大学原子核研究所(OSBAC-3400/51)
1974年3月、同研究所の中央計算機はTOSBAC-3400/41からTOSBAC-3400/51 1台に増強された。
日本の学界
1) 理工系情報学科協議会
このころ、国立大学に情報系の学科が順次設置された。教育に使用される計算機システムは、一度買えば終わり、というものではなく。技術の動向に従って性能を向上させる必要がある。そのためにはレンタル化が必須であるが、固定的な予算となるので、文部省は難色を示していた。そこで、1974年7月、理工系情報学科協議会を組織し、文部省専門教育課に対して粘り強く働きかけた結果、順次レンタル化の予算が認められるようになった。初代会長は大阪大学田中幸吉教授(1977年まで)。
国内会議
1) 数値解析研究会
自主的に企画している数値解析研究会(後の数値解析シンポジウム)の第4回は、1974年5月14日(火)~16日(木)に、赤城レーク・ハウスで開催された。世話役は春海佳三郎(群大)と平野菅保(東芝)、参加者は25名。
2) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所は、1974年10月31日~11月2日、高橋秀俊(東京大学)を代表者として、「数値解析とコンピュータ-」という研究集会を開催した。第6回目である。報告は講究録No.253にある。「複素関数論と数値解析」(高橋秀俊)と並んで「最近の大型計算機の進歩とベンチマーク問題」(村田健郎)などという講演もある。
日本の企業の動き
System/370に対抗するための通産省の政策の成果が出つつあった。
1) 日本電気・東芝(ACOS 200/300/400/500/600/700)
日本電気と東芝は1972年からACOSシリーズを共同で開発していたが、1974年5月には、日本電気はACOSシリーズ77システム200, 300, 400, 500を発表した。システム200は小型機で、OSはACOS-2であった。システム300、400、500は中型機で、LSIやMSIを採用したものである。ACOS-4(32ビット、バイトマシン)が搭載されている。ACOS-4は、1975年10月にACOS-4 R3.1として誕生した。
11月に、東芝は大型機ACOSシリーズ77システム600, 700を発表した。これらはTOSBAC-5600をベースに開発され、36ビット語で、OSはACOS-6が搭載されている。MSI、キャッシュメモリ、仮想記憶を採用している。ACOS 600/700ともよばれる。ACOS-6は最初東芝が開発した。技術提携していたGEを通して、遠くはMulticsの流れをくむOSである。1974年11月に発表し、12月から出荷した。1970年、Honeywell社はGEのコンピュータ部門を買い取った。日本電気はHoneywell社と提携していた。
2) 三菱電機・沖電気(COSMO 700)
同じ1974年5月、三菱電機・沖電気は、大型コンピュータCOSMOシリーズmodel 700を発表した。これは、LSIを採用し、多重仮想記憶方式で、256語のTLB (Translation Lookaside Buffer) によりアドレス変換の高速化を図っている。
3) 富士通・日立(Mシリーズ)
1974年6月10日、富士通と日立は、販売会社「ファコム・ハイタック」を設立し、教育機関への販売を担当した。1993年まで(営業は1992年まで)存続した。
富士通・日立は、汎用機Mシリーズを発表した。両社ともSystem/370を基本アーキテクチャとして採用した。富士通は11月20日にFACOM M-190を、翌年5月にFACOM M-160を、翌年9月にFACOM M-180IIを発表した。日立は11月にHITAC M-180を、翌年5月にHITAC M-170を、1977年2月にM-150を発表した。日立製作所神奈川事業所に保存されているHITAC M-180論理パッケージは、情報処理学会から2016年度情報処理技術遺産に認定された。
FACOM M-190は、Amdahl社と共同開発していたAmdahl 470V/6 (1975発売)をベースとしたものである。1号機は1976年4月27日、日本揮発油に納入される。。
日本のコンピュータ界初のパイオニアの一人、富士通の池田敏雄氏は11月10日羽田空港で倒れ、くも膜下出血のため11月14日亡くなられた。享年51歳。
4) 日本電気(μCOM-8、μCOM-16)
日本電気は1974年8月、Intel8080互換の8ビットプロセッサμCOM-8を発表した。ピン配置は異なる。また11月には、Intelより先にオリジナルな16ビットプロセッサμCOM-16を開発した。2チップで構成されている。
ネットワークの標準化
このころ、情報システムは分散処理型が急増し、コンピュータネットワークのアーキテクチャが重視されるようになってきた。そのためネットワーク・プロトコルの開発が進んでいる。
1) SNA
IBM社は、1974年9月にSNA (Systems Network Architecture)というプロトコルの体系とこれを実現するVTAM(Virtual Telecommunications Access Method) を開発した。これは、政府機関、銀行などのネットワークに広く使われた。
2) DCNA
IBM社のSNAに触発され、電電公社では1974年からDCNA (Data Communication Network Architecture)の研究が始められた。1977年4月、日本電気、富士通、日立、沖電気と共同して開発が進められ、1978年3月には論理構造・メッセージ転送を含む第1版を提案した。
3) TCP/IP
ARPANET関係では、1974年12月Vint CerfらによりTCP/IPの原型とも言うべきRFC 675が発表された。1975年には、Stanford大学とイギリスのUniversity College Londonの間で通信実験が行われた。1983年1月1日、ARPANETは完全にTCP/IPに切り替えられる。
標準化
1) 漢字コード
日本情報処理開発センターは、工業技術院の委託を受け、1974年、JIS漢字コードの開発を目指した漢字符号標準化調査研究委員会を設置した。森口繁一を委員長とし、3年計画とした。この結果、1978年1月1日にJIS C 6226-1978「情報交換用漢字符号系」が制定される。
性能評価
1) LINPACK
このころサブルーチンパッケージLINPACKの開発が始まり、FORTRAN 66で書かれた線形方程式の求解ソフトウェアが1974年に公開された。もちろんベンチマークではなく線形計算ライブラリとして開発した。1977年には次数100の方程式を用いてコンピュータの性能をMFlopsで評価したリストが公開される。たしか次数100ではコードの変更が許されず、as isでの測定が要求されたと思う。ライブラリだから当然であろう。ソフトウェアパッケージが完成したのは1979年であるが、当時のUsers’ Guideには、すでに17種のマシン上での性能値が示されている。
1986年には次数1000の方程式による性能評価が提案され、言語の制約がなくなり、チューニングが許された。
1991年にはLINPACK Table 3として、HPC (Highly Parallel Computing)が導入され、サイズも任意、アルゴリズムも任意(Gauss消去法の範囲で)となった。現在Top500で用いられているRmaxはこれである。
アメリカ政府関係の動き
1) CTRCC(後のNERSC)の設置
1974年、DOE (Department of Energy) は、LLLにCTRCC(Controlled Thermonuclear Research Computer Center, 制御核融合研究コンピュータセンター)を設置した。その後、NMFECC(the National Magnetic Fusion Energy Computer Center)と改名し、さらに1990年代初頭にNERSCと改名しその後Berkeleyに移った。当初CDC 6600を持っており、1975年10月にはCDC 7600を導入した。私が1986年7月25日に訪問した時には、Cray-1, Cray X-MP, Cray-2などが動いていた。ちょうど7600の撤去の最中で、ボードなどを持っていってもよいということで皆群がっていた。「ヨシオも持っていかないのか」と聞かれたが、あの警備厳重なLLLからどうやって持ち出せたであろうか。
中国の動き
1) 中国のコンピュータ
詳細は不明であるが、1970年代前半に中国で開発されたコンピュータを”Advances in Computer”から掲載する。試作か量産かも不明である。
|
年 |
機種 |
開発者 |
素子 |
Bit |
|
|
1970 |
111 |
CAS ICT |
IC |
48 |
|
|
1971 |
X2 |
Shanghai Institue of Computing Research |
|
42 |
科学技術用 |
|
|
TQ-11 |
Shagnhai Radio Factory No.13 |
IC |
36 |
データ処理 |
|
1972 |
709 |
Shanghai Institue of Computing Research |
IC |
48 |
科学技術用 |
|
|
TQ-16 |
Shagnhai Radio Factory No.13 |
|
48 |
709の改良型 |
|
1972 |
DJS-17 |
Beijing Telecom Factory |
IC |
24 |
汎用 |
|
1973 |
719 |
Fudan University |
IC |
48 |
大学では初 |
|
|
TQ-31 |
Shagnhai Radio Factory No.13 |
IC |
24 |
16個のI/O Channels |
CAS ICT = Chinese Academy of Sciences, Institute of Computing Technology
世界の学界
1) Dennardスケーリング
DRAMを発明したIBM社のRobert Dennardは、1974年のIEEEの論文で、MOSFETにおいて「トランジスタの寸法が小さくなっても面積当たりの消費電力はほぼ変わらない」というスケーリング則を提唱した。つまり、寸法がr倍になり、トランジスタ密度が1/r2倍となると、遅延がr倍になるのでクロック周波数が1/r倍になる。トランジスタ当たり、ゲートの静電容量がr倍となり、電圧もr倍で、消費電力がr2倍となるので、クロックが速くなり、トランジスタ数が増えても面積当たりの消費電力は変わらない、という魅力的な法則である。実際には、電圧には下限があり、リーク電流の問題も無視できなくなり、このスケーリングは2000年代半ばで成立しなくなった。
2) Ratfor
Bell研究所にいたBrian Kernighanは、1974年、FORTRAN66にはない現代的な制御構造を導入したratfor (rational fortran)を提案し、その処理系を開発した。処理系はratforで書かれ、出力はFORTRAN66プログラムである。1975年にSoftware—Practice & Experienceで発表した。1976年の本”Software Tools” (Kernighan and Plauger)(『ソフトウェア作法』木村泉訳、共立出版、1981年)で紹介されている。Fortran 77でいくつかの制御構造が導入されたので、これに対応して、ratforの改訂版ratfiv(rat-fourの次のrat-fiveという意味であろうか)も作られた。
3) Hyperplane法
Massachusetts Computer Associateds, Inc.(COMPASS、ソフトウェア会社)のLeslie Lamportは、”The Parallel Execution of DO Loops,” Comm. ACM 17, 2 (Feb., 1974), pp. 83–93においてHyperplane法を提唱した。ILLIAC IVのような限定された相互接続網の並列計算機において、依存関係のあるDOループをパイプライン実行が可能なように変形する方法である。筆者も、ベクトル計算機や並列計算機で大変お世話になった。Lamportは時間・空間を含む格子上の斜めの超平面を提案したが、空間だけの超平面法は、村岡洋一がUIUCに提出した博士論文(1971)で提案している。
なおLeslie LamportはLaTeXを含む多くの業績をあげ、2013年のチューリング賞を受賞する。
4) 格子ゲージ理論
Cornell大学のKenneth Wilsonは、1974年、ゲージ場を4次元の時空格子上に定式化することを提唱した。偏微分方程式の差分法と似ているが、格子上でもゲージ不変性を厳密に満たすことがポイントである。これに基づき、1980年にはMichael KreuzがMonte Carlo法で数値計算できることを示した。その後のスーパーコンピュータの多くの資源を占拠したQCD計算のはじまりである。なお、Kenneth Wilsonは1982年にノーベル物理学賞を受賞するが、これは相転移に関連した臨界現象に関する理論に与えられたもので、格子ゲージ理論は直接には関係していない。
国際会議
1) ISSCC 1974
第21回目となるISSCC 1974(1974 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1974年2月13日~15日にペンシルバニア州PhiladelphiaのMarriot Hotelで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE Philadelphia Sections、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はVirgil I. Johannes (Bell Labs)、プログラム委員長はHarold Sobol (Collins Radio)であった。会議録はIEEE Xploreに置かれている。
2) ARCS 1974
第3回目となるARCS 1974(Fachtagung Struktur und Betrieb von Rechensystemen)は、1974年3月20日~22日にドイツのBraounschweigで開催された。会議録はSpringer社からLNCS 8として出版されている。
3) IFIP Congress 1974
第6回目となるIFIP Congress 1974は1974年8月5日~10日にスウェーデンのStockholmで開催された。会議録は1974年、Information Processing 74, Proceedings of IFIP Congress 74のタイトルでNorth-Holland社から出版されている。
4) ICPP(第3回)
1974年8月20日~23日に、ニューヨーク州のAdirondack公園(Syracuseの北東約100km)にある、Raquette LakeのGreat Camp Sagamoreにおいて、第3回Sagamore Computer Conference on Parallel Processingが開催された。会議録はSpringer社からLNCS vol. 24 “Parallel Processing”(1975)と題して出版されている。翌1975年からはICPPと名付けられる。
この会議シリーズが最初からSagamore Computer Conferenceと呼ばれているところを見ると、第1回もここで開催されたのではないかと思われるが、確認は取れていない。Sagamoreはアメリカ北東部の先住民の酋長のタイトルのようである。Great Camp Sagamore近くに小さなSagamore湖がある。
アメリカ企業の動き
1) CDC社(STAR-100)
CDC社は、ベクトルコンピュータSTAR-100をLLL (Lawrence Livermore Laboratory、1981年からLLNL)へ2台とNASAのLangley研究所に1台納入した。4台目は1976年9月に自社のデータサービスCybernetに設置し、貯油層のシミュレーションなどに利用された。実効性能がCDC 7600の数倍程度にしか上がらず、後のCray-1に負けてしまった。納入先のLLLの部門は上に述べたCTRCCではないようである。
2) Data General社(Eclipse)
Novaに続き、1974年、16ビットミニコンピュータEclipseを発売したが、出荷が追い付かないほど売れたとのことである。同社の稼ぎ頭であったが、ワークステーションの性能が向上すると売れなくなった。
3) Motorola社(MC6800)
1974年、Motorola社(1928年創業)は、8ビットマイクロプロセッサMC6800を開発した。洗練されたアーキテクチャが魅力であった。16ビットのMC68000は1980年に出荷されることになる。
4) Intel社(Intel 8080)
Intel社は、1974年4月、8ビットマイクロプロセッサIntel 8080を発表した。これにはIntel社に出向していた嶋正利も関与している。8008を改良した後継プロセッサであるが、互換性はない。8080の命令は後に拡張(アドレス空間や乗算・除算命令など)され、Zilog社のZ80や日立製作所のHD64180に継承された。初期のPCの多くに採用された。
5) IBM社(テープロボットIBM 3850)
コンピュータの扱う情報量が急速に増大し、蓄積される磁気テープの数は膨大となり、磁気テープの人手による交換や保管の作業が問題となってきた。この問題を解決するため、IBMのBoulder研究所では、砲弾型の磁気テープカートリッジによる大容量記憶装置IBM 3850を開発した。1974年10月9日に正式発表された。記憶密度を増大させるため、回転ヘッドによるヘリカルスキャン方式を採用した。容量50MBのカートリッジ数千個を棚に収め、ロボットで記録再生装置に脱着する。1986年まで使われた。
6) NCR社
National Cash Register Corporationは、1974年、社名をNCR Corporationに変更した。
ヨーロッパ企業の動き
1) ICL社
1968年に設立されたイギリスのICL (International Computers Limited)社は、1974年10月、メインフレームとして仮想記憶方式のICL 2900シリーズを発表した。
企業の創業
1) Zilog社
1974年11月にIntel社を退社したFederico Fagginによって1974年5月、カリフォルニア州でZilog Inc.が設立された。嶋正利も1975年2月に加わった。1976年3月、Intel 8080の上位互換の8ビットプロセッサZ80を発売。1980年に一時 Exxon社の子会社となったが、1989年に再独立。1998年にTexas Pacific Groupによって買収された。
2) Tandem社
1974年、カリフォルニア州シリコンバレーのCupertinoにおいて、Jimmy TreybigによりTandem Computers, Inc.が設立された。目的はフォールト・トレラントな止まらない(NonStop)コンピュータを開発することである。1997年、Compaq社により買収された。
次回は1975年、Cray Research社はCray-1を発表する。同じ年、Microsoft社が設立される。ARPANETではTCP/IPの通信試験が行われ、日本では東大と京大の間でN-1ネットワークの接続実験が成功する。
(アイキャッチ画像:Star 100 出典:Computer History Museum)
 |
 |
 |

