HPCの歩み50年(第10回)-1975年-
小柳 義夫(神戸大学特命教授)
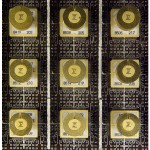
この年、Bill GatesらによりMicrosoft社が設立された。TCP/IPは前年Vint Cerfらにより提唱されたが、1975年、ARPANETを用いて、Stanford大学とUniversity College London 間で、2拠点間のTCP/IPの通信試験が行なわれた。日本でも、東大大型計算機センターの日立機と京大大型計算機センターの富士通機との間を電電公社のパケット通信網を使って実験的に接続された。これが初めてのN-1の接続であった。
日本では、3/10山陽新幹線が岡山・博多間開業、5/7エリザベス二世女王訪日、5/16田部井淳子エベレスト登頂、5/19東アジア反日武装戦線、一連の企業爆破事件で逮捕、7/19沖縄海洋博覧会開幕、8/4日本赤軍、クアラルンプールで2つの大使館占拠、超法規的措置で赤軍派5人を釈放、9/18新聞王の孫娘パトリシア・ハーストがFBIに逮捕される、11/26~12/3国鉄がスト権ストで8日間ほとんど運行停止、など。世界では、4/30南ベトナム政府崩壊、6/23メキシコで国際婦人年世界会議、11/15第1回サミット(フランス、ランブイエ)など。
筆者は、高エネルギー研にいたが、「PDG素粒子データグループ」に関する共同研究のため、9月に1ヶ月LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory)に滞在した。計算センターにはCDC6600が並んでいた。その時のカリフォルニア州知事はJerry Brownという人で、”Brown on Braun”(ブラウン管上のブラウン知事)という定期番組を持ち、盛んにテレビで情報発信をしていた。ずっと経ってから、2011年にまたジェリー・ブラウンという人が知事になったので、息子かなと思っていたが、なんと本人であった。このころカリフォルニアでは、ガソリンの値段がガロン(3.785 リットル)あたり1ドル(200円程度)を超えたというので大騒ぎであった。
1975年4月26日に、中川徹氏(当時、東大理学部化学教室助手)らとともに、SALSの開発を始めた。東大大型計算機センターの3階の1室はライブラリ開発者のための部屋であったが、隔週の土曜日に、そこを事実上占拠して開発作業を行った。当時は会話処理ではなく、80欄のパンチカードがベースであった。TSSも使ったが、修正は必ずカードに残した。翌年からは、統計関係の科研費の丘本班に加えていただき、財政的な援助を得た。1978年3月にSALS 1.0を公表、これを全面的に書き直して1979年9月にSALS 2.0を完成公表した。1982年11月にSALS 2.5を公表後、グループは解散し開発は停止している。
(後に赴任することになる)東京大学理学部情報科学科は1975年4月に学生定員15名で設立された。数年前から東京工業大学、京都大学などに情報関係学科が次々に新設され、東大でも1970年に理学部附属情報科学研究施設ができていた。
日本の動き
1) 数値解析研究会
自主的に企画している数値解析研究会(後の数値解析シンポジウム)の第5回は、1975年9月1日(月)~3日(水)に熱海の竜泉閣で開催された。参加者43名。
2) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所は、1975年10月30日~11月1日に、高橋秀俊(この年から慶應義塾大学)を代表者として「数値計算のアルゴリズム」という研究集会を開催した。第7回目である。報告は講究録No.269に収録されている。
日本の企業の動き
 |
|
| COSMOシリーズモデル500画像出典:一般社団法人 情報処理学会 Web サイト「コンピュータ博物館」 |
1) 三菱電機・沖電気
5月、三菱電機・沖電気は、中型コンピュータCOSMOシリーズモデル500を発表した。LSIを用い、仮想記憶方式を採用している。
2) 富士通
6月、Amdahl社は、富士通の製造したIBM互換470V/6の1号機をNASAに出荷した。
ネットワーク
1) ARPANET
ARPANETは、1969年にUCAL、Stanford、UCSB、Utah大の4ノードをつないだのが始まりであるが、当時のプロトコルはNCP (Network Control Program)であった。前回、1974年にTCP/IPの仕様が開発されたと書いたが、1975年、Stanford大学とUniversity College London 間で、2拠点間のTCP/IPの通信試験を行った。ARPANETが全面的にTCP/IPに切り替えられるのは1983年のことである。
2) N-1ネットワーク
日本でも新しい動きがあった。前に書いた特定研究「広域大量情報の高次処理」とも関係があると思われるが、N-1と呼ばれるネットワークの開発が進められていた。正式には大学間コンピュータネットワークと呼ばれる。1975年に、東大大型計算機センターの日立機と京大大型計算機センターの富士通機との間を電電公社のパケット通信網を使って実験的に接続された。これが初めてのN-1の接続であった。その後1980年頃までに多くの大学のセンターがつながった。当時は大型計算機の時代であった。ARPANETも当初は大学や研究所の大型計算機を結合していたのである。
1970年代に電子メールの利用が進んだARPANETとは異なり、N-1上の電子メールが可能になったのはずっと後で、主な利用形態はリモートログイン(当時の言い方ではNetwork Virtual Terminal)とリモートバッチ(同Remote Job Entry)であった。N-1ネットワークは異機種をつなぐという点で、また同一回線で複数の業務をサポートすると言う点で日本では画期的な試みであった。しかし、N-1からwebは生まれなかった。結局N-1は1999年末に「2000年問題」に対応できないためサービスを停止した。他方、ARPANETは現在のインターネットへと大きく発展した。
アメリカの企業の動き
1) Cray Research社
Cray Research社は、1975年、Cray-1を発表した。出荷は翌年である。
ベンチャー企業の創業
1) Microsoft社
1975年4月、Bill GatesらによりMicrosoft社が設立された。当初は、Altairコンピュータの上で動くBASICインタプリタの開発で始まったとのことである。
次回1976年、ついにCray-1がLLNLに納入される。
(タイトル画像 Amdahl 470V/6 Multi-Chip Carrier 画像提供:Computer History Museum)
 |
 |
 |

