新HPCの歩み(第68回)-1982年(c)-
|
Cray Research社は、Cray X-MP/2やCray-1Mを発表した。日本にも4台納入された。Denelcor社はHEPを出荷した。Intel社は16ビットマイクロプロセッサ80286を発表した。Sun Microsystems社、Compaq Computer社、Alliant Compute Systems社、Convex Computer社、Silicon Graphics社などのビッグネームがこの年創立された。 |
アメリカの企業の動き
1) Cray Research社(Cray X-MP/2、Cray-1M)
1982年4月26日、Cray Research社は、Cray-1の改良であるCray X-MP/2を発表した。開発責任者はLester Davis、主任設計者はSteve Chen(陳世卿)であった。2 CPUの共有メモリ並列ベクトル計算機で、クロックは9.5 ns、ピーク性能は420 MFlopsであった。メモリが16 MBのmodel 22と、32 MBのmodel 24とがある。Cray Research社はメモリをMW(8 MB)単位で表示する。外部記憶装置として新たにSSDを開発した(64 MB~256 MB)。出荷は1983年の予定。1984年には4 CPUのモデルCray X-MP/4が発表される。ピーク性能は840 MFlops。
一方、Cray-1Sの改良型として、Cray-1Mを1982年に発表した。クロックを83.3 MHzに上げ、主記憶にMOS RAMメモリを用いた。これらの日本への販売は以下の通り。
|
機番および納入年 |
納入先 |
機種 |
|
94) 1984 |
日本電信電話 |
Cray X-MP |
|
104) 1984 |
東芝 |
Cray X-MP |
|
121) 1985 |
日産自動車 |
Cray X-MP |
|
134) 1885 |
リクルート |
Cray X-MP |
2) IBM社(IBM 3083、IBM 3084)
IBM社は、1982年3月31日にIBM 3083(IBM 3081の下位モデル)を、9月3日に3084(IBM 3081の上位モデル)を発表した。
1969年1月に司法省が訴えていた独占禁止法違反の訴えは、1982年2月、コンピュータ市場が変化しIBM社が市場を独占しているとは言えないと司法省が判断して取り下げ、13年にわたる係争に終止符が打たれた。
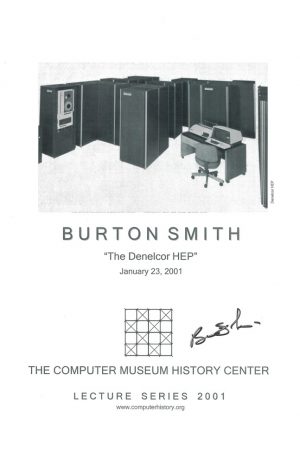 |
|
|
The Denelcor HEP |
|
3) Denelcor社(HEP)
Denelcor Inc.という会社がいつ創立されたのかは分からないが、研究開発担当副社長のBurton Smithらは1973年頃から新しいアーキテクチャのコンピュータを研究していたようである。その成果としてHeterogeneous Element Processor (HEP)が1982年に出荷された。マルチスレッディングを利用した画期的なアイデアにより、8個のプロセスを1個のCPUの上で同時に走らせることができた。合計8台が製造されたが、1985年10月にDenelcor社は閉鎖される。B. Smithは1988年同様なコンセプトに基づくTera Computer社を設立する。なお氏は2018年4月2日に死去した。
4) Hewlett-Packard社(HP 9000)
HP社は1982年、HP 9000シリーズの最初であるseries 520を発表した。OSとしてHP-UXを開発した。ただし、他のHP-UXと違い、series 500専用のSUNOS(Sun Microsystems社のSunOSとは無関係)の上に作られた。正式なHP-UXの始まりは、1984年にAT&T System IIIに基づいて開発されたHP-UX 1.0とされる。
5) Sperry社
1982年、UNIVAC 1100/90シリーズを発表した。1100/91から最上位の1100/94まで4モデルある。液冷で、最大4台のCPUと4台のI/O unitsを搭載できる。1100/90には、ISP(Sperry Intergrated Scientific Processor)を付加することができる。
6) Burroughs社
1982年末、Burroughs社は大型機B7900を発表した。主記憶容量が最大96 MBで、1プロセッサとしては最大規模。1台から5台まで拡張できる。NUMAアーキテクチャである。
7) NAS社
NAS (National Advanced Systems)社は、1982年4月、IBM4341-2対抗の自社製AS6130, 6150を発表した。5月には、日立製作所のM-280HのOEM販売で日立と合意し、M-280HベースのAS9060, 9080を発表した。9月には、IBM 3083B対抗のAS9040、3083J対抗のAS9050、3081K対抗の9070を発表した。
8) Intel社(80286)
1982年2月、Intel社は、16ビットマイクロプロセッサIntel 80286を発表し、1984年から出荷した。IBMのPC/ATやそのクローンのCompaqのPCなどに使われた代表的なCPUである。HPCとの関係では、iPSCなど並列コンピュータのプロセッサとしても使用された。IBM社はPCに搭載するCPUにセカンド・ソースを要求したので、1982年2月、Intel社はAMD社と8086セカンド・ソース契約を締結した。その後IBM PC/ATが爆発的に売れたため、Intel社では生産が追い付かず、AMD社の他、富士通、Siemens社などとセカンド・ソース契約を結んだ。
Intel社は、1982年12月、IBM社からの出資により80286生産のための設備投資を行う。IBM社はIntel社の株を12%取得。その後最大17%に達する。1987年8月には全額売却。
9) Motorola社(MC68010)
Motorola社は、MC68000に続いて、16/32ビットのマイクロプロセッサMC68010を1982年3月に発売した。仮想記憶と仮想マシンをサポートできる。
10) Microsoft社
Microsoft社は、1982年、IBMとの共同開発契約に基づき、IBM PC-DOSをIBM社以外のメーカにMS-DOSの名前でOEM提供を開始した。IBM PCの成功により、16ビットPCのデファクトスタンダードの地位を占めるようになる。MS-DOSが日本の雑誌に登場したのは、1983年2月号あたりからで、最初は日立のMB 16000や東芝のPasopia16が採用した。
ヨーロッパの企業の動き
1) ICL社
イギリスのICL社(International Computers Limited)は、1982年5月、富士通のM-380、382をAtlas10、25として発表した。11月には、IBM4341-10相当のパワーを持つ2957を発表した。
2) Nixdorf Computer AG (8890/30, 50, 70)
1982年2月、Nixdorf Computer AGは、米国国内市場でIBM 4331対抗の互換機Nixdorf 8890/30, 50, 70を発表した。
3) Inmos社(OCCAM, Transputer)
イギリス政府の援助のもと、1978年7月に設立されたInmos社は、1982年、次世代のコンピュータ言語としてOCCAMを発表するとともに、マルチプロセッサ構成を念頭においた革新的なマイクロプロセッサTransputerを開発中であると伝えられた。OCCAMはC.A.R. Hoare(Oxford大学)の提唱したCSP (Communicating Sequential Processes)に基づく言語であり、Hoare自身も開発に関与している。OCCAMという名称は、14世紀のOxfordの後期スコラ哲学者William Occamに由来し、簡潔性を象徴しているとのことである。Transputer T2やT4の仕様は、1983年11月に明らかにされる。
4) Bull社
フランスのBull社は、数々の買収や合併を経験してきたが、1982年国有化され、フランスの他のコンピュータ企業と合併された。1994年、Bull社は私企業に戻る。
企業の創業
この頃アメリカではコンピュータ・ベンチャーがまさに「雨後の筍(たけのこ)」のごとく登場しはじめた。1982年に登場した会社は以下の通り。後のビッグネームが並んでいる。
1) Sun Microsystems社
1982年2月、Andy Bechtolsheim, Scott G. McNealy, Vinod Khosla, William Nelson Joy (Bill Joy)らによって創立された。5月には10 MHzのMC68000を搭載したSun-1を発売した。日本では1982年11月、日商エレクトロニクスが輸入販売権を獲得した。創立から数年で世界企業に成長したが、2010年1月27日にOracle社により吸収合併された。
2) Compaq Computer社
1982年2月、Tesas Instruments社にいたJoseph Rodney Canion, Jim Harris, Bill Murtoの3人によって創立された。IBM PC互換のパソコンの製造で成功した。1984年ごろには、PC売り上げのシェアは、IBM社の39%、Apple社の28%に次いで、10%で業界第3位となった。Compaq社は1997年Tandem Computer社を買収し、1998年、Digital Equipment Corporationを買収した。しかし結局、2002年にHewlett Packard社によって吸収合併された。
3) Dataflow Systems社(Alliant Computer Systems社)
5月、SMP (Symmetric Multiprocessor)に基づく小型の科学技術計算用コンピュータを提供するために、Ron Gruner, Craig Mundie, Rich McAndrew の3人により、Dataflow Systemsの名前で創立された。比較的初期にAlliant Computer Systemsに社名を変更した。いわゆるミニスーパーコンピュータの走りである。1985年に発表されたAlliantの最初の製品FXは、MC68000にWeitek 1064/1065チップをFPUとして付加し、パイプライン的にデータ供給を行うためのハードウェアをもっていた(これをdataflowと呼ぶようである)。最大8並列。第二世代のFX (1988)では、Weitekチップの代わりにBipolar Integrated Technology社のFPUを用いた。1990年のFX/2800シリーズでは、Intel i860 というスーパースカラCPUを用いた。最後の製品は1991年に発表されたCAMPUS/800という超並列マシンであるが、1992年に倒産した。
筆者は1990年に筑波大学の予算で第二世代のFX(4プロセッサ)を購入したが、翌年東大に転任してしまった。その後、マシンを駆使した人の話では、思ったほど演算性能が出なかったとのことである。当時はFNHのベクトル計算機の最盛期であり、それと比べれば見劣りがしたのも無理なかった。
4) Convex Computer社
1982年、Bob Paluck と Steve Wallach が、Parsecという社名でテキサス州Richardsonに設立した。Cray Research社と互換のベクトル計算機C1, C2, C3などをCMOS技術により低価格で製造した。1993年に並列コンピュータ開発計画を発表し、翌年3月Exemplar SPPを発表したが、1995年9月Hewlett-Packard社に買収された。
5) Silicon Graphics社(SGI)
SGIは3次元グラフィックス・ディスプレー製造するためにStanford大学准教授だったJim Clarkによって1982年に創立された。2009年4月1日にChapter 11の保護を申請して倒産し、Rackable Systems社に買収され、同社はSilicon Graphics International社(ロゴは継承)を名乗った。
6) Adobe Systems社
HPCとは直接関係はないが、Adobe Systems社(2018年からはAdobe Inc.)が、1982年に、Palo Alto研究所にいたJohn WarnockとCharles Geschkeによって設立された。2人はページ記述言語Interpressを開発していたが、Xerox社がこれを商用化しようとしなかったので、独立を決意した。1985年にPostScriptを、1989年にPhotoshopを、1993年にPDFを開発した。なお、Geschke氏は2021年4月16日になくなられた。
次回は1983年、日本でも本格的なベクトルコンピュータの時代が始まる。同時に、筑波大ではPAX-128が製作される。お隣の中国では100 MFlopsのスーパーコンピュータ「銀河1号」が開発される。
(アイキャッチ画像:Delcor HEP 出典:Computer History Museum )
 |
 |
 |

