新HPCの歩み(第102回)-1991年(e)-
|
WOTUG 主催でSunnyvaleにおいてTransputing ’91が開催され、会議中にT9000の正式発表があったが、結局夢と消える。科研費島崎班は、九州でISS’91を開催する。Mannheim Supercomputer Seminar(後のISC)は会場を大学から市内のホテルに変えた。 |
国際会議
1) ISSCC 1991
第38回目となるISSCC 1991 (1991 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1991年2月13日~15日に、San Franciscoで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section、Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はW. Pricer (IBM)、プログラム委員長はJ. Trnka (IBM)であった。以下の基調講演、全体講演が行われた。
|
Microelectronics or Planetary Spacecraft |
R. Draper (Jet Propulsion Laboratory) |
|
The Future of The Notebook Computer |
S. Hiroe (Toshiba Corporation) |
|
Why We Need Design-for-testability |
E.J. McCluskey (Stanford Center for Reliable Computing) |
IEEE Xploreには会議録が置かれている。
2) CHEP 1991
高エネルギー物理学はコンピュータ技術の牽引役の一つであるが、1991年3月11日~15日、つくば市の高エネルギー研主催で、筑波大学大学会館において第5回目のCHEP (Computing in High Energy Physics)という国際会議が開かれ、筆者も手伝った。Proceedingsも発行されているが、CERN Courierの1991年9月号にかなり詳しい報告がある。実験のデータ処理、データベース、画像認識に関する話題が多いが、種々のシミュレーションの発表もあった。岩崎洋一(筑波大学)は格子QCD専用機(Columbia大、GF11、ACP-MAPS、APE、APE100、QCDPAX)について総合講演を行った。参加者272人中、所属で見ると、日本118名、米国35名、ソ連32名、スイス(CERNを含む)29名など15カ国に及んでいる。
写真は「世界規模のコンピュータ環境」に関する11人のパネル討論で、司会はTerry Schalk (UCIPP)である。Harald Johnstadは、テキサスのSSC研究所からビデオ会議リンクによりパネル討論に参加している(写真は上記CERN Courierより)。ビデオ会議とOHP (overhead projector)が共存しているのは面白い。高エネルギー分野では、実験グループの構成員が全世界に広がっているので、必要上ビデオ会議システムが早くから導入されていた。当時、ZoomはおろかWebさえない時代であった。
 |
3) PPSC 1991
5回目となるPPSC 1991 (the Fifth SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing)は、1991年3月25日~27日にテキサス州Houstonで開催された。SIAMから会議録が発行されている。
4) Transputing ‘91
WOTUG (World Occam and Transputer User Group)主催により、カリフォルニア州Sunnyvaleにおいて、1991年4月22日から26日まで開催された。Transputerを開発していたInmos社(1978年創業)は1989年4月にSGS-Thomsonに売却された後であるが、期待されていた新しいTransputerであるT9000の正式発表が会議中の4月24日午後行われた。クロックは50 MHz、64ビット浮動小数演算ユニットが内蔵され、ピークで200 MIPS、25 MFlopsの演算速度、シリアルリンクは100 Mb/sの通信速度と発表された。九州工業大学の鈴木裕がbit誌1991年12月号に報告を書いている。しかし、T9000の開発は遅れに遅れ、そのため他のRISCプロセッサに対する競争力が実現せず、ほどなく(時期は要確認)開発中止となる。T9000の利用を予定していた製品やプロジェクトは、計画変更や中止を余儀なくされた。
5) IPPS 1991
第5回目となるIPPS 1991 (The 5th International Parallel Processing Symposium)は1991年4月30日~5月2日にカリフォルニア州のAnaheimで開催された。委員長(組織かプログラムか不明)はV. K. Prasanna Kumarである。主催はIEEE/CSで、IEEEから会議録が出版されている。第4回以前については情報が得られなかった。
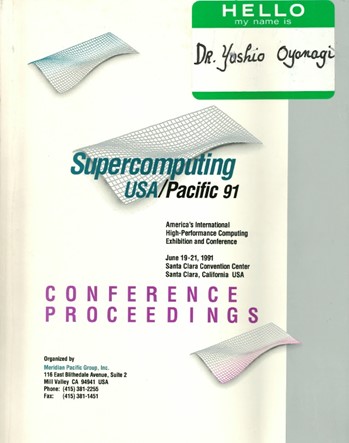 |
|
6) Supercomputing USA/Pacific 91
Supercomputing Japanを企画しているMeridian Pacificは、6/19-21に、カリフォルニア州Santa Clara Convention CenterでSupercomputing USA/Pacificを開催した。1回限りの会議であった。Proceedingsが出版されている(表紙写真)。基調講演はJ.R. Iversonによる“American High Technology’s Competitive Disadvantage”とN.H. Mansonによる“Global Technology Challenges and the Supercomputing Connection”であった。目に付く講演としては、G.C. Foxの“FortranD as Portable Software System for Parallel Computers”やH.D. Simonの“Massive Parallelism at NAS”など。日本からは、中田登志之(日本電気)らの“Dedicated Super-Simulators for Supercomputer/Superchips – A Struggle to Keep Up with the Designers’ Demands”や、姫野龍太郎(日産)の“Numerical Analysis and Visualization of Flow in Automobile Aerodynamics Development”など。
この会議でJohn Gustafson(Ames Lab.)も講演しているが、これが1986年にFPSを案内してくれたGustafsonとは気づかなかった。前述のJapan-US Workshop for Performance Evaluationで親しく会うのはこの2か月後の8月である。かれはちょうどSLALOM Benchmarkを完成したところであった。
この会議に出席する日本の企業関係者の訪米団(6/16-23)が組織され、どういうわけか筆者が団長を依頼された。17日SDSC訪問、18日UCB訪問とサンフランシスコ観光、19日~21日は会議、21日NASA Ames訪問というような行程であった。NASA Amesでは可視化について話を聞いたが、「遠隔ではどうするのか」と質問したら、「フィルムに撮って送ることもある」というようなことを言っていた。まだそういう時代であった。各訪問には日本人の通訳がついていたが、技術用語(たとえばi860など)には困ったようで、筆者が適当に助け船を出した。
訪米団参加企業は、東芝CAEシステムズ、東芝総合研究所、日本電気、日本経済新聞、三菱総合研究所、リクルート、富士通、三洋電機、住友電気工業など計10名であった。ガイド任せの楽しい団体旅行であった。
7) ICS会議
ICS (International Conference on Supercomputing)の第5回目が、1991年6月17日~21日にドイツのKölnで開催された。主催はACM SIGARCHである。ACMからプロシーディングスが発行されている。
8) Mannheim Supercomputer Seminar
1986年からMannheim大学内で開催されていたこの会議は、第6回目の1991年は大学からMannheim市内のHotel Wartburgに会場を移し6月20日~22日に開催された。設備は快適になったが、企業の展示参加料金はかなり高くなったのとのこと。以下の基調講演とパネル討論があった。
|
基調講演“Mikroprozessoren als Basistechnologie künftiger Computergenerationen”(次世代のコンピュータ基盤技術としてのマイクロプロセッサ) |
Georg Färber, TU München, Germany |
|
パネル“Supercomputing 1995 and Beyond — the Different Perspectives —” パネリスト:Steven Wallach (Convex), Justin Rattner (Intel), Carl W. Diem (Cray), |
|
基調講演の題名はドイツ語だが、講演もドイツ語か?アーキテクチャ関係では、BBN、MP-1、nCUBEなどに関する講演があった。
会議録“Supercomputer‘91: Anwendungen, Architekturen, Trends, Seminar”がSprinter社からInformatik-Fachberichte book series (INFORMATIK, volume 278)として出版され、14編の論文が掲載されている。内8編はドイツ語である。
9) ICPP’91
第20回目となるICPP’91 (1991 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL PROCESSING) 1991年8月12日~16日にイリノイ州St. CharlesのPheasant Run Hotelで開催された(Trier大学のdblpではテキサス州Austinとある)。パネル討論EVENING SUPER PANELが開催された。
|
テーマ: Toward Teraflop Computing |
|
パネリスト: Chris Hsuing, Cray Research, |
CRC Pressから3巻に分けて会議録が発行されている。
10) HOT CHIPS 3
1989年に開始された高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、第3回目のHOT CHIPS 3 (1991)を1991年8月26日~27日にStanford大学のMemorial Hall Auditoriumで開催した。基調講演はなかったが、夜7時30分から下記のEvening Panel Sessionが行われた。
|
Panel: Five Instructions Per Clock: Truth or Consequences |
Session Chairs: Alan Smith (UCB), John Mashey (MlPS) |
 |
|
11) Lattice 91
第9回となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 91)は、1991年11月5日~9日に高エネルギー研・筑波大・京大基礎物理研共催で、高エネルギー物理学研究所を会場に開催された。筆者は組織委員および募金委員長を務めていた。Lattice 91に対する企業からの募金は700万円を目標としたが、関係者のご尽力により600万円をいただくことができた。会議録はNuclear Physics B – Proceedings Supplements 26 (1992)として発行されている(写真)。
12) ISS’91
科学研究費総合研究島崎班『スーパーコンピュータの性能評価に関する総合的研究』は、91年から3年間の計画で始まった。年数回研究会を開くほか、国際シンポジウムISS’91(the International Symposium on Supercomputing 91)を11月6日~8日に九州大学国際ホールおよび福岡リーセントホテル(当時の九大箱崎キャンパス近く)で開催した。会議録は九州大学出版会から発行されている。『応用数理』には福井義成による報告がある。プログラムは以下の通り。
11月6日午前チュートリアル(九州大学国際ホール)。日本語で行われた。
|
9:10 |
「非構造格子データのボリュームレンダリング」 |
小山田耕二(日本IBM東京基礎研) |
|
9:35 |
「スーパーコンピュータS-820の動画像出力システムの概要について」 |
阿部仁(日立製作所、神奈川工場) |
|
10:00 |
“Scientific Visualization on CRAY Supercomputer” |
Shinichi Matsumoto, Kazunori Mikami (Cray Research Japan) |
|
10:25 |
Break |
|
|
10:45 |
「SX-3上のビジュアル・シミュレーション・システムSXview」 |
篠原明彦(日本電気、C&Cシステム技術本部) |
|
11:10 |
「可視化技術の応用と将来について」 |
中野守(日本DEC) |
|
11:35 |
「ビジュアリゼーションのためのコンピュータグラフィックス動画システム(CGMS)」 |
角文雄、恒川隆洋、A.Ogawa(富士通) |
11月6日午後(これ以降はリーセントホテル)
|
13:30 |
Opening |
K. Ushijima, M. Shimasaki |
|
13:35 |
Keynote Speech: Computational Science and Engineering |
E. Goto (Kanagawa Univ.) |
|
14:30 |
GRAPE: Special Purpose Computer for Simulations of Many-Body Systems |
T. Ebisuzaki et al. (Univ. Tokyo, Fuji Xerox) |
|
14:50 |
Using Abstract Interpretation to Detect Array Data Dependencies |
F. Masdupuy (CNRS URA, France) |
|
15:10 |
Dependence Analysis between Pointer Reference in Pascal |
A. Matsumoto, and T. Tsuda (Kyoto Univ.) |
|
15:50 |
Invited talk: Design and Implementation of a Vectorizing Compiler for the Block-Structured Language PASCAL |
T. Tsuda (Kyoto Univ.) |
|
16:20 |
Third Generation Message Passing Computer AP1000 |
H. Ishihata et al (Fujitsu Lab.) |
|
16:40 |
Fast Hardware-based Algorithms for Elementary Function Computations |
W. F. Wong and E. Goto (Riken) |
11月7日
|
9:00 |
Keynote Speech: Iterative Methods for Cyclically Reduced Non-Self-Adjoint Liner Systems |
G. H. Golub (Stanford Univ.) |
|
9:50 |
The Optoelectronic Multicomputer Project: A Semi-Dataflow Approach to Large-Scale Parallel Processing |
A. B. Ruighaver (Univ. Melbourne) |
|
10:10 |
Invited Talk: LAPACK: A Linear Algebra Library for High-Performance Computers |
J. Dongarra (U. Tennessee/ORNL) |
|
10:40 |
Coffee Break |
|
|
11:00 |
A Single-Chip Vector Processor Prototype Based on Streaming/FIFO Architecture |
T. Hironaka et al. (Kyushu Univ., Kyoto Univ.) |
|
11:20 |
A Multithreaded Processor Architecture with Simultaneous Instruction Issuing |
H. Hirata et al. (Matsushita Elec. Ind.) |
|
11:25 |
Hydra: A Resource-Shared Processor Architecture |
|
|
11:40 |
Supercomputing Pseudo Random Numbers – Proposals on Hardware and Software |
Y. Oyanagi et al. (Univ. Tokyo) |
|
12:00 |
Lunch |
|
|
13:30 |
Invited Talk: Parallel Computing and thePerfect Benchmark |
G. Cybenko (Univ. Illinois) |
|
14:00 |
Invited Talk: The Activities of the EuroBen Benchmark Group |
A. J. van der Steen (SARA) |
|
14:30 |
Coffee Break |
|
|
14:40 |
Six Benchmark Problems for Number Crunchers |
W. F. Wong et al. (Riken, Kanagawa Univ., Univ. Tokyo) |
|
15:00 |
Performance Evaluation of Mathematical Functions |
T. Nagai and Y. Hatano (Nagoya Univ. Chukyo Univ.) |
|
15:20 |
Benchmarking Vector Indirect Load/Store Instructions |
T. Uehara and T. Tsuda (Kyoto Univ.) |
|
15:40 |
Coffee Break |
|
|
16:00 |
Panel Discussion on Benchmarking Coordinator: Youichi Muraoka, Waseda University Panelist: Jack Dongarra, University of Tennessee and Oak Ridge George Cybenko, University of Illinois Yoshio Oyanagi, University of Tokyo Aad van der Steen, Academic Computer Centre Utrecht |
|
|
18:00 |
Party |
|
11月8日
|
9:00 |
Vector Processing in Symbolic Determinant Expansion on Supercomputer |
H. Murao (Univ. Tokyo) |
|
9:20 |
Supercomputing for Numerical Cascade Tunnel |
M. Furukawa and M. Inoue (Kyu shu Univ.) |
|
9:40 |
Parallel Image Generation for Visual Simulation |
I. Oyake et al. (Oki Electric) |
|
10:00 |
A Parallel Rendering Machine for High Speed Ray Tracing |
O. Gwun et al. (Kyushu Univ. Kyoto Univ.) |
|
10:20 |
Coffee Break |
|
|
10:40 |
Experiments and Analysis toward Distributed Supercomputing on a Distributed Workstation Environment |
B. Apduhan et al. (Kyushu Inst. Tech.) |
|
11:00 |
Vector Algorithm for Manipulating Boolean Functions based on Shared Binary Decision Diagrams |
H. Ochi et al (Kyoto U, Osaka U.) |
|
11:20 |
SPICE3: A Program for Simulating Integrated Circuits on Hypercubes |
P. S. Pacheco et al. (Univ. San Francisco) |
|
11:40 |
Lunch |
|
|
13:30 |
Invited: The Use of BiCG-STAB for Unsymmetric Linear Systems |
H. A. van der Vorst (Univ. Utrecht) |
|
14:00 |
Visualization of Convergence Behavior of BiCG-STAB Method |
S. Fujino and M. Mori (Inst. Comp. Fluid Dynamics, Univ. Tokyo) |
|
14:20 |
Highly Efficient Basic Numerical Software for Supercomputers |
K. Geers, and W. Walde (Univ. Karlsruhe) |
|
14:40 |
HIDM, A New Numerical Scheme to Solve Partial Differential Equations |
T. Watanabe (National Inst. Fusion Science) |
|
15:00 |
A Theoretical Stability Analysis for a Family of Convection Diffusion Difference Schemes using the Supercomputing Environment |
S. Nagoya and T. Ushijima (Univ. Electro-communications) |
|
15:20 |
Coffee Break |
|
|
15:40 |
Invited Talk: Language Features for Concurrent Programming |
K. Araki (Kyushu U.) |
|
16:10 |
Invited Talk: Solution of sparce linear equations on supercomputers |
I.S. Duff (Rutherford Appleton Lab./ CERFACS) |
|
16:40 |
Performance Evaluation Using Random Number Generator and Ising Monte Carlo Simulation |
N. Ito and Y. Kanada (JAERI Univ. Tokyo) |
|
17:00 |
Streamlined Access for Indirect Addressing of an Array |
M. Ohta and T. Maeno (Tokyo Inst. of Tech.) |
|
17:20 |
Closing |
|
前述のように、11月5日~9日には高エネルギー研主催で格子QCDの国際会議Lattice 91を開催しており、福岡にはとんぼ返りで出かけて参加した。
 |
|
 |
13) SC 91
第4回のSCは、1991年11月18日~22日にニューメキシコ州のAlbuquerqueで開催された。筆者は、東大に移ったばかりで時間の余裕がなく出席できなかったが、この回から会場のネットワークSCinetが用意されている。全参加者4442人、technical registrationは1711人。この年から、technical registrationが設定され、展示のみの参加と区別された。展示は80件。写真は展示会場。(SCXY Photo Archiveより)
日本からの論文発表(共著を含む)は以下の4件である。
|
Margaret L. Simmons, Harvey J. Wasserman, Olaf M. Lubeck, Christopher Eoyang, Raul Mendez, Hiroo Harada, Misako Ishiguro: |
A performance comparison of three supercomputers: Fujitsu VP-2600, NEC SX-3, and CRAY Y-MP. |
|
Hiroyuki Hirayama, Miiko Ikeda, Nobutoshi Sagawa: |
Solution functions of PDEQSOL (Partial differential EQuation SOlver language) for fluid problems. |
|
Yuetsu Kodama, Shuichi Sakai, Yoshinori Yamaguchi: |
Load balancing by function distribution on the EM-4 prototype. |
|
Yasusi Kanada: |
A method of vector processing for shared symbolic data. |
電子版の会議録はIEEE Xploreに収録されている。
前に述べたように、SC‘91での大きな出来事は、HPF (High Performance Fortran)が提案され、HPF Forumが始まったことである。また、D. H. Baileyらは、The NAS Parallel Benchmarksの構想を発表し、予備的なデータを示した。
14) AP1000 Workshop
富士通研究所は、1991年7月に並列処理研究センターを開所していたが、1991年11月28日~29日に、オーストラリアCanberraのANU (Australian National University)において、the Second Fujitsu-Australian National University CAP (AP1000) Workshopを開催した。この時までに、ANUにはAP1000が設置されていた。第1回は1990年11月に開催されたようであるが詳細は不明。Kahanerの報告によると、第2回のプログラムは下記の通り。
|
Paper Session 1: Hardware and Systems |
|
|
Low-Latency Message Communication Support for the AP 1000 |
T. Shimizu, T. Horie and H. Ishihata (Fujitsu Labs) |
|
All-to-All Personalized Communication on Wrap-around Mesh |
T. Horie and K. Hayashi (Fujitsu Labs) |
|
Paper Session 2: Software Tools and Compilers |
|
|
Developing Monitoring and Debugging Tools for the AP 1000 Array Multiprocessor |
C. W. Johnson, P. B. Thistlewaite, D. Walsh and M. Zellner (CS Dept, ANU) |
|
Parallel Loop Code Generation for the AP 1000 |
Gavin Michael and Peiyi Tang (CS Dept, ANU) |
|
Data Parallelism on MIMD Machines |
T. Bossomaier (CS Lab, ANU) |
|
Paper Session 3: Linear Algebra |
|
|
Parallel Direct Solution Method of Sparse Linear Systems and its Evaluation on AP 1OOO |
K. Motegi and S. Watanabe (U of Electro Communications, Japan) |
|
The LINPACK Benchmark on the AP 1000: Preliminary Report |
R. P. Brent (CS Lab, ANU) |
|
The Implementation of BLAS level 9 on the AP 1000: Preliminary Report |
P. E. Strazdins and R. P. Brent (CS Lab/Dept, ANU) |
|
Singular Value Computation on the AP 1000 |
A. Czezowski and P. E. Strazdins (CS Dept, ANU) |
|
Paper Session 4: Applications |
|
|
Application of Parallel Computer to Protein Engineering |
H. Iwama, S. Kawakita, M. Saito, H. Sato, Y. Tanaka, S. Tsutsumi and H. Yoshijima (Protein Engineering Res Inst, and Fujitsu Ltd) |
|
Parallelization strategies for MD simulations on the AP 1000 |
D. Brown and J. H. R. Clarke (Chem Dept, Manchester UK) |
|
Parallelization of the Monte Carlo Code MCACE for Shielding Analysis and Measurement of Parallel Efficiency on AP 1000 with 64 Cell Processors |
M. Takano, F. Masukawa, Y. Naito, A. Kawazoe and M. Okuda (Japan Atomic Energy Res Inst, and Fujitsu Ltd) |
|
Paper Session 5: Hardware, Systems and Visualization |
|
|
Performance Evaluation of the AP 1000 |
H. Ishihata, T. Horie, T. Shimizu and S. Kato (Fujitsu Ltd) |
|
Connecting AP 1000 with Mainframe: Application to Experimental HEP Computations at KEK |
S. Ichikawa, N. Ishida, S. Yamaki, T. Matsuura, A. Manabe, K. Amako, H. Fujii, S. Ichii, R. Itoh, A. Miyamoto, Y. Takaiwa and Y. Watase (Fujitsu Ltd, Facom-Hitac Ltd, and Japan Nat Lab for High Energy Physics) |
|
Scientific Visualization Algorithms on the AP 1000 |
P. Mackerras (CS Dept, ANU) |
|
Paper Session 6: File Systems, Software and Applications |
|
|
Implementation and Performance of the Acacia File System |
B. M. Broom (CS Dept, ANU) |
|
High Speed Search of Large Text Bases on the Fujitsu AP 1000 |
D. Hawking (CS Dept, ANU) |
|
Implementation of C-Linda for the AP 1000 |
R. Cohen and B. Molinari (CS Dept, ANU) |
|
PARACS: A Highly Parallel Circuit Simulator |
J. Niitsuma, K. Teramae, T. Kage, S. Shimogori and Y. Izuta (Fujitsu Ltd) |
|
Paper Session 7: Applications |
|
|
Particle Simulations Using Monte Carlo Method |
M. Okuda, M. Fujisaki, K. Watanabe, A. Kawazoe, M. Yokokawa, H. Yamamoto, H. Kaburaki, S. Inawashiro and F. Matsubara (Fujitsu Ltd, Japan Atomic Energy Res Inst, and Dept of Applied Physics Tohoku Univ Japan) |
|
QCD Lattice Monte Carlo Simulations on Cell Array Processor AP 1000 |
K. Akemi, Ph. de Forcrand, M. Fujisaki, T. Hashimoto, H. C. Hege, S. Hioki, J. Makino, 0. Miyamura, A. Nakamura, M. Okuda, I. 0. Stamatescu, Y. Tago and T. Takaishi (Fujitsu Ltd, ETH Zurich, Dept of Applied Physics Fukui Univ Japan, ZIB Berlin, Dept of Info Management Anan Coll Tech Japan, Dept of Physics Hiroshima Univ, FEST Heidelberg and Inst for Theoretical Phys Heidelberg) |
|
Combinatorial Optimisation on the AP 1000 |
K. Malysialc and B. D. McKay (CS Dept, ANU) |
|
Panel Discussion: The Future of Distributed-Memory Parallel Computers |
|
|
R. Brent (chair), T. Gojobori, M. Ishii, H. Kasahara, Y. Muraoka, R. Stanton and S. Tomita (CS Dept ANU, Nat Inst Genetics Japan, Fujitsu Ltd, CS Dept Waseda Univ Japan, CS Dept Kyoto Univ Japan) |
|
15) ParCo91
第4回のParCo (その後International Conference on Parallel Computing)であるParCo91がイギリスのLondonで開催された。この会議は1983年から奇数年にヨーロッパ各地で開催されているが、1987年は開催されなかった。日程はよくわからない。
世界の企業の話は次回。TMCが華々しくCM-5を発表したが、筆者は行く末を危ぶんだ。ConvexはGaAsを用いたベクトルコンピュータC3を登場させたが、時代は高性能な汎用プロセッサに移りつつあった。
 |
 |
 |


2件のコメントがあります
著者です。この記事に掲載したISS’91のプログラムは、準備段階のものでした。主催者の一人である島崎眞昭氏から正しいプログラムをいただきましたので、8月12日に差し替えました。
著者です。公開当初の記述では、CHEP91を高エネルギー物理学研究所で、Lattice91を筑波大学で開催したと書きましたが、これが逆であることが判明したので修正しました。記憶はかくもアヤシイものです。