提 供
HPCの歩み50年(第21回)-1984年-
日本の大学の研究者は、やっと数百MFlopsのスーパーコンピュータを使えるようになった。前年10月の東大に続いて、4月にはVP-100が京都大学大型計算機センターに設置された(翌年VP-200に更新)。またこの年、村井純等がJUNETの実験を開始し、日本の高エネルギー物理学の研究機関をつなぐHEPnet-Jの運用も始まった。日本でも遅まきながらネットワーク時代の幕開けである。アメリカではコンピュータ・ベンチャーの企業が相次いだ。CPUではMIPS Computer Systems社が、Hennessyを中心に設立された。また、このころ世界中でいくつかのQCD専用並列コンピュータを開発するプロジェクトが始まっている。
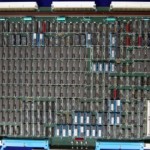
この年の社会の出来事は、1/1 AT&T分割、1/10アメリカとバチカン、外交関係樹立、1/19九州から関東まで大雪、1/26週刊文春「疑惑の銃弾」連載開始、2/8サラエボオリンピック開幕、2/15電気通信事業法成立(通信自由化)、3/5都はるみ引退宣言「普通のおばさんになりたい」、3/18グリコ・森永事件はじまる、4/1東京芝浦電気が東芝に社名変更、6/1第二電電企画創立、6/15エリマキトカゲ初来日、7/11松山事件無罪判決、7/25北朝鮮帰還事業終了、7/28ロサンゼルスオリンピック開幕、9/14長野県西部地震、9/19自民党本部放火、10/25コアラ到着、10/31インド首相インディラ・ガンジー暗殺、11/1新札3種類(福沢諭吉一万円札など)発行、11/6アメリカ大統領選挙、ロナルド・レーガン再選、11/16東京世田谷電話ケーブル火災、電話網麻痺など。
日本の学界の動き
1) 情報処理学会「数値解析研究会」
ベクトル計算機について、「京都大学大型計算機センターのベクトル計算機システムFACOM VP100とある種の線形計算ライブラリのベクトル化について」(島崎眞昭、京大大型センター)と「スーパーコンピュータS-810の応用性能」(唐木幸比古、東大大型センター)の発表があった。あわせて、並列コンピュータによる数値解析としては初めての発表「並列計算機PAXによる数値解析」(星野力、筑波大学、川合敏雄、慶応大学)がなされた。
2) 数値解析シンポジウム
1972年から自主的に開いていた研究集会「数値解析研究会」は、この回から「数値解析シンポジウム」と名称を改めた。回数は通しで数えている。上記の情報処理学会の研究会と区別するためであろう。第13回数値解析シンポジウムは、1984年6月7日(木)~9日(土)に愛知県民の森「森林学習館」で開催された。参加者は120名。
3) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所は、1984年11月29日~12月1日に、伊理正夫(東大)を代表者として「数値計算の基本アルゴリズムの研究」を開催した。第16回目である。報告は、講究録No. 553に収録されている。並列計算関係では、電総研の関口智嗣、島田俊夫がSIGMA-1によるモンテカルロ法について発表している。
それとは別に、「数論の数値解析への応用」という研究集会が一松信を代表として、5月31日から6月2日に開催され、筆者は大規模モンテカルロ・シミュレーションにおける乱数生成の問題について論じた。報告は講究録No. 537に収録されている。
4) PAX-32J
星野力等は、DC J-11をCPU として用いた新しい並列コンピュータPAX-32Jを製作した。新技術開発事業団(JSTの前身の一つ)の委託を受け、三井造船が製造を担当した。最初は64並列を計画したが、二つに分け、半分は慶應義塾大学に設置した。
 |
|
|
神戸大学 PEKマシン (画像提供:神戸大学) |
5) Prolog/ LISP マシン
数値計算用ではないが、5月には神戸大学でPrologマシンPEKが製作され、後藤英一(理研/東大)は数式処理用計算機FLATSを開発し、富士通はLISPマシンFACOM αを発表した。
日本のネットワーク
1) JUNET始まる
画期的なことは、村井純等がJUNETの実験を開始したことである。このときはインターネットではなく、電話回線をつかったUUCP接続であった。9月に接続したのは東京工業大学と慶應義塾大学であり、10月からは東京大学も接続。その後、どういうわけか筆者はJUNET-adminに加わり、ドメイン名割り当ての議論などに加わった。当時のトップドメインは.jpではなく、.junet であった。
2) HEPnet-J
このころ、日本の高エネルギー物理学の研究機関をつなぐHEPnet-Jの運用が始まった。KEK(高エネルギー物理学研究所)、東教大、農工大、京都大、広島大、名古屋大、中央大がNTTパケット網(9600 bps)で結合。プロトコルはDECnetを用いていた。翌年、VENUS-P国際パケット網(9600 bps)で海外と結合。1986年には日本とアメリカが9600 bpsの専用回線で接続。1990年56 Kbpsに増強。
日本の企業の動き
1) 富士通・日立のスーパーコンピュータ
富士通関係では、1月に名古屋大学プラズマ研究所でVP-100が稼動したのに続いて、4月にはVP-100が京都大学大型計算機センターに設置された(翌年VP-200に更新)。東大のHITAC S810/20に続いて、日本にも本格的なスーパーコンピュータ時代が到来した。メインフレームと互換性のある、ベクトル処理によるスーパーコンピュータと言う点では同じであるが、アーキテクチャ的には違った特徴を持つ。
S810/20の主要部は8本のベクトル演算器(演算パイプと呼ばれる)である。4本は加算器(論理演算を含む)、4本は乗算器+加算器という構成になっていて、それぞれが独立に動く。一種のデータフローのような処理を行う。14nsに最大12 浮動小数演算を実行することができ、ピーク性能は850 MFlopsである。他方VP-100/200では、機能的には1本の加算パイプと1本の乗算パイプであるが、中では複数の演算器が並行に動き、今の言葉でいう要素並列を実現している。ベクトル命令では今で言う「アウトオブオーダ」実行を実現していた。
ベクトルレジスタは、S810では256語(64ビット)の固定長のレジスタがmodel 10では16個、model 20では32個設置されている(アクセス時間40 nsの1KbバーポーラRAMを使用)。VP-200では、64 KB(8192語)のレジスタを、1024語×8や256語×32などダイナミカルに再構成することができる。VP-100では半分である。Cray Researchのマシンでは普通の論理素子でベクトルレジスタを実装していたが、日本ではメモリデバイスで実現したので、大きな容量のベクトルレジスタを持つことができた。
主記憶についても、当初のCray X-MPが16MBを上限としていた(1984年のX-MP/48でも64MB)のに対し、VP-200でもS810/20でも最大256MBまで搭載することができた。前回述べたように、東大のS810/20では当初64MBであったが、その後256MBに増強した。
世界の学界の動き
1) Gauge Theory on a Lattice
スーパーコンピュータの普及とともに、格子ゲージ理論の数値シミュレーションが世界中で行われるようになった。1984年4月5~7日に表記の国際ワークショップがアメリカのANL (Argonne National Laboratory)で開催された。最初は単発の会議のつもりだったかも知れないが、その後、類似のタイトルの会議が場所を変えながら毎年開催されるようになった(1985年には2回)。次第に格子ゲージ理論の分野の中心的国際会議に発展し、International Symposium on Lattice Field Theoryとして現在まで継続的に世界各地を廻って開催されている。1991年にはつくばで開催され、筆者も組織委員および募金委員を務めた。2015年6月には神戸で第33回が開催される。
世界の企業の動き
1) Cray Research社
日本クレイは、1980年に日本にCray-1を2台販売したが、その後しばらく売れなかった。1984年になって、8月にNTTにCray X-MP/22を、11月に東芝にCray X-MP/22を設置した。ただし東芝は諸般の事情によりCrayのスーパーコンピュータを保有していることを公表しなかった。
 |
|
| VAX8600 CPU | |
 |
|
| Apple Macintosh | |
 |
|
| MIPS R3000 | |
| 上記3画像出典:Computer History Museum |
2) DEC社
Digital Equipment Corporationは、1984年10月、ミニコンピュータVAX 8600を出荷した。これはVAX-11/785の後継機であり、もともとVAX-11/790と呼ばれていたが、発表前にこの名前に変えた。1986年1月にはVAX 8800やVAX 8700が登場する。
3) IBM
IBM社は、1984年8月14日IBM PC/ATを発売した。CPUはIntel 80286、メモリは256KB~16 MBであった。
4) Apple Computer社
1月24日、Apple Computer社(1977創立)は、初代Macintoshを発売。
5) Motorola社
1984年、Motorola社(1928年創業)が32ビットのMC68020を出荷した。
6) M-13 (ソ連)
Wikipedia(ドイツ語版)等によると、1984年、モスクワの計算科学研究所で2.4 GFlops(低精度の複素数演算らしい)のマルチプロセッサ・ベクトル計算機M-13が作られたとのことである。製作したのは、ウクライナ(当時はソ連の一部)の技術者Mikhail A. Kartsevである。かれは1950年ごろからソビエトのコンピュータ製作に関係しており、M-1、M-2、M-4、M-9、M-10など種々のコンピュータを設計製作している。今回初めて見つけたが詳細は不明(参照画像)。
ベンチャー企業の創立
アメリカではベンチャーの創立が続いている。
1) Multiflow Computer社
1980年代初期に、Yale大学のJosh Fisherは、通常のプログラミング言語で書かれたプログラムを水平型マイクロコードに変換するコンパイラを研究していた。1984年4月、FisherはYale大学を離れ、VLIWに基づくミニスーパーコンピュータを開発するために、Multiflow Computer社をコネチカット州New Havenにおいて創立された。Multiflowは1988年頃からTRACEシリーズというミニコンを販売した。1990年3月に活動を停止するまでに、125台のミニスーパーコンピュータを、アメリカ、ヨーロッパ、日本に販売した。
2) MIPS Computer Systems社
1984年、MIPS Computer Systems社が、Stanford大学のJohn L. Hennessyを中心とする研究者によってRISC CPUチップの設計製造会社として創立された。MIPSの語源は計算速度の単位ではなく、“Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages”の省略形である。最初のチップR2000は1986年1月に発表され、後継のR3000は1988年6月に発表された。SGI社は、1987年にIRIS-4DシリーズにおいてMotorolaに代わってMIPSのマイクロプロセッサを使用し始めた。1992年、SGI社に吸収され、MIPS Technologiesという子会社となった。アーキテクチャは他社にもライセンスしている。MIPSチップやMIPSアーキテクチャは組み込みシステムに広く用いられているが、サーバやHPC分野では、SGIの他、NECのEWS4800, UP4800やCenju-3/4、Concurrent Computer、Pyramid Technologyなどで使われている。また、中国がMIPSアーキテクチャに基づいたCPU(Godson、別名は龍芯 Loongson)を開発している(2002以降)ことも知られている(後述)。
3) Cydrome社
Cydrome社は、1984年、San Jose, CaliforniaにおいてBob Rauらによって創立された。目的はVLIWによって並列数値計算を実現することであった。今で言うsoftware pipeliningである。翌年のPresident’s Day(2月の第3月曜日)にCalifornia州Santa Clara郡のMilpitasに移転した。1987年、Prime Computersから出資を受け、Cydra-5を開発した。1988年、Prime ComputerはCydromeを買収しようとしたが、これに応じなかったので活動を停止した。
筑波大は1992年頃CP-PACSのためにslide window (一種のsoftware pipelining手法)を開発したが、このときCydromeに似ているという話があり、初めてこの会社の名前を知った。IntelのItaniumのrotate命令もこれに似ている。
4) Guiltech Research Company, Inc.
消えたコンピュータ・ベンチャーとして名前だけはよく出てくるGuiltech社は、Peter GuilfoyleによりSanta Claraで、いつの頃かに設立された。はじめ、光で相互接続したsystolic arrayを作ろうとしていたが、後に光を諦め通常のシリコン技術に変更した。2台ほど製造され、JPLなどにテスト用に出荷されたらしい。オリジナルのアイデアを記述したPeter S. Guilfoyle, “Systolic Acousto-Optic Binary Convolver” Opt. Eng. 23(1), 230120 (Feb. 91, 1984) という論文があるので、会社の設立はこれより前であろう。
後にSAXPY社と名前を変更した。その後の運命は不明。
5) Cisco Systems
ネットワーク機器の製造会社である Cisco Systems Inc.は、1984年12月、Stanford大学のLeonard BosackとSandy LernerによってSan Joseで設立された。
6) 聯想集団 (Legend)
中国でも新会社が設立された。11月、中国科学院計算機研究所の11名の研究員が「中国科学院計算所新技術発展公司」を設立した。1988年、香港連想集団公司、1989年北京聯想計算機集団公司を設立。聯想集団はLegendというブランドを使用していたが、2003年4月、商標および英語社名をLenovoに改めた。「新しい(novo) Legend」を意味するのであろう。2004年12月、Lenovo社はIBMからPC部門を買収することを発表し、世界を驚かせた。そればかりか、2014年1月23日、Lenovo社はIBMのx86サーバ事業を買収すると発表しさらにびっくりさせた。
Lenovo社はスーパーコンピュータも製作している。例えば、2008年11月のTop500において、Lenovo社製のDeepComp 7000(中国互聯網絡信息中心、北京)は、102.8 TFlopsで19位を獲得している。
量子色力学専用機
このころいくつかのQCD (quantum chromodynamics, 量子色力学)専用並列コンピュータを開発するプロジェクトが始まっている。ほとんどの性能は32ビット演算の数値である。
1) Columbia University
ニューヨークのColumbia大学では、Norman Christを中心としてマシンを開発している。ノードは、Intel 80286/287とTRW社製の22ビットDSPと1 MBのメモリから成り、全体は16ノードで256 MFlopsである。完成は1985年。その後、1987年には、Weitekチップを用いて、64ノードで1 GFlopsのマシンを完成した。1989年には、256ノードで16 GFlopsのマシンを完成している。
2) APE Project
Rome大学では、INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 国立原子核物理学研究機構) の協力のもと、QCD計算のためのAPE (Array Processor Experiment、「アペ」) プロジェクトを推進していた。初代のマシンは、1984年頃はじまって1988年に完成したAPEで、3081/Eプロセッサ(IBMの3081のエミュレータ)がドライバ。Weitekチップ12個(WTL1066 (register file)×4、WTL1032 (multiplier)×4、WTL1033 (adder)×4)を組み合わせたノードは、複素数のmultiply-and-addを64 MFlopsで実行する。16個のノードを1次元のループに接続しSIMDとして駆動する。このSIMDは命令のみならずアドレスも同一である。QCDはステンシル計算なので、これで十分というわけである。
次のAPE100 (APE cento) は、1989年に開発が始まり1994年に完成したが、これは2048個までのノードを3次元隣接接続したマシンで、ピーク100 GFlopsである。
APEmilleは1995年から2000年にかけて開発し、1 TFlopsのピーク性能をもつ。
3) GF11
IBMのWatson研究所のDon Weingartenは、GF11プロジェクトを1984年に始めた。これは576個のWeitekチップをSIMDで稼動するもので、名前の通りピークで11 GFlopsの性能である。SIMDと言ってもAPEとは違い高機能のスイッチを持っている。
4) ACPMAPS
アメリカの高エネルギー研究所であるFermi国立研究所ではQCDのためにACPMAPSプロジェクトを1987年に始めた。これはMIMDで、ノードは20 MFlopsのWeitek XL-8032チップを持つ。1989年に16ノード、1991年に256ノードを製作。改良型(1993年)はノード当たりi860を2個使い、306ノードで50 GFlopsのピーク性能をもつ。
5) QCDPAX
筑波大のこのマシンについては後述。
次回は1985年、世界中でベクトルコンピュータの性能は上昇を続ける。同時に、日米の性能競争が貿易摩擦にまでこじれることになる。IntelはやっとiPSC/1により並列市場に参入する。Meikoも創立される。
(タイトル画像 PAX-32J 画像提供:筑波大学計算科学研究センター)
 |
 |
 |

