新HPCの歩み(第123回)-1994年(e)-
|
Shorは、量子コンピュータを用いれば整数の素因数分解が多項式時間で解けることを証明した。アジア太平洋地区をベースとする国際会議HPC Asiaの計画が進む。6月のTop500では米国SNLのParagon XP/S140が日本のNWTを抜いてトップを奪還した。1985年から慶応義塾大学で開かれてきたPCGシンポジウムは、10回目として国際シンポジウム PCG’94を開催する。 |
世界の学界の動き
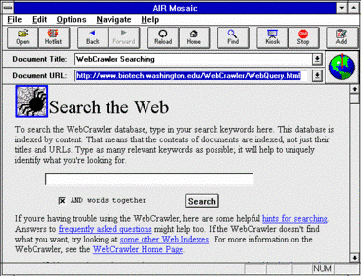 |
|
1) NCSA Mosaic
NCSAはMosaicのコードを無料ではあるが、制限付きで多くの会社に与えた。1993年には、Amdahl社、富士通、InfoSeek社、Quadralay社、Quarterdeck Office Systems社、Santa Cruz Operation社、SPRY社、Spyglass社などがライセンスを保有していた。1994年8月26日に、SPRY社は最新のMosaicであるAirMosaicを出荷した。図はその表示画面(Wikipediaから)。AirMosaicは、1994年、Datamation誌のBest Product of the Year賞を受賞した。
2) DNA 計算
Leonard Adleman (Univ. of Southern California)は、1994年、DNAを用いて7点のHamilton経路問題を解いた。DNA計算の嚆矢と言われている。
3) Shor’s Algorithm
1994年、Bell研究所にいたアメリカの数学者Peter Shorは、量子コンピュータを用いれば、整数の素因数分解が多項式時間(整数の桁数の多項式)で解けることを証明した。これに対し、1998年の第23回International Congress of Mathematiciansにおいて、Nevanlinna Prizeが授与される。1999年にはGödel Prizeを受賞。2003年からはMIT教授。
4) Fermatの最終定理
1994年10月7日、Andrew WilesによってFermatの最終定理が証明された。10月24日、Wilesは2件の論文をAnnals of Mathematicsに投稿したが、論文は1995年2月13日に査読を通過し、1995年5月に掲載される。
5) 33番目のMersenne素数
1994年1月4日、David SlowinskiとPaul Gageにより32番目のMersenne素数(p = 859,433、十進258,716桁)が発見された。発見にはCray C90が用いられた。
6) UNESCO PAC
9月に小沼通二教授(慶應大)からの依頼で、UNESCO PAC (Physics Action Council)のWG2 (Working Group 2)に日本代表として加わることになった。物理学研究および教育におけるネットワークの活用について働くことになった。
国際会議
1) ISSCC 1994
第41回目となるISSCC 1994 (1994 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1994年2月16日~18日に、San Franciscoで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section、Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はW. Pricer (IBM)、プログラム委員長はD. Monticelli (National Semiconductor)であった。IEEE Xploreに会議録が置かれている。
2) Petaflops Computing 会議
2月22日~24日、PasadenaのDouble Tree Hotelにおいて、”The Workshop on Enabling technologies for Peta(FL)OPS Computing“が開かれた。60人以上が参加した。参加者リストには日本人の名前はない。筆者は1999年の第2回会議には参加した。このワークショップの目的は、
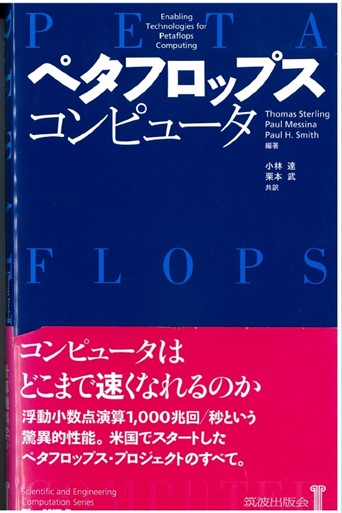 |
|
a) PetaFLOPSの性能を要求するアプリにどのようなものがあり、どんな資源を要求するか
b) PetaFLOPSの実効性能を実現するための技術的な課題は何か
c) PetaFLOPSの計算能力を実現する技術は何か
d) キーとなる研究課題を確立すること。
e) 近未来に行うべき研究テーマを勧告すること
となっている。それまでに、アプリ、デバイス、アーキテクチャ、ソフトウェア技術などのワーキンググループが作られ、その活動報告がなされている。報告書は、日本語に翻訳されて、筑波書房から出版された(写真)。1999年の会議において、筆者が、1994年の会議報告の日本語訳が出たと話したら、出席者がびっくりしていた。
ペタフロップスマシンは20年で実現可能であるが、最大の問題はコストである。部品数が多くなることから、信頼性の管理が重要になる。システム・アーキテクチャにはパラダイムシフトは必要ないと結論している。(実際にLINPACKでPFlopsを実現するのは2008年6月のリストにあるLANLのRoadrunnerである。この会議の14年後であった)
注目すべきことは、当時世界最高性能のスーパーコンピュータは日本のNWTであり、性能は100 GFlopsレベルであったのに、それより4桁も高い性能を見据えて活動を始めていることである。その先見の明には敬服させられる。その後、ワーキンググループの活動がさらに行われた。これに触発されて、日本でもAITEC内に「ペタフロップスマシン技術調査ワーキンググループ」が設置され、1996年から3年間の調査活動を行う。
3) HPC Asia準備
アメリカのSupercomputing会議、ヨーロッパのHPCN、日本のSupercomputing Japanなどの動きを受けて、アジア太平洋地区をベースとした国際会議が企画された。この会議は、Supercomputing 93 (Portland) において、David Kahaner によって提案され、会場でアジア太平洋の各国から2~3人ずつのボランティアが集まって相談を進めた。
1994年2月28日~3月1日には、台北の南西にある工業学園都市の新竹(Hsin Chu)のNCHC (National Center for High-performance Computing國家高速計算中心) において準備会を開き、アジア太平洋各国のHPCの現状を分析し会議の準備を進めた。筆者も出席した。当時は、NCHCの中文名に「網路(network)」は含まれていなかったと思う。このセンターは1988年から検討されていたが、前年1993年4月に正式発足しHPCサービスを提供し始めたばかりであった。
このころからこの準備会はInternational Steering Committeeと呼ばれるようになった。このとき、NCHCは会議の招致にきわめて積極的であった。その後、各国から開催提案を募ったところ、香港と台湾が名乗りを上げ、Email投票の結果台湾に決まった。その後、1994年9月29日~30日にシンガポールで開かれた HPCC’94 Singapore において更に準備を進めた(筆者はこの会には行っていない)。
本会議は、翌年、1995年9月18日-22日に台北の台北國際會議中心(TICC, Taipei International Convention Center) で開かれる。
4) PCG’94
1985年から慶応義塾大学で開かれてきたPCGシンポジウムは、10回目の1994年、国際シンポジウム PCG’94 “Matrix Analysis and Parallel Computing”として3月14日~16日、慶應義塾大学理工学部で開催した。講演は招待ベースで、プログラムは以下の通り。50分の長さのものは特別招待講演。
|
Monday, March 14th |
||
|
10:00-10:05 |
Welcome |
Takashi Nodera (Keio U.) |
|
10:05-10:55 |
“The Solution of Sparse Equation on High Performance Computers” |
Iain S. Duff (Rutherford Appleton Lab.) |
|
10:55-11:20 |
“Parallel Computation for Parametric Study” |
Yoshinari Fukui (Toshiba) |
|
11:20-11:45 |
“Matrix Calculations on Multiprocessor Based on the SSS-multistage Interconnection network” |
Hideharu Amano, Toshiro Hanawa, Masashi Sasahara, Jun Terada (Keio U.) |
|
11:45-13:00 |
Lunch break |
|
|
13:00-13:50 |
“Succesive rank-one modification method for solving solving a system of linear equation” |
Kunio Tanabe (Inst. of Statistical Math.) |
|
13:50-14:15 |
“Programming and Performance of Parallel Programming Language ADETRAN with Data Structures corresponding to Physical Processor Element” |
Yoshimasa Obayashi, Katsuyuki Kaneko, Tadashi Okamoto (Matsushita Electric Industrial Co.), Sadafumi Tomida, Takashi Ishikawa (Matsushita Soft-Research, In c.) |
|
14:15-14:40 |
“Parallel Processing Networks for Matrix Calculation” |
Taisuke Boku, Tetsuya Saito, Hiroshi Nakamura, Kisaburo Nakazawa (U. of Tsukuba) |
|
14:40-15:10 |
Coffee break |
|
|
15:10-16:00 |
“Experience with Regularizing Conjugate Gradient Iterations” |
Per Christian Hansen (UNIC, Danish Computing Center) |
|
16:00-16:25 |
“Some Useful Techniques for Large Scale Engineering Problems in Electromagnetics” |
Koji Fujiwara (Okayama U.) |
|
16:25-16:50 |
“A Solution of Nuemann Problem on Curvilinear Coordinate Systems” |
Takumi Washio, Shun Doi (NEC C&C Info Tech Research Lab) |
|
17:00-17:25 |
“Real Tridaiagonalization of Hermitian matrices by modified Householder Transformation” |
Osamu Shukuzawa, Toshio Suzuki Ichiro Yokota (U. of Yamanashi) |
|
17:25-17:50 |
“The Stability of Parallel Prefix Matrix Multiplication with Application to Tridiagonal Matrices” |
Roy Mathias (College of William & Mary, USA) |
|
17:50-18:15 |
“The Use of GPBi-CG for Nonsymmetric Linear System” |
Shao-Liang Zhang (Nagoya U.) |
|
18:20-19:30 |
Wine party |
|
|
Tuesday, March 15th |
||
|
9:30-9:55 |
“Efficient Implementation of MGCG Method on Distributed Memory Machine” |
Osamu Tatebe, Yoshio Oyanagi (U. of Tokyo) |
|
9:55-10:45 |
“Accuracy of Computed Solutions from Conjugate-Gradient-Like Methods” |
Anne Greenbaum (Courant Inst. of Math., NYU) |
|
10:45-11:05 |
Coffee break |
|
|
11:05-11:30 |
“An Experiment with a Network based Workstation Cluster for High Performance Computing” |
Satoshi Sekiguchi (ETL), Umpei Nagashima (Ochanomizu Womens’ U.) |
|
11:30-12:20 |
“Multigrid and Krylov Subspace Methods for the Discrete Stokes Equations” |
Howard C. Elman (U. of Maryland, USA) |
|
12:20-13:40 |
Lunch break |
|
|
13:40-14:30 |
“Variable Metric Conjugate Gradient Methods” |
Thomas A. Manteuffel (U. of Cololado) |
|
14:30-14:55 |
“Large Scale Circuit Analysis by Preconditioned Relaxation Methods” |
Reiji Suda (U. of Tokyo) |
|
14:55-15:20 |
“Block Triangularization by Means of Matroid Algorithms” |
Kazuo Murota (Kyoto U.) |
|
15:20-15:50 |
Coffee break |
|
|
15:50-16:40 |
“Inner and Outer Iterations for Solving Linear Systems” |
Gene H. Golub (Stanford U.) |
|
16:40-17:05 |
“Resistive Magnetohydrodynamic Spectrum and its Approximation by Finite Element Method” |
Takashi Kako (The U. of Electro-Communications) |
|
17:05-17:55 |
“Composite Step Conjugate Gradient Method for Nonsymmetric Linear Systems” |
Tony F. Chan, Tedd Szeto (UCLA) |
|
18:05-20:00 |
Symposium banquet |
|
|
Wednesday, March 16th |
||
|
9:30-9:55 |
“A Tuning Example using the Loop Transformation Theory for the Symmetric Eigenvalue Problem” |
Hikaru Samukawa (IBM Japan Ltd.) |
|
9:55-10:45 |
“The New qd Algorithms” |
Beresford Parlett (UC Berkeley), K. Vince Fernando (NAG Ltd) |
|
10:45-11:15 |
Coffee break |
|
|
11:15-11:40 |
“Origin-shift Strategies in the QR method” |
Yoshitaka Beppu (Shotoku Gakuen Womens’ College) |
|
11:40-12:30 |
“Parallel Preconditioned Krylov Subspace Methods” |
Youcef Saad (U. of Minnesota) |
|
12:30++ |
Concluding remarks |
Takashi Nodera (Keio U.) |
建部修見は筆者と連名で分散メモリ並列コンピュータAP1000上のMulti-Grid preconditioned CG Methodの実装について講演した。小柳研究室の須田礼仁助手は、Mac上のCanvasで作成した極彩色のスライド(トランスパレンシ)で講演したが、最初の質問は内容ではなく、「そのスライドはどうやって作成したのか」であった。そんな時代であった。
5) IPPS 1994
第8回目となるIPPS 1994 (The 8th International Symposium on Parallel Processing)は1994年4月にメキシコのCancunで開催された。主催はIEEE/CSで、会議録はIEEEから出版されている。佐藤三久ら(電総研)はEM-4について講演した。余談であるが、同氏はCancunでめがねを壊してしまい往生したとのことである。
6) HPCN Europe 1994
第2回目となるHPCN Europe 1994が、1994年4月18日~20日Munichで開催された。2件の基調講演が行われた。
 |
|
|
Information Processing and Opportunities for HPCC Use in Industry. |
Geoffrey C. Fox and Kim Mills |
|
Information Superhighways – Does Europe Need Them, Can Europe Build Them? |
David O. Williams |
会議録はLNCS 796/797としてSpringer社から発行されている。
7) CHEP 1994
第7回目となるCHEP 1994 (1994 Computing on High Energy Physics)は、1994年4月21日~27日に、San FranciscoのHyatt Regency Hotelで開催された。以下の8つのトピックのparallel sessionsが設定された。
|
1. Triggering, Data Acquisition, Online and Control Systems (including software specific to online and DAQ and neural nets applied in triggers) |
|
2. Hardware Architectures (including farms and parallel systems) |
|
3. Networks and Interconnections (including network and interconnection hardware and protocols) |
|
4. Data Handling and Storage Systems (including databases, data modeling, and disk and tape systems) |
|
5. Software Methodologies, Languages and Tools (including object oriented programming, software without programming, distributed software and software management) |
|
6. User Interfaces and Visualization (including computer aided detector design systems, virtual reality, 3-D graphics, and expert systems) |
|
7. Computation (including Monte Carlo, event reconstruction, theory and accelerator design) |
|
8. Information Systems and Multimedia (including World Wide Web, WAIS, Gopher, Groupware, video conferencing, digital libraries, and CD-ROM) |
8) Mannheim Supercomputer Seminar
9回目の会議は、1994年6月6月27日~28日にMannheim市内で開かれた。出席者168人。基調講演としてBerlin大学のWolfgang Giloiが、GMDでの並列コンピュータ開発について講演した。Supremum、Manna、Metaなどに言及した。
9) Top500(世界)
1994年6月の3回目のTop500では、米国SNLのParagon XP/S140が143.4 GFlopsで日本のNWTを抜いてトップを奪還した。SNLのTop獲得は1993年初めからの野望であったが、1993年11月のTop500では8位tieに留まっていた。上位20位は以下の通り。性能はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。20位までのうち10件が日本に設置されている日本製のコンピュータである。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
- |
SNL |
XP/S140 |
3680 |
143.4 |
184.0 |
|
2 |
1 |
航空宇宙研究所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
124.0 |
235.79 |
|
3 |
2 |
LANL |
CM-5/1024 |
1024 |
59.7 |
131.0 |
|
4 |
(3tie) |
Minnesota Supercomputer C. |
CM-5/864 |
864 |
50.5 |
110.6 |
|
5tie |
- |
オングストローム技術組合(日本) |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
|
5tie |
- |
筑波大学 |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
|
7 |
- |
理研 |
VPP500/28 |
28 |
30.8 |
44.8 |
|
8tie |
3tie |
NSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
|
8tie |
3tie |
NCSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
|
10tie |
- |
日立エンタープライズサーバ部門 |
S-3800/480 |
4 |
27.5 |
32.0 |
|
10tie |
(43) |
東京大学 |
S-3800/480 |
4 |
27.5 |
32.0 |
|
12tie |
6 |
日本電気(日本) |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
12tie |
- |
東北大学 |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
14tie |
- |
Cray社(アメリカ) |
T3D MC256-8 |
256 |
21.4 |
38.4 |
|
14tie |
- |
Pittsburgh Supercomputing C. |
T3D MC256-8 |
256 |
21.4 |
38.4 |
|
14tie |
- |
U. Edinburgh(イギリス) |
T3D MC256-8 |
256 |
21.4 |
38.4 |
|
17 |
- |
東北大学金属材料研究所 |
S-3800/380 |
3 |
21.3 |
24.0 |
|
18 |
7 |
Atmospheric Environment Service (Canada) |
SX-3/44 343 MHz |
4 |
20 |
22 |
|
19 |
- |
分子科学研究所 |
SX-3/34R |
3 |
17.4 |
19.2 |
|
20tie |
- |
Caltech |
XP/S35 |
512 |
15.2 |
25.6 |
|
20tie |
8tie |
ORNL |
XP/S35 |
512 |
15.2 |
25.6 |
Top500の表では、20位tieのXP/S35について、Rpeak=25.6 GFlopsとした年と26.0 GFlopsとした年があるが、同じ50 MHzのi860を512個搭載しているので、同じものである。四捨五入の仕方が違うだけだと思われる。
10) Top500(日本)
日本設置のマシンで100位以内は以下の通り。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
|
2 |
1 |
航空宇宙研究所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
124.0 |
235.79 |
|
|
5tie |
- |
オングストローム技術組合(日本) |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
|
|
5tie |
- |
筑波大学 |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
|
|
7 |
- |
理研 |
VPP500/28 |
28 |
30.8 |
44.8 |
|
|
10tie |
- |
日立エンタープライズサーバ部門 |
S-3800/480 |
4 |
27.5 |
32.0 |
|
|
10tie |
(43) |
東京大学 |
S-3800/480 |
4 |
27.5 |
32.0 |
|
|
12tie |
6 |
日本電気(日本) |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
|
12tie |
- |
東北大学 |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
|
|
17 |
- |
東北大学金属材料研究所 |
S-3800/380 |
3 |
21.3 |
24.0 |
|
|
19 |
- |
分子科学研究所 |
SX-3/34R |
3 |
17.4 |
19.2 |
|
|
40 |
- |
産総研RIPS |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.2 |
|
|
48 |
- |
通信総合研究所 |
VPP500/10 |
10 |
11.7 |
16.0 |
|
|
50tie |
30 |
核融合科学研究所 |
SX-3/24R 400 MHz |
2 |
11.6 |
12.8 |
|
|
50tie |
- |
日本電気社内 |
SX-3/24R |
2 |
11.6 |
12.8 |
|
|
57tie |
- |
動力炉・核燃料開発事業団 |
T3D MCA128-2 |
128 |
10.7 |
19.2 |
|
|
65 |
- |
宇宙科学研究所 |
VPP500/7 |
7 |
8.3 |
11.2 |
|
|
66 |
- |
オングストローム技術組合(日本) |
CM-5E/128 |
128 |
7.7 |
16.4 |
|
|
75tie |
- |
日立エネルギー研究所 |
S-3800/180 |
1 |
7.4 |
8.0 |
|
|
75tie |
- |
気象研究所 |
S-3800/180 |
1 |
7.4 |
8.0 |
|
|
94tie |
51tie |
日本原子力研究所 |
SX-3/41R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
|
94tie |
51tie |
大阪大学 |
SX-3/14R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
|
94tie |
51tie |
トヨタ中央研究所 |
SX-3/41R 400 MHz |
4 |
5.8 |
6.4 |
|
1994年後半の国際会議は次回に。首都ワシントンで開催されたSC94は史上最大の参加者を集めた。TMCやKSRの不振にもかかわらず企業展示は盛況であった。日本電気のCMOSベクトルコンピュータSX-4も注目を集めていた。
 |
 |
 |

