提 供
HPCの歩み50年(第34回)-1991年(a)-
いよいよアメリカではHPCCが国家プロジェクトとして始まった。そもそもHPCということばが広く使われるようになったのはこの頃からである。Fortran 90が規格として決定されると同時に、HPFやMPIなどのインタフェース規格がde facto標準として議論され始めた。ベクトルコンピュータC90が登場するとともに、超並列コンピュータのCM-5が発表され、KSR1が出荷された。日米貿易摩擦の中で、Japan-US Workshop for Performance Evaluationが開催され、筆者も参加した。東大では、GRAPE-3が開発され、筑波大では CP-PACSプロジェクトの準備が進んでいた。
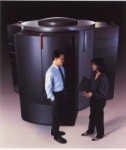
東西の壁が破れたのに続いて、ソ連の崩壊が起こった。日本のバブルはすでに崩壊が始まっているのに、この時からディスコクラブ「ジュリアナ東京」が始まっていることに驚く。1/17多国籍軍がイラクへの攻撃開始、湾岸戦争勃発、5/14信楽鉄道で正面衝突、5/15ジュリアナ東京オープン(1994年8月31日まで)、5/22ガンジー元首相暗殺、6/3雲仙・普賢岳で火砕流、43名死亡、6/3大学設置基準改定(いわゆる大綱化、施行は7/1)、6/9ピナトゥボ火山噴火、6/20四大証券が巨額の損失補填発覚、社会問題化、6/20東北上越新幹線、東京乗り入れ、7/11「悪魔の詩」訳者五十嵐一助教授(筑波大)殺害、8/19ゴルバチョフ幽閉事件、ソ連崩壊へ、9/27台風19号で被害、11/5宮澤喜一、首相に、11/13宮沢りえ写真集『Santa Fe』発売。
筆者は4月に東京大学理学部情報科学科に転任したが、1994年まではつくば市の宿舎から通っていた。五十嵐助教授が殺された時はすでに転任したあとであるが、この日はたまたま香港・マカオの3泊4日の観光旅行から帰ったところで、夕方は筑波大学に来ていた。夜、自転車で帰る時、犯人と鉢合わせした可能性もあった。
筆者の転任と同時に後藤英一教授が停年退官され、神奈川大学理学部情報科学に移られた。筆者のポストは後藤教授の後任ではなく、1年前に停年退官された米田信夫教授のものであった。ERATO(新技術事業団、現在のJSTの前身一つ)の「後藤磁束量子情報プロジェクト」は1990年度に終了したが、関係者の尽力で理研(和光)に「後藤特別研究室」を作り、磁束量子や半導体の研究を進めていた。筆者も1999年8月から2002年3月まで後藤特別研究室の客員主管研究員を兼務した。
これまで後藤英一教授と中澤喜三郎教授(筑波大学)の両研究室と、日立中央研究所の八部とは、定期的に非公開のGNH研究会を開いていた。筆者も東大に来た後に加えていただきGNOH研究会と称した。研究室の教員学生など2~30人の会であった。有益な意見交換を行った。
日本の学界の動き
1) Supercomputing Japan 91
昨年の第1回に引き続き、Supercomputing Japan 91が4月10日から12日に池袋サンシャインで開催された。この時は実行委員を務めた。
2) JSPP 91
第3回のJSPPは5/14-16に震災の跡も生々しい神戸で開催された。筆者は実行委員を務めた。参加者は250名、発表論文は49編(アーキテクチャ関係が25編で半分)。招待講演はC. D. Polychronopoulos (UIUC)とDennis Gannon (Indiana)であった。
3) SWoPP 91
第4回目のSWoPPが、「1991年並列/分散/協調処理に関する『大沼』サマー・ワークショップ (SWoPP大沼’91)」の名の下に、1991年7月16日(火)-19日(金) に、函館プリンスホテル(北海道)で開かれた。発表件数139、参加者数250であった。この回からは、情報処理学会からも多くの研究会が加わっている。すなわち、電子情報通信学会コンピュータシステム研究会、情報処理学会数値解析研究会、プログラミング-言語・基礎・実践-研究会、人工知能研究会、オペレ-ティング・システム研究会、計算機アーキテクチャ研究会の共催である。情報処理学会数値解析研究会からは15件の発表があった。
4) 数値解析シンポジウム
第20回数値解析シンポジウムは、1991年6月17日(月)~19日(水)に、茨城県のいこいの村 涸沼で開催された。担当は筑波大学数値解析研究室で、筆者が中心となって準備したが、予算の計算を誤り、直前に会費を値上げするというヘマをやってしまった。しかも、筆者自身は後述のようにSupercomputing US Pacificに出かけて、国外逃亡したので、非常に無礼なことになってしまった。参加者96名。
5) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所の研究集会「数値解析とそのアルゴリズム」は、三井斌友(名古屋大学)を代表者として、1991年11月20日~22日に開催された。第23回目であった。報告書は講究録No. 791に収録されている。
6) 科研費島崎班
大学の大型計算センター関係者が中心になって組織された科学研究費総合研究島崎班『スーパーコンピュータの性能評価に関する総合的研究』は、91年から3年間の計画で始まった。年数回研究会を開くほか、国際シンポジウムISS’91(the International Symposium on Supercomputing 91)を11月7~8日に福岡のリーセントホテルで開催した。
実は、11月5~9日には高エネルギー研主催で格子QCDの国際会議Lattice 91を開催しており、筆者は組織委員および募金委員を務めていたので、福岡にはとんぼ返りで出かけて講演した。Lattice 91に対する企業からの募金は700万円を目標としたが、関係者のご尽力により600万円をいただくことができた。
7) ISR Workshop
リクルートのスーパーコンピュータ研究所(ISR)は、ISR Workshopを12月11~12日にテピア青山(東京)で開催した。たしか実行委員を務めたと思う。
8) 筑波大学 CP-PACS
CP-PACSプロジェクトが正式に始まったのは1992年であるが、1991年春から、素粒子物理における格子QCD計算の具体的目標の検討や、計算機工学側のシステムに関する技術的な検討が行われていた。CP-PACSという名称が決まったのは5月16日である。
格子QCDの主要な演算であるサブルーチンMULT(3次元複素ユニタリ行列の乗算)をターゲットにアーキテクチャの評価を行った。当初PA-RISCのCPUを4個バス結合したノードを検討したが、このアプリのB/F比は2.5であり、644の格子に対し、実効性能12.3%という評価がでた。完全なメモリバンド幅ネックであった。これが発表されたのが8月10日(土)のミーティングであり、後々「暗黒のCP-PACSミーティング」として記憶されている。
この問題は、その後8月29日、中澤研究室から疑似ベクトル方式が提案され、これがCP-PACSの基本アーキテクチャとなった。このアイデアは筑波大学と日立製作所の協力のもと、開発と実装が進められた。1993年7月のICS93(早稲田大学)で、中村宏らの筑波大グループは日立関係者と連名で“A Scalar Architecture for Pseudo Vector Processing based on Slide-Windowed Registers”という講演を行い、slide-windowのアイデアを初めて発表した。
9) GRAPE-3
東京大学の杉本大一郎、牧野淳一郎らは、GRAPE-3を製作した。重力計算パイプライン回路を専用LSI上に作り、等価理論性能は15 GFlopsとなった。
10) FLATS2
東京大学/理研の後藤英一は、FLATS (1984)の経験を活かし、1986年度~1990年度のERATO(新技術事業団)の「後藤磁束量子情報プロジェクト」において、循環パイプライン方式の数式処理計算機FLATS2を開発した。
11) ICOT
ICOT(新世代コンピュータ技術開発機構)は、第5世代コンピュータ開発計画の成果として、1990年どまでに5種のPIM(並列推論)マシンを開発した。PIM/pとPIM/mは国立科学博物館で保存されているとのことである。
a) PIM/p:8プロセッサ(RISC)を共有メモリでバス結合したクラスタを64個ハイパーキューブ結合。GHCマシン。富士通が開発。
b) PIM/m:256プロセッサ(CISC)を2次元メッシュで結合。GHCマシン。三菱電機が開発。
c) PIM/c:8プロセッサ(CISC)を共有メモリで結合したクラスタ32個(目標)をクロスバネットワークで接続。GHCマシン。日立が開発。
d) PIM/i:16プロセッサエレメント(RISC)。沖電気が開発。
e) PIM/k:16プロセッサエレメント(LIW)。詳細不明。
12) 『アドバンストコンピューティング』
1992年5月、培風館から『アドバンストコンピューティング─21世紀の科学技術基盤』が出版された。有馬朗人、金田康正、村上周三編集で、川合敏雄、岩崎洋一、伊藤伸泰、川井忠彦などのそうそうたる研究者が寄稿した。超並列コンピュータを用いた数値解析、構造解析、バーチャルリアリティー、可視化等の解説を通して、科学と産業におけるアドバンストコンピューティングの具体例を平易に紹介する。さらに、米国の進んだスーパーコンピュータセンターの現状を紹介し、我国のアドバンストコンピューティングセンター設立の構想を提案している。この提案は、20年近く経って「京」コンピュータにおいてある意味で実現した。
13) 計算流体力学研究所
1985年に桑原邦郎が創業した計算力学研究所は、1991年前半、100億円を投資してさらに5台のコンピュータを導入すると発表した(日経産業新聞1991年4月10日号)。超並列機としては、TMC社のCM-2、BBN社のTC2000、松下電器産業のAdenaを、ベクトルコンピュータとしてはVP2600とSX-3である。これらによりHTDVを使った流体可視化の新しい画像処理技術を開発する計画であった。1992年には大阪にも4台のスーパーコンピュータを収容するビルを建設するということであった。 しかし、1991年末、日本電気のSX-3を撤去した。翌年には国産スーパーコンピュータをすべて撤去することになる。
14) インターネット
HPCと直接関係はないが、日本でもインターネットへの関心が高まっていた。1991年11月25日に、東京大学大型計算機センター主催で「学内LANとインターネットワーキングの展開」という講習会が開かれ、参加者がなんと600名を越えた。1990年発足したJCRNもセミナーの開催を検討していたが、1992年3月10日に「学術研究とネットワーク」というセミナーを工学院大学(新宿)で開催した。資料代を徴収したが、123名の参加があった。
1991年9月6日現在の日本のインターネットドメイン数は以下の通りである。
JP domains 2
AD domains 7
AC domains 153
GO domains 29
OR domains 29
CO domains 336
我が国でもインターネットの利用はようやく高まりつつあった。
日本の企業の動き
1) 三洋電機
この頃、三洋電機は、データ駆動の高並列コンピュータEDDEN (Enhanced Data-Driven Engine) を開発した。独自に開発したデータフローのPEを最大1024個まで結合できる。PEのピーク性能は10 MFLops。それぞれのPEがディスクに並列アクセスできるインタフェースを開発した。1992年、その商品版Cyberflowが発表された。4~64ノードの構成が可能なデスクトップシステムである。
2) 三菱電機
三菱電機は、上記の通り第五世代プロジェクトの一環としてPIM/mを開発した。また、1982年からNEDOの補助によりCAP (Cellular Array Processor)を開発してきた。これは64×64の2次元メッシュネットワークで結合されたSIMDマシンであり、画像処理を目的としていた。この頃、シャープと共同してデータ駆動プロセッサDDP(ピーク20 MOPS)を開発したようであるが、詳細は不明である。
三菱電機は、1991年中に米国ボストンにエレクトロニクス分野、とくに超並列コンピュータの基礎研究所を設立すると発表した。現在も、エレクトロニクス、通信、マルチメディア、データ解析、空間解析、メカトロニクス、アルゴリズムなどの研究拠点となっている。
3) 日本鋼管
日本鋼管は1989年12月にConvex社とリアルタイム機の共同開発契約を締結したが、1991年には超並列コンピュータのフィージビリティスタディの契約を結んだ。1991年末に、日本鋼管から約10名の開発担当者をDallasのConvex本社に派遣し開発を進めた。Exemplar SPPの発売は1994年。
アメリカでHPCC始まる
Lax Report (1982)、National Computing Initiative (1987)、Federal HPC Program (1989)などは、アメリカにおいてスーパーコンピュータの利用を推進することが国家的に重要であることを強調してきたが、George W. Bush大統領(父)は、2月、1992年度大統領予算教書の補足書(いわゆるBlue Book)“Grand Challenges: High Performance Computing and Communications The FY 1992 U.S. Research and Development Program”でHPCC (High Performance Computing and Communication)計画を公表し、Grand Challengeの解決を目指すことを表明した。アメリカ政府の文書に“high performance computing”という言葉が頻繁に用いられるようになったのはこの頃からであろう。ちなみに、アメリカの1992会計年度は1991年10月から1992年9月までで、日本とは半年ずれている。
12月9日には、上院議員Al Goreの提唱するThe High Performance Computing Act of 1991が成立し、HPCC計画およびNII (National Information Infrastructure)が発足した。 Bush政権下では、科学技術分野におけるGrand Challenge問題の解決に要求される、スケーラブルな高性能コンピューティングシステムやシステムソフトウェア、アプリ、高速通信などに重点を置いていた。クリントン政権(1993年~2001年)では、上記のようにNII構想が発表され、通信ネットワーク基盤、通信サービス、健康・医療・ビジネスなどのアプリケーションの3層構造が推進された。クリントン政権は1993年後半に、NIIの開発を含めた新しいHPCC計画を発表した。そこでは、グランドチャレンジに加えて、全国的な情報基盤アプリケーションであるナショナルチャレンジ問題(デジタル図書館、教育、環境、健康医療、生産統合、危機管理など)を定義し、高度な演算性能や通信性能により解決していこうとするものであった。
世界の学界の動き
1) SC 91
第4回のSCは、ニューメキシコ州のAlberquerqueで開催された。筆者は、東大に移ったばかりで出席できなかったが、この回から会場のネットワークSCinetが用意されている。全参加者4442人、technical registrationは1711人。この年から、technical registrationが設定され、展示のみの参加と区別された。展示は80件。 大きな出来事は、この会議でHPF (High Performance Fortran)が提案され、HPF Forumが始まったことである(後述)。
2) ICS会議
ICS (International Conference on Supercomputing)の第5回目が、6月17~21日にドイツのケルンで開催された。ACMからプロシーディングスが発行されている。
3) Mannheim Supercomputer Seminar
1986年からMannheim大学内で開催されていたこの会議は、第6回目の1991年はMannheim市内のHotel Wartburgで開催された。設備は快適になったが、企業の展示参加料金はかなり高くなったのとのこと。
4) Supercomputing USA/Pacific
Supercomputing Japanを企画しているMeridian Pacificは、6/19-21に、Santa ClaraでSupercomputing USA/Pacificを開催した。1回限りの会議であった。Proceedingsが出版されているようである。この会議でJohn Gustafson(Ames Lab.)と会ったが、これが1986年にFPSを案内してくれたGustafsonとは気づかなかった。かれはちょうどSLALOM Benchmarkを完成したところであった。 SLALOM (Scalable, Language-independent, Ames Laboratory, One-minute Measurement)は、問題を固定して計算時間を比較するのではなく、時間を1分に固定してどれだけ大きい問題が解けるかを比較するものである。時間を固定にしてスケーラブルなベンチマークにするというアイデアは面白いが、問題としてラジオシティ計算(連立1次方程式)を採用したことには首を傾げた。 この会議に出席する日本の企業関係者の訪米団(6/16-23)が組織され、どういうわけか筆者が団長となった。17日SDSC訪問、18日UCB訪問、17-19日は会議、21日NASA AMES訪問というような行程であった。通訳もついていたが、技術用語(たとえばi860など)には困ったようで、筆者が適当に助け船を出した。 訪米団参加企業は、東芝CAEシステムズ、東芝総合研究所、日本電気、日本経済新聞、三菱総合研究所、リクルート、富士通、三洋電機、住友電気工業など計10名であった。楽しい団体旅行であった。
5) CHEP91
高エネルギー物理学はコンピュータ技術の牽引役の一つであるが、1991年3月11~15日、つくば市においてComputing in high energy physicsという国際会議が開かれ、筆者も手伝った。実験のデータ処理、データベース、画像認識に関する話題が多いが、種々のシミュレーションの発表もあった。岩崎は格子QCD専用機(Columbia大、GF11、ACP-MAPS、APE、APE100、QCDPAX)について総合講演を行った。参加者272人中、所属で見ると、日本118名、米国35名、ソ連32名、スイス(CERNを含む)29名など15カ国に及んでいる。
6) CSNET停止
インターネットの先駆的な役割を果たしたCSNET(1981年開始)は、10月役割を終え運用を停止した。
長くなりそうなので、続きは次回。Fortran 90がISO規格として制定されるとともに、その上の並列言語HPFの議論が始まった。意外にもMPIの議論も同じ頃である。
(タイトル画像:Cray C916)
 |
 |
 |


1件のコメントがあります
これはテストです。
小柳義夫