提 供
HPCの歩み50年(第42回)-1993年(b)-
Mannheim Supercomputer Seminarと並んで、もう一つのヨーロッパベースの国際会議HPCNが始まった。残念ながら2001年で終わってしまった。MPPを普及させるには標準化が不可欠ということで、PVM、MPI、HPFの活動が進められた。WWWの普及にはブラウザが重要であるが、この年NCSA Mosaicが開発された。現在の多くのブラウザの祖先に当たる。
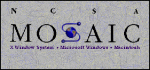
世界の学界の動き(続)
3) Mannheim Supercomputer Seminar
8回目の会議において、「並列コンピュータ対WSクラスタ」の対決があったようである。化学のAhlrichs教授(Karlsruhe大学)とReuter教授(Stuttgart大学)の対決であった。Ahlrichs教授は彼のグループが10万行のソフトTURBOMOLEをクラスタに移植したが、これをMPPに移植するとすれば数年かかってしまう。その間にクラスタの性能は10倍から100倍に向上するので、MPPに移植することは意味がない、と論じた。これに対しReuter教授は、クラスタはMPPの代わりをすることができない、なぜならMPPでは非局所メモリアクセスが比較的容易であるが、クラスタではそうではない、と反論したとのことである。
この回の基調講演はCray ResearchのSteve Nelson。
4) HPCN 1993
HPC分野のヨーロッパベースの国際会議として、第1回のHigh Performance Computing and NetworkingがRAI Conference Center (Amsterdam)で5月17~19日に開催された。日本関係ではISRのRaul Mendezが“Computing programs in Japan”と題して講演している。この回だけは会議録が出版されていないようである。2001年まで継続したが、それ以後は開催されていない。
1993: Amsterdam, The Netherlands (May 17-19, 1993)
1994: Munich, Germany (April 18-20, 1994) Springer LNCS
1995: Milan, Italy (May 3-5, 1995) Springer LNCS
1996: Brussels, Belgium (April 15-19, 1996) Springer LNCS
1997: Vienna, Austria (April 28-30, 1997) Springer LNCS
1998: Amsterdam, The Netherlands (April 21-23, 1998) Springer LNCS
1999: Amsterdam, The Netherlands (April 12-14, 1999) Springer LNCS
2000: Amsterdam, The Netherlands (May 8-10, 2000) Springer LNCS
2001: Amsterdam, The Netherlands (June 25-27, 2001) Springer LNCS4)
筆者は一度も参加していない。
ドイツのHans MeuerらのMannheim Supercomputer Seminarとも相互作用があったようである。そもそもHPCNの中心人物の一人であったWolfgang GentzschはMeuerの友人であった。
なお、ICS93は早稲田大学で開催されたので、日本の動きの方に記す。
5) ICCP-2
第2回のInternational Conference on Computational Physics (ICCP-2)が9月13~17日、北京の「国際会議中心」で開催され、筆者も参加した。国際会議中心は、今でこそオリンピックセンター(国家奥林匹克体育中心)の隣であり、地下鉄の駅もあるが、当時は交通不便で、隣のホテル(北辰五州大酒店)と行き来するだけであった。万里の長城や故宮など多少の遠足はあった。この会場はその後2回も使ったが、来るごとに周辺が賑やかになっている。
計算物理学(computational physics)の国際会議にはいくつかの系統があるが、これはアジアを中心とした会議で、Drexel University (Philadelphia)のDa Hsuan Feng(馮達旋)教授が主導していた。筆者が何で関係したのか昔のメールをひっくり返してみたら、東大物理学科の同級生だったT氏(東北大)の紹介でこの会議の国際諮問委員になるよう依頼があったようである。組織委員長は北京のDe-Yuan Li、副委員長はFengとMike R. Strayer (ORNL)であった。筆者は、“Parallel Computers for Computational Physics”という講演をした。
会議の副イベントとして地元の高校生向けの公開講演会があり、何人かの参加者が英語で講演し、Feng教授が中国語に通訳した。日本からは杉本大一郎が講演した。完璧な英語で質問する地元の女子高生がいてびっくりした。
第5回は日本で開いたが、それまでの会議の履歴は下記の通り。現在では、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの系列が連合して開催している。分かるものは会議録を付記した。
1) Beijing (1988)
2) Beijing (September 13-17, 1993) International Press
3) Chung-Li(中壢), Taiwan (December 4-8, 1995)
4) Singapore (Hyatt Hotel) (June 2-4, 1997)
5) Kanazawa, Japan (October 11-13, 1999) Supplement of Progress of Theoretical Physics
今回調べたら、Feng教授は、現在、台湾の国立清華大学副校長についておられた。
6) Mosaicの登場
筆者が1992年に2度も(1月と9月)WWWに関するTim Berners-Leeのデモを見ながら、その意味を理解出来なかったことはすでに述べた。1993年4月30日に、CERNはWWWの利用を無料で誰にでも開放することを発表した。そのころIllinois大学のNCSAのMarc Andreessenは、テキストと画像を同一のWindow内に混ぜて表示出来る画期的なブラウザNCSA Mosaicを開発した。2月にアルファバーションが公開された。最初はX-Windowで開発したが、すぐMacやWindowsにも対応した。
1991年12月9日には、上院議員Al Goreの提唱するThe High Performance Computing Act of 1991が成立し、HPCC計画およびNII (National Information Infrastructure)が発足したことはすでに述べたが、Mosaicはその大きな成果と言われる。GoreがInternetを発明したわけではないが、Andreessenは、「もしWWWが私企業にゆだねられていたら、Mosaicの開発は数年以上遅れていたであろう」と述べている。
AndreessenとNCSAとの間には権利を巡ってトラブルがあったようであるが、AndreessenはSGIの創立者のJim ClarkとともにMosaic Communication社を立ち上げ、Netscape Navigatorをゼロから再開発した。他方、NCSAはMosaicのコードを無料ではあるが、制限付きで多くの会社に与えた。1993年には、Amdahl社、富士通、InfoSeek社、Quadralay社、Quarterdeck Office Systems社、Santa Cruz Operation社、SPRY社、Spyglass社などがライセンスを保有していた。Microsoft社はSpyglass社からライセンスを受け、Internet Explorerを開発した。1994年8月26日に、NCSAは最新のMosaicであるAIR Mosaicを出荷した。
標準化
1) PVM
3月、PVM v.3が公開された。MPPが普及するかどうかは標準化に掛かっている、という認識が共有されていた。SC’93でも、各ベンダはPVMの標準サポートを謳い、さらにMPIへの動きが見られた。
1993年5月10~11日に、テネシー州Knoxvilleで第1回のPVM Users’ Group Meetingがテネシー大学とDOEの共催、NSF、Convex Computer社、Cray Research社、Digital Equipment社、Intel社の後援で開かれた。参加者は107名。多くのマシンベンダがPVMを実装しており、最適化版を開発したところもある。NetlibによるPVMソフトウェアの配布が9000を越えるなど、PVMは広範に利用されde factの標準になっている、と報告された。
2) HPF
HPF Forumは1993年3月10~12日、DallasのBristol Suites Hotelで会合を開き、HPF Version 1.0を確定した。公開したのは5月。SC93では、High Performance Fortran: Implementors and Users Workshopが朝早くあったが、多くの参加者でムンムンしていた。参考書(C. H. Koelber 他著”The High Performance Fortran Handbook” MIT Press, 1994)が、1994年のcopyright表示のまま、展示会場で売られていた(20ドル弱)。筆者も買ってきた。多くの発表があった。
a) Ken Kennedy (Rice):HPFコンパイラは不十分だし、ユーザの誤解もあり、HPFは失敗するかもしれない。
b) Chuck Koelbel (Rice):データ分散、FORALL、INDEPENDENTの説明。Version 2の課題として、並列I/O、明示的メッセージ・パシングなど。
c) D. Lovemann (DEC):DECのHPF開発戦略。ビジネスの困難。
d) Vince Schuster (PGI社長):PGIのHPFコンパイラについて紹介。多次元ブロック分割もサポートすると豪語。チャレンジとして、性能、デバッグ、ポインタなどを挙げた。
e) Guy Steele (TMC):HPFはmachine independentでなければならないと強調。
f) John Levesque (APR, Applied Parallel Research):HPFのためのツールを作っている。
g) Susan Mehringer (Cornell):APRコンパイラでCG法を書いている。
h) Dan Anderson (NCAR):ユーザをどうやてHPFに引っ張っていくか。
i) Piyush Mehrotra (ICASE):APRとVienna Fortranの比較。
このあとパネル討論があり、厳しい議論が行われ、最後は発散気味であった。本当に使えるものになるのか、早くも暗雲が漂い始めていた。
いよいよ次回はIBMとCray Researchが超並列スーパーコンピュータを発表した話題に移る。Cray-3はNCARに設置されたが、翌年Cray Computer社は倒産した。
 |
 |
 |

