新HPCの歩み(第78回)-1985年(d)-
|
Inmos社はT414を、Intel社は80386/387を発売する。並列コンピュータでは、IntelがiPSC/1を発表する。Convex社はC1を、IBM社は3090 VFを、Cray社はCray-2を発表する。Meiko Scientific社が創立される。ベストセラーSun-3が発売。 |
国際会議
1) ISSCC 1985
第32回目となるISSCC 1985(1985 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1985年2月13日~15日にNew York市のNew York Hilton Hotelで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE New York Section、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はJ. A. A. Raper (General Electric)、プログラム委員長はH. Boll (Bell Labs)であった。Raj Reddy (Carnegie-Mellon U.)が“Super Chips for Artificial Intelligence”と題して基調講演を行った。
日米の各社が、1 Mb DRAMに関する発表を競って行った。これは2月15日午前中に以下のようにまとめておかれている。
ISSCC 85, Friday, February 15, 1985, East Ball Room, 9:00am – 12:15 pm Session XVII “Megabit DRAMs” Chairman John J. Barnes
|
An 85ns 1Mb DRAM in a plastic DIP |
Y. Inoue et al. |
NEC Corp. Kawasaki |
|
A 90ns 1Mb DRAM with multi-bit test mode |
M. Kumanoya et Al. |
Mitsubishi Electric Corp., Itami |
|
A 90ns 1Mb DRAM with multi-bit test mode |
M. Kumanoya et al. |
Mitsubishi Electric Corp., Itami |
|
A 1Mb CMOS DRAM with a divided bitline matrix architecture |
R. Taylor et al. |
Mostek Corp., Carrollton, TX, |
|
A 1Mb DRAM with a folded capacitor cell structure |
F. Horiguchi et al. |
Toshiba VLSI Res. Center, Kawasaki |
|
A 16-levels/cell dynamic memory |
M. Aoki et al. |
Hitachi Ltd., Tokyo |
|
An experimental 80ns 1Mb DRAM with fast page operation |
H. Kalter et al. |
IBM General Tech. Division, Essex Junction, VT |
|
A 1Mb DRAM with 3-dimensional stacked capacitor cells |
Y. Takemae et al. |
Fujitsu, Ltd., Kawasaki |
|
A 1Mb CMOS DRAM with fast page and static column modes |
S. Saito et al. |
Toshiba Semiconductor Device Engineering Lab, Kawasaki |
|
A 1Mb CMOS DRAM with fast page and static column modes |
S. Saito et al. |
Toshiba Semiconductor Device Engineering Lab, Kawasaki |
|
A 1Mb CMOS DRAM with fast page and static column modes |
S. Saito et al. |
Toshiba Semiconductor Device Engineering Lab, Kawasaki, Japan |
|
A 20ns static column 1Mb DRAM in CMOS technology |
K. Sato et al. |
Hitachi Device Development Center, Tokyo |
|
A 1Mb CMOS DRAM |
H. Kirsch et al. |
AT&T Bell Labs., Allentown, PA |
IEEE Xploreに会議録が置かれている。日本の論文数が初めてアメリカを上回ったとのことである。ただし、日本の企業が会議前に発表内容をマスコミに流す例があり、問題となった。
2) Lattice Gauge Theory
1987年以降、International Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice xy(年号))と呼ばれる会議シリーズは、1984年4月5日~7日に”Gauge Theory on a Lattice: 1984”の名称で開始されたが、1985年は、2回開催された。1986年からは年1回開催されている。
第2回として米国フロリダ州のTallahasseeで、1985年4月10日~13日に“Advanced in Lattice Gauge Theory”の名称で開催された。会議録はweb上に公開されている。
第3回として西ドイツのWuppertalで、1985年11月5日~7日に、“Lattice Gauge Theory: A Challenge in Large-Scale Computing”の名称で開催された。会議録は2011年にSpringerが再発行している。
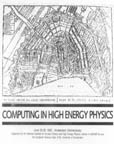 |
|
3) CHEP 1985
詳しい記録は見つからなかったが、1985年5月4日~6日にオランダのAmsterdamにおいて、第1回の国際会議CHEP (Computing in High energy Physics)が開催された。”Computing in High Energy Physics” Amsterdam conference 1985 という呼び方もあるようである。写真は不鮮明だが会議のポスターと思われる。(CHEP2016のページから)
高エネルギー物理学関係では、理論(素粒子論)でも実験でも計算機が重要な役割を演じており、市販品の利用はもちろん、研究者自身によって目的に応じて様々な専用コンピュータが開発されていた。このような問題を集中的に議論するために、1980年にはBologna大学(イタリア)、1981年にはCERN(スイス)、1983年にはPadova(イタリア)、1984年にはGuanajuato(メキシコ)で個別に開かれてきたが、これらを統合して一つの会議シリーズとして開催することにしたものと推測される。CHEP会議はこのあと、ほぼ1年半に1回のペースで開催されている。1991年3月には、初めて日本(ホストはKEK、会場は筑波大学)で開催される。1998年の第10回以降、略号のCHEPは変わらないが、正式名称にNuclearを入れ、Computing in High Energy and Nuclear Physicsと名乗っている。
4) ICPP 1985
第14回のICPP 1985 (International Conference on Parallel Processing)は、1985年8月、ペンシルバニア州中央部University ParkのThe Pennsylvania State Universityで開催された。会議録はIEEE/CSから発行されている。講演題目はTrier大学のdblpに収録されている。
5) PPSC 1985
SIAM主催のPPSC 1985(the Second Conference on Parallel Processing for Scientific Computing)は、1985年11月18日~21日に、バージニア州Norfolkで開催された。論文選集がSIAMから発行されている。このころ2年に一度開催されているので、第1回は1983年に開催されたと思われるが、不明である。第11回は2003年ではなく2004年に開催され、以後偶数年に開催されている。筆者は2008年の第13回(Atlanta)と2018年の第18回(東京、早稲田大学)には参加した。
6) ICS会議(Kartashevの)
この1985年、初めてスーパーコンピュータを冠した会議がアメリカで始まった。IEEE主催のInternational Conference on Supercomputing (Systems)である。この会議の仕掛人は、S. I. Kartashev(名はStevenらしい)およびS. P. Kartashev(名はSvetlanaらしい)という夫妻(二人とも並列アーキテクチャの研究者とのことである。Dynamic Pipeline Architectureなど共著の論文が多数ある)で、1969年にKievからアメリカに移住したという不思議な人物である。1985年12月から89年4月までアメリカで4回開催された。第1回はInternational Conference on Supercomputing Systemsで、第4回はInternational Conference on Supercomputingとなっているので、途中で名称を変更したらしい。
第1回は、1985年12月16日~20日にフロリダ州西海岸のSt. Petersburg近郊にあるInnisbrookという保養地で開かれ、600人~700人が参加した。日本からもかなりの参加者があった。第1回の名称はInternational Conference on Supercomputing Systemsだったようである。16日はチュートリアル、17日は基調講演と技術報告、18日はスーパーコンピューティング時代における教育、19日は国内および国際的なイニシアチブがテーマで、いずれもアメリカ、ヨーロッパ、日本がそれぞれの立場を話したあと、多数のパネリストとともに議論するという構成であった。基調講演ではCDC社のW. C. Norrisが「大学や研究所が積極的に使うこと、リスクに備えること」を実現するために政府の積極的な援助が必要であると強調した。19日には電総研の弓場敏嗣が、電総研での研究内容とともに、スーパーコン大プロと第五世代について紹介した。10月末に急逝した(ILLIAC IVの)Daniel Slotnickの追悼集会がバンケットの前にあり、三浦謙一などが思い出を語った。企業展示では、Intel社が発表したばかりのiPSC/1を大々的に宣伝していた。広島大学の阿江忠がbit誌1986年3月号に報告を書いている。IEEE/CSから会議録が出ている(ハードカバー、ペーパーバック、マイクロフィッシュ、North Holland版と4種出ているようである)。
そもそも保養地のお祭り気分で、表彰の乱発や、政府機関との不透明な関係など運営上いろいろ問題があり、参加者の不興を買っていたとのことである。ちなみに、1987年、D. Kuckらを中心に始まり、第2回からはACM/SIGARCHの下で現在まで続いている類似名の会議ICSとは別系統である。
7) ParCo85
第2回のParCo (その後International Conference on Parallel Computing)であるParCo85が再びBerlinで開催された。この会議は奇数年にヨーロッパ各地で開催されている(1987年を除く)
アメリカの企業の動き
これまで発足したベンチャー企業を含め、新製品の発表や出荷が続いている。
1) Cray Research社(Cray-2)
1985年、Cray-2を出荷した。これはCray-1を設計したSeymour Crayが設計した。X-MPはSteve Chenが設計したものである。Cray-2はクロックが8 ns、4並列でピーク1952 Mflopsである。回路全体をFluorinertという液体に浸け、気化熱で冷却する新しい冷却方式を採用した。OSはUNIX System V。CPUが1個の版は2システムが前年から社内で動いていた。フル構成のCray-2の1号機は、1985年6月14日にLLNLのMagnetic Fusion Research Center(現在のNERSC)に納入された。筆者は翌1986年にLLNLを訪問し実物を見たが、筐体が透明で泡が出ているのが見えた。マシン名はBubblesだった。2号機はNASA Amesの予定である。(設置の日付は不明だが、1986年にはNASA AmesにはNAS (Numerical Aerodynamic Simulation) Systemが稼働し、Cray-2が使われている)
2) IBM社(3090、VF、CEO交代)
IBM社は、米国時間1985年2月12日、IBM 3090シリーズ(コード名Sierra)のmodel 200およびmodel 400を発表した。3090シリーズでは、TCMとともにECL論理回路の採用により18.5 nsのサイクルを実現した。また、拡張記憶機構により主記憶を256MBまで拡大することができた。1986年2月には下位モデルのmodel 150およびmodel 180が発表される。1987年1月には、model 300Eおよびmodel 600Eが追加される。そのほか多くのモデルが発表される。1987年5月以降には1 Mb DRAMが採用され、32 MBを越える主記憶のマシンに使われる。
3月、IBM3090対抗として、NAS社はAS-XLシリーズ2機種、Burroughs社はA15シリーズ8モデル、Honeywell社はDSP90シリーズ5モデルを発表した。
1985年10月1日、IBM 3090にベクトル演算器を付加したIBM 3090/VFを発表。VFはVector Facilityの意味である。Model 20では最大2台、model 400では最大4台、model 600(1988発表)では最大6台までVFを設置できる(6台の場合ピーク性能は648 MFlops)。VFではキャッシュと演算器との間に8 kBのベクトルレジスタが置かれている。対話型で使え、仮想記憶をサポートする。
1981年からCEOを務めていたJohn R. Opelが退任し、John Fellows AkersがCEOとなった。
3) IBM社(Token Ring)
IBM社は1985年10月15日、IBM独自のToken Ring製品を発売した。4 Mb/sで動作し、メインフレーム、ミッドレンジコンピュータ、IBM PCを接続することができた。その後、IEEE 802.5として標準化された。一時はEthernetを追い上げていたが、16 Mb/sや100 Mb/sの高速化にもかかわらずあまり普及せず、2002年IBM社はToken Ring製品の営業を停止する。
4) IBM社(RP3)
IBM社のWaston Research Centerでは、1979年以来、New York大学のCourant Institute of Mathematics Scienceと協力して、画期的な高並列計算機RP3(IBM Research Parallel Processor Prototype)(これはICPP 1985に発表した論文)の開発を進めていたが、1985年8月、試作に成功したと発表した。これは最大512台の32ビット汎用RISCプロセッサが2 GBの主記憶をOmegaネットワークで共有する構造になっている。実装は64台であった。共有メモリと分散メモリはダイナミックに切り替えることができる。プロセッサ毎に32 KBのキャッシュが実装されているが、ハード的なキャッシュコヒーレンシは実現していない。結果的にあまり良い成果は得られなかったが、上記のICPP 1985の論文では、「期待外れの結果も貴重な成果で、今後の発展に役立つ」と述べている。ここで開発されたRISCプロセッサは後のPowerに、ネットワークはSP1などに影響を与えた。RP3は1991年に稼働を停止する。
 |
|
5) Convex Computer社(C1)
Convex Computer社(1982年創立)は、1985年、Cray-1と互換のミニスーパーコンピュータC1を出荷した。しかしベクトルレジスタは128本あり、Cray-1の倍である。また、仮想記憶方式を採用したために使いやすいマシンとなった。OSはBSD系UnixのConvexOSである。写真はWikipediaから。
6) DEC (MicroVAX II)
1984年に出したMicroVAX Iに続いて、1985年5月14日、MicroVAX II(コード名Mayflower)を発表し、ほどなく出荷した。このマシンはVAX/VMSとULTRIX(DEC版のUnix)のどちらでも動く。5 MHzで動くMicroVAX 78032 マイクロプロセッサと、浮動小数演算チップ MicroVAX 78132が搭載されている。VAX-11/750と同程度の性能を達成した。同時にMicroVAX IIをベースとしたVAXstation IIを発売した。
7) Floating Point Systems社(FPS-264)
Floating Point Systems社(1970年創業)はTTLでなくECLを使ったFPS-264を出荷。FPS-164より5倍高性能であった。
8) nCUBE社(nCUBE 10)
12月、nCUBE 10をリリースした。
9) Alliant Computer Systems社(FX)
FXシリーズを発表。
10) Silicon Graphics社(IRIS 2000)
1985年8月、MC68010/68020を搭載したワークステーションIRIS 2000を発売した。
11) Sun Microsystems社(Sun-3, SPARC)
1985年、Sun Microsystems社は、Motorola社のMC68020マイクロプロセッサ、MC68881数値演算コプロセッサを用いたVMEバスベースのワークステーションSun-3を発売。筆者にとってはQCDPAXのホストとしてなつかしい。
また同社は、UCBのRISC Iをモデルに独自のアーキテクチャを開発し、1985年にSPARC (Scalable Processor ARChitechture)を発表した。最初の32ビットアーキテクチャ(SPARC V7)の実装は同社のワークステーションSun-4 (1987)である。
12) Prime Computer社
同社は1979年以来50-seriesとして高性能ミニコンピュータを発売してきたが、1985年Prime 9955/9655/2655などを発売した。9955は4.0 MIPSの性能を持ち、メモリは6-16MB、2.7GBのディスクを装備している。5台がSalford大学に設置された。
13) Encore Computer社(Multimax)
1983年に創業したEncore Computer社は、1985年、National Semiconductor社のNS32332(または高速のNS32532)プロセッサを最大20個搭載するMultimaxを発表した。これはバス・スヌーピング(1983)によりキャッシュコヒーレンシを実現した最初の商用マシンである。
14) Intel社(80386、80387、iPSC/1)
1985年10月、32ビットのIntel 80386(別名i386)を発売した。Intel社は、1983年5月に、80386を1984年後半に出荷すると発表していた。数値演算コプロセッサは80387。80386からはセカンド・ソース契約をせず、全てを自社で生産することとした。これに対しAMD社は、1982年の契約に基づきセカンド・ソース契約を要求し訴訟となった。1987年2月に仲裁が行われ、「Intel社はAMDにライセンスを供給すべし」との仲介案が出るが、Intel社が拒否した。これを受けてAMD社が提訴し、1994年に米上級裁判所で仲介案を支持する判決を出した。
Intel社は1984年にSSD (Supercomputer Systems Division)を創設し、並列コンピュータの開発を開始した。1985年に発表されたiPSC/1は、80286 CPUと数値演算コプロセッサ80287、512KBのメモリ、8本のイーサーネットポートからなるノードを32~128台ハイパーキューブ結合した並列コンピュータである。ハイパーキューブ結合はGeoffrey C. FoxらのCalTech Cosmic Cubeから受け継いだ技術である。当時はもちろんまだMPIはなく、Paul Pierceはメッセージ通信のインタフェースとしてNXを開発した。このインタフェースはParagonまで使われる。
15) Intel社(訴訟、DRAM撤退)
1984年末、日本電気はIntel社を相手取り、V20/V30/V40/V50のマイクロコードがIntel社の著作権を侵害していない旨の債務不存在確認訴訟を米国カリフォルニア州連邦裁判所に提訴した。1985年6月、Intel社もV20とV30が著作権法違反であるとして提訴した。1989年に日本電気はIntelの著作権を犯していないとの判決を得る。ただし、その直接の理由は、8086に著作権表示がなく当該製品に対して著作権が認められないからであった。一方で、著作権表示があればマイクロコードにも著作権があることが判示され、互換プロセッサの製造が困難となった。この係争中、日本電気はVシリーズの世界市場での販売を控えていたと言われている。
世界初のDRAM製品を売り出したIntel社は、1985年、DRAM製造の6工場を閉鎖し30%の従業員をレイオフした。Intel社はDRAM市場から完全撤退した。1986年には$200Mの赤字を計上した。これが日米半導体摩擦の一つのきっかけとなった。このとき、Intel社はかなりの数のエンジニアを韓国に派遣して、韓国企業のDRAMの立ち上げを支援した。
16) National Semiconductor社
1982年のNS32016、1984年のNS32032に続き、1985年にNS32332のサンプル出荷を開始した。量産は1986年から。アドレシング専用ハードを追加し、命令プリフェッチ機構、バスプロトコルの強化などにより、32032の3倍の性能を謳った。同時に、NS32382 MMU、NS32381 FPU、WeitekとのインタフェースNS32310も発売された。
17) Microsoft社(Windows 1.0)
Microsoft社は、1985年11月20日にWindows 1.0を発売した。同社として初めてのGUI環境である。1983年から開発を進めていた。日本電気は1984年5月頃、PC-9800シリーズに搭載することを決め、Microsoft社と日本語版の開発を始めた。MS-DOS Ver. 3.1とともにバンドルOSとして搭載したPC-9801VX4/WNは1986年11月に発売される。
18) EMS
Microsoft社とIntel社とLotus社の3社は、1985年、MS-DOS上でのメモリ拡張のためにEMS (Extended Memory Specification)の仕様を定め、EMS仕様のメモリボードの普及を計った。バンク切り替え方式を用いている。筆者も一時愛用した。80386からは、仮想86モードを用いたソフト的なEMSの実装が一般的となる。
ヨーロッパの企業の動き
1) Inmos社(イギリス)(T414)
1978年11月にイギリスでInmos Limitedが設立されたことは前に述べたが、1985年に最初のTransputer T414 (32ビット)が発売された。このRISC CPUチップは、2KBのメモリと5 Mb/sのシリアル通信リンク4本を内蔵している。1987年に登場するT800は、初めて64ビットのFPUを内蔵する。Meiko, Floating Point Systems, Parsytec、Parsysなどの並列ベンダがTransputerを用いている。
なお英語版Wikipediaによると最初のいくつかのTransputerは前年1984年にリリースされたとあるが、これは16ビットのT2シリーズのことであろうか。
さらに意欲的に改良したT9000の開発に取りかかったが、性能目標が達成できず、1989年4月、会社ごとSGS-Thomsonに吸収される。その後1991年頃(要確認)T9000の開発は断念される。
企業の創業
1) 計算流体力学研究所
1985年11月、流体現象の解析サービスを専門とする株式会社計算流体力学研究所が東京目黒区で創立された。社長は、日本クレイにいた武田喜一郎。この会社の社屋は、主要出資者である桑原邦郎(宇宙科学研究所)の自宅駐車場に立てた3階建ての建物である。親の遺産をつぎ込んだといわれる。後述のように、1987年5月に最初のスーパーコンピュータFACOM VP-200を設置し、その後多くのスーパーコンピュータを導入する。
2) Ardent Computer社
Allen Michelsによってグラフィックス用のミニコンピュータを目指してSilicon Valleyで創立。チーフアーキテクトにGordon Bellを迎えた。MIPS R2000 CPUと独自開発のベクトルプロセッサを接続した4プロセッサの共有メモリのデスクトップ・コンピュータTitanを目指したが開発が遅れ、ようやく1988年に完成。日本の機械メーカのクボタが資金提供した。さらにStellarに対抗するため、2個のR3000と4個のi860からなるデスクトップを開発しようとした。
3) Stellar Computer社
Bill Poduska (Apollo Computer社の創立者)によってBostonで創立。高性能のワークステーションを開発。1989年、クボタはArdent社とStellar社の合併を強行し、Stardent Computer社となった。1991年、Stardent社は倒産し、クボタがすべての権利を引き継いだ。
1994年、クボタは新規ハードウェアからの撤退を決めた。
4) SuperTek Computer社
元、Hewlett-Packard社のプロジェクトマネージャーであったMike Fungによって1985年Santa Claraにおいて設立された。目的は Cray互換のミニスーパーコンピュータを開発するためであった。1989年にCMOSによりCray X-MP互換のSuperTek S-1を製造し10台販売した。1990年、Cray Researchによって買収された。そのころ、Cray Y-MP互換のSuperTek S-2を開発中であったが、買収後 Cray Y-MP ELとして1992年にCray Research社から発表される。
5) Meiko Scientific社
INMOS社の経営陣が1985年、transputerの発表を遅らせると示唆したとき、transputerの開発部隊にいたMiles Chesneyら数人が INMOS社を退職し、イギリスのBristolで、transputerを用いた超並列計算機を開発するためにMeiko Scientific社を設立した。社名は日本語の「名工」から命名したとのことである。
32ビットのT414を用いたシステムを1986年Meiko Computing Surfaceとして発表し、1990年までに300システム以上を販売した。最初はSun-3やSun-4をフロントエンドとするシステムであった。後継のtransputerの開発が遅れ、性能的に競争力がなくなると、2個のIntel i860チップと32 MBのRAMを含むボードを作成した。この場合、transputerはプロセッサ間通信を担当した。SPARCプロセッサのボードも開発した。日本の代理店は松下電器貿易。
1993年に、SuperSPARCやhyperSPARACと富士通の1チップベクトルプロセッサμVPからなるMeiko CS-2を発表し、224プロセッサの最大のシステムをLLNLに設置した。これが愛国者の神経を逆なでしたらしい。1993年3月、New York Times紙は、国立研究所であるLLNLがイギリスのCS-2を買うことは、アメリカの経済競争力を損ない、国家的安全保障を危険にさらすと批判した。日本だけでなくイギリスでもだめらしい。Jack Dongarraも、”I’m stunned that they would make this choice. Meiko doesn’t have an established track record compared to others in the field.”と否定的意見を同紙に述べている (HCwire March 12, 1993)。Meiko Scientific社は直ちに反論した。
しかし、同社はほどなく経営難に陥った。1996年、技術陣はイタリアの Alenia Spazio社との合弁会社であるQuadrics Supercomputing World社に移り、相互接続技術をQsNetとして開発する。
6) Parsytec社
1985年、西ドイツのAachenでFalk-Dietrich Küblerによりtransputerを用いた並列コンピュータを開発するために政府の補助金を受けて設立された。社名はPARallel SYstem TEChnologyに由来する。1988年から1994年の間に、64個から16384個までのtransputerを用いた様々な Parsytec GigaClusterを製造した。日本の代理店は松下電器産業。2007年7月、ISRA VISION AGが52.6%の株式を取得した。現在は表面検査システムを販売している。
7) Concurrent Computer Corporation
Perkin-Elmer社(1937年創業)のコンピュータ部門(大本はInterdata社)が独立し、 Concurrent Computer Corporalionとなった。詳細は不明であるが、1994年1月、同社は最初のMaxionマルチプロセッサシステムを出荷している。
8) ATI Technologies社
1985年、中国出身のHo Kwok Yuen(何国源)らは、PCのグラフィックカードなどを製造するために、カナダOntario州MarkhamにおいてArray Technologies Inc.を創立した。その後、ATI Technologies Inc.と改名。1993年にNASDAQとトロント株式市場に上場。2006年6月AMD社が買収すると発表し、10月に合併終了。
9) Qualcomm社
Qualcomm Inc.は、1985年、移動体通信の通信技術および半導体の設計開発のために、Irwin M. JacobsとAndrew James Viterbiらによりカリフォルニア州のSan Diegoで創立された。CDMA方式携帯電話の実用化に成功して成長を遂げた。当初は携帯電話端末と通信設備の部門を併せ持っていたが、その後、携帯電話端末部門は京セラに、通信設備部門はエリクソンにそれぞれ売却される。ファブレスメーカーであり、半導体の製造は大手ファウンドリであるGLOBALFOUNDRIES、TSMCなどへの委託で製造している。
10) NeXT社
Appleの創業者Steve Jobsは、1985年9月13日(金曜日)に辞任し、同年、元従業員らとともに新会社NeXT, Inc.をカリフォルニア州Redwood Cityで創立した。1987年、テキサス州の実業家Ross Perotは$20Mを出資し最初の社外投資家となる。Perotは1992年と1996年の大統領選に無所属候補として立候補したので有名である。1986年、社名をNeXT Computer, Inc.に変更する。最初のNeXT Computerのプロトタイプ(25MHzのMC68030 CPU搭載)は1988年10月12日に披露される。黒色で一辺が約1フィートの正立方体という特異な形状から、一般に “the cube” と呼ばれる。当初は販売先をアメリカの高等教育機関に限定した。1990年から1993年にかけて、NeXTSTEP OSを搭載したハイエンドワークステーションNeXTstationを販売する。売上げはそれほど多くはなかったが、革新的なオブジェクト指向型OSであるNeXTSTEPと開発環境は、1997年にSteve JobsがApple社に復帰後、Appleに買収される。
企業の終焉
1) Denelcor社
Burton SmithがHEPを開発していたDenelcor社は1985年10月に閉鎖された。日本では昭光通商がHEP-1の国内販売を開始したところであった。売れなかったと思う。
2) ソード社
PIPSの好調で発展を続けてきたが、1984年にOAブームによる深刻な半導体不足が起こると、自社で半導体の調達ができなかったソードはパソコンを生産できず、業績が悪化した。1985年3月6日、東芝の傘下に入ることが発表された。東芝はソードの株式を37.6%取得し、副社長を含む常勤役員2人を送り込み、生産、販売両面で相互協力体制を組むことになった。その後、1999年に東芝の完全子会社となり、社名を「東芝パソコンシステム」に変更する。2016年には、社名を「東芝プラットフォームソリューション」に変更する。2018年、東芝が全株式をTOPSホールディングスに売却し、7月に「株式会社ソード」に戻すことになる。
次回は1986年、西ドイツではISCの前身であるMannheim Supercomputer Seminarが始まる。中国では、鄧小平国家主席の決断により、”863”計画が決定される。
 |
 |
 |

