新HPCの歩み(第80回)-1986年(b)-
|
電子通信学会は第1回データフロー・ワークショップを開催した。これが、1989年からのJSPPに繋がる。第五世代プロジェクトは並列推論マシンの開発を進める。Unixの両巨頭4.3 BSDとSystem V R3.0が公表された。日本の7大型計算機センターは、4月から共通利用番号制を開始し、他のセンターでの利用料金を自分のセンターのアカウントにつけることができるようになった。 |
日本政府の動き
1) 学術情報センター
1986年4月、東京大学文献情報センター(全国共同利用施設)を改組し、学術情報センター(NACSIS)を設置した(2000年には国立情報学研究所へ)。
2) 新技術開発事業団(後藤磁束パラメトロン)
新技術開発事業団(JRDC、JST科学技術振興機構の前身の一つ)は、ERATO(創造科学技術推進事業)の課題として、1986年10月から、後藤英一東京大学教授(理化学研究所兼務、1991年4月から神奈川大学教授)を総括責任者として「後藤磁束量子情報プロジェクト」を開始した。後藤らは、すでに量子磁束パラメトロン原理の確認に成功したと1986年1月17日に発表している。プロジェクトは1991年9月に終了するが、その後も、理化学研究所に後藤特別研究室を設けて研究を推進する。ERATOは1981年から開始しているが、物質材料とバイオ分野のみであった。後藤プロジェクトは、初めての情報分野のERATOであったが、これも超伝導という物質材料分野の研究として評価されたのかもしれない。筆者は、1990年代ERATOの課題選定に協力して、情報分野の重要性を強調した。
言うまでもないが、このプロジェクトは磁束量子を情報信号の媒介として、高速で低消費電力の古典的コンピュータを実現しようとするものであり、(いわゆる)量子コンピュータではない。
3) 第五世代コンピュータプロジェクト
1986年5月27日~28日に、東京虎ノ門のニッショーホールで、第五世代コンピュータに関するシンポジウムが行われた。これは年度ごとのICOTの研究成果を発表するもので、4回目である。これまでの3年間は、逐次型推論マシンPSIの開発後基礎ソフトウェアシステムの確立に重点が置かれていたが、これらの成果を受けて、今後は100ノード規模の並列推論マシン、VLSIアーキテクチャ、知識ベースマシンなどの研究を進める、
日米両政府は、同プロジェクトの日米共同研究について1月から協議を続けてきたが、第一段階として、1987年春に米国側からNSFの推薦する大学や民間企業の研究者をICOTが受け入れ、第五世代コンピュータプロジェクトに参加する。日本側も、ICOTの賛助会員の中から技術者をアメリカに派遣する予定である。
三菱電機では、逐次推論マシにPSIとそのOSであるSIMPOSを開発してきたが、1986年MELCOMPSIとして製品化した。
4) 前川レポート
前川春雄を座長とする首相の諮問機関「国際協調のための経済構造調整研究会」が、1986年4月7日、危機的な日米貿易摩擦解消のため輸出指向から内需拡大・国際協調への経済構造転換策を提言した〈いわゆる前川リポート〉。
日本の大学センター等
1) 共通利用番号制
全国の7大型計算機センターは、4月から共通利用番号制を開始し、他のセンターでの利用料金を自分のセンターのアカウントにつけることができるようになった。18年間運用されたが、2004年からの国立大学法人化に伴い廃止された。
2) 北海道大学(HITAC M-680H+S-810/10)
1986年8 月、北海道大学大型計算機センターはスーパーコンピュータを導入しHITAC M-680H+S-810/10(主記憶256 MB)の構成とした。
3) 東北大学(SX-1)
東北大学大型計算機センターでは、1986年3月、SX-1を設置し、5月に運用を開始した。メモリは192 MB、フロントエンドはACOS-1000。
4) 東京大学(HITAC M-680H+M-682H)
東京大学大型計算機センターは、1983年にS-810/20を導入したが、メインフレームはHITAC M-280H×6のままであった。1986年、HITAC M-680H (128 MB)とHITAC M-682H (384 MB)にリプレースされた。M-682Hは2 CPU機である。
5) 名古屋大学(VP-100)
名古屋大学大型計算機センターは、1986年10月、VP-100 (64 MB)を設置した。フロントエンドはM380Q。1987年にはVP-200に変更。
6) 京都大学(FACOM M380)
京都大学大型計算機センターは、前年中止していたFACOM M380のサービスを再開した。
7) 大阪大学(SX-1)
大阪大学大型計算機センターは、1986年3月、SX-1 (192 MB)を設置した。フロントエンドはACOS-2000。6月からサービス開始。
8) 茨城大学
1986年3月に、日立地区ではHITAC8250をHITAC M-240Hに、水戸支部ではHITAC10IIをHITAC L-450に更新した。(4月からか?)情報処理センターに組織替え。端末も多数設置。
9) 大分大学
1986年3月、大分大学計算機センターは、FACOM M360Rに更新。
10) 熊本大学
1986年8月1日、情報処理センター発足。11月1日、情報処理センター開所式。FACOM M-360(主記憶 24 MB)設置。1987年1月1日本稼働。
11) 青山学院大学
1986年4月、厚木キャンパスにパソコンシステム(PC-9801)を導入した。
12) 東海大学(SX-1E)
東海大学計算センターは、1986年9月、SX-1E (128 MB)を設置した。スタンドアロンで運用。
13) 甲子園大学
1986年4月。甲子園大学は、情報処理教育センター設置、FACOM M340導入。
14) 分子科学研究所(HITAC M-680H+S-810/10)
分子科学研究所電子計算機センターは、1986 年1月に、HITAC M-200H 2台から、M-680Hと、スーパーコンピュータHITAC S-810/10の構成に更新した。
15) 高エネルギー物理学研究所(HITAC S-810/10)
1985年6月10日、高エネルギー研では、待望のS-810/10の利用が開始されたが、1986年頃の利用状況はこんな感じであった。ジョブクラスは以下の通り。Iジョブはテスト用で自由に投入してよいが、他は基本的にユーザグループ間の自主管理で利用する。
|
ジョブクラス |
I |
J |
K |
L |
M(特認) |
|
CPU時間 |
10分 |
1時間 |
1時間 |
1時間 |
1時間 |
|
拡張リージョン(実記憶) |
16 MB |
32 MB |
64 MB |
96 MB |
112 MB |
通常、昼間は (I + J + K) で、夜間は (I + L)で運転する。Mの場合は単独運用。一般のセンターとは異なり、ユーザグループ間で協議して毎日の利用時間を決め、24時間以内に割り当てられたCPU時間に相当する以上のJobをIJQ (Input Job Queue)に溜めないことを紳士協定。
1985年9月から同年12月までの運転統計を示す。4か月の総運転時間は1567時間。
|
ジョブクラス |
I |
J |
K |
L |
M(特認) |
合計 |
|
ジョブ数 |
1466 |
520 |
458 |
645 |
197 |
3286 |
|
CPU時間(時間) |
67 |
388 |
309 |
544 |
121 |
1430 |
|
VPU時間(時間) |
50 |
340 |
280 |
538 |
122 |
1333 |
|
VPU/CPU比 |
74.6% |
87.7% |
91.1% |
99.1% |
100.4% |
93% |
CPUは、VPU (Vector Processing Unit ベクトル演算器)を起動した後、次のベクトル処理の準備をして待ち状態に入るがCPUタイマーは動いているので、VPU時間はCPU時間を上回らないはずである。しかし、VPUが余りに長時間動き続けると(VPUにはタスク切り替えの割り込みは入らない)、たまに他のジョブやOSが割り込みでCPUの制御権を獲得して、自分のジョブのCPUタイマーが止まることがあり、VPU時間の方が多くなることも起こりうる。クラスMの例では、同時に走るジョブはないにもかかわらず、200件近いジョブの平均で100%を上回っているのは面白い。逆に、このような超ベクトル化プログラムがLジョブで走っている時、一緒にIジョブを走らせると、CPU時間10分のジョブなのに、実時間では数時間以上もかかることがあり、テストにならないと苦情が出た。
この頃の主要な利用グループは以下の通り。
|
格子場の理論 |
|
|
THPO |
繰り込み群で改良した格子作用を用いた、クェンチ近似による研究。163×48という大格子で、ハドロンの質量およびクォーク間ポテンシャルに対し、信頼しうる結果を導いた。 |
|
THPC |
ランジュバン方程式により、クェンチ近似によらないハドロン物理。有限温度QCDの相構造。93×18格子状でのハドロン質量。 |
|
THPM |
繰り込み群モンテカルロによる4次元φ4理論の存在性の研究。Higgs機構の研究。 |
|
格子場の理論以外 |
|
|
|
QED 8次の計算。数式処理システムからの出力を積分 |
|
|
Radiative correction of e+e- reactions. Reduceからの出力を積分。式が5000行にもなり、コンパイラの能力を超えるので、プリプロセッサを作成。 |
|
|
3次元磁場解析 |
|
|
加速器の軌道計算 |
すでに計算速度、記憶容量の不足が感じられた。とくに、クォークループを取り入れた動力学的クォークで163×32の計算をするには、約十倍の性能向上が必要と筆者のメモにある。
16) 東京大学生産技術研究所(VP-100)
東京大学生産技術研究所は、1986年11月、VP-100 (64 MB)を設置した。スタンドアロンで運用。
17) 東京天文台(VP-50)
東京天文台は、1986年3月、VP-50 (32 MB)を設置した。フロントエンドはM-380Q。
18) 気象研究所(S-810/10)
気象研究所では、1986年9月、S-810/10 (32 MB)を導入した。フロントエンドはM-280D。
19)宇宙科学研究所(VP-200)
文部省宇宙科学研究所は、1986年VP-200を設置した。翌1987年にVP-400を設置。
20) 航空宇宙技術研究所(VP-400)
航空宇宙技術研究所(NAL、JAXAの前身の一つ)は、1986年12月、それまで稼働してたM380を撤去し、VP-400 (256 MB)を設置した。フロントエンドはM-780/10。これは、第1期数値シミュレータNSI(Numerical Simulator I)の主要マシンである。同じころVP-200も導入しているようである。
日本の学界の動き
1) (SM)2-II
慶応義塾大学の天野らは、この頃疎行列計算のための並列計算機(SM)2-IIを開発した。これは1983年ごろ開発した(SM)2を改良したものである。CPUはM68000で、20ノードで動作した。
2) 円周率
金田康正(東大)と田村良明(緯度観測所)は、1986年9月、東大のS-810/20を23時間用いて、円周率を3300万桁まで計算した。Gauss-Legendreの公式を用いた。1986年1月にDavid H. BaileyがCray-2により2936万桁まで計算した記録を破り、この時点での世界記録である。1981年に三好和憲(筑波大)と金田康正が筑波大学のFACOM M-200を137時間用いて200万桁求めて以来、日本人の日本のマシンによる活躍が目立っている。
3) 人工知能学会
1986年7月24日、人工知能学会が発足した。初代会長は福村晃夫名古屋大学教授。福村教授は、1984年から3年間にわたり、特定研究「多元知能情報の知的処理と統合化に関する研究」(15億円)の代表を務めている。
4) 日本計算機統計学会
日本には、当時統計学会、応用統計学会があったが、3番目の学会として計算機統計学会を創立しようということになり、筆者も発起人の一人となった。1986年10月3日~4日、富士通関西システムラボラトリで発会式があり、出席した。
5) 『超高速電算機が切り開く第3の科学』
週刊朝日の蜷川真夫編集委員が取材をしたいというので6月14日に上野の東天紅で取材を受けた。「電子テクノ・エリート」という特集で、7月11日号の『超高速電算機が切り開く第3の科学』という記事に登場した。他に、金田康正、桑原邦郎、柏木浩が登場している。筆者は、この記事では、PAXではなく商用のベクトルスーパーコンピュータ利用者として登場している。この特集は後に単行本『電子テクノ・エリート』(1987年1月、朝日新聞社)になる。
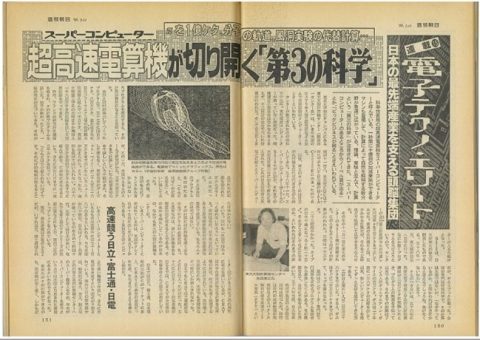 |
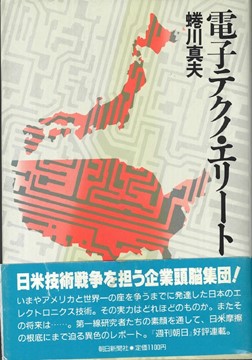 |
6) 緯度観測所
経緯は忘れたが、岩手県水沢市の緯度観測所(現、国立天文台水沢VLBI観測所)の1985年度の客員研究員を7月に委嘱され、1986年2月5日~7日に所内に滞在して、「最小二乗法によるデータ解析」の講義を行った。東北新幹線水沢江刺駅を降りて観測所に向かうと一面の銀世界で、その中で所員が働いていた。広い所内を案内していただいた。木村栄(ひさし)博士以来、緯度観測所の発足の由来である天体観測は、すでに自動化していたが、精神を忘れないように当番制で交代に観測しているとのことであった。
いろいろな研究が行われていたが、一番興味を引いたのは、重力加速度の絶対測定であった。特殊な鏡を真空中で自由落下させ、距離を光の干渉で、時間を原子時計で計れば、重力加速度が直接計れる。一番問題なのは鏡を離す瞬間で、振動が残ると精度が落ちる。緯度観測所では重力測定の長い歴史があり、佐久間式とか言って、下から支えたピエゾ素子で静かに投げ上げ、鏡が宙に浮いた瞬間、支えを外して自由落下させるんだそうである。父子相伝だという話も聞いたような記憶がある。様々な工夫により測定の精度は極めて高く、人間の活動が静まった深夜に測定しても、遠くの東北自動車道を走るトラックの振動が雑音になるとのことである。
当時、素粒子物理では「第5の力」が問題になっており、それが正しければ重力に原子番号に依存する成分が含まれるとのことであった。違う物質と鏡をくっつけて落下させれば重力加速度の違いがあるかが検証できるはずである。特に、並べて同時に測定すれば、色々な不確定性が相殺する。そのようなことを申し上げたが、怪訝な顔をしておられた。緯度観測所の方々は、超精密測定の専門家ではあるが、(素粒子屋のように)物理法則そのものを疑うという発想はないようであった。筆者一人では頼りなかったが、別の物理研究者の助言もあり、この実験は行われ、否定的な結果(第5の力はない)が得られたそうである。個人的な思い出である。
なお、2019年、世界中の8基の電波望遠鏡が協力して構成した国際研究チームEvent Horizon Telescopeは、楕円銀河M87の中心部にある巨大ブラックホール(の影)の撮影に成功したが、日本からは国立天文台水沢VLBI観測所が参加している。
国内会議
1) 大型行列シンポジウム
1985年に慶應義塾大学の野寺隆を中心に、日吉校舎図書館AVホールでPCGシンポジウム(PCG Symposium on Large Sparse Sets of Linear Equations)が行われたが、これに引き続き、1986年3月14日に「第2回大型行列シンポジウム――共役勾配法とスーパーコンピュータ――」が開催された。筆者は「格子ゲージ理論における共役残差法と最小残差法」という講演を行った。
2) データフロー・ワークショップ
電子通信学会(1987年1月からは電子情報通信学会)は、1986年5月に(工業技術院筑波研究センター共用講堂)で第1回データフロー・ワークショップを開催した。当時日本では、上記電子技術総合研究所を初め、大阪大学、旧電信電話公社などでデータ駆動コンピュータの研究が盛んであった。なお、このワークショップの発展として、1989年からJSPPが始まる。
3) 数値解析シンポジウム
自主的に組織している第15回数値解析シンポジウムは、1986年5月22日(木)~24日(土)に、日本大学平野菅保研究室の担当で日本大学軽井沢研修所において開催された。参加者は141名。筆者も参加した。
4) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所は、1986年11月13日~15日に、伊理正夫(東京大学)を代表者として、研究集会「スーパーコンピュータのための数値計算アルゴリズムの研究」を開催した。第18回目であるが、初めて「スーパーコンピュータ」を冠した研究集会であった。報告は、講究録No. 613に収録されている。富士通、日立、日本電気、日本Cray社のベクトルの発表、PAXの並列処理の発表、ベクトルの利用法やアルゴリズムなどの発表もあった。
5) 統計数理研究所
統計数理研究所では、12月22日~24日に研究会「確率過程とその周辺」が開催され、筆者は「格子ゲージ理論のランジェバンシミュレーション」と題して講演した。
日本の企業の動き
1) 半導体産業(不平等協定)
1986年、ディジタル半導体の日本のシェア(おそらく金額ベース)が45%となり、アメリカを抜いて世界の首位となった。1986年7月31日、日米半導体交渉が最終合意し、「日米半導体協定」(第一次協定)が結ばれた。これには「日本政府は日本国内のユーザに対して外国製(実質上はアメリカ製)半導体の活用を奨励すること」という不平等な内容が含まれていた。しかし、1987年に日米半導体摩擦が起こる。日本の首位は数年続いたが、89年以降、下降の一途をたどる。バブルの崩壊とも軌を一にしている。2008年ごろには、アジア・太平洋勢にも負けてしまう。
2) 日本電気(ACOS 2000、EWS4800)
日本電気は1986年2月、汎用コンピュータACOSシステム2000シリーズを発表した。OSはACOS-6である。出荷は1987年6月から。
1986年9月、日本電気はEWS4800を発表した。プロセッサはM68020、OSはSystem VベースのEWS-UX/Vを搭載した。1280×1024の高解像度20インチ大型ディスプレイを装備し、専用の高速グラフィックスプロセッサや、マルチウィンドウ制御用にグラフィックプロセッサを搭載していた。1990年からはMIPS R3000を搭載した。
1986年7月、アメリカのHARC (Houston Area Research Center)にSX-2を初輸出した。
3) 日立製作所(S-820)
日立製作所は1986年3月、ピーク性能が1.6 GFlopsのスーパーコンピュータを開発し、1号機を分子科学研究所に1987年夏に出荷すると報道された。実際には、1987年7月にピーク性能3 GFlopsのHITAC S-820が発表され、12月に1号機が出荷される。
4) 富士通(VP-30)
1985年4月に下位機種VP-50(ピーク性能は142 MFLops)を発表したが、1986年9月にさらに下位のVP-30を発表した。ピーク性能は110 MFlopsである。後に示すように企業などに多数販売された。
5) 三菱電機(ME1000)
1986年10月、エンジニアリングワークステーション、ME1000シリーズ(ME1200とME1500)を発表した。プロセッサはMC68020、浮動小数プロセッサとしてMC68881を搭載していた。OSにはUNIX System Vを採用した。
第五世代プロジェクトの成果をもとに、三菱電機は、AIワークステーションMELCOM PSIを商品化し1986年5月に発表した。7月から出荷の予定。
6) ソニー(NEWS)
ソニーは土井利忠を中心に社内ベンチャーの形でNEWS (Network Engineering WorkStation)を開発していたが、最初のシリーズとしてNWS-800シリーズを1986年10月に発表した。MC68020を2台搭載し、1台は計算用、もう一台はI/Oプロセッサである。OSはUNIX 4.2BSDで、NFSやX-Windowを搭載していた。発売は1987年1月。
7) キヤノン(RC-701)
キヤノンは世界初の電子スチルビデオカメラRC-701を1986年発売した。価格は500万円を超えていた。1984年に開催されたロサンゼルスオリンピックでキヤノンが開発し、報道写真の画像伝送に使われたシステムを製品化したものである。記憶媒体は2インチのフロッピーディスクであるが、アナログ方式(FM記録)で記録再生する。この時、業界で規格統一が行われ、スティルビデオカメラ(SV)の規格が決められた。同様なものは、ソニー、ミノルタ、カシオ、ニコン、京セラ、富士フィルムからも発売された。
画期的な機械であったが、高価格の割に画質が悪く、消費電力が大きく、アナログ記録のためPCとの接続が困難、再生が不便(テレビ接続または再生機など)などのため、一般商品としては成功したとはいえないが、現在のデジカメの先駆であった。
8) 東芝(J-3100、フラッシュメモリ)
東芝は、海外向けのT-3100(ヨーロッパで1986年4月、アメリカで6月に発売)をベースに1986年11月、国内向けのラップトップコンピュータJ-3100(モデルB11、B12)を発売した。CPUはIntel 80286、メモリ640 KB、B12モデルでは10MBのハードディスクを内蔵している。ラップトップとはいえ重量は6 kgを越え、膝に乗せるとまるで拷問だというジョークもささやかれた。
東芝の舛岡富士雄は、1986年頃、NOR型に続きNAND型フラッシュメモリを発明した。
9) 松下電器
1986年6月、松下電器は、4 Mbおよび16 MbのDRAMの開発に成功したことを発表した。4 Mbは0.8μm、16 Mbは0.5μmの最小線幅である。4 Mbのサンプルは3年後、16 Mbのサンプルはさらに数年後に出荷される予定。
10) 日本電気(PC-VAN、PC-9801VX)
日本電気は、1986年4月3日、一般向けのパソコン通信サービスPC-VANを開始した。アスキーネットなどとともに日本における有料パソコン通信として最古の一つである。
また、1986年10月、PC-9801VXを発売した。CPUは8 MHzの80286と10 MHzのV30である。VX4は20 MBのSASI HDDを搭載。
11) ATR研究所
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(Advanced Telecommunications Research Institute International、通称ATR)は、1986年4月、大阪ビジネスパーク(OBP)を暫定的な場所として、通信システム研究所、自動翻訳電話研究所、視聴覚機構研究所、光電波通信研究所を設立した。1987年7月から京都府精華町(関西文化学術研究都市)にATR本研究所を建設しており、1989年4月に開所する。
標準化
1) 情報処理学会(情報規格調査会)
1961年に発足したISO/IEC国内委員会は、1961年に情報処理学会規格委員会と改名して活動と続けてきたが、1986年9月に情報規格調査会に発展的に改組された。規格委員会の会計は、1975年から国産メーカ6社と日本IBM社、電電公社の負担により一応独立して扱ってきたが、専任職員の給与や共通事務経費など管理費的なものは学会全体と一体で処理していた。情報企画調査会になってからは、会計的に完全に独立した。
規格標準化のために多数の(1980年頃で700人弱)委員が活動していたが、そのうち大学・研究所・電電公社などの委員は少数(200人程度)で、大部分はメーカらからの委員であった。当時国際的な情報技術の標準化は、大半の原案はIBMなどによる事実上の標準だったので、メーカから見れば、規格の審議というより情報入手の場であった。しかし、1977年のOSI審議のころから、既成事実の追認でない標準化の議論が盛んになり、情報処理学会でもその対応が必要になったのである。
2) 日本工業規格「情報部門」
1986年8月18日、通産省・工業技術院は、情報技術分野の標準化の進展に対処し、その規模の体系的整備を図るため、日本工業規格に「情報部門」(部門記号・X)を新設することを決めた。JISの部門新設は1953年以来33年ぶりのことである。8月中に細目規定を決め、1987年3月1日に情報部門に移行する。
3) 新JISキーボード
1986年、通商産業省により「仮名漢字変換形日本文入力装置用けん盤配列」JIS C 6236 として標準化された。通称「新JIS配列」。仮名文字をASCIIキーボードの英字の範囲にすべて割り当て、特殊文字キーの部分は使っていないのが特徴である。シフトキーは常にロックされ、次に押すまで保持される。濁点キーは右手薬指の位置に置かれている。1987年にJIS X 6004と改名される。指の運動特性を精密に配慮した配列であったが、結局普及せず、1999年に廃止される。シフトキーのロック機構は英文を入力するときに極めて使いにくく、「誰がこんな規格を決めたのか」とJISを呪ったことを記憶している。
4) Unix
1986年4月、Berkeleyから4.2 BSDの改良版である4.3 BSDが発表された。4.3 BSDの一部はDEC社のUltrix-32 V1.2にも取り入れられている。
1986年6月には、AT&TからSystem V R3.0が発表された。これはBerkeley版の特徴とされていたネットワーク機能を大幅に強化し、ネットワーク内でのファイル共有機能も含まれている。IBMのUNIXであるAIXはRelease 3から派生したOSである。
5) Mach
Carnegie-Mellon大学では、DARPAの支援により、1985年からMachプロジェクトによりマイクロカーネルタイプのOSの開発が始まった。Machは”Multiple Asynchronously Communication Hosts”に由来する。1986年にMach 1.0が研究開発の進捗報告としえ発表された。新しい仮想記憶とIPCは実装されていたが、タスクとスレッドはまだ実装されていなかった。1989年にリリースされるMach 3.0で初めてマイクロカーネル化され、MkLinuxのカーネルとしても使われる。
6) SGML
IBM社にいたCharles Goldfarbが開発していたSGML (Standard Generalized Markup Language)は、1986年にISO 8879:1986として国際標準となった。日本標準はJIS X 4151:1992である。
7) SCSI
Small Computer System Interface、略してSCSI(スカジ)は、周辺機器とコンピュータ間のデータのやり取りを行うインタフェース規格の一つである。SCSI-1と呼ばれる最初のSCSI規格X3.131-1986は、1986年にANSI (American National Standards Institute)のX3T9技術委員会によって制定された。SCSI-2は1990年8月に、X3.9.2/86-109として制定される。
8) NNTP
1986年5月、UCBのPhil LapsleyらがNNTP (Newtowrk News Transfer Protocol)の仕様であるRFC 977を完成させた。
DOEは従来から稼働していたHEPnetとMFEnetとを統合しESnetを創設した。中国は、鄧小平の決断により「863計画」が承認され、コンピュータなど情報技術も7つのハイテク分野の1つとして国家的に推進されることになった。LINPACK 1000がベンチマークとして提案され、Livermoreループも発表される。Burroughs社はSperry社を買収し、Unisysという新会社が発足した。
 |
 |
 |


1件のコメントがあります
著者の小柳義夫です。「15) 高エネルギー物理学研究所(HITAC S-810/10)」の項に間違いがありましたので、16日朝に訂正しました。「格子ゲージグループの利用状況」として示した表は、85年9月から85年12月まで4か月の全体の運転状況でした。あわせて、利用状況も加筆しました。