新HPCの歩み(第112回)-1993年(b)-
|
IBM社がマルチチッププロセッサPOWER1を用いた超並列機SP1を発売し、日本でもそれを使いこなそうと、HPCユーザーズ・フォーラムにパラレル分科会ができた。日本電気がCenju-3を、富士通がVPP500を出荷する。リクルートISRは閉鎖され、Mendez所長は独立の会社ISRを創立する。 |
国内会議
1) NSUG
NSUG(日本サン・ユーザ・グループ)は、1993年2月2日、仙台国際ホテルにおいて、NSUG 2月仙台セミナーミーティングを開催した。
|
13:30-13:40 |
挨拶 |
NSUG幹事 東北大学応用情報学研究センター 野口 正一 |
|
13:40-14:40 |
「ToolTalkプログラミング」 |
日本サン・マイクロシステムズ 五十嵐 賢二 |
|
14:40-14:55 |
コーヒーブレイク |
|
|
14:55-15:55 |
「分散開発環境のアーキテクチャ構築技術の動向 -PCTEを中心として」 |
(株)SRA 岸田 孝一 |
|
15:55-16:05 |
ブレイク |
|
|
16:05-17:05 |
「Solaris2.1技術概要」 |
日本サン・マイクロシステムズ 増月 孝信 |
|
17:10-18:40 |
懇親会 |
|
また、9月17日には、第5回NSUGシンポジウム/総会が、川崎市のホテルKSPで開催された。
|
9:45-10:15 |
[NSUG総会] |
|
|
10:15-10:20 |
[祝辞] |
日本サン・マイクロシステムズ 社長 天羽浩平 |
|
<NSUGシンポジウム> |
||
|
10:20-11:20 |
基調講演 I 「超並列計算システムの基本アーキテクチャ」 |
東京大学理学部情報科学科 平木敬 |
|
11:35-12:35 |
基調講演 II Spring – A Distribute Object-Oriented Operating System」 |
Vice President & Sun Fellow, SunSoft, Inc Jim Mitchell |
|
パラレルセッションA |
||
|
13:30-14:30 |
「UNIX ネットワークセキュリティ」 |
奈良先端科学技術大学院大学 山口英 |
|
14:45-15:45 |
「OpenXPress」 |
(株)アステック 木下仁 |
|
16:00-17:00 |
(A):「Sunのネットワークソリューション」 |
サンコネクト主任 八木 寅光 |
|
(B):「Wabi Overview」 |
サンセレクト 田中 努 |
|
|
パラレルセッションB |
||
|
13:30-14:30 |
「High Availability in a Distributed Sun Architecture」 |
日本フュージョンシステム(株)Micheal Arefont |
|
14:45-15:45 |
「サン・プラットフォーム上のオラクルの戦略および技術動向」 |
米国オラクル サン担当製品開発部門 Joseph Vassallo |
|
16:00-17:00 |
「グラフィックスの新製品および新技術」 |
日本サン・マイクロシステムズ 野瀬昭良 |
|
パラレルセッションC <パネル討論>「Solarisに向けて」 |
||
|
13:30-17:00 |
司会: 青島 茂 日本サン・マイクロシステムズ(株)(NSUG幹事) パネリスト: 岩瀬浩治 (株)東芝 坂下秀 (株)アステック 吉田茂樹 東京大学生産技術研究所 |
|
|
17:15~ |
ビア・パーティー |
|
2) PCG’93
1985年から毎年慶応義塾大学理工学部で開かれてきたPCGシンポジウムは、9回目のこの年「並列処理と科学計算シンポジウム」として3月2日に開催された。たまたまDavid Kahanerの報告に英語版のプログラムがあるので紹介する。シンポジウムは基本的に日本語で行われた。
|
10:00-10:05 |
Opening remarks |
Takashi Nodera, Keio U. |
|
10:05-10:20 |
Numerical analysis of natural convection betweeen two eccentric cylinders using GSMAC-FEM |
Noboru Miyamoto, Takahiko Tanahashi, Keio U. |
|
10:20-10:35 |
Numerical analysis of natural convection of thermo-electrically conducting fluids using GSMAC-FEM |
Yoshiatsu Oki, Takahiko Tanahashi, Keio U., |
|
10:35-10:45 |
Cutting and pasting pictures and figures using Latex |
Takashi Nodera, Keio U. |
|
10:45-11:15 |
– coffee break – |
|
|
11:15-12:15 |
Lanczos-type methods for solving nonsymmetric linear systems |
Kang C. Jea, Fu Jen Univ., Taiwan (speaker), David M. Young, U. Texas at Austin, USA |
|
12:15-13:30 |
– lunch – |
|
|
13:30-14:00 |
Right-hand side dependencies of preconditioned conjugate gradient methods |
Hidehiko Hasegawa, Univ. of Library and Info. Science |
|
14:00-15:00 |
A Matrix Analysis of Conjugate Gradient Algorithms |
Steven F. Ashby, LLNL, USA (speaker), Martin H. Gutknecht, ETH, Zuerich |
|
15:00-15:30 |
– coffee break – |
|
|
15:30-16:00 |
Parallel computation for solving elliptic partial differential equations based on domain decomposition |
Takumi Washio, Ken Hayami, C&C Lab, NEC |
|
16:00-16:30 |
Monte Carlo and averaging methods for the biharmonic Dirichlet problem |
Kazuo Amano, Josai Univ., T. Saito, Toppan Insatsu |
|
16:30-17:00 |
Calculation of the spectrum of a model equation for resistive magnetohydrodynamics |
Takashi Kako, U. Electro- Communications, M. Chiba, Engineering, Saitama Univ. |
3) HAS研
HAS研(Hitachiアカデミックシステム研究会)は、1993年3月30日、特別講演および第6回研究会を開催した。
|
特別講演 |
|
|
大学コンピュータセンターの90年代後半へ向けてのアプローチ |
広島大学 池田 秀人 |
|
第6回研究会 「WSのシステムインテグレーション」 |
|
|
WSの持つ文化と3050R |
千葉大学 橋本 明浩 |
|
高エネ研におけるワークステーション環境 |
高エネルギー物理学研究所 八代 茂夫 |
|
NetWareによるCSS構築事例 |
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 舟窪 憲一 |
|
3050/Rによるネットワーキングと256色カラーグラフィックス |
埼玉大学 井門 俊治 |
|
工学院大学におけるWSを中心としたシステム導入事例 |
工学院大学 佐古 卓史 |
11月24日~25日には、第5回シンポジウムと第7回研究会を開催した。
|
製品紹介(1993年11月24日) |
||
|
FLORA3100の紹介と3050RX/200の紹介 |
株式会社日立製作所 金子 徹 新 善文 |
|
|
第5回シンポジウム(1993年11月24日) 「教育研究現場におけるPC/WSの多様な活用とこれからの展望」 |
||
|
情報教育におけるPCとWSの比較 |
日本大学 戸川 隼人 |
|
|
教育現場におけるPCの多様な活用提案 |
信州大学 中村 八束 |
|
|
ヒトゲノム計画における計算機利用 |
東京大学 高木 利久 |
|
|
製品紹介(1993年11月25日) |
||
|
オープンシステム用ディスクアレイサブシステムのご紹介 |
株式会社日立製作所 熊沢 清健 |
|
|
特別講演(1993年11月25日) |
||
|
インターネットにおける公開情報サービス |
東京大学 石田 晴久 |
|
|
第7回研究会(1993年11月25日)テーマ「WS/PCをめぐる教育現場の現状と課題」 |
||
|
工学部における情報教育の実践について |
工学院大学 荒 寛 |
|
|
マルチメディアCAIを用いた相互教授の実践と評価 |
日立電子サービス株式会社 山本 洋雄 |
|
|
ネットワーク化されたマルチメディアPC/WSを利用した文系学部専門教育のいくつかの試み |
千葉大学 土屋 俊 |
|
4) JSPP 93
第5回目のJSPP93は、「並列処理技術や応用」をテーマとして、早稲田大学総合学術情報センター国際会議場で5月17日~19日に開かれ、筆者はプログラム委員長を務めた。主催は、情報処理学会・計算機アーキテクチャ研究会、データベース研究会、アルゴリズム研究会、プログラミング-言語・基礎・実践-研究会、数値解析研究会、電子情報通信学会・コンピュータシステム研究会、協賛は、日本ソフトウェア科学会、人工知能学会であった。委員長は村岡洋一、副委員長は小柳 義夫(プログラム委員長)と島田 俊夫、幹事は、上田 和紀,中島 浩,村上 和彰であった。
5) 数値解析シンポジウム
第22回数値解析シンポジウム(1972年発足)が、6月9日(水)~11日(金)に宮城勤労総合福祉センター蔵王ハイツで開かれた。参加者93名。
6) 愛媛大学
山本哲朗(愛媛大学)主催の国際シンポジウムが7月5日~9日に奥道後ホテルで開かれ、筆者はマルチグリッド前処理CG法について講演した。主要な論文は、JCAM 60 (1-2) (1995)に出版されている。愛媛大学は1990年8月(世界数学会議に続き)にも同様な国際会議を松山のANAホテルで開催している。
7) SWoPP 93
第6回目のSWoPPは、「1993年並列/分散/協調処理に関する『鞆の浦』サマー・ワークショップ (SWoPP 鞆の浦’93)」の名の下に、1993年8月18日(水)~20日(金)に 鞆シーサイドホテル(広島県福山市)において開催された。発表件数127、参加者数248であった。共催研究会は、電子情報通信学会からは、コンピュータシステム研究会, フォールトトレラントシステム研究会、情報処理学会からは人工知能研究会、アルゴリズム研究会、計算機アーキテクチャ研究会、プログラミング-言語・基礎・実践-研究会、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会、システムソフトウェアとオペレ-ティング・システム研究会であった。筆者は覚えていないが、会場のマイクがカラオケ用のマイクで、誰かの講演の最中にカラオケの採点が始まり大笑いになったとのことである。当時RWCPの金田泰の報告が残っている。
8) ISR Workshop
リクルートISR (Institute for Supercomputing Research)は1993年3月に閉鎖され、Raul Mendezは1993年9月に東京で同じイニシャルのISR (International Systems Research)という会社を立ち上げた。インターネットを活用したビジネスをターゲットとしている。MendezはwebブラウザMosaicに注目し、webページをデータベースと連動させるためのミドルウェアZolarの開発に着手し1995年に完成した。現在でも、クラウドサービスやパスワードを使わない認証などにもビジネスを広げている。氏のインタビュー記事を参照。
ISR Workshop「実用化時代の並列処理」が、8月30日に筑波第一ホテル(現在のホテル日航つくば)において開催された。ワークショップとあわせて並列コンピュータ展示会も開かれた。プログラム委員は、R. Mendezと朴泰祐と筆者であったが、主催のISRはリクルートISRでもMendezのISRでもなく、Craig Lundを社長とするアメリカのコンサルティング会社(所在地Durham, New Hampshire)であり、MendezのISRのアメリカ側のパートナーらしい。協賛は(財)科学教育研究会で事務局も担当した。参加者は約100人であったが、前に述べた1993年度の補正予算でスーパーコンピュータを購入する予定の日本の11組織から参加を得て、アメリカのISRとしてはこれらのカストマーを米国のベンダと結びつけるよいチャンスであった。
ちなみに、Craig Lundは元々Mercury Computer Systemsという組み込みシステム会社の技術者であったが、この頃はISRの経営とともに雑誌Parallelogramの編集者もやっていた。
ワークショップのプログラムは以下の通り。
|
10:00 |
“High Speed, Wide Area Networking” (in Japanese) |
Mr. Mitsuru Miyauchi, NTT |
|
11:00 |
“Case Study 1: Large-scale Simulation in Plasma Physics”(in Japanese) |
Prof. Kunihiko Watanabe, National Institute for Fusion Science |
|
12:00 |
LUNCH |
|
|
13:30 |
“Case Study 2: An Amateur’s Experiences with Parallel:Processing: Large Scale Computing on the AP-1000″(in Japanese) |
Prof. Atsushi Nakamura, Yamagata University |
|
14:30 |
“Using Workstation Clusters as Parallel Computers” (in English) |
Mr. Craig Lund, ISR America |
|
15:30 |
COFFEE BREAK |
|
|
16:00 |
“The High Performance FORTRAN Standard for Parallel Computing” (in English) |
Mr. Larry Meadows, Portland Group |
|
17:00 |
“Supercomputer Performance: Past, Presence, and Future”(in Japanese) |
Mr. Satoshi Sekiguchi, Electro Technical Laboratory |
9) 数理解析研究所
京都大学数理解析研究所の研究集会「数値計算アルゴリズムの現状と展望」は山本哲朗(愛媛大学)を代表として、1993年10月25日~27日に開催された。第25回目である。報告書は講究録No. 880に収録されている。
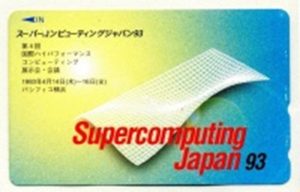 |
|
10) Supercomputing Japan 93の延期
第4回目のSupercomputing Japan 93は、昨年と同様にパシフィコ横浜で4月14日~16日に計画していたが、出展者から、昨今の経済状況に鑑み、あと一年景気の回復を待ちたいとの希望が出され、今年は中止して1994年6月15日~17日に、東京池袋サンシャインシティーに会場を戻して開催することとした(結果的にはこれも中止される)。せっかく作ったテレフォンカードが宙に浮いてしまった(写真)。
日本の企業の動き
1) 日本電気(Cenju-3)
日本電気は、並列処理マシンCenju(1988年)、Cenju II(1992年)の経験を元に、1993年3月31日、Cenju-3を発表した。これは超並列MIMDコンピュータの商品であるが、「当面はユーザに実験マシンとして使ってもらいながらソフト環境の整備を進める」ということでテストベッドの扱いであった。プロセッサとしてはMIPSのR4400のNEC版であるVR4400SC(1992年11月発表)を用いた。VR4400SCは75 MHzで動作し、最大50 MFlopsの演算性能をもつ。相互接続網は多段接続であり、最大256個のPEを接続できる(ピーク12.8 GFlops)。エントリモデルでは50 MHz動作で、最大33.3 MFlops/nodeである。
日本電気は1995年1月、川崎市の中央研究所内に並列処理センターを設置し、大学や研究機関の研究者にCenju-3(64プロセッサモデル2台と32プロセッサモデル1台)の提供を開始した。
2) 富士通(VPP500)
航空宇宙技術研究所(NAL)のところに書いたように、富士通は数値風洞(NWT)を設置し稼働した。 その商用機であるFACOM VPP500も共通の技術開発が行われており、CPUボードではBiCMOS、ECL、GaAsの3種類のLSIが使用されている。主な違いは、VPP500のクロックが10nsである(したがって、プロセッサ当たりのピーク性能が1.6 GFlops)のに対し、NWTは9.5 nsであること(ピーク性能1.68 GFlops)である。演算ノードは140台なので、ピーク性能(Top500ではRpeakという)は235.79 GFlopsである。
VPP500の主要な納入先は以下の通り。Top500欄はTop500の初出の年月。設置日より早いこともある。Rmaxはチューニングにより漸次改良されているが、初出の値を示す。関係者によると、Aachen工科大学には一足早く1992年11月に日本から出荷し、調整の上12月末に引き渡したとのことである。
|
設置年月 |
Top500 |
設置場所 |
ノード数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1992/12 |
(94/6) |
Aachen工科大学(独) |
4 |
4.8 |
6.4 |
|
1993/1 |
(93/11) |
航空宇宙技術研究所(NWT) |
140 |
124.0 |
235.79 |
|
1993/12 |
(94/6) |
宇宙科学研究所 |
7 |
8.3 |
11.2 |
|
1994/2 |
(94/6) |
筑波大学 |
30 |
32.9 |
48.0 |
|
|
(94/6) (95/12) |
オングストローム技術組合 |
30 →32 |
32.9 46.1 |
48.0 51.2 |
|
|
(94/6) |
理化学研究所(和光) |
28 |
30.8 |
44.8 |
|
|
(94/6) |
通信総合研究所 |
10 |
11.7 |
16.0 |
|
1994/8 |
(94/11) |
4 |
5.6 |
6.4 |
|
|
1995/1 |
(95/6) |
高エネルギー物理学研究所 |
80 |
98.9 |
128.0 |
|
|
(95/6) |
日本原子力研究所 |
42 |
54.5 |
67.2 |
|
|
(95/6) (95/12) (96/11) |
富士通システム評価センター |
16 8 6 |
21.7 11.0 9.6 |
25.6 12.8 9.6 |
|
|
(95/6) (95/12) |
京都大学 |
16 →15 |
21.7 20.3 |
25.6 24.0 |
|
|
(95/6) (95/12) |
東京大学物性研究所 |
16 →40 |
21.7 56.9 |
25.6 64.0 |
|
|
(95/6) |
Fujitsu America(米) |
4 |
5.6 |
6.4 |
|
|
(95/6) |
IFP Énergies nouvelles(仏) |
4 |
5.6 |
6.4 |
|
|
(95/6) |
都立科学技術大学 |
4 |
5.6 |
6.4 |
|
|
(95/6) |
トヨタ自動車 |
4 |
5.6 |
6.4 |
|
|
(95/12) |
国立遺伝学研究所 |
40 |
56.9 |
64.0 |
|
1996/1 |
(95/12) |
名古屋大学 |
42 |
59.9 |
67.2 |
|
|
(96/11) |
動力炉・核燃料開発事業団 |
16 |
23.6 |
25.6 |
3) 富士通(PCW’93その他)
昨年に引き続きPCW’93 (Parallel Computing Workshop)を川崎市中原の富士通川崎工場において11月11日に開催した。招待講演は、John Darlington(Imperial College of Science, Technology & Medicine, London)による”Parallel Computing in Europe, Trends and Speculations”であった。一般講演のタイトルは以下の通り。( )は、アブストラクトから類推した内容。
|
Simulated Annealing Heuristics for Static Task Assignment |
Kazuo Horikawa et al. (Kyoto U.) |
|
(Functional programming) |
Tetsurou Tanaka et al. |
|
(the PVM system to the Fujitsu AP1000) |
C. W. Johnson et al. (ANU) |
|
(the new collective communication primitives distribute and concatenate) |
Gavin Michael et al. (ANU) |
|
Performance Measurement of the Acacia Parallel File System for the AP1000 Multicomputer |
Bradley M. Broom (ANU) |
|
An Image Fileserver for the AP1000 |
Kazuichi Ooe et al. (Fujitsu Laboratories) |
|
A Reconfigurable Torus Network |
Kenichi Hayashi et al. (Fujitsu Laboratories) |
|
Data distributed volume rendering on the Fujitsu AP1000 |
Raju Karia (ANU) |
|
Parallel FEM Solution Based on Substructure Method |
Hideo Fukumori et al. (Waseda U.) |
|
(Linear Algebra) |
R. P. Brent et al. (ANU) |
|
Progress Report on the Study of the Effect of Presence of Grain-Boundaries on Martensitic Transformation |
Tetsuro Suzuki (U. Tsukuba) |
|
Parallelization of 3-D Radiative Heat Transfer Analysis in Nongray Gas |
H. Taniguchi et al. (Hokkaido U.) |
|
Probabilistic Fracture Mechanics Analysis on Massively Parallel Computer AP1000 |
Shinobu Yoshimura et al. (U. Tokyo) |
|
Domain decomposition program for polymer systems |
David Brown et al. (U. Manchester) |
|
A new technique to improve parallel automated single layer wire routing |
Hesham Keshk et al. (Kyoto U.) |
|
Towards a Practical Information Retrieval System for the Fujitsu AP1000 |
David Hawking et al. (ANU) |
|
Parallel Computer System for Visual Recognition |
H. Takahashi |
|
Futurespace: a coherent, cached, shared abstract data type |
Paul H. J. Kelly et al. (Imperial College, London) |
|
Design of a Programming Language for Set-Oriented Massively Parallel Processing |
Hirofumi Amano et al. (Keio U.) |
|
Implementation of UtiLisp/C on AP1000 |
Eiiti Wada et al. (U. Tokyo) |
|
Implementing the PVM (Parallel Virtual Machine) on the AP1000 |
Shigenobu Iwashita et al. (Kyushu U.) |
|
Improvement of Communication Performance by Reduction of Traffic Conflict in a Parallel Computer |
Hiroyuki Kanazawa et al. (Fujitsu) |
|
Using the Bulk-Synchronous Parallel Model with Randomized Shared Memory for Graceful Degradation |
Andreas Savva et al. (Tokyo I. T.) |
|
The LINPACK benchmark on the AP1000 with Numerical Computation Accelerators |
Kazuto Kamimura (Fujitsu Laboratories) |
|
Parallel Processing of Logic Functions Based on Binary Decision Diagrams |
Shinji Kimura et al. (Nara I. Sci. & Tech.) |
|
Neural Network-Based Direct FEM on a Massively Parallel Computer AP1000 |
Genki Yagawa et al. (U. tokyo) |
|
Error Analysis of Parallel Computation: Direct Solution Method of Linear Equations |
Syunsuke Baba et al. (U. Electro- Communications) |
|
The Effect of Parallel Processing and Hill-Climbing Methods on Genetic Algorithms |
Hajime Ohi et al. (Fujitsu) |
|
Dynamic balancing of computational loads of multiprocessor system in the DSMC simulation |
Mitsuo Yokokawa et al. (JAERI) |
|
Monte Carlo Shielding Calculation without Variance Reduction Techniques |
Makoto Takano et al. (Donen) |
|
Parallel computing of Si-slab energy-band |
Itsuo Umebu (Fujitsu) |
|
Direct simulation of Homogeneous Turbulence by Parallel Computation |
Kazuharu Ikai et al. (Science U. Tokyo) |
|
The Implementation and Evaluation of Large Scale Neural Network “CombNET-II” on AP1000 |
Shinji Kuno et al. (Nagoya I. Tech.) |
|
Toward Parallel Simulation of Ecology System |
Tomomi Takashina et al. (U. Electro- Communications) |
|
Parallel Speculative Computation of Simulated Annealing on the AP1000 Multiprocessor |
Andrew Sohn (New Jersey I. Tech.) |
|
A Parallel Genetic Algorithm Retaining Sequential Behaviors on Distributed-Memory Multiprocessors |
Jongho Nang (Fujitsu Laboratories) |
日経産業新聞6月7日付によると、富士通はAP1000に組み込む演算加速装置NCAを開発したとのことである。数値計算性能が20倍になるという。詳細は不明である。
富士通アメリカは、1993年6月22日、TimeSlice Technology Inc.からベクトルコンピュータVPX260/10(日本のモデル名ではVP2600/10)の注文を受けたと発表した。ピーク性能は5 GFlops。アメリカでは2月のGeco-PraklaからのVPX220の注文に次ぐ2台目の受注である。
4) 日立製作所(3050RX、HITACHI 9000)
日立は1993年4月、Hewlett-Packard社のPA-RISC PA7100を搭載したワークステーション3050RXを発表した。UNIXサーバ3500シリーズも同時に発表された。
また6月には、HP社のOEM製品として、HITACHI 9000シリーズを発表した。
Hewlett-Packard社と日立は、1993年7月26日に共同声明を発表し、日立は今後HP社製のPA-RISC-baseのワークステーションを日立のブランドとして販売することになったと述べた。これまで日立が販売してきた日立製のPA-RISCチップを搭載したシステムの販売も続ける。
5) 日本IBM(分社化、社長交代)
日本IBM社は、1993年1月1日付で、PCを含む中型以下のコンピュータを販売してきた情報システム事業本部と、サービス・ビジネス事業本部を、100%出資の子会社「日本IBM情報システム株式会社」および「日本IBMサービス株式会社」として分社化した。また本体の日本IBMの新社長に北城恪太郎を指名し、椎名武雄社長は代表権のある会長に就任した。
日本IBM社は、1984年11月に東京千代田区の大手町センタービルに「IBM情報科学館」を設置し、これまで数十万人が来館したが、1993年12月8日(日本工業新聞では28日)で閉館し、1994年3月に同社の幕張テクニカル・センター1階に開館することとなった。
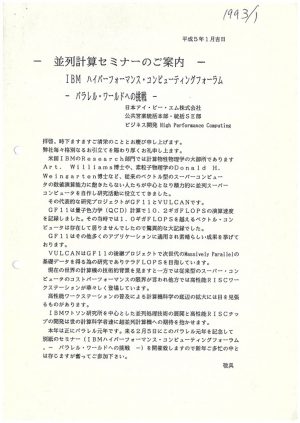 |
|
6) 日本IBM(SP1披露)
後述のように、IBM社は2月2日、SP1を世界的に発表した。日本でも、2月5日(金)に白金の都ホテル(現シェラトン都ホテル東京)でSP1のお披露目が開かれ、筆者も統計数理研究所(南麻布)での講義を終えて駆けつけた記憶がある。写真のように、招待状には「並列計算セミナーのご案内 IBMハイパフォーマンス・コンピューティングフォーラム -パラレウ・ワールドへの挑戦-」とあり、文中にはGF11とVulcanを紹介するという趣旨が書かれている。少し先のページには、Parallel Strategyとあり、”RISC System/6000 nodes”とか”Scalable System”などと書かれていて、若干は匂わせているが、SP1への言及はなく、1月に招待状を見たときにはこんな大ごととは気付かなかった。
懇親会で、突然壇上に上げられたので、「IBMという会社はいつも出遅れる。コンピュータ自体もそうだし、PCもそうだし、今度の並列機もそうだ。でも、その後市場を席巻する(つまり後出しじゃんけんで勝っている)。今度のマシンも市場を席巻するであろう。」などと北城社長の前で言ってしまった。
7) 日本IBM(HPCユーザーズ・フォーラム)
日本IBM社はユーザグループとしてHPCユーザーズ・フォーラムを組織し、東京理科大学教授(東京大学名誉教授)川井忠彦教授を会長にお願いしていた。SP1の発売開始にともない、ユーザーズ・フォーラムの中に約半年の予定で「パラレル研究分科会」を作り、筆者が座長、八尾徹(三菱化成)と窪島達雄(日産車体)両氏が幹事となった。設立記念を兼ねて、12月9日に第1回の定例会を開いた。定例会はほぼ月1回のペースで開催した。
パラレル研究分科会では、川崎のIBMに設置されているSP1を、参加者に試用させ、並列処理を体感させるワークショップを行った。主として企業のメンバ10数名が参加した。応用テーマとしては、PVMやFORGE90の試用のような練習レベルから、FEM、分子科学、3次元乱流、中性子モンテカルロ、ILUCGS法などの実用問題までいろいろあった。
8) 計算流体力学研究所
桑原邦郎が私財を投じて設立した計算流体力学研究所は、バブルの崩壊に伴って業績不振に陥ったが、日経ビジネス1993年6月14日号のインタビューで、桑原氏は「父親の遺産を惜しげもなくスーパーコンに投入、100億円もの資金を使ったが、それ自体には悔いはない」と語っている。
新会社「流体力学研究所」を設立してソフトウェアを中心とした事業を継続した。日本クレイがこの会社に出資し、スーパーコンピュータを貸与するとのことである。一部のソフトをクレイ製品に移植する作業が始まった。
なお、桑原氏は、2008年9月13日、心不全で亡くなられる。享年65歳。筆者は東大での同学年で、早世が惜しまれる。ご冥福を祈ります。
9) 日本Convex社
日本Convex社は、1993年12月2日、第5回 日本コンベックスユーザコンファレンスをホテルニューオータニで開催し、汎用プロセッサPA-RISCを用いた並列計算機SPP-1などについて発表した。アーキテクチャとして一番のポイントは、分散共有メモリを実現するメモリ回りのクロスバスイッチあたりであるが、重要なことはまだ秘密だと言うことで説明はなかった。パーティの席で、副社長(社長かも?)のTerrence L. Rock氏に、「メモリ回りのハードウェアは高速が要求されるので大変でしょう。」と水を向けると、「そうだ、GaAsを使うんだ。」と、ポロリ。「その話は知ってますが、秘密じゃないんですか。」と言うと、「うん、秘密だ、でも僕は君に言ってしまった。」そして、「秘密というとかえって広まるから宣伝になる。」とか。C3800シリーズでも富士通製のGaAsクロスバスイッチを使っているので、技術的には連続しているのであろう。参加していた某氏の勘によると、プロセッサ8台(これをノードという)までは高速だが、それを越えた通信は遅いのではないか、と予想していた。コヒーレンシをどうするのかなど知りたいことは山ほどあったが、まだ聞けなかった。製品としては、1994年2月に正式発表し、3月に初出荷とのことであった。
10) キヤノンソフトウェア株式会社
キヤノンソフトウェア株式会社(1974年創立)は、1993年5月、KSR (Kendall Square Reserch)社と契約を結び、KSR社の高性能並列コンピュータの、日本国内での販売、サポート、サービスを担当することになった。
11) IIJ
株式会社インターネットイニシアティブ(1992年12月3日に株式会社インターネットイニシアティブ企画として設立)が、1993年7月にUUCPサービスを開始し、11月にはインターネット接続サービスを始めた。外資系を除き日本で初めての商用インターネットであった。1994年2月28日に、旧電気通信事業法に基づく特別第二種電気通信事業者に登録。資金集めには相当苦労したようで、ある大企業の幹部からは、「インターネットが事業で使われるようなことになれば、全裸で逆立ちして銀座を歩いてみせますよ」とまで言われたそうである(日本経済新聞電子版2020年4月30日)。この幹部は逆立ちで銀座を歩いたのだろうか?
次回は、日本における超並列コンピュータの設置一覧を載せる。続いて標準化や性能評価に関する活動など。MPIやHPFの規格化の議論が急速に進み、Unixの標準化の動きも激しい。Jack Dongarraらは、LINPACK HPCを用いてTop500を始める。
(アイキャッチ画像:ORNLに設置されたIBM SP1 出典:Wikipediaより )
 |
 |
 |

