新HPCの歩み(第130回)- 1995年(d)-
|
航技研の数値風洞NWTは、チューニングの成果により、1994年11月から連続3回Top500の首位を占める(合計4回)。Globusプロジェクトが始まり、ScaLAPACKが初めて公開される。リオデジャネイロで開催されていたCHEP95の最終日、日本人参加者が市内でひったくり事件のため死亡した。コンピュータ草創期のビッグネームの訃報が続く。 |
アジアの動き
1) 曙光
中国科学院コンピュータ技術研究所は、曙光一号に続いて、曙光二号(Shuguang Erhao)を開発し、1995年5月11日に政府の証明書を獲得した。このマシンは後にDawning 1000と改名した。CPUなどは不明であるが、36ノードで構成され、ピークは2.5 GFlopsである。中国科学院生物物理学研究所においてDNA解析のために使われている。
2) シンガポール国立大学
National University of Singaporeは、1995年、初めてのCrayのベクトル計算機Cray J90をキャンパスに設置した。ピーク2.4 GFlops(12プロセッサ)。これ以前には、1987年末からNEC SX-1AがThe Advanced Computation Centreに設置されていた。
世界の学界の動き
1) Globus Project始まる
グリッド環境を構築するために必要な基板技術の開発を行うプロジェクトGlobus Projectが1995年ごろ始まった。参加者は、ANL、シカゴ大学、南カリフォルニア大学、IBM、Microsoft等の大学、研究所、企業である。その成果として、資源配分管理などの基本的なグリッド環境を構築できるミドルウェアGlobus Toolkitをオープンソースとして公開している。2003年9月に、Globus Allianceに名称変更する。
2) ScaLAPACK V1.0
J. Dongarraのグループは、1995年2月28日、ScaLAPACK、PBLAS、BLACSを初めて公式にリリースした。ScaLAPACK Version 1.0は、LAPACKの分散メモリ版である。これまではテスト版のリリースを発表してきた。ScaLAPACKのルーチンは、BLAS、BLACSおよびPBLASを用いて書かれており、Intel i860/Paragon、IBM SPシリーズ、CM-5およびPVM上に移植された。MPI版も近い将来公開する。1995年3月20日にはScaLAPACK Version 1.1が公開された。
3) GF11
IBM社Watson 研究所のDon Weingartenが開発していたQCD専用計算機GF11は、1991年ごろからやっと稼働し始め、1993年にはQCDの論文を発表したが、その後もGF11を利用して広範なQCDの計算を行っており、448プロセッサ構成で2年間の計算をおこない、グルーボールの質量と崩壊などに関する成果を得た。
4) Fermatの最終定理
1994年10月7日、Andrew WilesによってFermatの最終定理が証明され、10月24日、Wilesは2件の論文をAnnals of Mathematicsに投稿した。両論文は1995年2月13日に査読を通過し、1995年5月に掲載された。
5) ATIP
NIST(アメリカ国立標準技術研究所)所属の数値解析研究者であったDavid Kahanerは、1990年にONRFE (Office of Naval Research Far East)に最初2年の予定で出向し、日本に滞在していた。彼は、日本やアジアでのコンピュータを中心とした技術状況を研究し、電子メールやネットニュースなどにより膨大な量の情報を世界中に発信していた。その後延長して仕事を続けていたが、1995年2月、NISTやARPA他からの資金を得て、New Mexico大学の協力の下でATIP (Asian Technology Information Program、アジア科学技術交流協会)を創立した。
ATIPは米国ニューメキシコ州登録の非営利団体(所長 Dr. David K. Kahaner)で、欧米と日本、アジアの間の技術情報ギャップを埋めるため相互の関係機関間の協力や交流を仲介し、また正確な情報の提供を行うことを目的としている。その活動としては、レポートと解析、ベンチマーキング、訓練、個別の説明会、インタビュー、ワークショップ、セミナーの開催、技術調査ツアの便宜等がある。対象とする技術分野にはHPCを始め、ユビキタスコンピューティング、ナノテク、フエルセル、半導体技術、ロボティックス、スピントロニクスなどHPCを越える広い分野をカバーしている。
本部はニューメキシコ州Albuquerqueで、東京事務所を国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)の六本木のオフィスの一部に日本の事務所を置いた。2005年ごろまでに、韓国、北京、台湾、シンガポール、マレーシア、インドなどに事務所を置く。
ATIPは、東京事務所において、以下のセミナーを開催した。
|
3月15日 |
Legal Issues and the Protection of Software |
Prof Gideon Frieder (George Washington University, Washington DC) |
|
5月11日 |
Virtual Engineering as an Extension of Strategic Computing |
岩田修一(東京大学人工物工学研究センター) |
|
11月14日 |
What C++ is and Why |
Dr. Bjarne Stroustrup, AT&T Bell Labs |
六本木の東京事務所は2007年2月に閉鎖し、以後バーチャルオフィスとなる。
6) Eckert死去
ENIACの設計者の一人であったJohn Adam Presper Eckert Jr.は、白血病により1995年6月3日ペンシルベニア州で死去した。享年76歳。
7) Atanasoff死去
ブルガリア系の家系に生まれ、アタナソフ&ベリー・コンピュータ(ABC)の発明者であったJohn Vincent Atanasoffは、1995年6月15日、脳卒中のため自宅で死去した。91歳。1967年5月26日、Honeywell社がENIACの特許を買ったSperry Rand社を訴え、ENIAC特許の無効を主張したが、このときAtanasoffのABCマシンを提示したので有名になった。1973年10月19日に、ABCにはENIACより先行するアイデアがいくつかあったとして、Sperry Rand社の寡占の無効が決定された。
8) Zuse死去
ドイツの土木技術者でコンピュータの先駆者としてZ1~Z4などのコンピュータを作ったKonrad Zuseは、1995年12月18日にドイツで死去した。85歳。
国際会議
1) Frontiers ‘95
The Fifth Symposium on the Frontiers of Massively Parallel Computationは、1995年2月6日~9日にバージニア州McLeanで開催された。IEEE/CSが後援。会議録はIEEE Xploreに置かれている。
2) ISSCC 1995
第42回目となるISSCC 1995 (1995 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1995年2月15日~17日に、San Franciscoにおいて “The Digital Highway”のテーマで開催された。組織委員長はW. Pricer (IBM)、プログラム委員長はTimothy Tredwell (Eastman Kodak)であった。3件の全体講演が行われた。
|
Digital Storage Media in the Digital Highway Era |
Toshiyuki Yamada (Sony) |
|
The Making of the PowerPCTM Microprocessor |
Raymond DuPont, et al. (IBM) |
|
Gigachips: Deliver Affordable Digital Multimedia for Work and Play Via Broadband Network and Set-Top Box |
Pallab Chatterjee (Texas Instruments) |
Intel社はこの会議でP6マイクロアーキテクチャ(Pentium Pro、Pentium II、Pentium IIIなどが採用)の詳細を公表した。すでに第1四半期にサンプル出荷を始め、P6を搭載した装置が第2四半期に出荷されると述べた。実際に発売されたのは11月1日である。IEEE Xploreに会議録が置かれている。
3) PPSC 1995
第7回目となるPPSC 1995 (the Seventh SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing)は1995年2月15日~17日にカリフォルニア州San Franciscoで開催された。“Is Scalable Parallel Computing a Myth?”(スケーラブルな並列計算は神話か?)というパネルが行われた。会議録はSIAMから発行されている。
4) IPPS 1995
第9回目となるIPPS 1995 (The 9th International Parallel Processing Symposium)は、1995年4月25日~28日にカリフォルニア州Santa Barbaraで開催された。基調講演として、Richard M. Karpが“Modeling parallel communication”という講演を行った。主催はIEEE/CSで、IEEEから会議録が出版されている。
5) BIES’95
BIES ’95 (Biologically Inspired Evolutionary Systems)が、1995年5月30日~31日に東京のソニー・コンピュータサイエンス研究所で開催された。目的は、生物システムの持つ進化性が今後の人工システムに適用できるか、逆に理論的工学的研究が生物学の研究に何を寄与できるか、について議論することである。基調講演と招待講演は以下の通り。
|
(基調講演) Biologically Inspired Evolutionary Systems |
Chisato Numaoka (General Chair of BIES’95, Sony CSL, Japan) |
|
Using evolutionary mechanisms for behavioral development |
Luc Steels (VUB, Belgium) |
|
DISPARITY THEORY OF EVOLUTION —A symmetrical DNA Replication Promotes Evolution |
Mitsuru Furusawa (Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd., Japan) |
|
Toward Complex Adaptive Intelligent Systems |
Hiroaki Kitano (Sony CSL, Japan) |
 |
|
6) HPCN Europe 1995
第3回目のHPCN Europe 1995(High-Performance Computing and Networking, International Conference and Exhibition)は、1995年5月3日~5日にイタリアのミラノで開催された。会議録はLNCS 919としてSpringer社から出版されている。図はCERNのレポートのロゴ。
7) 18th Pacific Science Congress
ひょんなことから、1994年9月に、UNESCO PAC (Physics Action Council)のWG2 (Working Group 2)に日本代表として加わることになったことは述べた。この関係で、Pacific Science Association主催の第18回Pacific Science Congress(6月5日~12日)の中のthe Global Information Infrastructure Symposiumに参加することになり、6月5日~9日に北京の国際会議中心に赴いた。7日に”Research Networks in Japan”という講演を行った。Steven N. Goldstein (NSF)などインターネット界の有名人に何人かお会いした。筆者にとってこの会議場は1993年のICCP-2に続き2回目であった。近所にスーパーマーケットができるなど、前よりだいぶ開けたが、やはり交通不便であった。余談であるが、そのスーパーで2リットルのペットボトル入りの緑茶を買ったら、なんと砂糖入りだった。よく見るべきであった。
その時は何が何だかわからなかったが、Pacific Science Congressは1920年にHonoluluで第1回が開かれ、4年に1度環太平洋地域の回り持ちで開かれている。前回は1991年のHonolulu。
8) Lattice 95
第13回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 95)は、1995年6月11日~15日にオーストラリアのMelbourneで開催された。会議録はNuclear Physics B – Proceedings Supplement 42 (1996)として出版されている。
9) Mannheim Supercomputer Seminar
第10回目にあたるこの会議は、1995年6月22日~27日にMannheim市内で開催された。参加者は157人。6日間にわたって開催したのは初めてである。基調講演はChris R. Johnson, University of Salt Lake City, USA。
おそらくこの会議中に5回目のTop500が発表された。上位20位は以下の通り。性能はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
|
1 |
1 |
航空宇宙研究技術所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
170.0 |
235.79 |
|
2 |
2 |
SNL |
XP/S140 |
3680 |
143.4 |
184.0 |
|
3 |
- |
ORNL |
XP/S-MP 150 |
3072 |
127.1 |
154.0 |
|
4 |
- |
アメリカ政府某機関 |
T3D MC1024-8 |
1024 |
100.5 |
153.6 |
|
5 |
- |
高エネルギー物理学研究所 |
VPP500/80 |
80 |
98.9 |
128.0 |
|
6 |
3 |
LANL |
CM-5/1056 |
1056 |
59.7 |
135.0 |
|
7 |
- |
日本原子力研究所 |
VPP500/42 |
42 |
54.5 |
67.2 |
|
8 |
(4) |
Minnesota Supercomputer C. |
CM-5/896 |
896 |
52.3 |
114.7 |
|
9tie |
- |
LANL |
T3D MC512-8 |
512 |
50.8 |
76.8 |
|
9tie |
- |
Pittsburgh Supercomputer C. |
T3D MC512-8 |
512 |
50.8 |
76.8 |
|
11tie |
- |
Cornell Theory Center |
SP2/512 |
512 |
44,2 |
136,2 |
|
11tie |
- |
Maui HPC Center |
SP2/400 |
400 |
44.2 |
106.4 |
|
11tie |
- |
IBM |
SP2/256 |
256 |
44.2 |
68.1 |
|
14tie |
5tie |
オングストローム技術組合(日本) |
VPP500/30 |
30 |
39.8 |
48.0 |
|
14tie |
5tie |
筑波大学 |
VPP500/30 |
30 |
39.8 |
48.0 |
|
16 |
7 |
理研 |
VPP500/28 |
28 |
37.2 |
44.8 |
|
17 |
- |
Air Force Research Lab(米) |
XP/S-MP 41 |
816 |
33.7 |
40.8 |
|
18 |
- |
Univ. of Edinburgh(英) |
T3D MC320-8 |
320 |
31.7 |
48.0 |
|
19tie |
8tie |
NSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
|
19tie |
8tie |
NCSA |
CM-5/512 |
512 |
30.4 |
65.5 |
前回はほとんど入れ替えがなかったが、今回は上位20位中11件が新顔である。特にCray社のT3DとIBM社のSP2が目立つ。なお11位tieの3台のSP2は、ノード数が違っているのに同一のRmaxを出しており、ちゃんと測定していないことが明々である。おそらく最小の256ノードの測定値で代用したのであろう。日本設置のマシンで100位以内は以下の通り。
|
順位 |
前回 |
設置場所 |
機種 |
コア数 |
Rmax |
Rpeak |
||
|
1 |
1 |
航空宇宙研究技術所(日本) |
Numerical Wind Tunnel |
140 |
170.0 |
235.79 |
||
|
5 |
- |
高エネルギー物理学研究所 |
VPP500/80 |
80 |
98.9 |
128.0 |
||
|
7 |
- |
日本原子力研究所 |
VPP500/42 |
42 |
54.5 |
67.2 |
||
|
14tie |
5tie |
オングストローム技術組合(日本) |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
||
|
14tie |
5tie |
筑波大学 |
VPP500/30 |
30 |
32.9 |
48.0 |
||
|
16 |
7 |
理研 |
VPP500/28 |
28 |
30.8 |
44.8 |
||
|
22tie |
(10tie) |
日立エンタープライズサーバ部門 |
S-3800/480 |
4 |
28.4 |
32.0 |
||
|
22tie |
(10tie) |
東京大学 |
S-3800/480 |
4 |
28.4 |
32.0 |
||
|
31tie |
16tie |
日本電気(日本) |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
||
|
31tie |
16tie |
東北大学 |
SX-3/44R 400 MHz |
4 |
23.2 |
25.6 |
||
|
33tie |
- |
富士通 |
VPP500/16 |
16 |
21.7 |
25.6 |
||
|
33tie |
- |
京都大学 |
VPP500/16 |
16 |
21.7 |
25.6 |
||
|
33tie |
- |
東京大学物性研究所 |
VPP500/16 |
16 |
21.7 |
25.6 |
||
|
36tie |
- |
北海道大学 |
S-3800/380 |
3 |
21.6 |
24.0 |
||
|
36tie |
18 |
東北大学金属材料研究所 |
S-3800/380 |
3 |
21.3 |
24.0 |
||
|
40 |
20 |
分子科学研究所 |
SX-3/34R |
3 |
17.4 |
19.2 |
||
|
63 |
41 |
産総研RIPS |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.2 |
||
|
48tie |
- |
東北大学流体研究所 |
Y-MP C916/16256 |
16 |
13.7 |
15.2 |
||
|
76 |
47 |
通信総合研究所 |
VPP500/10 |
10 |
11.7 |
16.0 |
||
|
73tie |
54 |
動力炉・核燃料開発事業団 |
T3D MCA128-2 |
128 |
12.8 |
19.2 |
||
|
73tie |
- |
東北大学流体研究所 |
T3D MCA128-8 |
128 |
12.8 |
19.2 |
||
|
87tie |
65tie |
核融合科学研究所 |
SX-3/24R 400 MHz |
2 |
11.6 |
12.8 |
||
|
87tie |
65tie |
日本電気社内 |
SX-3/24R |
2 |
11.6 |
12.8 |
||
|
95tie |
69tie |
航空宇宙技術研究所 |
XP/S25 |
336 |
10.0 |
16.8 |
||
|
100 |
75 |
宇宙科学研究所 |
VPP500/7 |
7 |
9.65 |
11.2 |
||
10) ICS 1995
第9回目となるICS 1995 (9th ACM International Conference on Supercomputing)は、1995年7月3日~7日にスペインのBarcelonaで開催された。主催はACM SIGARCHで、組織委員長はMateo Valero, Universitat Politecnica de Catalunya、プログラム委員長はMichael Wolfe, Oregon Graduate Instituteであった。会議録はACMから出版されている。
11) HPDC-4
第4回目となるHPDC-4 (Fourth IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、1995年8月1日~4日、バージニア州Pentagon CityのRitz Carlton Hotelで開催された。主催はIEEE/CS TC on Distributed Processingと•Northeast Parallel Architectures Center (NPAC) at Syracuse University、講演はACM SIGCOMMとRome Universityであった。初日には5件のtutorialsが行われた。基調講演、招待講演等は以下の通り。
|
Keynote |
Lionel S. Johns, OSTP |
|
|
Invited |
Jameshed Mirza, IBM |
NOWs, MMPs, and Scalable Parallel Systems |
|
Invited |
Paul Woodward, University of Minnesota |
Distributed Computing on Clusters of Shared-Memory Multiprocessors to Simulate Unsteady Turbulent Flows |
|
Keynote |
Walter Johnston, NYNEX Science and Technology Inc. |
|
|
Panel |
G. C. Fox, Syracuse University |
Concordance or Discordance between Parallel, Distributed |
12) HOT CHIPS 7
1989年から始まった高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、第7回目のHOT CHIPS 7 (1995)を1995年8月13日~15日にStanford大学Memorial Auditoriumにおいて開催した。基調講演とパネルは下記の通り。
|
“Nanometers and Gigabucks” |
Gordon Moore (Intel) |
|
Panel: What is the Role of Competing Architectures in an x86 World Order? |
Moderators: John Warton (Consultant), Analyst (Applications Research) |
13) ICPP’95
第24回目となるICPP’95 (1995 International Conference on Parallel Processing)は、1995年8月14日~18日、イリノイ州Urbana-Champainで開催された。主催は、Pennsylvania州立大学、会議録はIllinois大学の編集でCRC Pressから発行されている。電子版はIEEE Xploreには置かれていないようである。
14) PERMEAN’95
国内会議のところに書いたSWoPP 別府’95に先立ち、「計算機性能と解析に関する国際ワークショップ — PERMEAN’95 –」(PERformace MEsurement and ANalysis 95)が、8月20日~23日に同じ会場で開催された。主催は、情報処理学会計算機アーキテクチャ研究会(ARC)ならびにハイパフォーマンスコンピューティング研究会(HPC)である。これは第2回のJapan-US Workshop for Performance Evaluation (1994)の時に計画されたものである。共同実行委員長は、Gary Johnson (George Mason University)と筆者が務めた。会議録はなく、プログラムも残っていないが、手元に筆者の書いた招待講演セッションの概要がある。
招待講演のセッションは、”Experiences in Performance Measurement and Analysis”という副題のもとに、並列計算機の現場で得られた、性能測定と解析の実際を3つのグループから発表していただいた。4件計画したが、一つキャンセル。
Prof. Margaret Martonosi (Princeton University) は、”Analyzing and Tuning Memory Performance in Sequential and Parallel Programs” と題して、超並列計算機が性能を出せない最大の原因であるメモリの遅さをどう対処するかを論じた。キャッシュを有効に利用するには、tiling とかprefetching などの手法があるが、その有効性を実測するにはデータ指向の性能測定ツールが必要である。測定方法として、ソフトウェアによるシミュレーションと、ハードウェアによるモニターとがあるが、両者の長短について議論した。
Dr. Donna Bergmark (Cornell Theory Center) は、”How Performance Analysis Tools are Used to Analyze and Characterize Parallel Applications on Cornell Theory Center’s IBM SP2″ と題して、SP2 のユーザを教育する立場から、様々な性能測定ツールがどんなに役立っているかを事例を交えて紹介した。とくに、High Performance Fortran で書いたプログラムを実行させ測定し大幅に改善したケースの話は面白かった。
Dr. Gordon E. Lyon and Dr. Robert Snelick (NIST) は、”Computer-Assisted Statistical Screening of Parallel Programs” と題して、統計解析の手法を用いて実行過程を分析し、性能向上をはかるツール S-Check について紹介した。これは、Cで書かれたプログラムの自動化された感度解析ツールで、従来のプロファイラーを拡張して、プログラムの一部に変更を加えてその影響を測定することにより、部分毎の相互作用を解析し、どの部分を改良すればどの程度の性能向上が出来るのかを明らかにすることができる。
日本では、並列処理の実用化は始まったばかりで、チューニングも手探りで行われていることが多いが、アメリカでは、さまざまなツールが商品またはフリーウェアで流通し、現場で用いられていることを強く印象付けられた。まだ未完成な部分も多いが、わが国でも今から積極的にこのような分野を推進して行くことが重要である。
15) Workshop “State of the Art Academic and Research Telecommunications — A Dialogue on Policy, Management and Infrastructure for the 21st Century”
WG2の活動の一環として、9月17日(日)に上記の会議を東大で開催した。主催はUNESCO、日本物理学会、日本応用物理学会、アメリカ物理学会。筆者がお世話をしたが、HPC Asia 95の前日で、台風が関東を襲撃し大変であった。議論としては、ネットワーク技術の状況、ネットワークビジネスの今後、国際協力の可能性、ネットワークによる教育支援など。
16) HPC Asia 95
第1回のHPC AsiaであるHPC Asia 95は、1995年9月18日~22日に台北の臺北國際會議中心(TICC, Taipei International Convention Center) で開かれた。別の章として記す。
17) CHEP 1995
第8回目となるCHEP 1995 (1995 Computing in High Energy Physics)は、1995年9月18日~22日に、ブラジルのHotel Glória, Rio de Janeiroで”Computing for the next millennium”(次のミレニアムに向かうコンピューティング)のテーマで開催された。主催は、アメリカのFERMILAB (the Fermi National Accelerator Laboratory)と、ブラジルのLAFEX/CBPF (Laboratorio de Cosmologia e Fisica Experimental de Altas Energias)で、共同組織委員長は、Vicky White (FERMILAB) and Alberto Santoro (LAFEX)であった。主要テーマは、「データ解析」「データアクセスと記憶装置」「データ収集(DAQ)とトリガー」「ツール、言語、ソフト開発環境」「その他」とあり、素粒子理論より高エネルギー実験の方に比重があるようである。前述のように参加した森田洋平(高エネルギー物理学研究所)は、1995年12月8日に開催されたHAS研特別講演で「第13回高エネルギー物理におけるコンピューター利用国際会議の報告」をおこなっている。
リオデジャネイロということで食指が動いたが、遠いことと、治安が不安なこともあり躊躇した。最終的には、国際組織委員(Steering Committee member)をしている上記HPC Asia 95と重なって行けなかった。ある朝(おそらく、台北から帰国した翌日の23日(土)であろう)、ラジオのニュースで「リオデジャネイロで開かれている国際会議に出席していた日本人が、ひったくりに遭い、市電から転落して死亡した」と報じていて、一瞬CHEPではないかと心配になった。続報で、亡くなったのは福井大学の川口湊教授であることが判明した。川口教授には、東大物理に居られたころたいへんお世話になった。日本人参加者の中から高エネルギー物理学研究所の森田洋平(現在、沖縄科学技術大学院大学)が滞在を伸ばして、遺族や現地との対応に当たったとのことである。なお、森田洋平氏は1992年(d)にある日本最初のWWWホームページを作成した物理学者である。
会議録はWorld Scientificから出版されている。写真はその表紙と目次の一部。目次の次のページには、「川口湊教授を偲んで」との弔辞が掲げられている。
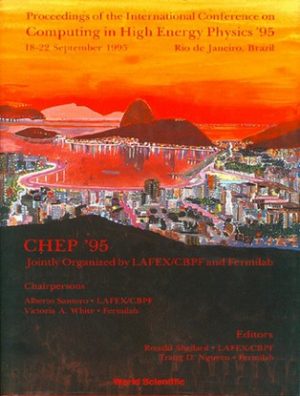 |
 |
18) ParCo’95
第6回目となるParCo’95 (International Conference on Parallel Computing)は、1995年9月19日~22日にベルギーのGent(ヘント)で開催された。HPにはFifthと誤って記載されている。主催はGent大学のVakgroep Electronica en Informatiesystemenである。前回に引き続きプログラム委員を務めたがまた出席はできなかった。3件の招待講演が行われた。
|
Parallelism in CG-like Methods |
Henk A. van der Vorst |
|
High Performance Computing for Finance |
Peter Dzwig |
|
HPCC: The Interrelationship of Computing and Communication |
Oliver A. McBryan |
会議録は、Erik H. D’Hollander, Gerhard R. Joubert, Frans J. Peters, Denis Trystram: Parallel Computing: State-of-the-Art and Perspectives, Proceedings of the conference ParCo 1995, Gent, Belgium, September 1995. Advances in Parallel Computing 11, Elsevier 1996, ISBN 0-444-82490-1として出版されている。
19) ICPA’95
International Conference on Parallel Algorithm (ICPA’95)が、1995年10月16日~19日に、中国の武漢大学(Wuhan University)で開催された。外国からは、12か国40人(アメリカ23人、イギリス2人、ドイツ2人、オーストラリア1人、カナダ1人、フランス2人、オランド2人、日本2人、イタリア1メイン、スウェーデン1人、スロバキア1人、韓国2人)が参加し、全部で86の講演があった。シリーズではなく単発の会議と思われる。基調講演および分野別の招待講演は以下の通り。かなりのビッグネームを集めている。
|
基調講演 |
|
|
The changing high performance computing environment |
Ann Hayes, Los Alamos National Laboratory, USA |
|
Dawning 1000 and its applications |
Guojie Li, Chinese Academy of Sciences, China |
|
On increasing the parallelism in numerical analysis |
David J. Evans, Loughborough University of Technology, UK |
|
Comments on PVPs, MPPs, NOWs, and future computer architectures |
Bill Buzbee, National Center for Atmospheric Research, USA |
|
I: Massively Parallel Computation |
|
|
Biologically motivated computationally intensive approaches to image pattern recognition |
N. Petkov, University of Groningen, Netherlands |
|
CAM-Brain: the evolutional engineering of a billion neuron artificial brain |
Hugo de Garis, ATR HIP Labs, Japan |
|
II: Parallel Computer Systems |
|
|
Cray research massively parallel processors |
Guangye Li, Cray Research, USA |
|
Parallel benchmarks for complex-geometry turbulent flows |
George Em Karniadakis, Brown University, USA |
|
III: Parallel Software |
|
|
Parallel electronic prototyping of physical systems |
Elias Houstis, Purdue University, USA |
|
The PMESC parallel programming paradigm and library for task parallel computation |
E.R.Jessup, University of Colorado at Boulder, USA |
|
Objected-oriented software tools for parallel PDE solvers |
Michael Thune, Uppsala University, Sweden |
|
IV: Domain Decomposition |
|
|
Innovative parallel algorithms for various flow simulation |
Jacques Periaux, Dassault Aviation, France |
|
Two-level additive Schwarz preconditioners for plate elements |
Susanne C.Brenner, University of South Carolina, USA |
|
Cached based multigrid algorithms |
Craig C. Douglas, Yale University, USA |
|
V: Scientific Computing |
|
|
Challenges and potentials of parallel scientific computing on Heterogeneous networks of workstations |
Xiaodong Zhang, University of Texas at San Antonio, USA |
|
Parallel methods for immiscible displacement in porous media |
Jim Douglas, Jr., Purdue University, USA |
|
VI: Parallel Algorithms |
|
|
A survey about genetic algorithms and their application on optimization |
Heinz Muehlenbien, GMD, Germany |
|
A model of memory dynamics
|
W.L.Miranker, IBM T.J.Watson Research Center, USA |
|
VII: Parallel Algorithms |
|
|
Stability analysis of neural network |
M. Sambandham, Morehouse College, USA |
|
Massively parallel algorithms for a multiplication of matrices |
Marian Vajtersic, Slovakia Academy of Sciences, Slovak Republic |
|
VIII: Scientific Computation |
|
|
Parallel minimization algorithms by generalized subdifferentiability |
C. Sutti, University of Verona, Italy |
|
Massively parallel algorithms from nature |
Lishan Kang, Wuhan University, China |
20) SC95
12月3日(日)~8日(金)にSan Diego Convention Centerで、開催されたSupercomputing 95国際会議については独立の章として記す。
21) HiPC’95
2回目に当たる、HiPC’95 (International Conference on High Performance Computing 1995)は、1995年12月27日~30日に、New DelhiのThe Hyatt Regencyで開催された。基調講演は以下の通り。
|
“Hot Machines” |
Anant Agarwal (MIT) |
|
“The Stanford DASH and FLASH Projects” |
Anoop Gupta (Stanford大学) |
|
“The Parallel Software Crisis – ‘The Problem’ or just a Symptom?” |
Uzi Vishkin (Maryland大学) |
次回は、台北で開かれた第1回HPC Asiaである。登録参加者は700を越え大盛会であった。
 |
 |
 |

