提 供
HPCの歩み50年(第66回)-1998年(d)-
Cray Researchを吸収したSGIの新CEOのBelluzzoは4月記者会見を行い、大きな方針転換を発表した。Intel社はサーバ用のXeonを初めて発表した一方、Itaniumの出荷は大幅に遅れた。
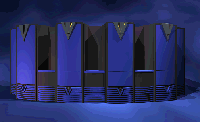
世界の学界の動き
1) Mannheim Supercomputer Seminar
Hans Meuer教授の主催するMannheim Supercomputer Seminarは、第13回目を6月18から23日にMannheim市内で開催した。参加者は183名。基調講演はLarry Smarr (UIUC)であった。
2) HPC Asia 98
International Conference & Exhibition HPC ASIA 98 は、シンガポールのRaffles City Convention Centre において、1998年9月22日から25日まで開かれた。1997年4月末にSeoulで開かれた第2回に続く第3回である。会場はシンガポールの中心部に位置し、Westin Plaza Hotel および Westin Stamford Hotelとが一体の建物を構成している。今回は、シンガポール国立大学のIHPCが主催し、かなりの力を入れていたことが感じられたが、参加費が750S$(約62000円)と高く、学生料金もなく、会場といい、食事といい、バンケットといい贅沢な会議であった。19カ国から276人に出席者があり、176編の論文が発表された。このほかに、パネリストや座長のために地元の研究者を100人ほど非登録で参加させたようである。
Keynote Address では、Dr. Sid Karin (Director of NPACI, San Diego) が “The Computing Continuum”と題して講演した。従来、スーパーコンピュータはそれ以外のコンピュータから隔絶した性能を持っていたが、いまやコンピュータの性能は連続スペクトラムで、そのうち比較的上位のものをスーパーコンピュータと呼んでいるに過ぎない、というようなことを述べた。
Industrial Keynote Address としては、R. E. Belluzzo (new CEO of SGI)が”Big Data: The Big Picture and the Long View” と題して講演した。組織委員会は事前に、会社の promotion talk ではなくscientific talkをするようにと念を押し、アブストラクトはそうなっていたが、「SGIの strategic direction は、graphic & media と、cc Numa & supercomputerとの融合である。その証拠が ASCI Blue Mountain である。」というような全くのセールストークで評判はよくなかった。
アジア全体の不景気ということもあって、展示は前回の半分ほどの面積である。出展数は前回よりかなり少ない。大きなブースを占めたのが国際的大企業で、SGI、IBM、Hewlett-Packard、Sun、Fujitsu、Compaq の6社であった。ソフトウェアでは、Portland Group、NAG、Pallas の3社。 地元の企業としてはTechSourceという会社が出展した。研究展示が5件、日本の航技研、Centre for Development of Advanced Computing (India)、Interactive Visual Simulation Laboratory (Singapore)、Sydney Vislab (Australia)、The Cooperative Research Centre for Advanced Computational Systems (Australia)であった。
バンケットは、オーチャードロードの端の超高級ホテルシャングリラで、前回と同じく、中国・マレー・インドの3文化を代表するダンスがあった。
会議のあと、NUS(シンガポール国立大学)で非公式セミナーをやって何人かの人と討論したが、Rice大学から来ている人で、OpenMP から Message Passingコードを生成する研究をしている人がいた。OpenMPが並列性を記述しているのなら、このような道もあるとかねがね考えていたのでおもしろかった。XcalableMPの遠い先祖ですね。
3) ICS 98
ACMが主催するICS (International Conference on Supercomputing)の第12回目は、オーストラリアのMelbourneで7月13~17日に開催された。論文投稿数は116編で、相当数日本からの投稿があったとのことである。ACMからプロシーディングスが発行されている。
4) HPCN Europe 1998
High-Performance Computing and Networking, International Conference and Exhibition, HPCN Europe 1998は、4月21~23日オランダのAmsterdamで開催された。会議録はLecture Notes in Computer Science 1401, Springer 1998から出版されている。詳細は不明。この会議は2001年まで継続した。
5) QCDSP
1998年4月、QCD専用計算機QCDSPが、Columbia大学(0.4 TFlops)とBNL (0.6 Tflops)に設置された。
6) LANL
LANLの理論天文学グループは68台のAlpha EV56搭載のPCを通信販売で買い、Avalonという名のクラスタを自作した。相互接続には3Comのネットワークスイッチを用いた。費用はわずか15万ドル。19.33 GFlopsで1998年6月のTop500の314位を占めた。部品がそろってから3日で動いたと豪語していた。
7) AEARU
東アジア研究型大学協会 AEARU (The Association of East Asian Research Universities)は1996年1月に創立された地域大学連合であり、東京大学は最初からのメンバーであった。日本からは他に京都大学、大阪大学、東北大学、筑波大学、東京工業大学が加盟している。全体で17校。1996年10月に、東京大学の蓮實重彦副学長から理学部長を通して連絡があり、1998年4月16~17日にコンピュータ科学関連の集まり(AEARU CS Meeting)があるので出席せよとのことであった。会場は台湾新竹市の國立清華大學 (National Tsing Hua University)であった。
参加者は、中国、香港、台湾、日本から計12名であった。日本からは筆者の他都倉信樹(大阪大学)が参加した。代表を送らなかったのは、KAIST(韓国)、POSTECH(韓国)、Seoul国立大学(韓国)、筑波大学、東京工業大学であった。大部分の参加者は中国語圏で、ときどき中国語が飛び交っていた。学部レベルの交流は現実的ではなく、大学院レベルおよび若いスタッフの交流について努力しようという結論になった。
企業と大学の関係についても議論になり、筆者は1997年4月からの民間企業との兼業の新しいルールについて報告した。各国事情はさまざまで、香港のようにアメリカと同様なやり方のところもあるし、ある国のように公式には企業から給料はもらえないが、実際は under the table だ、というところもあった。またある国では、教授が(実質上)作った会社の大半は潰れてしまったとか。
実は、前月(3月15~18日)にも台湾に出かけた。研究室の台湾からの留学生(修士)の結婚式に出席するためである。家内と出かけ、旅費の心配はしなくてもいいから、台湾式の結婚式次第を全部見せてくれと頼んだ。新郎が友人達と車を連ねて新婦宅にでかける「猟妃行列」まで全部参加した。猟妃行列が新婦を乗せてまさに新婦宅を出ようとするとき、新婦の母親が泣きながら陶器の皿を地面にたたき付けた。何事かと思ったら、「覆水盆に返らず」みたいなものだ、と誰かが解説してくれた。
8) インド
インドのC-DACは、Sun Enterprise 250サーバ(400 MHzのUltraSPARC II)をノードとして160台結合したPARAM 10000を開発した。ピークは6.4 GFlops。
アメリカの企業の動き
1) SGI社
前HP副社長のRick BelluzzoはSGIのCEOに就任した。4月14日にニューヨークで記者会見を行い、ビジュアル・コンピューティングとシステムの高速化に焦点を絞った「戦略的ビジネス計画」を発表した。とくに、これまで使っていたMIPSプロセッサに加えて、Intel社のプロセッサを搭載したWSを開発すること、OSとしてUnixだけでなくMS Windowsを搭載したコンピュータを開発していくと発表した。製品は1998年後半に出荷される予定。でも競争の激しいNTマーケットでビジネスができるのか危ぶむ向きもあった。同時に、SGI社が1992年に買収していたMIPS Technologies社を手放して1000名規模の解雇を行うなどリストラ策も発表した。2000年頃までに全保有株を手放したのでSGIの子会社ではなくなった。MIPS Technologies社は今後、ゲーム機やセットトップボックスなど家庭用電気製品への組込型プロセッサを中心に開発を進める予定と報道された。1998年11月、MIPS Technologies社はR12000を発売した。製造は日本電気と東芝。
HPC関係の戦略ははっきりと述べられなかったが、T90、J90、T3E、Origin2000と4本あるラインを2本にすると述べた。Origin2000ともう1本は何が残されるであろうか。
2) SGI/Cray社
SGI社は、1998年6月、ベクトルコンピュータCray SV1を発表した。それまでJ90++と呼ばれていたようである。先行のCray J90と同じくCMOSのプロセッサを用いている。OSはUNICOSで、J90やY-MPと互換性がある。浮動小数表現はいわゆるCray表現を用いており、IEEE 754はサポートしない。その点ではCray T3EやT90と互換ではない。クロックは300 MHz、ピーク性能は1.2 GFlopsであるが、改良型のSV1eやSV1exは500 MHzで動く。最大32プロセッサまで搭載可能である。従来にない特徴はベクトル・キャッシュが装備されていることである。また4個のプロセッサをパイプライン的に動かして仮想的に1個のプロセッサに見せるマルチ・ストリーミングと呼ばれる特徴を持つ。12月に、Cray SV1を、Naval Oceanographic OfficeとETHにはじめて出荷した。SV1はTop500には登場しないようである。
SGI社は子会社であるCray Research社がT90、J90、T3Eなどのプリント基板を製造してきたウィスコンシン社の工場を、カナダの電子機器製造請負企業のCelestica Inc.に売却し、引き続きスーパーコンピュータ用の基盤の製造を委託することとした。工場の従業員はすべてCelestica社が雇用する。なおCelestica社は、電子機器の製造請負企業としては世界で3番目の規模とのことである。(日経エレクトロニクス5月25日号)Celestica社は、IBM社の100%出資の子会社で、1993年に電源やカードの製造業者として独立したようである。
前年のSC97の開会式でSeymour Cray賞の発表の際に追悼演説したIrene Qualters女史が、7月1日づけでCray Research社長、兼SGI副社長の職を辞すことが5月20日に発表された。着任は1997年5月なので、1年だけの在任であった。
3) IBM社
10月5日、POWER3チップとこれを用いたワークステーションRS/6000 43P Model 260が発表された。POWER3はPOWERシリーズ初の完全な64ビットプロセッサである。技術的にはP2SCの後継である。当初は200 MHzのクロックであった。
12月22日号の日経コンピュータによると、IBM社はSequent Computer Systems社からNUMA技術の提供を受け、100個以上のプロセッサを搭載可能な共有メモリ・サーバを開発していることが明らかになった。2000年末にも128プロセッサ機を出荷予定とのことである。RS/6000の現在の共有メモリの最大構成は12プロセッサまでであり、Sun Microsystems社やHP社などの競合他社に遅れをとっていた。
後に述べるように、IBM社は1998年10月からSequent社などと64bit向けのUnix OSを開発するProject Montereyを進めており、これをハードウェア分野にまで拡大したとも見られる。実際には、1999年7月にIBM社はSequent社を買収した。
4) Sun Microsystems社
E10000(コードネームStarfire)は順調に販売が進み、6月には500台目を販売した。1998年8月頃、IBM社がSun Microsystems社を買収するという噂が流れた。1990年前半までUnixシステムで一人勝ちの状況であったが、このころCPU開発競争やエンタープライズ系への対応で遅れが目立っていた。この噂は外れたが、2010年1月、Oracle社に買収された。
1998年11月3日、Sun Microsystems社は、UC BerkeleyのDavid A. Patterson教授が、同社のNetwork Storageのチーフ・サイエンティストを兼務することを発表した。
Japan ERC (Education and Research Conference) ‘98が7月22日に東京ヒルトンホテルで開催され教育研究担当副社長Kim Jonesが来日した。
5) Intel社(Xeon)
Xeonシリーズの皮切りとして、1998年6月からPentium II Xeon (400 MHz)が発売された。Pentium IIの技術に基づくものであるが、Xeonは業務用のワークステーション、サーバ、組み込み系などを標的とした製品系列である。一般向けPCに使われるPentium系の製品とアーキテクチャ的には同系統であるが、より進んだ技術を用い、高い性能を狙っている。6月25日、Intel社はXeonにバグがあることを確認し、同社の株価が急降下した。問題は複数のCPUを並列に動作させる450NXチップセットにあるとのことで、バグのため各社のサーバの出荷が延期された。
5月にはIA-64 processer(コード名Merced)の出荷が大幅に遅れると発表したところであった。
6) AMD
Intelの互換メーカAMDは、Intelに対し価格性能比を保つために、P5バス互換プロセッサの開発を進め、K6に「3DNow!」を追加した350MHzのK6-2を発表した。K6-2はPentium IIに迫る性能をもち、大手メーカが製造するPCに採用された。下位のチップではIntelのCeleronを凌駕しようとした。
7) Microsoft社(Windows 98)
Microsoft社は、1998年6月25日にWindows 98を一般向けに発売した。朝日新聞によると、ビル・ゲイツ会長は同日夕(日本時間26日朝)、サンフランシスコで開いた98発表記念行事で、約1000人の聴衆を前に「パソコンは生活にもはや不可欠」「扱いやすい理想のパソコンへの第一歩」と自信をみせた。95と代わり映えしないとの批判もあり、口の悪い評論家は「98なんて95のバグ・フィックスさ」と酷評していた。シリコンバレーでは、98を売っている脇で、LinuxのCD-ROMをタダで配っていたそうである。日本語版のリリースは8月25日。筆者は、この年5月にMS/DOS 3.11からWindows 95に進化したばかりで、全くの浦島太郎であった。
Microsoft社は、早くも1998年10月27日、次期OSはWindows NTの系統を引くWindows 2000となり来年中の発売を目指すと発表した。これはビジネス向けで、家庭用は98のままのようである。
アメリカ企業の続きや標準化、日米貿易摩擦は次回。
(タイトル画像: Cray SV1 出典: http://www.craysupercomputers.com/)
 |
 |
 |

