アカデミアと企業の連携こそが未来のHPCを築く
スポンサー記事
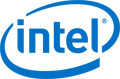
HPC分野において、エクサスケール・スーパーコンピューティングの要となる企業と言えばインテルであり、常に新しいニュースに事欠かない。最近では米国エネルギー省のAuroraの業者にクレイとともに選定された。ところで日本におけるインテルの活動はどうだろうか? 実はインテルは日本でも、目立ちはしないが地道な活動をHPCの世界で続けている。今回、インテル株式会社は6月26日金曜日にベルサール神田において、インテル単独主催では初となるHPCワークショップを開催する。開催に合わせてインテル株式会社 ビジネス・デベロップメント・グループ エンタープライズ・HPC担当部長の根岸 史季 氏に話を伺った。
まず最初にインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーはどの程度国内に普及しているのだろうか? 国内におけるインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーの最大規模のインストールと言えば筑波大学のCOMAであり786台のインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを搭載し、性能は1001TFLOPSで国内最大だ。次に、京都大学のCray XC30システムであるCamelliaで、482台のインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを搭載し、性能は583.6TFLOPSである。しかし、規模はこれより小さくなるが、比較的大きいシステムが他にも導入されていると根岸氏は語る。
「九州大学、統計数理研究所などでも100台前後の規模で導入されていますが、特徴的なのは民間での利用で、代表的なものに計算科学振興財団とみずほ証券のスーパーコンピューターが挙げられます」。神戸にある計算科学振興財団が所有するFOCUSスパコンのEシステムは、公表されている仕様によればインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを192台搭載しており、システム全体の性能は213TFLOPSとなっている。計算科学振興財団によるとFOCUSスパコンは、「スーパーコンピューター『京』の産業利用の促進を図り産業界のスパコン利用企業層を拡大するための技術高度化支援を中心に供用を行うほか、産学連携研究や実践的な企業技術者の育成を推進することを目的に整備された国内唯一の産業界専用の公的スーパーコンピューターです」とあり、民間利用を前提としたスパコンである。
また直接的な民間での導入であるみずほ証券については以前HPCwireの記事でも取り上げており、並列化による業務の高速化に成功している。
しかしながら、この手のアクセラレーターで一番気になるのがアプリケーションだ。実行できるアプリケーションなしにはなかなかアクセラレーターの普及は望めない。インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーの場合、商用アプリケーションでは現在ANSYS社のANSYS MechanicalやAutodesk社のMayaがサポートされているとのことだが、それでも非常に少ない。そこでインテルはアプリケーション・ソフトウェアの拡充を目指す新たな試みを続けている。先にHPCwireでも中国におけるインテルの活動記事として取り上げた「Intel Parallel Computing Center (IPCC)」がそれだ。
IPCCはインテルが主導する助成プログラムで世界中に設立されており、日本にも東京大学情報基盤センターを含め3件が稼動している。これは助成ごとにターゲットとされるアプリケーションが定められ、成果はコミュニティーに戻される仕組みだ。そのためソフトウェアは基本的にオープンソースが原則である。各センターではターゲットとなるアプリケーションの並列化が主な作業となるが、この並列化はインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに限らず、通常のインテル® Xeon® プロセッサーに対する並列化も行われている。根岸氏によると、「実はインテル® Xeon® プロセッサーへの最適化とインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーへの最適化は本質的に同じで、それはアプリケーションの並列化とSIMD化ですが、その恩恵は両方が享受できる。逆に言うと、そもそもインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーはおろか、インテル® Xeon® プロセッサーに対してすら最適化が行われていないことが多いのです。そのため、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーへの最適化をきっかけにアプリケーションが並列化・SIMD化されインテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーの両方で高速化し、最終的にはその成果はコミュニティーに還元されますから、どなたでも利用できるようになります」。根岸氏によると、このIPCCは日本国内でも拡大を続ける予定で常時応募を受け付けているとのことだ。
インテルの最近の話題と言えば、この春に米国エネルギー省から発表された2億ドルのスーパーコンピューターがHPCwireの記事でも紹介したように記憶に新しい。この「Aurora」と呼ばれるシステムは180ペタフロップス以上の性能が計画されており、2018年に登場する予定である。この大型案件を契約したのがインテルであり、システム自体はクレイ社が提供する。
今回のようなスーパーコンピューター案件をインテルが直接受注するのはASCI Red以来となる。「インテルが主契約者となるのはおおよそ20年ぶりのことです。これはお客様からの強い要望で実現したもので、インテルが今後積極的に主契約者となることはありません。インテルはスーパーコンピューターの部品に関する総合商社を目指してはいますが、完成品をつくる会社ではないと考えています」と根岸氏は今回の件について語っている。またAuroraの性能について根岸氏は「最終的にお客様のご購入予算にもよりますが、180ペタフロップスから450ペタフロップスの間あたりになるだろうと予測されています」と語る。
Auroraのさらに詳細については今回のイベントでも話が出る予定とのことで、「乞うご期待」とのことだ。
今回インテル主催で開催されるイベントは6月26日にベルサール神田で開催され、詳細については別途イベント情報でも提供される予定だ。今回のイベントの主旨について根岸氏は次のように語った。
「このイベントでは、従来のアカデミアのHPCとエンタープライズのHPCの関係者に集まっていただき、両者のHPCの何が同じで何が違うのかについて議論できる機会を提供したいと考えています。共通の課題に対しては一緒に取り組んでいった方がより効率的だからです。そのため、今回のイベントにはアカデミアおよびエンタープライズの管理者、エンドユーザーばかりでなく、OEMベンダーの方々にも参加を呼び掛けています。これまで日本ではこのような異分野のHPCの関係者が集う場がありませんでした。インテルはその中で一番中立的であり、このような場を主催するのに最も適していると考えています」。
今回のイベントの詳細は下記のリンクから。







